1:3�̒���g�g�����X�̑����100V:200V�̐≏�g�����X�͎g����́H
�g����B�ł�������d�����g���ɓ������Ă邩�特���ɉe�����o��Ǝv���B
�^��ǃ��W�I�͏������݂�������
���W�I���쑍���Ɛ^��Ǒ����ɂȂ����̂��ƁA�p���ł��邩��
�^��ǃ��W�I�Ő≏�d���g�����X�̏d���̓n���p�Ȃ�
�����d���g�����X�̌`�������m�C�Y�̏��Ȃ��y��SW�d�����j�b�g�������̂��낤��
�X�C�b�`���O���g�����ςł���Ȃ��B
>>10���������Ȃ�(���ʏ������Ȃ�)���ǒ�R�g�����������͂����B
�m�C�Y������B >>12
10����Ȃ����ǎQ�l��H��]
�`���[�N�̒�R�u��������2�`3���W�I���炢�����o���Ȃ���
ST-30�������Ȃ��Ƃ��̋���̍�
SL-50�A���e�i�̃^�b�v����Ă��܂��ċ��������c
�^��ǃ��W�I��10�N�ȏ����ĂȂ����Njv�X�ɑg�݂����Ȃ��Ă��� �����͓��h�ϐ����1000�~���炢��1:3�g�����X�g�������B
�ʔ̃y�[�W����Ƃ܂��ڂ��Ă܂��ˁB
�T���X�C��TR�pST�V���[�Y�ł��g����炵����
��������ƂȂ�����w
>2 1:3�g�����X�Ȃ�H�t���}���c�p�[�c�i�H���d�q�ʏ��߂��́j�ŃW�����N�@1:3�g�����X�Ə������
1��100�~��1�����ɏo�Ă�����B�@������Ƒ傫�߂������̂Ő^��Ǘp�B
10H30mA���������H�`���[�N�g�����X��100�~�������B
1��������������A�������l�����ɂ����邩�ȁH
>>17
�����ɏZ��ł�l���R
���ȓޗ� �ŋ߂͏H�t�ŏo���Ȃ�Ă߂����ɂȂ���B
�ޗǂȂ�f�W�b�g������̂ق����o����������ˁH
�f�W�A�i�ϊ��큨RF���W�����[�^�[�{�^��ǃe���r�ōŐV�̔ԑg������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://a.pd.kzho.net/1458209363249.jpg)
�R���X�[�p�[�Ƃ��S���X�[�p�[���v���o���Ă���ĉ�����
�T�u�~�j�ǂ̂����
>>13 �u���b�h�{�[�h���W�I���Q�l�ɂȂ邩���B
�g�����X���ăV�r�A�łȂ��Ă��A�����悤�Ȃ̂Ȃ�Ƃ肠������B
�Z���^�[�^�b�v�Ƃ��Ȃ��Ă�������B �̂̃e���r��FM���g�Ɏg���Ă�6DT6�́A���W�I�̍�����6BE6�ƍ�����
���Ă݂��犮�S�Ɍ��������������Ƃ��ǂ����̃u���O�ł݂����Ƃ��邯��
�ǂ��Ȃ�
6BE6��7�Ɋǂ�6DT6��5�Ɋǂ�����
�A���e�i�R�C���̊����n�߂⊪���I���ɘX�����邱�Ƃ����邯�ǁA
���̔S�x�������X���ĉ����g���Ă�̂��m���Ă�l����H
�y�[�p�[�R���f���T�̘X��S40�N�O���TR���W�I�̊�ɐ��炵�Ă�X��
������������̍d����S��C�͓����悤�Ɏv�����ǁA
�Č����悤�Ǝs�̂̋T�R���[�\�N���g���ƃp�T�p�T���Ă��Đڒ��ł��Ȃ�
�p���t�B�����b�N�X�B�@�g��Ȃ��y�[�p�[�R���f���T�W�߂Ă����ĎςĎ��o���Ă��i��
�X�C�b�`���O���M�����[�^�Ƃ���
�R���f���T�ɔS�y�݂����Ȃ̂��Ă��邪���O�͂Ȃ�Ă����́H
����ɂ��Ă��A�Â��X�C�b�`���O���M�����[�^�̓R���f���T���p���N�A�e�ʔ����������ȁB
���ꂪ�����⍂���g�E���b�v���Ɏキ�������Z���d���R���f���T�̎d�l
���܂����U���~�܂�o�͂��~�߂���Δ����ւ����v���ێ��ł���
�Ɠd���i�̎�����SW�d���ō�荞�߂�ƌ����\��
�����ł������̂��ɂ́A���t�@���ŗ�₷�Ƃ����ȁB
��㉹����OS-220 �g�����X���X �}�W�b�N�A�C�t��5���X�[�p�[�����X�g�A���Ȃ��A
�p���t�B���ܐZ�y�[�p�[�R���f���T�Ɠd���R���f���T�̌����͕K�{�Ƃ���
�I�C���R���f���T(�_�h JCP-A)�̓V���[�g���[�h����Ȃ�����̂܂܂ł�k�H
�������̎���(1957�N��)�̃I�C���R����100��PCB�ܗL�ň��肵�Ă�Ǝv�����A
���������Ƃ���ŏ����ɍ���w
���ዉ�i�̃��X�g�A�͂�߂Ă����A�����T���X�[�p�[
�ዉ�i���܂Ƃ��ɑg�����̂��I�����C�ŁB
>>39�@��Q�i
�i�V���i���L�b�g�i�����i�̊ł�������������j
�����J�[�����W�I�i�~�[�̋Z�p�ȍH��j
�X�^�[���W�I�@�x�m���쏊 �i���̑��}�j�A�����̓\�j�[�̃C���u���V���[�Y�ő��̍��j ���Ԃ����ƃu�c�u�c�m�C�Y���o�郉�W�I�B
���X�����킩�炸�z���G������R���f���T�̑����������B����ꂾ�����B
�܋��X�[�p�[���ăq�[�^�[�̕Б��V���[�V�ɗ��Ƃ��Ă��邯�ǃm�C�Y(�n��)�̌����ɂȂ�Ȃ��̂��H
>>42
�q�[�^�[�d�����āA���̂˂�����łȂ��Ł@�V���[�V�ɗ��Ƃ����肷��H �Б��V���[�V�ɗ��Ƃ��Ȃ����������ƃm�C�Y(�n��)�̌����ɂȂ��Ȃ�
�q�[�^�[�z���̓c�C�X�e�b�h�y�A����ԗǂ��B
�N���{�����[���̃��X�g�A���@�����āB
����2��H2�ړ_�X�C�b�`�t���̒P�A50K��
��Ԃ̓K���Ɖ��ʂ��i���Ȃ�
���Ԃ���C�\�v���A���R�[���𗬂�����ł݂����K�����������������x
>>44 �����s���ł����B�^��Lj�{�Ɉꃖ�����ɃV���[�V�ɐڑ����Ă���B �����ł��邩�����傫����ΐړ_�ʒu�����B
*������x�͎d���Ȃ��Ǝv���Ē��߂�APU��ւ����߂Ď��������H�\�Ȃ�V�i������
��R�́H�̕����C���ł��Ȃ��̂��ȁH���������Ȃ����ǁB
>>46
���A���^�Ȃ̂� CRE CRC226�𐁂�����K���͂����Ă�����B
�����͉�������Ȃ��B ���M�̐c���������������ł��炭�O���O�����玡�肻��
�����R���Ɏg�����d�h���H������炵���������炵���B
������������
���S�܂ňꎞ�I�ɂ�݂������Ă��ꂵ�݂������������Ƃ���
�������Đړ_�������Y�������璼����w
>>42
�X�C�b�`�����āA�������ȃn�����Ƌ��ɕ������������Ă��������A���a���g�����ۂ��Ă����B �傫���X�s�[�J�[���ƃn�����C�ɂȂ�B
�S���n�����Ȃ��Ȃ�Ɖ��������オ�����H�����ŕ������Ă���B
�y�������g�H�m�C�Y�̓��g���b�ۂ��B
�Ӂ[��
�����_���[�h�������畷����ׂł��邩��
�g�����X�̊E���A�X�r�[�J�[�̊E��
�t�B�[���h�R�C���X�s�[�J�[
�NJԂŃm�C�Y���傫�����W�I�͍����x
�I�[�f�B�I�A���v�݂����Ɉ�_�A�[�X����Ƃ����B
�{�a �A���v��(���i)�̕����R���f���T��220�ʂe�Ɍ���������d���n�����Ȃ��Ȃ����B
�����ǂ�����������A���i��20~40�ʂɗ}����ׂ�
���ɃV���R���_�C�I�[�h�ɂȂ��Ă����炢���̂���
���ɔ�א�����̓d�������߂ɏo�邩���R�œK�X���Ƃ�(�g�����X)
�g�����X���X�͂��̍����Ȃ�d���Ő��\������҂ł��邩�炻�̂܂܂ł悢
�Ƃ�����������B�i�^��ǂɂ�����d���͔͈͓��炵��)
���i���Ē���g��H�̏��i�B
�����̏��i����Ȃ���B�����̏��i��10�`20�ʂł����B
�I�N�Ŕ�����5���X�[�p�̃I�C���R�������ׂ�0.1uF�t�B�����ɒu������������A���傱���Ɩ炵�������ŕ����ۂ��Ă���A�����ƒ��������B
�����͒Z�g���s����TRIO 9R-59D�����B
�I�C���R���������A���F���~�Տ�̃Z���~�b�N�R���f���T��
�}�C�J�̃p�b�e�B���O�R���f���T���P���Ă��B
�R���f���T�n�͑S�_���Ȃ��(�L��֥`)
���̊ԁA���߂ăR���f���T�[�̗����������B
�����H�ŁA����50�N�O��TV��10�N�قǎg��ꂽ�Ǝv����0.047��F�i�����j���g�����B
DC100V���C����100k���ƒ���ɂ��ĂԂ牺������A��R�̗��[��20V�قǏo�₪�����B
�i�f�W�^���e�X�^�[�Ōv���B�j
�≏��R�́A�P���v�Z��1M���ȉ��c�Ƃ������ƁB
�Â�5���X�[�p�[�̒���g���i�̓��͑������R���f���T�[��ς���Ɖ������悭�Ȃ�Ƃ����̂��A���Ȃ�����b���B
�i�≏����ƁA�O���b�h���[�N�𗘗p���č���Ă���o�C�A�X���Ȃ��Ă��܂��B�j
�O���b�h��DC�o�Ă�Ƌʂ�����B
>>71
*AV6�͂����������������g������������́B �V�i�̃}�C���[�R�������N�����i�̓��[�N����̂�10%�قnj�����B
�A���v�̂悤��2���c�C�X�g���ƃ��W�I�̋ǔ����q�[�^�[���C���ɏd�āA��������₱�����Ȃ�̂ŁA�q�[�^�[�̕Б��̓O�����h�ɗ����B�i���W�I�H��̊�b)
2�ɁE3�ɂ̕����ǁA���Ƃ���6Z-DH3A,6AV6�̃q�[�^�[�͐ڒn�s���Ńn�����̗ʂ��Ⴄ�B��������W�I�H��̊�{�B�����ČN�͌Â��{��ǂނ��ƁB
>>75
���a30�N��̖{�ɂ͂��Ȃ�̋L��������̂ŁA�w�Ԉӎ������^�C�v�Ȃ�m���Ă���m���B �������ɏ��a30�N��̎G���͂Ȃ��A�A
���̎��������Ďc���������Ȃ����B
���܂ꂽ�N���炢���ȁB
�����m��Ȃ��n�Y�ł�(��)
���������A�R���Z���g��
�v���O��}��������ς��Ă��A�n����m�C�Y���ς���������B
���a30�N�ォ�`�e�������܂�ĂȂ���(���a40�N���܂�)
�ߏ��̃��T�C�N���V���b�v�ɑ�ʂ�2HA5��6HA5�����J��1�{50�~��������
����Ń��W�I�Ƃ��A���v��ꂽ�肷��H
��o�͓͂��
�`���A�������Ȃ�����W�I���A���v���o�����łȂ�
���T�C�N���V���b�v��6080��100�~�Ŕ����Ă����A�g�����X���\�Z�I�[�o�[�Œf�O�B
���t�I�N�ɏo������c
>>84
���̋��͋S��ł���(�L��֥`)
�{���̗p�r�̒ʂ���艻�d�����̂������̂��ȁA�A >>82
�A�i���O�e���r�������ɂǂ��g�����͕ʂƂ��āA�A�����������\�̋��ȂȁA�A
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/04/PC900.gif)
6080�͑����M���Ȃ邩��g�[���˂��炢�����������A���ʂɎg���ɂ͓��B�Ă͂��x��
���͂����炵���B
12AX7-6SN7-6080�̍\���ŃA���v���������B
���ȃo�C�A�X�̃V���O���A���v�����A���������M�ŏo�͂�������3W���B
�ȒP�ȉ�H�ł͎��p�ɂȂ�܂���B
�^�L�b�g���[�J�[�����^OTL����@������Ă����ǁA���i������邱�Ƃ͖��������B
����Ȃ�̋K�͂Əo�͂�ڎw���̂łȂ���A���̋��������Ďg�����R����������Ȃ��ˁB
������������ǁc�c
>>83 >>87
�Ƃ肠����6HA5��4�{�A2HA5��1�{�����Ă���
6HA5��2�{�g����YAHA�A���v������Ɏg���邩�ȁH
2HA5�̓v���[�g���g�̋L�������������炻�̂܂ܑg��ł݂�
��H�v�ł��Ȃ���������̉�H��g�ނ��Ƃ����ł��Ȃ��E�E�E 6080�̓ʂ�������2�����Ȃ�����A�h���C�u����̂ɑO�i�ł��Ȃ�Q�C����
�҂��Ȃ�����Ȃ�Ȃ��̂��v�����Ƃ���B
>>90
YAHA�łȂ��Ƃ��w�b�h�z���A���v���炢�Ȃ疞�������������o�邩�͂Ƃ������Ȃ炷�̂͏o����B
���W�I���g�����X���X�̍Đ����g���ƃv���[�g�d��20~30V���Ă̂����邩��d���d����50v�ȉ��ɂ��ă`���[�N���ׂɂ���A�����Ƃ��ď[���ŁA����̑ψ�50v���i���g���邩�炢�낢��Ǝ�����B
���x�����������邩�������ǁA���ɂ���Ă�12v�ōĐ����g�o���Ă邩��A�����܂ŗ��Ƃ����Ƃ��o�����AF������386�ӂ�ɔC���ăX�s�[�J�[�쓮���y���߂��łȂ��H >>92
��H�T���Ă���Ă��肪�Ƃ�
2HA5�����X�g�ɓ����Ă�̂ˁB�������������ė��悤w
>>93
���������ΐ̂̃J�[���W�I��12V�쓮�������炵������A
����l���Ȃ��Ă����Ƃł��Ȃ邩
������2HA5��2V(�V�[�����{�d�r)�Ńv���[�g���g���Ă݂���
NHK����NHK���1N60��3���������x�̉��ʂŎ�M�ł�����
�����̓N���A�ȃQ���}�ɔ�ׂĂӂ����炵������ 5MHH3���̃e���r���ŃA���v����Ă�ˁB
�����s�Ŏ��X�����Ă邩�炠���������Ă݂����B
�����A�����o�͊ǂƂ��_���p�ǂŃ��W�I�g�l���Ă���̂��ȁH
�����n�ȊO�̃e���r�����ĐV�i�ł�1�{100�~�Ƃ��ŗp�r�����낤�ȁ[
�����ǃR���o�[�^�����삵����͌��\����Ă�
��ς����Ǐo���Ȃ����Ƃ͂Ȃ����ۂ�
EH7 �͎g���₷�����ƌ����Ă��������ɉ�H�}�]�����Ă����
�� TV�p���������L���ɂȂ�ƕ����ăR���N�V�����̐^��ǃJ���[�e���r(����i)
�Ƃ����Ɏg�������ȋ������̃e���r�̋X�y�[�X�ɓ˂�����ŕs�R���݂̓���
�̂ĂĂ��܂����̂����ƂȂ��Ă͉���܂��B�e���r�̋��Ȃ��W�I�Ɏg�����Ƃ�
�S���v���Ă��Ȃ���������B
*EH7��SG�d�����߂ɂ���Ƃ���6BA6���炢�ɐ��\�𗎂Ƃ��Ǝg���₷���ł��ˁB
�A���v��TV���g�����Ⴊ�����Ă��Ă��邵�A
���̂���TV���A���v�A���W�I���W�Ƃ��o����
���̓G�A�o���R���AIFT����
�g�����W�X�^�p�����܂Ő��Y�����̂��킩���
�Ƃ���Ō���Ȃ��Ȃ����g�[���[6E5D�̊��p�@����H
>>102
3�Ɋǂ̕����ʂ�3�ɊǂƂ��Ďg���܂��B
�^�[�Q�b�g�d�ɂ�2�ɊǂƂ��Ďg���āA6Z-DH3A�̑���ɍ����Ƃ����g������������w >>101
�e���r����FM���W�I���ɂ͂�����Ȃ����H >>103
���[���������ΐ̉����̖{�œǂ悤��
>>104
FM�X�e���I������ƂȂ�ƁE�E�E��ς��� �X�e���I���Ăǂ����̂��ȁH�Ǝv������RCA�̎�M�ǃ}�j���A����RC26�ɃX�e���I�����̗Ⴊ�������B
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org867472.png)
���������Ȃ�(�L��֥`) >>106
�������������̂ɂ��邵���Ȃ��̂�
������pIC�o�Ă�̂��ȁH 19kHz��38kHz�̃g�����X�i�R�C���j���Ȃ��E�E�E
�����Ŋ��������Ȃ�����
�p�C�I�j�A��AM/FM�X�e���I���V�[�o�[������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/EGh3OYU.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/Ded9PrT.jpg)
����ρAMPX�̕����͓�������Ȃ��A�A
�X�e���I�̘b����Ȃ����ǁAAM/FM���W�I�͉��B���̕��������I�ɂ������肵�ĂĂ�����ˁB
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/FMprot2-sch.jpg)
>>110
���������Ő���ӗ~��D����З͂������Ă��
����AM�͕������������������K���K������Z�g�͉p�ꂶ��Ȃ����A
���m�����ł���������FM�g�݂����ȁBTV���g���Ĉ�����w �Z�g�̉p�������5���X�[�p�[�ŕ�������̂�BBC�A R.�I�[�X�g�����A�AR.�j���[�W�[�����h���炢���ˁB
���{�C�������璆�ؘI�̕������蕷�����Ă���
�G�߂ɂ�邪�A�C���h�̉p�����������@���x�ł���������ȁB
�����̃X���ŕ����Ă����̂�������Ȃ����ǁA
���[VHF�̃��V�[�o�[��^��ǂőg�݂������d�r�ǂŎ��삵���l���Ă���H
AF������IC�ł��������ȂƂ��v���Ă�
>>113�@�܂�MW/SW�͊�����12AV6 30A5 35W5��12AX7A(12AX7(T)) 30A5x2 50��5W��
�u��������ΊȈՃX�e���I�ɂȂ�B SP2�P���Ă���Ȃ���ăX�e���I�ɓK�p������̂܂g����B
���W�I���̌��g�̓Q���}�_�C�I�[�h�ōs�������o�͂������o���ă^�J�`�̃A���~�̏����Ƀ��[�^���[�X�C�b�`
��t����AUX�Ɗ��S����������W�I�̔���ւ��Ȃ��Ă��ςނ̂ł͂Ȃ����낤���B ���i�I�ɂ͎O�H 5H-662�������Ă��Ȃ��̂����A��H�I�ɊY������B�@���R�[�h�v���[���[��
�X�e���I�Z���~�b�N�s�b�N���g�����������疳�ɐ��R���f���T�Ő≏����
�����Όg�щ��y�v���[����������B(���ʂ͏������߂ɂ��Ȃ��Ƌ��̓��͂��s�����������j
http://oomaguro.eco.coocan.jp/radio/radio173.htm �O�H 5H-662����NFB���������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/11696ssch.jpg)
>>120
S3�́A�d��ON�|NFB�A�җʏ��|NFB�A�җʑ�@�̐�ւ����ȁB�@�Â��Ă�ȁB ���B���̃��W�I����NFB�ʼn�������������Ă�̂���܂���ˁB
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/nordmende/nordmende_carmen56_am-fm_radio_sm.pdf_1.png)
>>122
�J�\�[�h�̏������� [���Ɓ�] �̂Q��ނ���̂́A�����Ӗ�������̂��ȁH 5���X�[�p�[��12BA6���G�~���A�Ƃ������v���[�g�̐茇�������ɖʂ���
�K���X�Ǔ��ǂ��g���Â��̃O���[�����݂ɃM���M�����Ă����
�d���グ����g���邩�ȁH
>123
���͒��M�ǂ̃q�[�^�[�ł͂Ȃ��ł����B
���̕Е����Z���Ȃ��Ă��āA�O���ɂȂ����Ă��Ȃ����
�J�\�[�h�̉\���͂���܂����A
>>123
�Ȃ�قǁA�A�����Ȃ��Ă܂��ˁB
�ǂ������g�������Ȃ낤�A�A�H�H >>125
�}�ʂ̉����ɂ���Nj��[�q�����}�ł́A�S���T�M�ǂł���ˁB
ECC85��ECH81�����J�\�[�h�����ɂ���K�v�����킩��Ȃ��B
�P�ɏ������l�̋C���Ƃ���̖��H �J�\�[�h�̕����I�`���\�����Ă�A�Ƃ��B
50EH5���g�����A���v����y�ł����ȁB
�^��ǎg���ďo�̓g�����X�����Ńw�b�h�z���쓮������ɂ�YAHA�A���v���������́H
���A6BA6�ŃO���b�h���g����6DJ8��NJM4558�Ńw�b�h�z���炻���Ƃ��Ă�
�A���e�i�R�C����SL45GT�A�o���R����260PF�̒P�A
�w�b�h�z���Ȃ�J�\�t�H���łȂ�Ƃ��Ȃ邩�������ǁA���W�I�p�Ȃ�B�d��50V�ʂŃg�����W�X�^�p�̃g�����X�g������H
12BH7A�ŊȒP�ȃV���O���A���v������������邪���X�ǂ������B
���ʂ͂��Ȃ菬�����B
�悭�g�����W�X�^�p��OSC���Ƒϓd��������Ȃ����疳���ƕ����܂������ۂ̂Ƃ���͂ǂ��Ȃ�ł��傤���H
>>133
OSC���ċǔ��p�R�C���̂���?
���Ƃ�����A�^��Ǘp�ƃg�����W�X�^�p�͍\�����̂��Ⴄ
�g�����W�X�^�p�̓R���N�^�[�������U��H
�^��Ǘp�̓n�[�g���C���U��H
���M�̓d�r�ǂȂ�g�����W�X�^�p�Ɠ����\�������ǂ� �ԈႦ�܂���
�g�����W�X�^�p�̓R���N�^�[�������U��H�ł͂���܂���
>>133
6SA7���g�����X�[�p�[�̎��g���ϊ��ŒZ�g�p��FCZ�Ⓦ���R�C�����g�������ǂ������傤�Ԃ�������B >>136
�ӊO�Ƒ��v�Ȃ�ł���
>>137
���ꂾ�ƊȒP�ɍ�ꂻ���ł���
���肪�Ƃ��������܂� �g�����W�X�^�p�̃g�����X�ł����Ă�20����50V�͑ς��邵�A�M�������̑ψ��z����傫���ɂȂ�Ȃ�Ă̂̓X�s�[�J�[�Ȃ炷�d�͑����i���炢
�ꎟ�n�Ɠn�A�V�[���h�P�[�X�ɒ��ڍ�������Ȃ��悤�ɃR���f���T�Ő��Ă��Ε��i�Ƃ��Ă̑ψ��ȓ��ɔ[�߂邱�Ƃ͏o����Ǝv��
�g�����W�X�^�p�͒�C���s�[�_���X�O��Ƃ��Ă邩��^��ǂ��Ɩ����������ɂȂ邩��
�b�ς�邪�A�ψ��Ƃ����ƁA�^��ǂ�[�J�\�[�h]�|[�q�[�^�[]�Ԃ̑ϓd����
100�`200�u�ʂ����鎖���s�v�c�ȋC������B
�ǂ�����Đ≏���Ă��H
���̐≏���Ȃ�100V���炢�͂��ł���
�≏�w���M��U���Ŕ�����Ȃ��悤�ɕi���Ǘ����Ă邩�ǂ����łȂ����Ȃ�
>142
1934�N�Ɋ��s���ꂽ�k�d���y�^��ǁx�ɂ��ƁA�^��ǂ̔r�C���s������^��|���v�ł�
���⒌��1�����̂P�~���͗e�Ղɓ�����Ƃ̂��Ƃł��B
����͋C���Ɋ��Z����ƁA
�P�D�S�~10�O-7�C���ɂ�����܂��B
>>143
��O�̖{����Ȃ����X�Q�[ �}�O�l�`�b�N�X�s�[�J�Ȃ�ok
�}�O�l�`�b�N���č�������̂��ȁH
�ꂽ�ׂ������������ďC������l�������B
������n�C�C���s�[�_���X�̃w�b�h�z���~�����B
�}�O�l�`�b�NSP�͎q���̍��A�Ƃɂ������Â����l�ɂ��Ă����B�\����U���X�g���[�N��
���Ȃ��̂ňꐡ���ʂ��グ��Ƃтт肾���A�����͎q���̎��ŕ����Ă��@��E�悤
�ȃ��S���S���������̈������������B
�ǂ����ɋ��U�̃s�[�N������悤�ȉ������܂����
>155
2,000Hz����3,500Hz������Ƀs�[�N������܂��B
�Â�����@�Ń��[�h�����m��Q���Ă���̂����邯�ǃR���f���T�̑���H
FM�`���[�i�̃~�L�V���O�Ń��[�h���ԗe�ʎg���̂�������
���t���b�N�X�̋A�җp�L���p�V�^��P������Ă̂͂悭�������ȁB
�a�e�n�̃J�b�v�����O�ł���Ȃ̂���Ă��ȁB
>>159
����c�C�X�g������Ȃ��āA�ǂ��ɂ��q����Ȃ�����2cm�قǔQ���Ă���
���肵����1pF���炢�Ȃ��Ǎ��ψ��R���f���T�̑��肩�Ǝv���� ���e�ʍ��ψ��R���f���T�̑���ł�
�������L���������^�}�C�J�R���f���T�͍����i�������̂��ȁH
���[�h����p���e�ʍ��ψ��R���f���T����1KV���炢�ς����̂��낤��
>>161 �̃j���[�g���h������Ȃ����H
�����̖{�œǂC������ �j���[�g���h�����g�������W�I����Ă݂����B
12AU7�Ƃ��ł�����̂��ȁH
�����q�����˂��ꂻ���Ȋ�Ȃ����O��
�j���[�g���_�C����M�@�̉�H�}�A�A�A�A
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/egyeb/freed_eisemann_nr-5_nr-6_battery_receiver_sch.pdf_1.png)
���̎���̂�͌��Â炢�ˁA�A�A �q�[�^�[��H��]����������A���[��s�v�c�B
���Ă�ƁAC�d�r�ɂ��o�C�A�X�͒���g�����ɂ͂������Ă邪�����g�����ɂ͂������ĂȂ��̂ˁB
�f�l�ŃX�}�k�����W�I��V�삷�鎞�R�C����o���R���͂ǂ�����́H
20�N���炢�O�Ȃ�g�����X���X���W�I�������������i���o�����B
�j���[�g���h������������L�����ĂȂ����ǁA�Ӗ����Ȃ������̂��낤���H
��178
�j���[�g���h���̐���L���͂����B
�������A���ł͂Ȃ����A
�����P��w��������M�G���~�l�[�^��M�@�v�Ƒg���x�i1929�N�j
�ɂ́A�j���[�g���h�����g�����u�j���[�ƃg���_�C���v�̋L����
��t�̂��Ă���B
���Ȃ݂ɁA�u�G���~�l�[�^�[��M�@�v�Ƃ����̂́A
�𗬎���M�@�̂��ƁA
�ƂȂ�̃j���[�ƃg���_�C��
�A���e�i����������e�����鐢�т�����
��������Ă��Ȃ��O���A���e�i�����X�[�p�[�w�e���_�C�������킢���E�E�E
�G���~�l�[�^�[���ă^�[�~�l�[�^�[�݂����ŃJ�b�R������
TV�����g�����A1�`2�����x��FM�������͒Z�g���W�I���Ăł���?
�C���z����p�̃|�[�^�u�����l���Ă�
1�`2����FM�Ȃ璴�Đ��ɂ��邵���Ȃ�
>>184
���Đ����Ɖ������ė�����?
3�`5���ł��ǂ����ǔ@������^��Ǘp��IFT��o���R�������荢��
�v���[�g�d����50V���炢�܂ŗ��Ƃ�����TR�p�g���邩��? ��������Ă���Ȃ��B�c�݂��悤�Ȃ��́B
>>186
�}�W���c�d�r�ǂ�3�`4��FM���W�I���Ă������̂���? ���d�E�n�����Ń`���[�i�[�Ƃ��Ďg���Ȃ�
�ǔ�1,����1,��1�Ƃ��ă_�C�I�[�h���g�Ȃ畡���ǎg�p�łQ���ɂ����܂邩���m���B
���ʂ͒�2�ɂ��邾�낤���A�ߍ���FM�ǐ����Ƌǔ��R�ꌸ�炷�̂ɍ�1�͂������Ƃ���
�g�����W�X�^�p�̕��i�̓g�����X���X��100v�����p�ɂȂ��Ă��킯������H�v����B�d�������ɂ�����Ȃ��悤�ɂ���Ύg���Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤���ǁA���͘A���o���R�����Ȃ��B
�g�����W�X�^�p�͎Օ��Ȃ����甭�U��������m���
>>187
��������B���B���[�J�[�̒��������W�I�ɂ� >>188
��H�}��������Ȃ��c
>>189
IFT�̓R���f���T��������̂���? >>185
IFT�͎����Ŋ����Ηǂ��B455k��肺��y���B�@�n�l�J���s�v�����B
�Ƃ肠�����P�����ł����A�}�C�N���C���_�N�^�[�ƃg���}�[�ł�ok�B
�o���R����TR�p��ok�B�@�^��ǂ�TV���Ȃ�������ǂ�����y����B
�������̂��ƁAIF��30M�ʂ܂ŏグ��Ƃ�������݂�B >>192
�芪��!?
�m���ɂ�������ƂȂ��������v���邾���ŁA
����Ă݂�ƊȒP�Ȃ̂���? �T���̃C���_�N�^���X�𑪂��A�������͑債�����Ɩ�������o����Ǝv���B
���ƁATV�p��4.5M��IFT�ł������ˁB�@�g���b�L���O�ō��킹��Ύg����B
���g����A���b�N�h�I�V���[�^�[�Ƃ��Q�[�e�b�h�r�[���Ƃ��s�[�N�f�B�t�@�����V�����Ƃ�
�F�X�݂邩�猟������Ɗy�����B
IF������Ɖ����ăp���X�J�E���^�[���o����Ǝv���B
���j�^�[�̗�A�ɕ��d�ǂ̃g�����X��������Əł�����Ŋ������������Ȃ炠��
�����[�ׂ̍������������ɓn���ăR�A��d�h���ʼn�
�T�u�~�j�ǂ�FM�X�[�p�[���W�I������l�̓g�����W�X�^�p�̕��i�ł���Ă��
���傢�X���`�����m���
���W�I�C���Ɋւ���X������������Ȃ������̂ł����ŕ������ĉ�����
�ԍڗp�̃ʓ������̃A�i���O���W�I�̎�M���g�������Ԃ����Ə���ɂ���Ă��܂��̂���
���������Ȃ낤�H
�^��ǃ��W�I�Ŕ��M�Œi�X�������������Ă̂͒m���Ă邪
��������Ȃ��ă��W�I���Đ��\�����炢�����Ă�Ǝ��X�ˑR���g�����ς��
�j�͓����ĂȂ�
���������ꂽ�Ƃ��̓_�C�A����50�`60KHz���炢��̎��g���ɂ܂킷�Ǝ�M����
�C�̂�����������Ȃ�������������Ă�Ƃ��̕������x�����悤�ȥ��
�����g�n�̐ڐG�s�ǂ���i���̃\�P�b�g�Ƃ��j�H
���M���ċ������c������ƐڐG����Ƃ�
>>201
9R-59D�ŋǔ���6AQ8�܂��̃R���f���T�̕s�ǂł������������ɂȂ������Ƃ��������B
��M���g�����҂��҂����ł��B
�R���f���T���������ĉ��������B �݂�Ȃ��肪�Ƃ�
�����S����������Ȃ��ĐȂ��
�ԍڗp�ŋ������W�I�Ȃ�ĂقƂ�ǎ�ɓ���Ȃ���
�ԍڗp�œ`���Ǝv���������t���炸��������
����ς�R���f���T���Ȃ����
�X���^�C�̂ǂ����ǂ������烉�W�I�����X���Ɍ������
�R�ŃR�A���쓮�H
�j�͓����ĂȂ��Ă������|���肪�����ĉ����̔��q�œ����Ă���̂����B
�P�~�R�����e�ʂʂ����ĂĎ��Ԃ������Ĕ햌���č\������邱�ƂŐ≏�Ɨe�ʂ��������Ĕ��U���g���������̂���
�X�[�p�[���낤����ǔ��̎��g���ϓ��ǂ�����ǔ��̕ω��Ȃ̂��A�������̕ω��Ȃ̂����邩���m��Ȃ�
�^��ǃJ�[���W�I����������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/59/48/bea47990db16e67e6e257e7f6e719c09.jpg)
>>208 �̂̃J�[���W�I�́A�قڂ���ȃf�U�C���������ƁB
�J�[���W�I���ăK�b�`������Ă���ȁB >>209
���[NISSIN�̃o�C�u���[�^�����Ă邪
�܂����A���W�I�ɂ��̑����Ƃ̂𗧂Ă�̂��H
401��H���Ȃ̋L���́A�o�X��MIC�A���v���Ȃ�
�ꏊ������Ă��ǂ��@�B���Ƃ����Ƃ���
�Ƃ������A���W�I�ł��m�C�Y�łȂ��̂��ȁH >>209
���[NISSIN�̃o�C�u���[�^�����Ă邪
�܂����A���W�I�ɂ��̑����Ƃ̂𗧂Ă�̂��H
401��H���Ȃ̋L���́A�o�X��MIC�A���v���Ȃ�
�ꏊ������Ă��ǂ��@�B���Ƃ����Ƃ���
�Ƃ������A���W�I�ł��m�C�Y�łȂ��̂��ȁH �d�r�ǃ��W�I��DC-DC�R���o�[�^�g�����Ⴊ���邯�ǃm�C�Y�o�Ȃ��́H
���Ԃʂɏo���Ȃ�����
��߂����������Ƃ͎v��
�Ă��u�����Ȃ�v�̃^�C�~���O�̖�肾��B
�u���b�N���ɑg�オ������ڎ��A���ʃ`�F�b�N�̂��Ɓu�����Ȃ�v��d�����Ȃ��Ńu���b�N�̓���`�F�b�N���Ă��邯�ǁB
�^��ǃ��W�I�̗��W�̊O�������킩��Ȃ�
�^��ǃ��W�I���₵�Ȃ���g���Ă���l����H
AM���[�v�A���e�i���g������l����H
�^��ǃ��W�I��A���v�Ƀt�@���t���Ă�̕��������Ȃ��ȁB
���[�v�A���e�i���\��������
��������ז��ŁA�O���Ƀ����O���C���[�����Ă�B
>>226
���������T�C�g����������
>>227
�����O���C���[�̕����ז�����Ȃ��H nhk��ꂷ���M�ł��Ȃ����
���Ȃ��M�ł������
>>225
���[�v�́A90cm5mm�p�̃q�m�L�_�ō�����g���C�A���O�����g���Ă�B�ӂ���́A�ǂɂ����Ă���B
�����A�������ŕ��������̂�����Ƃ��A����Ȏ��ɂ����o�Ԃ͖��������B
���ʂ͐��ƌ����Ă������炢�A�������ǁB
���[�v�͂ł����̂ƁA�w�����̖��(�ǂɂ���Č����ς�)�ŁA�ז���������B
���C���[�́A���W�I�܂��͐����������B >>230
�ł����˃��[�v�A���e�i�����Ə������̂��� >>231
���x���l����A�قڃ��|�v�ʐϔ�Ⴞ����A�t��TV��ʂ��炢�̑傫���͋��e����Ȃ��́H
�Z��W�n�ŋt�G���Ŏ��ӂ̃m�C�Y���E���Ă���̓}�V�ȉ����B
�E�����Ă��Ƃ� I ��Q�������B��Q�҂������ɋC�t���Ȃ��ď������Ă���B �ʐM�@�^��M�@�ł��t�@���͕t���ĂȂ��B
���M�@�Ȃ�t���Ă�ƁB
>>228 ���[�v�͎����B
�O�Ȃ�ז��ɂȂ�Ȃ����A���[�e�[�^�[���K�v������˂��B >>233
�A�}�`���A�����̐���L���ŁA�����P�[�X�̑��M�ǂ�
����ő�d�͉������̂��������Ƃ�����B >>235
����I80�̌�V�̑��y�I(w
���^���ǂɊʂ��n���_�t�����Đ���A�ʏ�Ȃ�A�m�[�h���͂Q�TW���A
�{B�d�����v����グ�ĂT�OW�`�P�O�OW�˂����b���o�b�N�i���o�[�Ƃ������A�ÓT�œǂ�(w
�u�����Ǝ����v�����������u���W�I�Z�p�v�����������肩�łȂ����A�W�����N�s��͕ČR���o���^���ǑS������B
�����d�͂Ƃ��Ă�A3��10W���u�ԓI��20W�`40W�ő��M�������Ęb�ŁA
���̔��펯�I��@�^�p100W�`kW�Ƃ͔�r�ɂȂ�Ȃ����K�̓A�}�`���A�����B >>232
�܂�NHK��ꂪ������������炢�̃X�^���X������
�s�̂̏�������ł�������TECSUN ��
����ł���������NjZ�p���Ȃ�
>>234
������ �����ČN�Ő\����Ȃ���
�^��ǃ��W�I��AM�A���e�i���ĕW���A���e�i�͍���12m����8m����������
�����12m�̍����ɂ��������ɃR�[�h�ł���������̂��H���W�̊G�͂�������Ȃ����ۂ���
������Ē�����Z�����邱�Ƃ��ďo���Ȃ��̂��H
���ƃ��[�v�A���e�i�̏ꍇ�ǂ��q�������H���[�v���̗��[���A���e�i���ƃA���e�i�A�[�X���Ɍq���ł����ʂ��Ȃ���
�������Ƃ��S�ʼn����ɓd�g�����Ȃ��Ƃ����I�`�ł͂Ȃ��ؑ������牮���ł��ʏ��M�͉\
>240
�W���A���e�i�̎d�l
�������F���a0.8mm�����b�L�����V�{��荇�킹�����́C����12���C����8m�B���[���V�q�ŁC�|�[���Ɛ≏����
�������F���ɂ��ẮC���Ɍ��y���Ȃ����C�������Ɠ����Ǝv����B
�A�[�X�F�n����Pm�̏��ɁC0.3m�~0.3m�̓��ł�����B
���̃A���e�i�̒萔�́C1000kHz�ɂ����āC
Ra��50���CXa=-1000���C�������F7m
�w���W�I�v�H�w�x�i�h�쏼��E�����ǁE�����C�������V���ЁC1951�N�j���
��241
�u�����v�͉��₩�łȂ��ł��ˁB�u���݁v�̌��ł����B
���炵�܂����B
�A�[�X�̉��ɒY����Y��Ȃ��ŁB
>>241
�T���N�X
�����ƒ������t�������Ȋ��Ⴂ���Ă�
�����Ⓑ����Z������Ǝ��s�����������Ċ��x�������邾�������
����Ƃ����̐��@�Ŗ����ƃA���e�i�Ƃ��đS���@�\���Ȃ��Ȃ�́H >>247
���W�I�̐��\����Ƃ��̕W���Ƃ������Ƃł́H >>240
������O�ɂǂ�ȃ��[�v�A���e�i�Ȃ��ł邩���� >247
�����́C���W�I�����肵�Ă�������C���̂��߂̕W���Ƃ��đ債���������Ȃ�
��߂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���B
�Q���}���W�I�ɂ悳�����ȃA���e�i���ȁB
�c�ɂ��������A�W���A���e�i�������ȃA���e�i��
�グ�Ă�ƌ������Ȃ��B
7MHz�̃_�C�|�[���͌����ȁB
�g���ɑ��ĒZ�����邩�狤�U�Ȃ�Ă��Ƃ͍l���ĂȂ��Ăǂ��炩�ƌ����Α�n�Ƌł̓d�E�ω��𑨂���d�ɂƌ����ׂ����́B
����������ԂȂ炱������������Ĕ�r�̂��߂̊�Ƃ����Ӗ������Ȃ��Ǝv���Ȃ�
�T���N�X
�W���A���e�i�͂��̖��̒ʂ肠���܂ŕW���I�Ȋ�ł����Ȃ��̂�
����������Ə_��ɍl���Ă݂��
>>249
�ŋ߂̃R���|�Ȃɂ��Ă���悤�Ȏl�p���^�C�v
�ł������悭���Ԃ��Ă݂�Ƃǂ����傫�����S�R����Ȃ��悤��?
�Œ�ł��t���e���r���炢�̑傫������Ȃ��Ɗ��x�҂��Ȃ����Ă��Ƃł����H >>254
5���X�[�p�[�Ȃ炻���܂ł���Ȃ���Ȃ��́H �����̋ʉ�����
�^��ǃ��W�I�ł������l����H
�����Ɠy���������낤�ȁA�I�}�G��B
���ɂ��É��̌�O�ł��邼�I
�Ԃ����Ⴏ�A�V�����̂��ƂȂǁ[�ł��������[�́I
���Ă̂��z�E���E�l��
�������u�Ń`�����l���ς��������킗��
����[�ǂ����@�����A���̓V�c�́@���q�@�ɂ����I���E�V�c�̂��w���ŁB
>>252
�������͐�������
���͓d������1KV 100PF�̃}�C�J����ł邯��w
�{�d�������Ɏʃ����ł��̃R���f���T�g���邩�ȁH
����122��F�őψ���300�`400V���炢���Ǝv�� ���꒷���Ԃ̗��p���l�����ĂȂ�����@������X�����B
�|������A���}�C�g�̊ʂɓ���Ď�������H
>>261
���W�I�Ȃ�{���ɂ���K�v�Ȃ����낤���A�I�[�f�B�I�p�Ȃ烊�v���d���I�ɓ����Ȃ��H
���G�l���M�[�����ꏊ�͈��S���̓P�`�P�`���Ȃ��������� �ʃ����ł��̃R���f���T���I�[�f�B�I�Ɏg�������������T�C�g���L�������nj������
>>262-264
�t���b�V���p�͘A���g�p�Ɍ����ĂȂ��̂�
�ʐ^���Ɋ�������ς��]�����Ă��đS������Ă��������w
�p���ڑ�����12V���炢�Ȃ���Ȃ�����
�����͈Ⴆ��SMG�N���X���낤�����͗ǂ��Ǝv�� >>265
���삵�āA�������݂Ă�O�Ŏg�����ɂ͂��܂�S�z�Ȃ���B
�t���b�V���̍����Ȃ�ēd�r���Ȃ��Ȃ�܂Ŋ|������ςȂ����o��̐��i�����炻��ȂɃ�������Ȃ��B
���M�����������Ύg�p����߂�ł���B
���������Ή������҂ł��Ȃ����l�ɂ���Ă̓C�J���B >>266
���S��150V�܂łŎg���Ă݂�B���肪�Ƃ��B >>263
���b�v���ߑ�͂����܂��ɂ��ėe�ʔ�������I�h��ɉ����Ȃ������S���K���ɂȂ��ĕ����Ɋ����Ȃ������B
�ԍڊg����ōł��g�p�䐔�������̂��I���p�B4�N��1�x�A��ĂɎg���Č�͑q�ɂɖ����Ă����A
����10�����g�������������肾����A1��10���ԃt���Ɏg�����Ƃ���100���ԂȂ��A
���ꂪ�I���Q�`�R��Ō������e�ʔ������Ă��܂��B
�@�d���d����13.2V�����A�����o��60W�i100Wmax�j�AB��PP�o�̓g�����X���Ȃ��A
�d���R���f���T�[��2200��F�`3300��F���炢�������B
�o�͌���60%�Ƃ��āA�������͂͐���100W��7.6A�A���̎��̉������v���d����10A�O��ɂ͂Ȃ�B
�Ƃ��낪�A�R���f���T�[�̃��b�v���ϗp�K�i��1.8A�ƁA2A�ɖ����Ȃ��Ǝ�ȃ��m�������B
����Ȃ�őI��2��Ńm�b�N�A�E�g�I�Ɨ��������B
�j�`�R�������S���A�E�g�ŁA�j�b�P�~���������c���Ă��B
CEATEC�̓W���u�[�X�Ńj�b�P�~�̊J���ɉ����Řb���ƁA
�g�����������A�ύ����v���^��3�{�قǕ���ɂ��Ďg���Ƒσ��v�������傫�����シ��B
�j�`�R�����������I���Ĕ��f�͉��z���A���ăe�L�ɑ��ėD�����́B
�@���͑σ��b�v�������˓��d�����l�������ɓ�����H�����肵�đ僊�v���Ή��v�ɂȂ��Ă邪�A
�u�j�`�R���S�ŁI�v�͏Ռ��I�������˂��B�������A���v�̓P�~�R���Q�`�R�{�p���ڑ��ɂ����B �Ȃ�ق�
�I�[�f�B�I�����ǁA�������P�~�R��������������ׂĎg������Ⴊ��������
����͉�H�v������l���J�X���������Ď��H
���N�ʼn������ǂ��v�Ƃ�������
>>270
�����̃l�B�܂������b�v���K�i�̉��{������Ă�Ƃ͎v��Ȃ������B>>271���ˁI(w
37���~������ԍڊg����A���v�Ƃ��Ă̓v���p�̓��̓g�����X�Ȃǂ��g����
�ō����i���������A�I��3��A8�N�Ŏ����͒ɂ������I
�A���A���ɗႪ�Ȃ����i���������A�j�b�P�~�g�p�̂͂����`���b�ƒ�������������A���i���[�J�[������ޏ����s�ǂł͂���B
�|�M��2���~���Ă��������c�}�Ȃ́A�I������тɐV�i�B���Ă��݂����ŊW�Ȃ������B
�@�ނ�10�N20�N���x���x���g���v�����^���A�}�����肪�����ڂɑ����āA�C���ɋZ�p���̎x���҂��哮���B
�ł������I�ɃG���C�l�́A�Ɠd���o�Łu�����ē��R�v�Ǝv���Ă邩��A�K���ɒ����Ă�x���҂�
���Ɏז��ɂ��ꂽ�肵�ėǂ��ʂ̔�(w�B �q�[�^�[�d����2V��4V�̐^��ǂŒP�����W�I����肽���Ǝv���Ă���A
�d����3V��6V(�K���ȏ��^�g�����Xor���d�r)�œd���~�������鎞��
�_�C�I�[�h������ɓ���ēd���~����������@���Ă��肩�ȁH
>>273
��������͂悭�g�����ǒ�d���q�[�^�[�ǂ͓d���H�����畡���q���Ƃ��ɏ���d�͍l���Ȃ��ƕ��M�ł����ɉ��鎞����B
SG�ł���Ȃɓd������Ȃ���1W�ϓd�͕i������Ȃ�Ƃ��Ȃ邾�낤�ƃc�F�i�[���Ă�����w
SG�{�̂ƃs�����q�����{�����Ռ`�������Ȃ��Ă�www �Z�������āAVf�����́H�V���b�g�L�ڍ�������Ⴛ���ȋC�����邯�ǁA���ꂾ���d���~��������̂ɉ����K�v�H
2V��4V�ŒP�����W�I���ƒ��M�ǂ���ˁH
���������ނ������̉ϒ�R����g�������Ƃ��낾�Ȃ�
>>275
��Ԃ̂��c����͂���Ō��Ă݂����悤�ȋC������
>>277
����TV�p�̖T�M��
�������̎��q�[�^�[�ƒ���ɓ��d�������邩�� >>278
�𗬂Ȃ�A�R���f���T�[�����܂��������B
�������A��d���Ȃ̂ŃR���f���T�[�̒�i���ނɗ��ӂ���K�v����B
>>���d��
���d�����͒�R�̕�������B
���d�����q�[�^�[���A�₦�Ă���Ƃ��͒�R�l���Ⴍ�ĉ��܂�ƒ�R�l�������Ȃ�B
���������āA���b�V���J�����g���傫���Ȃ肪���B
�i�������A���d���Ɛ^��ǂ̃q�[�^�[�̓����ɂ���Ă͒�R���悢�ꍇ���l������B
�������A�������Ȃ��Ɖ��Ƃ������Ȃ��B�j >>279
�J�b�g�A���h�g���C���c
���낢�����Ă݂��A���肪�Ƃ� KORG�ƃm���^�P���J������VFD���p�̑o�O�ɊǁA���W�I�g�߂邩�ȁH
>>281
2FET���f���A��FET�̉�H�ɒu��������B �d���Ƃ�Ȃ�����C���z���p���Ȃ�
�����Ȃ��ƁA�l������ˁB6E5�̒P���Ȃ��������Ƃ���B�}�W�b�N�A�C�����g�ł�����A�����͈ꏏ���B
�������Ă݂�ƁAVFD�ō����g�������Ă�Ƃ��͑O�ɘb�̂�����
�j���[�g���_�C���ɂȂ��Ă�ˁB
�Ƃ������Ƃ̓}�O�l�g�������������O���ΐ����ǂƂ��Ďg����̂��H
����ł��B
ST�ǂ��烁�^���ǂ��o��GT�ǂ��o�������킯�ł����A�Ȃ����^���ǂƌ����X�e�b�v���K�v��������ł��傤���B
����������ST�ǂ̃K���X�ǂ�P���ɏk������Ɖ������e���������ł��傤���H
>>291
�R�p�I
��r���g�p�ō��������ł��Ă����Ƃ��Ă����Ȃ��I
���{�ɂ͐��Đ�̌R���o�i�E�������i�Ƃ��ē����Ă��ĕ��y�����B
�ČR�̓��[�Y�Ńo�Y�[�J�C�܂ňŎs��ɉ��������āA�����������B >>292�@�ǐL
���^���ǂ̋K�i���̓K���X��GT�ǂƓ����������͂��B >>292-293�@���肪�Ƃ��������܂����B
����Ɏ���ł��B
ST�ǂ��o�ꂷ��O��S�ǂ�AST�ǂł͓d�ɂƃK���X�ǂ̊Ԃɑ傫�ȋ�Ԃ�����܂����A����͂Ȃ��Ȃ�ł��傤�H
ST�ǂ͓����i���ēd�ɍ\����≏����Ďx����悤�ɂȂ��Ă��܂����A�d�ɖ{�̂̎��͂ł̓K���X�ǂ������c���ŋ�Ԃ�����܂��B
�d�ɂƃK���X�ǂ̊Ԃɋ�Ԃ�݂��Ȃ��Ƃ����Ȃ����R���������̂ł��傤���H >>294
����Ȑv��̎�������Ă��A���{����1980�N���ɂ͐�����ł����Đݔ��p�����Ă�킯�ŁA36�N�O�p���ɒ��͓̉�����낤�B
���肷��ɁA�M���t�œ`�M�f�ʐς͎��Ȃ���������x���オ���Ă��܂��AS��ST�ǂ̓����قǗ]�T��傫���̂��Ă����̂ł́H
MT�ǂ̏o�͊ǂȂǔ��ɔM���ĐG��Ȃ��������A�^��ǖ{�̂��A���ӕ��i�̑ϔM�����オ�菬�^���ł����Ƃ������Ƃ���Ȃ����ȁB
���M�ʂƂ��āA�V���O���o�͊ǂŃq�[�^�[�łQW�i��6.3V�~0.3A�j�A�A�m�[�h�����TW�̂VW�A���̑����łSW�~�R�A�����łQW��21W�B
���̔M�ʂ��A�傫�ȓd�~�Ȃ���M�͊y�����A���^���W�I�ɂ����祥�����ƍl����ƁA���M�̓_���珬�^���ɂ͌��E���o�Ă���B
�o�͊ǂ�2���͑��߂��������AMT�ǎ嗬�̎���ɍŌ�܂�GT�ǂ��g���Ă����̂͂��̔M�����̕��M��肾�낤�Ǝv���B
TV�Z�b�g�ōł��M�����̑傫�������o�͊ǁi�����Ό������������j�͂قƂ�ǍŌ�܂�GT�ǂ������͕̂��M����낤�B
���`�M��R�́A�`�M�f�ʐςɔ���Ⴕ�A�`�M�����ɔ�Ⴗ��B
�傫�Ȏ��[�e�킾�Ɠ`�M�ʐς��傫��������U����M�ʂ������ē��B���x��������B�������قǍ����ɂȂ��ĒʉߔM�ʂ𑝂₷�B �u�S���{�^��ǃ}�j���A���v��7p mT�`ST 16�܂ł̃T�C�Y�̐^��ǂɂ���
�q�[�^�[���܂ޓ��͓d�͂ƊǕlj��x�̊W���v���b�g�����O���t������܂��ˁB
���ꌩ��Ƃ킩��₷���B
�i6AQ5�ōő�v���[�g����12W���Ă̂͂������������킯���ȁA�A�A�j
>>296
> �i6AQ5�ōő�v���[�g����12W���Ă̂͂������������킯���ȁA�A�A�j
�����͗ǂ��čD��Ŏg��ꂽ���A�r�[���S�ɊǂŁAIg2���S�������Ȃ߂Ƃ͂���������������B
����������ė]�T�̑傫��5�ɏo�͊�6BQ5���g�����������������B �j���[�r�X�^�ǂƂ��f�[�^�V�[�g����ƕ��C�Œʓd���ɂ͕\�ʉ��x100�x�����Ƃ������Ă�������
�d�ɂ��x�����邽�߂Ƀi�X���̓����i���đ��͏]���ǂ���Ȃ̂��_���}�����Ǝv���Ă�
�����Ă邤���ɐ����Ŏ�M���g��������Ă����炢�����瑊���Ȕ��M�����
���̎��������G�A�R�������ł͎g���Ȃ�
�^��ǃ��W�I�Ő^��ǂ��ꂽ��
�L���r�l�b�g����V���[�V���O���āA�^��ǂ���������́H
>>301
���W�����O���ΐ^��nj����ł���̂��t�c�[����B
��Ƃ��₷���悤�ɂ��A�V���[�W�[�O���ɐ^��ǂ�z�u����̂����������B >>302
���肪�Ƃ��A�ł�1���������ɂ����� ����@�Ƀ}�W�b�N�A�C�t���悤�Ƃ�����A�J�o�[�̕t�����\�P�b�g��
���̎��t����������ĂȂ��̂ō��������Ƃ���ȁB
�ؔ�����V���V���O���悤�ɂȂ��Ă�A�^���ŗx��Ȃ��悤�ɌŒ肳���͂�������
>>307
���������ǥ����������Œ���A�c�}�~���O������A
�@��ɂ���Ă̓_�C��������j�n����O�������
���\��Ԃ��|���郂�m�B
�^��nj����̘b�Ȃ���A���W���J����Β��Ɍ�����Ƃ��o����B�S�̂��o�������Ƃ͂Ȃ��B
�������������o���h�~�̃o�l�N���b�v���A�^��Ǘp�̃V�[���h�P�[�X���O�����x�ōςށB ���ɋ��������ĊO���Ȃ��Ȃ�o���������肪��������Ȃ���
>>309
���ɂ����Ă��܂��O�����B
�����̐^��ǎ�TV�ɂ悭����ꂽ�\�������A�^��ǂ̕��������ԈႦ�Ȃ���Ό����ł����B
�V���[�V�[���O���Ȃ��Ɛ^��nj����ł��Ȃ��Z�b�g���Ă̂͑����������Ƃ��Ȃ��B
����Ζ��_�A�V���[�V�[���O�����B�����ǐ^��nj����͌��\�p�ɂ�����ʎY���i�Ƃ��ă����e������B ����i�ŃV���[�V�܂Ŏ��삵�Ă���ƋH�ɋ��̔z�u���悭�l���ĂȂ��悤�ȃZ�b�g���L��悤����
���[�J�[�i���Ɣz�u�̊W�ŃV���[�V���o�����ق�����ւ����y�ȋ������邩������Ȃ���
���o���Ȃ��Ă����ʉ��Ƃ��t���ւ�����Ǝv�����ǂ�
������V���V�[(chassis)�����O���āC�C������
�������ɖ߂��Ă˂����߂悤�Ƃ��āC���̃l�W���Ȃ��āC
�茳�̃l�W�ŗ��߂���C���̃l�W�������āC���i�ɂ������āC�V���[�g����
���W�I���I�V���J�ɂ����Ƃ����b��������܂�����C�V���V�[����肾����
���͂��ꂮ��������ӂ�
�_�C���������ēd�q���i���ɒu���Ă�H
�}���c�ɍs��������������������
>>318
�ނ莅�͎��������njł�����c >>320
PE�͌ł��Ȃ���B�L�т͑S���ƌ����Ė�������_�C�����ɍœK�B
���a0.09mm��PE��200���[�g����Ɋ|������5�Z���`�̃s���M�X�̓����肪������ʐL�тȂ��B ���t�I�N�I�ɍ��Y�i(���̂���)�蔄�肵�Ă�l�����
>>317
�y�퉮�ɍs���ĎO���������Ƃ����B �v�[���[�������Ă��Č������킹�ŁB
>>327
���W�I���N�̃g�����X���ĞH���t���������悤��
>>328
�����Ăт�����
�d�r�ǂ���B�d��45V��67.5V�̂ǂ��炪���������̂��낤
�ǂ���ɂ���5W�N���X�̃Z�����g��R���邩 1:3�̃g�����X��
�_�˓d�q�T�[�r�X�œ���������A�܂���t�����B
��J����ǂ����Ă܂����H
������KDS���i���^������������
�������Ă�1��3�g�����X�̓C���_�N�^���X�����Ȃ菬��������
�̂̉�H�}�Ƃ���ɍ���Ă����\������Ȃ��ꍇ������B
�܁A�g���Ă݂邵���Ȃ����ȁA
���W�I���N�̃R�A�������������C���_�N�^���X�̑���ŏd��d����ς���Δ���
���Ȃ̂́A�ǂ̂��炢�̐M�����x���Ŏg�p���邩���Ă��ƂȂB
�d��DC��������Ȃ��āA�����M�����x���ŃC���_�N�^���X���ς���Č�����B
>>�M�����x��
���샌�x�����Ⴉ������R����ST�g�����X������1:3�̃`���C�X���\��
�Y�@27���̈��p���s���܂��B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
�E�W�c�X�g�[�J�[����ʂł͂Ȃ��A�e�^�҂�����
���v���~�X�@�����Ј�97�N���� �����^�P�V�}�R�E�C�`�A�T�K�����E�C�`
���v���~�X�o�����Ј�97�N���� ���V�_�^�J�R�A�T�T�L���V�q���A�^�P�C���V�I�A�^�P�C���V�R
���v���~�X�l�����Ј�97�N���� ��������V�_���L�I�A�^�e�V�i�N�~�R�A�N���_�t�~�R�A�^�J�V�}�P���C�`�A�^�i�J�R�E�]�E�A�^�J�I�J���V�q���A�t�W�^�^�J���V�A�t�W�C�}�R�g �A�^�J�n�V�V���C�`�A�I�K���V�Q���L�A�T�N�����V�q���A�E�c�~�}���R�A�^�e�V�i�N�~�R
���v���~�X�l�����Ј�98�N���� �A���L�R�E�W
���v���~�X�l�����A���o�C�g97�N���� �A�x�g�V�A�L
���T���V���O�O�b�h93�N�����c�ƕ����@�^�J�M���V�^�J
���T���V���O�O�b�h93�N�����c�ƕ��Ј��@�^�P�C���V�q�R�@�p��A�^�J�n�V�t�~�I�A�^�V�����E�R�A�T�g�E���V�A�L�A���E�G�C���C�A�A�T�k�}�P���C�`
���T���V���O�O�b�h93�N�����J�������@�^�i�J�q�f���L
���T���V���O�O�b�h93�N�����J�����Ј��@�t�N�n���~�L
���T���V���O�O�b�h93�N�����Z�N���^���[�̃A���o�C�g �J�������W�����R
���T���V���O�O�b�h93�N�����T�|�[�g���Ј��@�^�J�C
���T���V���O�O�b�h93�N�����T�|�[�g���A���o�C�g �N�}�m���~�R
���T���V���O�O�b�h93�N�����c�ƕ��A���o�C�g �^�L�U���V���C�`
�A���_�XKK94�N���� �^�i�n�V���V�q��
���\�j�[�E�G���N�\���@�o�c���ہ@2003�N�� �ے��@�R�o���V�q�f�I�i�\�j�[�{�Ђ���̏o���j
�T�[�o�[�`�[���@���[�_�[�@�^�����R�E�C�`
�T�[�o�[�`�[���@�Z�N���^���@�}�c���g���E�R
�T�[�o�[�`�[���@�n�V���g�R�E�W
�w���v�f�X�N�@���[�_�[�@�J�g�E�}�h�J
�w���v�f�X�N�@�Z�N���^���@�N���L���E�R
�w���v�f�X�N�@�q���C
�A�v���P�[�V�����`�[���@���[�_�[�@�`�o�P���C�`
�A�v���P�[�V�����`�[���@�^�J���M�A�^�J�n�V�A�^�O�`
15�N�ȏ㖳�E�B���������Ƃ̖����j�[�g
�^�J�n�V���E�C�`�A�Z�L�O�`�}���~�A�A�I�L�}�T�q���A�^�W�}���V�q���A�^�P�C�^�J�R�A�^�J�n�V�P�C�R�A�^�P�C���V�R�A�^�i�J�W�����R�A�^�i�J�V���C�`�A�^�i�J���J�A�^�J�n�V�R�E�C�`�A�^�J�n�V���V�G �Y�@27���̈��p���s���܂��B
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%B7%8A%E6%80%A5%E9%81%BF%E9%9B%A3
1998�N12����{�A�v���~�X�l�����Ɉ�l�̔h���Ј����h������Ă���
�������ԋ߂ɍT����A�����h���Ј��̎p���݂Ă���A�l�q�����������Ȃ�
�{�C�Ȃ̂��ǂ��Ȃ̂��킩��Ȃ����A�ǂ����A��������ƕʂ�b���������̂悤��
�����Ԃ��̎Г��ł̕ʂ�b�̂������������̌�A�A���L�R�E�W������A���ɘb�������Ă���
�A���L�R�E�W�u�l�̍l�����킩�鑕�u�͂���Ȃ��H�v
A���u�~�����v
B���u�����v
�A���L�R�E�W�u���[�AB�����H���Ђ�Ђ�Ђ�v
���x�́AC���ɂ��A
�A���L�R�E�W�u�ǂ��H����Ȃ��H�v
�c�cetc
���̂悤�ȗ���ŁA���Q���u���L�܂��Ă����������� >>334
���s�ň�ԃ}�V�Ȃ̂͂ǂ����낤�H����d�@�̂���ȁH
>>337
ST��1:3�Ȃ�Ă����������H 30V������̓d���g�����X���t�Ɏg�����������ˁH
>>343 �W�����N���p�͊y�����B ST����ψ�����Ȃ���ˁH
AC�g�����X�̕�������B
ST�g�����X�͓d�r�ǂŎg�������Ƃ���ȁB���͏o��B
�ψ�����������ψ��K�i���^��ǎ���ƃg�����V�X�^�[�p�Ƒ傫������āA
�ȈՃ`�F�b�N�̃��K�[���^��ǎ��ザ��500V���K�|�`1000V���K�[�������̂��A
�g�����V�X�^�p��100V�K�i�������肵�č��d�����|���ă��[�N���Ȃ��ۏ�͂Ȃ��B
�̗p�͍�郄�c�̌l�ӔC�Ƃ��Ă��\�����ӂ��K�v
>>343
���̎肪��������
�ƌ����Ȃ���100V:3V�̃g�����X���o�̓g�����X�̑���Ɏg���Ă�w
�Ƃ����4BQ7-A��5U8�A6CB6��1�{��������������g�߂�H >>342
����ɕ����Ă݂�Ηǂ���B�@�������Ă���邾��B
��ʘ_�ł����A1��3�͒ʏ��1�����v���[�g��H�ɂȂ邩��ő�10mA���x�̒����������B
�Ⴆ�A���̏�Ԃ�100Hz�ɉ�����100k�����x�̃C���s�[�_���X���K�v�Ȃ�A
160H�ʂ̃C���_�N�^���X���K�v���B�@��������ƁA0.1�ӈʂ̐��Ŋ����Ă�
���\�Ȋ����ɂȂ邩��A�T�C�Y�͑傫���Ȃ�B�@
�܂Ƃ��ɍ��ƃV���O����5W�N���X��OUT�g�����X�݂����ɂȂ邩���B
�d���g�����X�Ƃ��𗬗p����Ȃ�ADC���R���f���T�[�Ő��āA����g�̃`���[�N
�g�����X�����ɓ����̂��ǂ����A���̃`���[�N���傫���Ȃ�B
���\��Ë����邵���Ȃ����ȁB
TR�p��ST�g�����X���Ƒψ����S�z�����A�C���_�N�^���X������Ȃ��ł��傤�B
>>326�̉�H�Ɏg�p����ƂȂ��DC120V�ʂ͊|����܂��B
�܂��A�푪�苅�̃v���[�g�d��������܂��̂ŁA�܂Ƃ��ɍl����Ƒ�ςł��B
�ł��A���̃e�X�^�[�͗Ǖi���Ƃ̔�r�ŗǔۂ肵�Ă���悤�Ȃ̂ŁA
����1��3�ł��g����̂ł͂Ȃ����B
����ƁA�����̉�H�����Ȃ�A�g�����X2�����̃��[�^�[��H�̓}���`���[�^�[��
�𗬓d�������W���g���������ǂ��Ǝv���B
���x���ǂ��Ȃ邩��1��3�͕s�v�ŁA����ɐ^��Ǘp�̏��^OUT�g�����X�Ƃ��`���|�N��
����āA���̗��[�̓d���𑪂�悤�ɂ���ΊȒP�B ����d�@���Ĉ��������g�����X����Ă����݂�����
�����m���Ă�Ηǂ�������
�����a�����̃��W�I��@������`�̕����ɓw�͂���Ă�����X�̂��߂ɓ��荢��Ȓ���g�P�F�R�g�����X�B�`���[�N�Ȃǐ���v���Ă���܂��B
����͂��肪����
>>349
�M�����̎��g�����グ��g�����X�͏��^�ōςނ̂����B >>350
�Z�g���Ă��Ƃ̓A���e�i��ς���K�v�����邩�c
�E���́A
117
VAC
�Ƃ����\�L�Ɉ�u�˘f����w >>356
�ȒP�ɂ���Ȃ瓯����H�ʂ̒��g�p�̃o�[�A���e�i�ƃ|���o���R���ɂ��Ă��܂��肪����܂��B
�������Đ��p�̃^�b�v���o���͍̂���Ȃ̂ŁA�����ł�����Ƃ��͍Đ��p�̃R�C����
�o�[�A���e�i�Ɋ��������܂����B >>357
�Đ��t���̃o�[�A���e�i(BA-200)�̎莝����������
�Ɗ�Ԃ����̊ԁA260pF�̃|���o���R���������c
�莝����2�A140pF/40pF��2�A300pf/20pF
�p�[�c���s���Ă��܂� >>358
����͍Đ�����Ȃ��āA��������B >>358
�����͓̂�����ǁA�����̂͊ȒP�B
�����Ƃ��Ă݂č������g������M�ł��Ȃ�������ABA-200�Ȃ�����قǂ��邩��A��M���Ȃ���قǂ��Ă��������B �R�A����Ȃ犪�������Ȃ�����ŏ����犪���������y�ł���B
>>359
2���������Ȃ̂��B�����ƍĐ��R�C�����Ǝv���Ă�
>>360
�]�T���ȁ[�Ǝv�������ǃ}���c��260pF�����Ă���
�ň��ʓ�����������Ď�����������ǂ� >>362
���Ƀ��m������O��Ȃ̂ɁA�u�����v���Ăǂ�ȑI�����H >>364
�������킹�Ŋ����߂��̂ƐV�����{�r���Ɋ����̂Ƃ͎��ԓI�ɑ卷�Ȃ��B
�\���m�C�h�Ő��X100t�Ƃ��ł���B
�^�b�v�o������Đ��R�C���Ƃ�2���R�C���Ȃǂ��D���Ȃ悤�Ɋ����邵�B
���̂��̂͂����炸�Ɏ���Ă����A���W�I�����܂��o���Ȃ������Ƃ���
���i�Ƃ��ĕ����ł���B >>366
�܂�A���ɐ��i��BA-200���茳�ɂ���̂ɁA�킴�킴�u���ނ��w�����Ċ����v�ƁH�@��������������Ă��B
��������Ȑl���āA����s�\����B �w�j�ǂ߂���
�y���L�ŌŒ肳��Ă��邯��
�O�������Ƃ͂ǂ�����́H
�L���r�l�b�g�ɓ���Ă������͓̂���H
���|���_�C�A���́A�O���ƌ��\���������
�|����ɂ̓R�c������
�O���Ȃ��̂��x�X�g�ł�����
���Ȃ��Ƃ��O���O�Ƀf�W�J���ɉ摜���B���Ƃ��Ƃ����Ȃ��Ƃ킩��Ȃ��Ȃ�
>>369
�O���Ȃ���
�L���r�l�b�g������o�����@�Ȃ�ĂȂ����� ��̃l�W�ŋ���łȂ����H���w�j�ƃ_�C������
�w�j�̋���Ƌ��ݍ��ݗp�̏���������Ŏ������݁A�l�W�ŋ����߂���X�^�C����
�����ȁB�P�O��ȏ�C�������o���ł́B
�v�����X���Ƌ���ƃl�W�������悤�ȋC������
�l�W���̑��ɁA�w�j�̋���ɍ��E�����A�^��������ɒ܂����肻���Ɏ���
�͂��ގ����������B
�g�����X���X5����35W4��p���������ǃ_�C�I�[�h�Ő�������ꍇ�A
�q�[�^�[����35V�͒�R���ׂ�12V0.15A�̓�����3����̂ǂ��炪�������낤�H
>>377�@��X�������ʓ|�ɂȂ�̂Œ�R�̕��Ł@�M������(�P�~�R�����߂�)�ꍇ
4.7��F�̃t�B�����R���f���T������B ������ɂ���PL���g���Ȃ��̂�NL��
���������Â��̂����x�����B >>377
�𗬓_�Ȃ�A�M���قڏo�Ȃ��R���f���T�Ȃ��Ƃ˂��B(�d�����g���Ɉˑ������邯��)�@�����ł��Ȃ�A��R�����S�z���Ȃ������肵�Ďg���邩�ȁB5W�����邩��A������ƑI��Ŕr�M���ĂˁB
�d�������܂��f�U�C���Ɏ����Ă�����Ȃ�A�A�����Ȃ��B�����A�����Ȃ���ˁB �ۈ������˂ăg�����X�����������H
>>378-379
�R���f���T�_���֗�����������R���f���T�ɂ��邩��
���肪�Ƃ� 381�͖����H
�v�b�V���v���o�͂�5���X�[�p�[�ɂȂ邯��
��O�̃g�����X���X�Ƃ��o���X�g�ǂ��Ă����ł����d���݂����Ȃ̓����Ă��ȁB
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/11829ssch.jpg)
>>381>>383 �v�b�V���v���œ����܂�������Ⴄ�̓���Ă��Ȃ��B
�P�[�X�ɃX�s�[�J�[2�����12AV6��12AX7+GeDi 30A5x2 �q�[�^�p50���Z�����g��
���W�I�����Ȃ���O��(�X�e���I)���͂ɓ�������B
(�{�����[���͍��E�ʂŃo�����X�����Ȃ��ƂȂ�Ȃ��B �����̓����^��ǂȂ�����B�j >>382
���Ȃ݂ɁA>378��4.7�ʂƏ����Ă��邯�ǁA50Hz�̂Ƃ��͖��炩�ɑ���Ȃ��B�d�����d��������Ȃ��Ȃ��B������ƌv�Z�����ق����ǂ��B >>387
�u4.7+1.5�v�Ɠǂ߂邯�ǁB�v�Z��A6.283��F������B
�]�ڂ̏�ɂ��̓]�ڂ���ł��Ă��炸�A�v�Z���ł��Ă��Ȃ��B ���肾���ŁA���������ɏ������Ƃ��炢���邾�낤�āB�܂��A�ӂ߂Ă��Ȃ�B
>>388
�P�~�R�����ƁA���̒��x�́u�덷�͈́v�łn�j�I�Ƃ���邱�Ƃ������B
���i�K�i���덷�{�T�O���ȓ��Ƃ���A�قƂ�ǂ̐��i���v���X�ڂ��������シ�炠��B
��R�`�S�N�ŗe�ʔ������Č�������̂�������������A�v���X�ڑ_���ŐS������������(w >>390
�܂��������Ȃ̂��N���Ă����B�^��nj𗬓_�̍~���R���f���T�ɁA�P�~�R���Ȃg�����炳�Ăǂ��Ȃ�̂��ȁH�@�����ǂ߂�B
�~���ɂ͕��ʂ̓��^���C�Y�h�t�B�������g���̂ŁA�덷����5%���炢�B6.2�ʂƂ������Ƃ���Ƃ����4.7�ʂł́A�덷�͈͂ǂ���ł͂Ȃ��B
�q�[�^�[�d���͒�i��-10%���x�܂ł͌����܂��̂����Ă��Ă��A4.7�ʂł͒�i��80%���傢�����o���ɑ���Ȃ��B�덷��+5%�ɐU��Ă��A����ς葫��Ȃ��B >>385
�g�����X���X�p�^��ǂłȂ��̂������Ďg���ƃ_���Ƃ����������ǁA
12AX7�͑��v�Ȃ̂��ȁH >>392
12aX7�̓g�����X���X�Ƃ��Ă̎g�p��͂��Ƃ���
�悤�̓q�[�^�[�̓d���l�������Ă������ >>393
���Ⴊ�L�x�Ȃ���Ȃ��낤���ǁA
�g�����X���X�p�̓q�[�^�[��R�l�̗����オ������𑵂��Ă���Ƃ��B >>394
TV�����͂��߂Ƃ����g�����X���X��
�ꉞ11�b�ő�����Ƃ�����������
����ł��d���������Ɉꕔ�̋������ٗl�Ɍ��邱�Ƃ�
���邪�Ë������ɂ����Njy����ɂ͍H�v������ >>392 ���Ńt�@�~���[�X�e���I�V���[�Y310�@TAS-310 �O�H 5H-662�^�ȂLj�ʏ��i�ɓK�p�Ⴊ����B
12AX7�� 6V��0.3A 12V��0.15A �Ńg�����X�ł��g�����X���X�ł��g���鋅�B�����q�[�^�[���𗬓_��
����ƃn�����o�₷���X�������菼����12AX7(T�j���ł�12AX7(HiFi)���������B
>>394-395 ���W�I�ł͗����オ�莞�Ԃ̖��m�Ȏw��͂Ȃ��B
�K��d�����������Ƃ��̓��쎞�̓d����0.15A�@�Ƃ������Ƃ����B
TV��>>395�̎w�E�ʂ� ���쎞�Ԃ��K�肳��11sec�ƂȂ��Ă���B
�������R���p�N�g�����ǂ��o�n�߂�������ł��̂������Ȃ��Ȃ� �|���p(�q�[�^�\���M)������
�̂ɂ����B(�Ȃ��|���p�̓u���E���ǂƍ��������ǂ݂̂ő��̉�H�̓\���b�h�X�e�[�g���������́B)
�g�����W�X�^�����x�ꂽ���[�J�͎g�p���Ă��邷�ׂĂ̐^��ǂ�\���M����Ƃ����ȃG�l�Ƃ͑������邱�Ƃ������B
�Ȃ���ꎟ�I�C���V���b�N�̍��ɂ͂��ׂẴ��[�J��IC�{TR���𐬌������Ă���B(�ƒ�̃e���r�͂܂��^��ǂ���������) �g�����X���X�̃q�[�^�[�ɂ��Ă͑S���{�^��ǃ}�j���A���ɐ������������ˁB
�����̃��X�ɑ����[�J�[�̋�������ƒf�����₷���C��������C�̂����H
�s�J�b���ƌ���̂͏����܂߂��t�B���b�v�X�n���ȁB
PCL86�Ƃ������قǃs�J�b�Ƃ���̂����w
�ǂ����Ă��������d�l�ɂȂ��Ă�w
�R�X�g�_�E���ŁA�q�[�^�[�̐����ׂ��Ƃ��H
>>396
���[�A���W�I���͋K��Ȃ������I
���ɂȂ�܂������B���� >>398-400 >>397 �̖{�ɂ��ƃ^���O�X�e���q�[�^�ƃ^���O�X�e���E�����u�f��������
�q�[�^�̈Ⴂ���Ƃ������ŁA�ł��邾�����ꃁ�[�J�[�̐^��ǂ��g���Ə�����Ă���B
�܂�PL���ꂽ�瑁���������Ȃ���35W4��PL�����o�����̃q�[�^�[����Ă��܂��B
�܂��Z���Ԃł̓d���ē����̓q�[�^�APL�Ƃ����Ă��܂����X�N���傫���Ə�����Ă���
���Ȃ��Ƃ�3���҂ĂƁB �f��Ȃ̂ł����A�W�c�X�g�[�J�[�E�d���g�ƍߔ�Q�̓��e�ɂ�������ł��B
�ɂ���������A���ĉ������B
�N���[�v�]�[�� : �}�C���h�E�R���g���[��
https://goo.gl/UQ9t4m ���[�U�[�E���[�U�[�A�t�H�m�����[�U�[���K������@�������̍��ɂ͖����悤�Ȃ�ł�����
����܂����� ^^;
����
�U�����o�����d���g�A���g���K������@��
�ƌ��������܂�
UY-227��6E2�������A���ꂾ���Ń��W�I�g�߂Ȃ���ˁH
�}�W�b�N�A�C�ōĐ��O���b�h���g�A227�ŃX�s�[�J�[��炷���O�����̃��W�I
>>407
��H�킩���c
���Ǝ莝����KX-80BK��30A5������ 227 �ōĐ����g 6E2��AF�������Ă��]���̋��d�E�łȂ���30A5�̃h���C�u�d���͏o���Ȃ��Ȃ��B
80BK��RECT�� 227�����112B�̑���ł�����B ��H�̓O�O��6E2����227���o�₷���Ǝv����
���Ƌߏ����f�ɂȂ邩�����d�E�ȂǂŒ����A���e�i�ł��̑ʃW�I�g��Ȃ��悤�ɁB
�܂��Z��C G De��CS�����܂����̂ŗƂ̂��������l�키�邳�������Ȃ���������Ȃ��� ���
>>406
227�́A1�{�ŗ��Ă��������h���������
�ł����R�C���ƃo���R��1�ōĐ����g���W�I
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%9B%9E%E8%B7%AF#/media/File:Regenerartive_Receiver-S7300056.JPG)
���Ȃ�i�X�ǂȂ�Ėܑ̂Ȃ��Ďg�����
227-226-112A-112B�Ȃ�Đ̂̕��l���ƁA2.5V��1.5V�ɉ�����5V�̊�����2������w
�́X�̉�H�͑S�Ď����ŏ�����ĂĂ�₱�����ˁB
���W�I���̂܂Ȕɓ��_�z�������獇�킹����ł��i��
R�BC ���Œ�����������Ă��܂���
��������������ƌ��₷��w
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5b/01/8b3b6500910dc7e9533df45f8c9eab40.jpg)
���� 2��F �͎��R���ł����H �'�ց@`�@�
�̂̃}�O�l�`�b�NSP���āA50Hz�̃n�����łȂ������̂��낤���H
���MAC�_���{2��F �̓d���t�B���^�[
10H�̃`���[�N�R�C�����ł����̂��H
>>416
�����͎l�p�������P�[�X�ɓ����Ă�y�[�p�[�R���f���T����Ȃ��ł����� >>418�@�o���@�������}�O�l�`�b�N�ł��̐U���͏o�ɂ�������
>>419�@������R���f���T���Ǝv�����PCB�����Ղ������ >>420
���̓���PCB�قƂ�ǎg���ĂȂ����� �g���I�̕��l�R�C���̐������ɏo�Ă�R�����W�I�̗�ł�6�ʂȂ�
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.funkygoods.com/garakuta/3_tubes/namiyon_03.jpg)
>>419-421
�y�[�p�[�R���f���T�[�͘X�F���b�N�X�ܐZ�ŁA�⎆�����o���ėV�ԍޗ��������B
��e�ʂ����ɂ����A����������H�ɓS�S����̃`���[�N�R�C�����g�����Ƃ��悭�������B
PCB�͂����ƌ�ŁA�≏���Ƃ��Ă̓d�C�I��������ϗǂ��ĐȊ��������߂ɁA
���������Ő�����g�p�֎~�ɂȂ��āA���̑�ɍ�����J���Ă���B
�댯���Ƃ��Ď�����̉i�v�ۑ��I �ŏ��͎̂O�Ɋǂ�����30H���邩�炽�Ԃ�50Hz�͌������Ă邾�낤���A��҂�SG������Ɉ���ɂȂ��Ă邾�낤������p�ɂȂ�����łȂ����Ȃ�
������H�̃R���f���T�e�ʏ��������ǁA�̂͂���ŗǂ������ȁB
���g�܂łȂ�n�������͂��������낤���H
�������Č��邩�ȁB
����������e�ʂ̃R���f���T�����Ȃ������Ƃ��H
>>426
���̒ʂ�I
�X����U�d�̂Ƃ��ăA���~���ŋ��\��������A��^�����Ă��܂��đ�e�ʂ͍̂��Ȃ������B
�����։�������U�d�̂Ƃ���d���R���f���T�[�������10�}�C�N���t�@���b�h�Ƃ���������悤�ɂȂ邪�A
�����̋Z�p�ł͂Q�`�R�N�ŗe�ʔ������Ă��܂��A�n�����ڗ����Č������Ă��B �Ód�e�ʂ͓��̊ԋ����ɔ���Ⴗ�邩���
�����̃A���v��X�s�[�J�[�ł̓n�����C�ɂȂ�قǒ��͏o�Ă��Ȃ��������낤��
�O�ɔ�����6E2���o�Ă����̂ŁA���g�ǂɂ��ĒP�����A6AQ5�ł������āA�Đ����W�I��낤���ȁB
6E5�ł�������Ƃ�����̂ŁA���������ł������ȁB
>>427
1940�N��㔼�̐���L���݂Ă��30��F�`50��F�ő�e�ʂ��ď����Ă�� >>427,431
����ς�Z�p�I�Ȗ��Ȃ̂�
�܂�����܂�傫���Ă������ǒɂ߂邾�������� 30H �� 2��F �̕�����H��̋[���Ă݂܂����@Ё@'�@�t`�
�̋[����
�d���F 180Vrms, 50Hz �����g
������F ���z�_�C�I�[�h �{ 100��
�~�d��F 2��F �~ 2
���ցF 30H �{ 800��
���ׁF 7.45k��
����
�o�͒����d�����ϒl�F 149V
�o�͒����d�����ϒl�F 20.0mA
���v���U���F 29Vp-p
�����͓�Ɋǂ̓����̂����ł��������܂��Ȃ̂ł��傤���B
�^����ǂ͎O�{�� 20mA ������Ȃ��̂ł��傤���B
30Vp-p �̃��v��������Ă�d���ʼn����M����������������܂�����B
�I�V���̉�ʂ��Ԃ�Ē�܂�˂� �'�t�@`�@�
�܂��ŋ߂����炶�イ�ɏ��ւ܂����炵�ĉ���Ă�̂�
�����Ȑ��i����Ȃ��Ĕ������̂̍����i�͂ǂ��Ȃ��Ă邩�Ǝv������
���Ƃ��ARCA Radiola 17
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://images.campyent.com/sites/default/files/schematics/rca_victor_co_inc_radiola_17_pg1-1.png)
�i���̕��̐}��RCA Radiola 17�j
280�ŗ��h�����Ń`���[�N�C���v�b�g�ł���ɂ���1�i�`���[�N�ƃR���f���T�Ńt�B���^���Ă�ȁB
�R���f���T��4�ʂɂȂ��Ă�B�}�C�i�X���Ƀt�B���^�������Ă�̂̓`���[�N�̑ψ��̂��߁H
���łɃp���[�ǂ�171A�ɃO���[�h�A�b�v�B >>430
���g-�d�͑������ă��W�I��������Ƃ���܂����ǁA6K6/6AR5����
6V6/6AQ5�̕����Q�C���������̂ŁA���Ȃ������̎��͗L���ł��ˁB
��r���Ă݂���������������Ă�w >>429
> �����̃A���v��X�s�[�J�[�ł̓n�����C�ɂȂ�قǒ��͏o�Ă��Ȃ��������낤��
�悭����I
���@�����̋Z�p�ł͂Q�`�R�N�ŗe�ʔ������Ă��܂��A�n�����ڗ����Č������Ă��B
�n���̊�{�g��100Hz�`120Hz�����A�[���d�ŋ�����g���̔g�`�ɂȂ��āA�����g������������������t�c�[�ɕ��������B
����Ȃ�œS�S����̒���g�`���[�N�R�C����d��������H�Ɏg���̂��W�����������������B
>>431��30��F���L������A�����u��e�ʁv�ŁA�R���f���T�[�E�C���v�b�g��H�̗p�ŁA�����`���[�N�E�R�C���͎g��Ȃ��B
�����������1940�N��㔼�Ȃ�ĎG����ǂ������Ă�˂��I
�ꎞ�͍Ő�[�Z�p�ňꐢ���r�����ނ́u���W�I�Z�p�v�������āA�n���͊m��1949�N���̂͂��B
�u�����Ǝ����v�����ȁH����͐�O���甭�s����Ăĕ\���ɂ͉E�����Łu�����v�ƃX���[�K�����������Ă�(w >>437
>>�E�����Łu�����v�ƃX���[�K�������
����͎v���Ⴂ�ł��傤�B
�u�����v�Ɓu�\���̉E���v�Ɉ�����Ă���܂������A�u��������v�ƉE�����ł͂���܂���B
���a18�N9�������茳�ɒu���ď����Ă���̂ł�����A�ԈႢ����܂���B
�������s�v�c�Ȃ̂́A�������s�����A����p���Ȃǂ���������Ă������Ȃ̂ɁA
���̍��ɂ����炸�A���̂���́w�����Ǝ����x�͕Ő���80�ŋ߂�����A
�L������R�f�ڂ���Ă��邱�Ƃł��B
���Ȃ݂ɁA1947�k���a22�j�N11-12����������32�Łi����ɓs���̂悢�Ő��j
��������܂���B
�z������͂����Ɣ��������͂��ł��B
���炭����ɉ����G���Ƃ������ƂŎ������Ɋr�ׂĖL�x�ɔz�����ꂽ�̂ł��傤�B ����438
�u�z���v�́A��������̂悤�Ɂu�s��v�̊ԈႢ�ł��B
���W�I�W�����Ɂu�s��v���u�z���v�ɉ����Ă��܂��܂����B
�ȏ�����܂ŁB
>>433
415�̉�H�́A���M�q�[�^�[�ǂŏo��n����
30V�̃��b�v������ŏ����Ă����̂ł͂Ȃ����H
�����łȂ���A2�i�������Ă���h���C�o�[�g�����X��
�R����ST�g�����X�̂悤��100Hz�Ń��[��
�s���X���[�v�Ő�Ă���Ƃ� 1920�N��`���a25�N����̓d�r�����W�I�Ŋ��d�r���g���Ă�������
�d�r��͌��Ɋ�炮�炢�������Ă����낤�H
���ł����̒P4�}���K���d�r�Ɠ����̒P1�}���K���d�r���������\�̎���c
1940�N��㔼�̉Ȋw�G�����Ă�Ǝg���I������d�r�ɓB�Ō��������āA
�H�����𒍓����Ďg�p����Ƃ������Ă��邵w
>>437
�����ĂȂ�w
����}���قőS�y�[�W�R�s�[���� >>441
����}���قł�1��ŃR�s�[�o����ʂ́A���Ђ̔����̕ł܂łł��B
�ł�����A�S�ŃR�s�[���悤�Ǝv�������Ȃ��Ƃ��A2��s���Ȃ���Ȃ�܂���B
����ɁA����}���ق̃R�s�[�����́AA4/B4�łP�ł�����25.92�~�ł��B
�ł�����A100�ŃR�s�[����Ƃ���A2592�~�|����܂��B
�����Ȋo�傪�Ȃ��Ƃ�������ƃR�s�[�𗊂߂܂���B >>441
��O�ɓd�C�̂Ȃ����ɕ��C�����Z���搶���q�������Ɏq���������W�I�ԑg��
�������������A���R�d�r���ɂȂ�̂ŋ�J����b���������Ȃ��A�A�A >>442
�P�Ԃ�30��������Γ������邩��ɂȂƂ����Ă��Ă�
>>443
����ʁc
>>444
�q�[�^�[��A�d�r�͉��{�d�r��B�d�r��C�d�r�͐ϑw�������H
�d�C�̖����X���Ɠd�C�����������낤����d�r�̓������ς��낤��
�ł��y������w >>436
6AR5�͍����Ĕ����Ȃ��āA6AQ5��5�{�E�����̂ŁA���܂��茳��w >>446
���͉������ĕʕ��ɂȂ��Ă܂����A6SJ7-6V6���ă��W�I�͂��Ȃ�ǂ������ł��B ���[�U�[�E���[�U�[�A�t�H�m�����[�U�[���K������@�������̍��ɂ͖����悤�Ȃ�ł�����
����܂����� ^^;
����
�U�����o�����d���g�A���g���K������@��
�ƌ��������܂�
6AQ5�̕W�������ɂ���P�d��250V��4.5W�o���̂́AP�����Ƃ�
���̃T�C�Y���Ƃ��Ȃ肫���Ǝv���̂ŁA�����ƌy���g�������������ł��ˁB
>>452
�E��ɂ���^��ǂ͋������Ɛ��₾��w
�Ȃ������ɕ����Ă邽�ߐ^��ǂɌ����Ȃ��c �n�Y�E�F���^��ǁ��K���X�̐_�a
30�Z���`���̃K���X�~����T�d�Ɏ����グ
1150�{�̐_���ȃs������M/B��\�P�b�g��
���₤�₵���}������B
����Ȗ��������@�@�@�悤�ȋC������
>>454
Loewe��3NF���g�������悤�ȊO�ςŊ�] >>438
�싅�́u�X�g���C�N�I�v�u�{�[���I�v�R�[�����ւ����Ă���������A
���{�W�O�����������n���n������������`���������ė͐s���ō������x�z���Ă���������A
�s�풼�O�Ȃǂɂ͉E��������������Ă邩���m��Ȃ���ŁA
�����|�C���g�̍������\���̒ł́u�E���������݂��Ȃ����Ƃ̏ؖ��v�ɂ͂Ȃ�܂���˂��B
�u�q��v�Ƃ����X���[�K�����\���ɏ������܂�Ă����̂́u�q���v���B
���������R���钆�ŁA�����͈����Ă����s�͌p������Ă��܂����B���̍��E�͉��̂��L���ɂ���܂���B
���Z�����x���Ŕ�s�@�̊�{�v���o���Ă��܂��l�A�Z�p�̐�����g���čq��@�����ɑ��荞�̂ł����A
��̌R�ɂ��q��Y�Ƌ֎~�߂Ŕp���ɂȂ��Ă�͂��B
�s���b���͖{�������Ă��܂��̂ŁA2�d��z������l�����������B
���W�I�Z�p�n������b���̎���܂ő����܂����B >>456
���́A�������������݂��邱�Ƃ��ؖ������̂ł����āA�E�����������݂��Ȃ����Ƃ�
�ؖ����Ă͂��܂���B
���̎v���Ⴂ�ł͂Ȃ����Ǝw�E���������ł��B
�E�����̑��݂𗧏���̂́A�����������������ꂽ���Ȃ��̂ق��ł͂Ȃ��ł����B
�������A���Ȃ���
�����u�q��v�Ƃ����X���[�K�����\���ɏ������܂�Ă����̂́u�q���v���B
�������������R���钆�ŁA�����͈����Ă����s�͌p������Ă��܂����B���̍��E�͉��̂��L���ɂ���܂���
�Ə�����Ă��āA�u���̂��L���ɂ���܂���v�̂ɁA�ǂ����āA�E���������������ƒf��ł���̂ł����B
�E�����������݂���Ɗm�M�������Ă������߂ɂ́A�A�u�q���v���E�������ł������؋���
���Ȃ��̋L���ł͂Ȃ��āA�o���Ă��������������̂ł��B
�u >>457
�H����{���Ă�̂�������Ȃ�����ǁA
�풆�́u�����Ǝ����v���A�u�q���v���͓ǂL��������A
���̂��������Ǝ������ɂ͕\���Ɂu�����v�X���[�K��������A
���ꂪ�E�����������N���ȋL��������A�v�q�̌����u�v���Ⴂ�v�ł͂Ȃ����낤�A�Ǝv���Ă�B
�����玞���ɂ��\�L���ς���ė����L�����\�����w�E���A
�us18�N�ɍ��������L�����Ƃ����������A�E�����������������Ƃ̏ؖ��ɂ͂Ȃ�Ȃ��v
�Ǝw�E���������B
�u�v���Ⴂ�v����Ȃ��Ɓu�v���v�������Ɣ��_�������A�ǂ����C�ɏ�����́H
����u�q��v�̕��ɂ͍��E�̋L�����S���Ȃ��B >>�Ɓu�v���v�E�E�E�E�E�E�Ɣ��_������
�Ƃ���܂����A���Ȃ��́���456�̏������݂̉����Ɂu�v���v�Ə����Ă���̂ł���
�v����Ɏ����u�����Ȃ����Ĕ����Ȃ��v
�����܂��Ȃ��Ƃ����������ł��������̂悤�ɂ����̂́A����߂Ȃ����Ƃ������Ƃł��E
�L���������܂��Ȃ�A�u�Ǝv���v�Ƃǂ����ɏ����Ă���悩�����̂ł��B
>>459
�Ђǂ�Wikipedia�nj�Q����Ȃ��́H
���̎��M��̑����������ł́u�\�[�X��`�v�ɂ����Ȃ��B
Wikipedia��ł����A�������N���Ȃ�����������̂��ƁB
���m�ȋL�����q�ׂ邱�Ƃ́A��ʎЉ��S�����Ȃ����ƁB
������֎~������A�ٔ��ł̏ؐl�q�₳�����藧���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B
�u�����Ǝ����v���́u�����v�X���[�K�����E�\�L�������̂�ǂ��o���Ă�̂́A
�����u��������v�Ɠǂ�ŁA�Ȃ���Ⴀ�H�H�ƂȂ����o������N���Ɋo���Ă����ŁA
�������̍����L���Ă��A���͉E�������L�������ǂ���������S���W�Ȃ��̂��B
�����Ǝ������ɂ��Ă͞B���ȋL������Ȃ����Ƃ͂����Əq�ׂĂ�ʂ肾�B
�q�����Ɍ����āA�E�������̋L���������Ə����Ă邾���B
������A���܍��̋ɒ[�Ȕ�����悤�Ȃ��Ƃ͈�؏����ĂȂ����B������ǂ݊ԈႦ�āA�ɒ[�Ȕ��������Ă邾���̘b�B �V�l�z�[���̒k�b���݂�������
>>461
���̔S�̂����������
�ق�ƌ��ɂȂ��
�H���X���Ƃ��n���������Ă������ĂȂ� �^��ǂƔ����̂Ńn�C�u���b�h���W�I���č���H
�o�̓g�����X���g��Ȃ����j��AM/FM��2�o���h���W�I
AM/FM��2�o���h���W�I
�@�����g����IC�ł���ăA���v�����^��ǁ�����( �L��`)
�@�����g����^��ǂł���ăA���v����IC��( ɄD`)�����c
>>464
����Ȃ̋N���E��~���J�ڎ��̓d�ʂ̕ۏႳ���C������Ώ\�����삷��B
�����Ă͐��S�{���g�̃��M�����[�^���\������̂ɁA���d�����o�͕������^��ǂŁA
����i�̓g�����V�X�^�[�Ȃ�Ē��������Ȃ�������B��d�����͕������Ă��H���������B >>463
�C�O���āA�q�[�^�[�d���Œ��������Ⴄ�̑�����ˁB�Ƃ���ŁA���͈���5676�ɏo��������Ƃ������ł��B�ᏼ��1400�Ȃ�ڂ���Ԉ����悤�ȁB5678�́A���������B �����Ȃ����̂��A�A�A5676
tubedepot���Ă݂���6�h��95�Z���g�����������ˁA�A�A
��̃N���X���[�̃p�N���̒P���Đ����W�I��5676��5678��3���Ɍ�������
���������Ƃ�����܂����A�����9V�d�rx2��18V��B�d���ł�k�ł����B
�̂�1920�N�キ�炢�̒��M3�Ɋǃ��W�I���Ă��낢��ʔ������Ȃ̂ł����A
�܂����{����UV-201��199�łł���킯���Ȃ��̂ŁA�T�u�~�j�ǂ͕֗��ł��ˁB
3A5�Ƃ��̓d�rmT�ǂł����������邩�ȁB
>>468
2HA5�������TV���łǂ����H
�������j�b�P�����f�d�r2�{�œ_�ł��邼 �d�r���Ƃ���σt�B�������g�d���̏��Ȃ����M�ǂ���Ȃ��ƁA�A�A
5676��push-to-talk�p�Ȃ̂ő��߂�0.12A�A��ʂ̂����50mA�ASF�ǂ�25mA���B
���ɂ̏ȃG�l�ǂ��ƕ⒮��p�^��ǂŃt�B�������g�d��10mA�Ȃ�Ă̂�����܂��B
http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ck549dx.html
Vf 0.625 Volts / If 0.01 Ampere�Ȃ̂�2�{����ɂ���1.5V�d�r�œ_�B �p�������Ȃ���p�ꂪ�S���_����>>470�̃T�C�g�̎g������������Ȃ����Ǔo�^�����ł����낤��
����Ƃ���t�݂����Ȃ̂��K�v�H >>471
�����͉摜�Ɛ������ꏏ�ɏo�Ă�̂Ŏg���Ă݂������ł��B
���邾���Ȃ炻�̂܂܂ł�k���� >>472
�傫�ȉ摜�Ō��悤�ƃN���b�N������|�b�v�A�b�v�Ń��O�C�����Ă˂ƌ���ꂽ�̂Łc >>473
�K�i�Ƃ��Ȃ�ʓr�ɋK�i�\���u���Ă���T�C�g�Ō��Ă�������Ȃ��ł��傤���� >>474
�������͉̂�H�}�̕��Ȃ�ł����
����Ȃ��ƂȂ炿���Ɖp��iry >>475
�Ȃ�قǁA�A�A
��̕⒮��^��ǂ̂Ƃ��̉�H�}���ƁA
Radio und Fernsehen 13/56 Egon Strampe
�Ȃ̂ŁAEgon Strampe����̒摜�ŁA�hRadio und Fernsehen�h�Ƃ���
���W�I�e���r�Z�p�̃h�C�c��G���A�A�A�A �����悤��12V�d���̂�12BH7A�ł�������Ƃ��邪�A�Ȃ��Ȃ��悭���������B
�o�O�Ɋǎg���āA�C���z���͖����킟�B
�P������
�[���l�Â��ɕ����鉹�ʂ��ȁB
�ۑ�
12�`�w7����{��7���K�p�����\0-�u-1�����B�r�r�a/�b�v��������
�����邱�ƁB
>>484
�R�Ɋǂ������Ă̂��h���Ȃ��B
�T�ɂR�ɂ̂U�a�k�W�A�U�t�W�����肾�ƌ��\�ǂ����\�̂��\���ł����������ǁB
�T�Ɋǂ̍��ʂ͖��͂����B�ő�70dB���炢�͉҂��āA����ɍĐ��_���B
�������̃N���X�^���E���V�[�o�[�̂��o�܂��ŁB �I�[�g�_�C���͈��̂u�e�n������A�a�d�������艻���邾����
���\���p�I�ɂȂ�B
���U������L���L�����G�G����
�Đ��Ƃ����A
http://www.tubebooks.org/technical_books_online.htm
�ɂ���Radio Amateur's Handbook, American Radio relay League, 1941�����Ă����A
����ɃX�[�p�[��M�@�̃~�N�T�[�ɍĐ����������Ă�Ⴊ����B�摜�ɗ��Ƃ��܂���������ł��B
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1035435.png)
�\�����͂Ƃ������A���ۂ̂Ƃ���ǂ̂��炢���ʂ�����̂��ȁH >>488
�������i���[�����W�ɂȂ��čs���܂����w >>490
�m�C�Y�̉����ς��Ƃ��܂ōi��ȃA�J��
�ȒP�ɔ��U����̂͒������Â��� �e���r�ǂ�AM/FM�X�e���I�g�߂邩�ȁH
�撣��ł��邾�낤���ǒ��߂���ς��낤��
�����������n�R�Ȃ́H�܂Ƃ��Ȑ^��ǂ������Ȃ��́H
�e���r�i���ɃJ���[�j����̐^��ǂ͎�ނ��L�x�������\���ǂ���
�S�i������ނ̋����g�������W�I������炵�����A�������͗ǂ����낤��
���\�����������薳���Ȑv�Ō̏ᑽ���Ƃ����Ɩ{���]�|������
>>494
���ʂ܂łɍɏ�����������B
���������ǁB ���Ƃ��d�C�����������ǁA��(40)�����܂ꂽ���͔���e���r�͊��Ƀ\���b�h�X�e�[�g(�|���p�Ƃ��������炵��)���������ǁA�^��ǂ̃e���r�̏C���͂܂����\�������炵���B
�^��ǃe���r�̗��̓����A�A�A�ݶ�ݶ
�|���p�̓q�[�^�[�\�M���Ă�s�u����Ȃ��������ƃO�O���Ă݂���
�L�h�J���[����y�ޗR���̃L���b�`�t���[�Y���ƍ��m����
>>500
�������ˁBCRT�W�͗D��Ă����B�ϑ��pCRT�Ȃǒ�]���������B
�A���A�^��ǂő����X�^�[�g������ɂ͏펞�]�M���K�v�œd�C�㖳�ʌ����̑��������ŁA���̓����~���[�h�������Ė��X����Ȃ������B
��ɂ̓g�����V�X�^�������CRT�̂ݒ��M�t�B�������g�ɂ��ċN���𑁂������B �L�h�J���[�̑����|���p�̃e���r�Ƃɂ����IC��g�����W�X�^��������
������ON�ɂ���d���X�C�b�`�̃m�u��OFF�̏��(���������)�ʼn�
�X�C�b�`�e��PL���t���ău���E���ǂ̃q�[�^�[���]�M�����
�����ǂ���g���Ă������قnj��ʂȂ������Ǝv��
�\���b�h��X�e�[�g����Ȃ��Đ^��ǎ��őS���̃q�[�^�[�\�M���Ă������Ȃ�Ɍ��ʂ���̂���
>>502
����͖T�M�^�J�\�[�h��CRT���g���Ă郄�c����Ȃ����ȁB
���ƋN����10���b�ȏ�|����̂��A�\�M���Ă������ƂŔ������炢�̎��ԂŌ�����悤�ɂ���B
������ŁA�N���ɂ͌��\���Ԃ��|����B
�ł����̒n�f�WTV���������m������̂Ɍ��\���Ԃ��|����A�|���p�ȏ�̒x�ꂪ����l�Ɋ����邪�B >>500�@�X�C�b�`���|���Ɖ����p�b�Ɖf�邪�|���p�̃l�[�~���O�B
���̌�^��ǃe���r�������Ȃ��������[�J�[������Ăăq�[�^�[�g����
���ė]�M����(���ŁFQuick Start �����FMagic Start�@��)
�����ɂ����̃��[�J�[�������Ό����̃g�����W�X�^���ɐ������]�M����
�q�[�^�[�̓u���E���ǂ݂̂ɂȂ����B
�����Ă��̃u���E���ǂ��q�[�^�[�̍ގ��ύX�ŗ\�M���Ȃ��Ă����b��
�f���o����悤�ɂȂ�]�M�X�C�b�`�͂Ȃ��Ȃ����B�i���������R���ҋ@�̏���d�͂�)
�n�f�W�͂����������@�R�[���h�X�^�[�g��>>504�������ʂ�TV�p�^��ǂ̊�{�X�^�[�g
���Ԗ�11sec�ȏォ����ƁB ����̃t���[���O���b�h�ȍ�Gm�ǂȂǃI�X�X��
6EH7��6BA6���炢�ɐ��\���Ƃ��ă��W�I�Ɏg���ł��ˁA�A�A
>>486
6U8 ��@6BL8�@���ƎO�ɕ��̃v���[�g��1�ԃs���A5�ɕ��̃O���b�h��2�ԃs����
�Đ����U�Ɠ����ɒ���g���U���N�����Ă��܂��̂ŁA6AN8�������݂������ˁB
�u���W�I�̐���1975�N7�����@�Z�g�p0-V-1�v�̋L������B >>504
�Ȃ�ق�
�\�M���Ă����Ă��t���݂����ɏu���ɉf�肾���킯����Ȃ��̂�
�����Ċm���ɒn�f�W�e���r���ċN���x�����
�u���E���ǂ͌Â��̂͏��X�ɉf���ė��邵
�q�[�^�[�Œg�߂Ă�Ȃ��Ă̂��������Ă邩�牽���v��Ȃ�����
�t�����Ɨ��ʼn��Z�����Ƃ����������̂�����Ă����Ă킩���ĂĂ�
�f��̂��x���Ƃ��C���C�����Ă��܂�����
�Ƃ���Ń��W�I�̘b��ɖ߂����ǃ}�W�b�N�A�C��6DA5���ĉ��������������������ď����Ǝ��̂��́H �n�f�W�̂�����ւ����x���̂̓_�������
�s�u�͘^��ł������Ȃ����ǂ�
TRIO����Lafayette HA-500�Ƃ�����M�@���ǔ��ǂ̃q�[�^�[���펞�ʓd�݂�������
�̂̃r�f�I�f�b�L�͌��I�h�~�Ƀq�[�^�[���Ă���
���̂͂��ĂȂ��̂��H
>>513
���̂͂��āA���B�@�ǂ�������ĂȂ��̂ɁB >>513�A515-516
VHS�f�b�L�͍Ō�܂Ő������Ă����t�i�C�����N���i�̐��p�Ő��Y�𒆎~������
�����݃r�f�I�e�[�v�̃f�b�L������Ă郁�[�J�[�͖���
����Ƀq�[�^�[�Ȃ�ĕt���Ă����H
���I�����ꍇ�ɂ�����Ƃ邽�߂Ƀe�[�v�������ŏo���Ă��炭�w�b�h����]������@�\������̂͂��������� �r�f�I�f�b�L���ăe�[�v����������Ȃ�����B
�e�[�v���͌��I����Ɨ��܂�̂��H
>>518
���������ACD��DVD�Ȃǂ��u�f�b�L�v�ƌ����Ă�̂����܂莨�ɂ��Ȃ��悤�ȋC������B
�e�[�v���̂Ɂu�f�b�L�v���g���āA�f�B�X�N���̂́u�v���[���[�v�������悤�ȁB
>�e�[�v���͌��I����Ɨ��܂�̂�
�r�f�I�f�b�L�̏ꍇ�́A�����p�̃w�b�h�̂悤�Ƀe�[�v�ĂĂ���̂ł͂Ȃ��āA
�w�b�h�ɔ����ȏ㊪���t��������Ńw�b�h���̂���]���Ă����B
������A�e�[�v�ƃw�b�h���ǍD�ɃX���b�v�����ԂłȂ��Ƃ����Ɠ��삵�Ȃ��B���I�͑�G�B �w�b�h�̓e�[�v�ɐڐG���Ă��镔�����������ǁA�w���J���X�L���������邽�߂Ƀe�[�v�p�X�Ƃ��ĉ�]�w�b�h�̑O��ɓ��a�̌Œ�h�������݂����Ă��āA���I����Ƃ��̌Œ�h�����Ƀe�[�v������t����Q���N����B
���I����ƃe�[�v���h�����ɒ���t�����
>>517
�ȑO�o�������u�g�r�̃f�b�L�ɂ̓��J�̃V���V��
�P�O�����p�ʂ̃Z���~�b�N�q�[�^���l�W�~�߂��Ă������� �\�h�I�Ƀq�[�^�[�ʼn��M����̂͂�߂āA���I�Z���T�[�����o������
>>517�Ă��Ƃɕς�����낤�ȁB�@�ȃG�l�ƃR�X�g�_�E���ŁB
�O���[���Ȃ�Ƃ��ŁA�ҋ@�d�͂��������Ȃ������B >>521
>>522
�����Ȃ̂̓q�[�^�[�t�����L�����̂�
���̓q�[�^�t���͎g�������Ɩ���
���I�����^�C�v�̂͌��I�����m����Ƃ�����莺�����}�ɏオ��ƍ쓮����݂���������
�ፑ������t�@���q�[�^�[���^�C�}�[�ł��ė\��^��̎��ԂƏd�Ȃ��ĉ��x�^��Ɏ��s�������Ƃ� �w�b�h������g�߂Ă�悤�ȋL�����������ȁB
>>499
�Z������
�e���r���ŕ�3�g�����Ƃ��Ă�����I�X�X���̋�����H >>525
6CB6��6BD6�ƍ����ւ��ėV�L������B ���������e���r�̍��������ق��ė̑т����Ă������悤�ȋL�������邯��
���������Ƌ����I�L�i�L���A�⎆�������̂悤�Ȉ�ۂ̏L���������̂���ۓI
1X2���ȁB
���ɂ����p�ł��Ȃ��Ƃ����E�E�E
������ː��ŃK���X���ώ����Ȃ����߂��ĕ��������ǖ{���Ȃ̂��ȁH
�g���Ȃ����́ALED�ŏƂ炵�ď���ɂ��邵���Ȃ��ȁB
>>527
�u�̑сv���Ă̂͂��������Łi�}�c�_�j�́u���M���ǁv�Ȃlj��炩�̃Z���N�g�`���[�u�������͂��B>>530�Ⴄ�B >>533
���傤��>>531�̃T�C�g��1X2B�Ƀg���u���h�~�Ɂ[���ď����Ă邯�LjႤ�̂� >>527
X�����O�ɘR���̂����N�ɊQ���o�Ȃ����x�Ɍ���������ׂ̉�����h�����ĕ��������Ƃ����� �l���Ă݂���̂�����̓d���ɂȂ��X�����ɋ߂Â��Ă����
�Ƃ���ŁA�v���[�g��������w�Ƃ��̃G�l���M�̕��o�}�̂͂Ȃ�Ȃ낤
�m���ɃK���X�͂�����ۂ����M���邯��ǁA�^��Ȃ̂ŋ�C�̑Η��͂Ȃ��͂�
IR�H
>>535
�Ȃ�قǁB����Ƀu���E���ǂ݂����Ɍu���̍�������A���̎���Ȃ�E�P�邩����
�r�W���A���n�I�[�f�B�I�}�j�A�����Ӗ��ɓo�ڂ�����
���̏L���͂Ȃ����낤�B�q���Ȃ���Ɋ댯����Ȃ��C������L�������� X���Ɠ������A�A�m�[�h�ɏՓ˂���d�q�Ŕ��M���ăX�e������Ȃ����ǃK���X�ɓ`���M���Ȃ��ˁH
���Ȃ݂Ɏd���Ŕ������n�}�z�g��X�����̓I�C���z�ŗ�p���Ă�B
>>536
�K���X�͐ԊO���ł͓�������Ȃ��̂ŁA�v���[�g����K���X���t�˂œ`��邩�� ����}�̂͂Ȃ�Ȃ낤
���̓_�ڐG�Ȃ납�H
�������A��o�͂̂̓v���[�g�ނ��o�������ǁB
�^��ǂ̐^��x�Ȃ�đ債�č����Ȃ�����M�͓`���
>>543
�Q�b�^�܂Ŏg���Ă�̂́A�^��x��萬���̖��Ȃ�ł�����
����d���ł͂��Ȃ�̐^��܂ň����܂����ǂˁB�܂�����̓|���v�q�����ςȂ��̊��ł�����B �^��ǂ̐^��x�ƁA���@�r�̐^��x�͓������炢(10^-8Torr)�����ǁH
�`���ƕ��˂����C������Ȃ��̂���
�u���E���ǂ͉����d������������d�q�r�[���Ŋm���ɕ��ː����o�đ��߂�ꂽ���ǁA
�����ǂ��Ă̂́A�t�����͑S������Ȃ����A�������͂قڒZ���ŁA
���d���ɂ��d�q�̉����̏�ʂ��������ǥ������B
�ł͍��d���Ƃ͊W�̂Ȃ����M���ǂ̗Αт͉��H�H
�X�b�L�����Ȃ��b�B
�M���˂͐^��ł��`���B���z���G�l���M�[�ȂǓT�^�ł͂Ȃ����I
�^��ǂ̏ꍇ�A�x�[�X�̖����\�����ƃX�e���������ʂɓ`��邵�B
>>546
�d�q�e���āA�v����Ƀx�[�^�������킾����ˁB�l�Ɍ������B >>546
�~�̊������́A��C�╗������Ƃ͂������ˌ��Ă����K���X���̂͗₽���܂�
���܂肻��قlj��x�ς��܂����H ���K���X�͌���ʂ�����Ȃ�������
���Ȃ݂ɃT�b�V�͌��\�M���Ȃ�
>>548
�{�C�Ō����Ă�Ȃ珬�w�Z�̗��Ȃ����蒼���Ƃ����� >>550
�����爫�����A���ɂ��Ĕے肵�Ă�̂��ȁH
>>548�@���������������̂����킩��Ȃ����
�����Ă��������ȁB >>551
�~�̑��z�Ȃ�Ă���Γd�r�ǂ̃t�B�������g�݂����Ȃ���Ȃ���₽�����Ă���Ⴛ����
�Ă͑��K���X�����Ȃ�M���Ȃ�ł��� �܂����A�M�͐^�Ɠ����Ȃ��Ǝv���Ă��Ȃ���ȁH
������������Γ`��/�Η��͋N���Ȃ���
�^�ł����˂ŔM�͓�����B�^�щ����ԊO���B
>>552
���K���X�̉��x�͋C���ƃT�b�V�̉��x���`���̂��傫������B >>554
�C���̉e���Ȃ�C���ȏ�̉��x�ɂ͂Ȃ�Ȃ����T�b�V����̔M�`���Ȃ�T�b�V���痣�ꂽ�Ƃ���̉��x�͒Ⴍ�Ȃ�ł��� �N���T�[���O���t�B�ő����Ă�B
�������Ղ����������ׂāB
>>556
��{�́u���́v�t�˂����瓧���Ȃ��̂Ƃ����˂�����̂͑����ȁB
�M�d�Γ\��t���đ���낤�ˁB >>558
���̃e�[�v���g�������ŔM���Ȃ�Ǝv��Ȃ��H ���g����B
���肷�鎞�ɓ������Ղ��Ă���\�t���đ���Ηǂ��B
�e�[�v���̂̔M�e�ʂ͏\������������w�ǎ��Ԃ��������ɑ�����B
�Ȃ��̒��x�̃R�~���j�e�B�������̂��A�����B
>>548�ŐU�����b�肪����ȂɂȂ�Ȃ�� �킩��₷�������
�܂ǂ����ɂ����Ă����т��݂Ă�Ƃ˂������
�ł��܂ǂ͂��̂���قǂɂ͂����Ȃ炸������ɂ�������
(���Ȃ��������Ȃ�������Ƃ���)
���傤���������ނ��̂Ђ�������Ă�ɂ̂��Ă�����
�Ƃ��߂���͂�߂�͂ق����Ⴈ��ǂ����ł͂���Ȃ���
�ق������Ƃ����ǂĂ���傤�����ɂ����̂ŁA
���̂������ɂƂ肭�����Ƃ͂Ȃ��Ȃ��䂤������������
>>564
�Ă̔M���������K���X�͔M���Ȃ��̂��H�� �l�����n���ɂ���z�Ƀ��N�Ȃ̂͂��Ȃ�
���K���X�ƌ����Ă��F�X
�M���z���K���X�Ȃ�Ă͔̂M���Ȃ肻�������A
���ʂ̃K���X���ƋC��+���ɂȂ邯�ǁA���̕��݂�����
�A�b�`�b�`�ɂ͂Ȃ�Ȃ���Ȃ��̂��H
���ǂ̂Ƃ���A�u�����Ă���M>>>���ˁE�Η����Ŏ�����M�ʁv�Ȃ�A�K���X�͔M���Ȃ�B�i�ȉ�ry
���Ȃ݂ɁA���ӂɔZ�����x�̋�C�̑��݂��Ȃ��q�����ڋ@��ł͑Η��ɂ���p�͂Ȃ����߁A���M�v�͂��Ȃ�ʓ|���������B
>>547
���G�l���M�[�̓d�q���Փ˂��邱�ƂŔ�������K���}�[���̖��B
�A�m�[�h�d����1000V���x�̊ϑ��pCRT����قƂ�ǖ��ɂȂ�Ȃ����ATV�pCRT��
14000V�`24000V���Ƌ���ȃK���}�[����X�����������āA
���s�\�����ƌ��N��Q�����O����邱�ƂƂȂ�B >>569
���������ΐ́A�g���I���������P���E�b�h���������̍��A�I�V���̐�`��
�����d���̍������₽��Ƌ�������Ă��ȁB
CO-1303D������t���������Z���ɂ́A�_�̏�̂悤�Șb���������ǁB >>568
�K���X�ɕ���ꂽ�^��ǂ̃v���[�g�͂���ɋ߂��C���[�W�Ȃ�ł����A
IR�Ƃ��Ă����ӂ̍\����@��ɔ�׃K���X���\���ɔM������̂��t�V�M �����M�ʁ����U�M�ʂŕ��t��ԂɂȂ�A�����قǕ��M�ʂ��傫���Ȃ��ŔM���t����B
�^��ǂ̔��M�ʂ͂قڃq�[�^�[�{�A�m�[�h�����ŁA6.3V�~0.4A�{250V�~37.5mA��11.9�mW��J/s�n��6AQ5
���ꂾ���̔M�ʂ��A�X�e���ƃK���X�Ǖǂ��痬��o�ĔM���t���Ă��ԁB
������אg��6AR5�͍����ɂȂ�₷���A������������Ă��A���Ȃ葾�߂�6BQ5�͂������߂Ƃ��������ۂɂȂ�B
�X�e������̔M���o�͓`�������A�K���X�Ǖ��͕��˔M�Ƃ��ĐԊO���Ŏ��������āA�ꕔ���K���X�ǂ�M���āA�O�C��ĕ��o�ŗ�₳���B
>>570
�g���K�[�h�E�I�V���X�R�[�v���V���N���X�R�[�v�i���i���j�ŒZ���Ԃ̌��ۂ�����Ƃ��ɍ��P�x���v������č��������ɂȂ������́B
�u�A���E�u�����L���O�v�@�\�ŁA�|�����������������邪�A���̔������Ԋ������Z���قǍ��P�x�ɂ��Ȃ��ƌ����Ȃ����炾���A
�z���g�͉����܂ŕK�v���������A�J�^���O�f�[�^��������Ȃ��������A�ƂȂ�ƃ}�C�i�[�ȃ��[�J�[�قǍ������ւ肽�������낤�˂��B ���Ɣ�r���ĉ��x���z���v�ł���
>�}�C�i�[�ȃ��[�J�[�قǍ������ւ肽������
������J�^���O�X�y�b�N�ł��ˁB
���͂ō��𐘂������[�J�̐�`�͎��f�Ƃ����̂���ʂł���
����ɒނ���悤�ȑf�l��ɂ��Ȃ��Ƃ����̂�����ł��傤���ǁB
>>572
�g���I���ă}�C�i�[�ȃ��[�J�[�Ȃ̂��H
��w�̎��A�g���I�E�P���E�b�h�E�e�N�V�I�ɂ͂����b�ɂȂ�����w >>575
��Ƃ�Y�ƂŃ��C���Ŏg���Ă���āA�܂������̗l�q�����C���ǂ߂�Ǝv����B �H�ƍ��Z�����w�Z�A4��ł���b��H���K���ăC���[�W���ȁB
�e�N�g���͍��������̎��͂���
>>575
�I�V���Ȃnjv���탁�[�J�[�Ƃ��Ă͎��Ƀ}�C�i�[�B
�A�i���O����̓e�N�g���A�f�b�h�R�s�[�̊�ʂ������āA
�������ŏ����͂��̉��A�RQ�A�g���I�A���[�_�[�Ȃǂ�����ɉ��B
��ʂ̎��Ԏ��͈��肵�Ă��ĕs�����邱�ƂȂ��g���Ղ�������ŁA���o���Č��\�D������������w�B
>>578�̒ʂ�B���{����㔭�ɂȂ���HP���ǂ������B >>575 >>579
�����āA�u�g�����V�X�^�[�E�A���v�̉��͍d���I�v�Ƃ����T�_���m��������悤��
���������̃I�[�f�B�I�A���v��^����ɏ��i������A����ƓI���[�J�[�I
�g�����V�X�^�[�����ŃJ�E���g����Ă����ꊴ�Ƀ}�b�`���āA
�g���I���g�����V�X�^�[���L�̃q�X�E�m�C�Y��m�b�`���O�c�݂��c�����܂ܐ��ɏo���Ă��܂��������̂Ђǂ���
���炭�����Ȃ��}�C�i�X�C���[�W��蒅�����Ă��܂����B
�@���ۂɂ�SONY���A���̌�Ɏ��А��V���R���E�v���[�i�[�^�̃g�����V�X�^�[�ŃA���v���\�����A
����TV�o�͗p�g�����V�X�^�[����̃Z���N�g�i���g�����Ӑg�̃p���[�A���v�ŕ���Ȃ��������Ă����̂ɁA
�����ق������^���ɋL���������ق����܂Ƃ��Ȏ����Ȃ��āA�s���ȓ`�����Ɉ��������Ă��܂��A
�����܂����ɐ₦�Ă��Ȃ����e�����c�����ƂƂȂ����I
�@�����̃g���I�̃A���v�v�w�͒��������c���f�[�^���d������悤��
���̗ǂ��Ȃ��z�����茠�������Ă����̂ł͂Ȃ����낤���B >>575
�e�N���̒����d�����_�����Ă��܂�B
�����Ă������Ă�����̂ŁA�����̉�Ђ͏o����֎~�B ���������Ђ̓s���ł��̃��[�J�[��DC�d���g�������Ƃ���
�����Ƃ��e���̖�����g�������������ǁB���̎���Ȃ珼�����l����
DC�o��(���SV��A)�́|�R�����Ɛ�����͂̃R���������ʂ�
�p���X��̕��ׂʼn�荞�݂ł̃g���u�������B
�ł܂��Ă��܂��ēd�����Z�b�g�B
���Ђ���S�R�]�T�Ŏg���Ă��̂ɁB
>>580
CM�Ƃ��������������ȁB
30�N���炢�O�A�j�m�~�������Ń��[�_�[��g���I�̃I�V�����߂�
�J�^���O�����ċA���Ėϑz�ɐZ���Ă��Ȃ�
���̎����ɕ����Ԃ̂́A4����8�g���[�X�̂ɂ��₩�ȉ�ʁ�AM�̕ϒ��g���r�f�I�R���|�W�b�g�����T�[�W���B�A�i���O�g�`�̐^�����B �g�����V�X�^�[�̎Ⴂ���ɃR�X�v����������
6R-DHV1�݂����ȕϑԐ^��ǂœ��萫���ǂ��̂��Ă���H
5-3-2�Ɋǂ��Ɠd�r�ǂ���1D8��tubedepot��5�h��95�Z���g����
�����ɂ����邪�P�����W�I������
>>586
�d�r��1�{�ł��낢��y���߂�������
�֗������Ȃ̂ɕ��y���Ȃ������͉̂��̂��낤�c
����Ɠd�r�ǂ�q�[�^�[2.5V�`3V���őo�O�ɂ��Ă��������ȁH
��������������ƂȂ� >>587
1���Ńg�����V�[�o������`���̑o3�Ɋǂ�3A5�����邶��Ȃ��ł����� >>587
�d�r�e�ʂƏo�̖͂�肾�낤��
�g�����W�X�^���W�I�̑傫���Ő�10mW�Ȃ�܂������A���������̑傫���ł͎��p�����C�}�C�`
3.5V�܂ŋ��e����Ȃ�7AU7���o�O�� >>588
�m��Ȃ�����w
>>589
�m���ɃC���z����p�̃|�[�^�u���ɂȂ����Ⴄ��
�o�O�ɊǂŃO���b�h���g�Ƒ�������d�r���|�[�^�u���g�݂�����
1T4�A1U5�͉��i���������Ă邩����������Ƃ��� >>590
�C���z����p�ɂ�肫��Ȃ�T�u�~�j�ɂ���Ƃ��������R���p�N�g >>585
�R���p�N�g�����Ȃ�̂Ēl�ł�����ł� 5678��������Ή��ł��o�����w
5678�́A�d�r�ǂƂ��Ă͖��\�ǂ���ˁB�̂���A��Ⴊ�������B
5678��5672�͔����Ƃ��đ����Ȃ���ˁI
5678����VT�M�ǂɎg���Ă������H
>>596
VT�p�͌^���s�������ǁA�����Ə��������h���^��ǂ���B
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.tubecollector.org/equipment/proximity-fuse-valves.jpg)
��H�}������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://patentimages.storage.googleapis.com/pages/US3166015-1.png)
>>598
�ǂ�����5678�����Ă̂������������Ȃ�
���ɂȂ����Ƃ����������̂Ȃ̂��� ���˖C�e�����˂���鎞�̉����x�ɑς��Ȃ��Ⴂ���Ȃ��������ǂȂ�
>>596
�G�[�R���ǂ���Ȃ������H
�T�u�~�j�̓g�����V�[�o�[�̃C���[�W ���̉摜������肾�ƃT�u�~�j���ۂ�
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/b7qsCeZ.jpg)
����������Ȃ�����p���ʎY���ăo�J�X�J�����Ă��鍑�͂���ϋ����� >>603
���ʂɃ~�j�A�`���A�ǂ���Ȃ����H
�e�������͏������悤�Ɍ����邯�Ǘ���ŕ�����T�C�Y����
(FH70��M107�֒e�A�d�������ȁ`)
�d�r�͂ǂ��ɓ����Ă���̂��ȁH >>604
�o�b�e���[�́A>603�̍��̃l�W�̓���������B�K���X�A���v���ɓd���t�������Ă��āA���ƃA���v���u���[�J�Ɋ����Ĕ��d���J�n����B >>605
���d�r�Ȃ̂��B�Ă�����M�d�r���Ǝv���Ă� ���������ΐ̃��W�I�]���f���^��ǂ�����
���͕̂��i���̗]�n���Ȃ����瓖���E����������w
�A�L�o�ŃW�����N�i�̌Â��d�r�ǎ��̃��W�I�]���f�̒��g���Ă�̌������Ƃ���B
�o���ĂȂ��A�A
����DF**�Ȃ�Ă��������h���Ă����ē��{������Ȃ�����
���B�n���B�@���Y�̃\���͗L���������ł���VHF�т̎��Ê�̋����E�⋅ �悭�̔��o������
�G�@�ƌ㔻�ʂ�����
������DF�Ȃ����Đ^��Ǐo���ĂȂ������H
�����悭�����̂͐���4�������̂��
�����̓t�B���b�v�X����Z�p������������@DF���t���������\�����邩��
���O��(����?)GT�Ǎ���Ă������͐��\���o���@**-***GT-M
���ĕt���Ă��l��
>>614
DF 67 �� 6008
DF 91 �� 1T4
DF 92 �� 1L4
DF 95 �� 1AJ4
DF 97 �� 1AN5 �����̓d�rmT�ǂ̓t�B�������g��25mA�̂��������ˁB
1A**/DF**�Ƃ����͕̂��L�ɂȂ��Ă��B
��l�̉Ȋw��
�d�r�ǃX�[�p�[���W�I�o���Ă���Ȃ����ȁB
�g���d�r�͂������}���K���d�r��
>>617
-SF�̂�H
>>619
A�d�r�̓��N�����V�F�d�r�AB�d�r�̓{���^�d�r��w ������^��ǃ��W�I�͂��ׂāA�܂Ȕ������B
�ŋ߂͂ǂ�Ȃ܂Ȕ��g���������̐^��ǃ��W�I�̃e�[�}�ɂȂ��Ă���B
�Ȋw���ގЂ̂��܂ڂ��V���[�Y�݂����Ȋ����H
�́A�i�X�ǂ�RH�ǂ����h��̔ɔz�u�������W�I��������w
�J�Z�b�g�P�[�X�V���[�Y�Ȃ�Ă̂�
�t�B�����P�[�X�R�C���Ƃ��B����Ȃɂ������̂ɁA�t�B�������������B
>>625
�ʐ^�p�t�B�����͂܂������
�t�W�̃l�K�����Ńv�������܂߂Ă܂�6��ނ���
�ʐ^�X�s���������ɂ����Ă����
�R�_�b�N���܂�����Ă邯�ǂ������͂Ȃ��Ȃ������Ȃ� >>627
135���o�[�T���������ˁB�I���̗]�n���قƂ�ǂȂ�
�Ȃ�ł��R�e�R�e�R���g���X�g��� �I���́ATri-X������������B76�́A���܂���B
�≖�J�������b��ɂȂ��Ă��ĂӂƋC�ɂȂ����̂Ł@�v���Ԃ�ɐG���Ă݂�
�y�g�� FT �����グ�������|�����ē����Ȃ�(2���)�@�e���g���Ă������날�����������B�C���L�^���B
����@OM-1 �v���Y��������āc
�L���m�� �I�[�g�{�[�C�e�� �d�r�I���B�@�����炵���ĂȂ��Ă悩����
�x�m�@�`�F�L�@���[�����Δ������������Ȃ��Ɓ@�d�r�͏I����Ă��邵��̈�掆�P�[�X��������ςȂ��B
�y�g���ɂ��您�邿���ɂ���H-D������ł��Ȃ��Ȃ��Ă͂邩�̂̐��V��Fxx�ŃV���b�^���x1/xxx�ɖ߂��āi��
>>630
H-D�d�r�͎_����d�r�܂��͕⒮��p�ɔ����Ă��C�����d�r�ő�p�ł���
�_����d�r�͓d�������������d����H�������ĂȂ��ƘI�o�l�������炻�̏ꍇ
��C�������g�������������1��V�[�����͂����Ǝg��Ȃ��Ă����d�𑱂��Ď����Ɏ����Ă��܂����璍��
�Ƃ���Ő���d�r�͉��Ƃ���p�i���L�邯�Ǔd�r�ǃ��W�I��A�d�r��B�d�r���č��ǂ����Ă�́H ���J�̑��M���̋L�O�قɂ͂��������Ƃ�����
�^�p��Ԃ̖{�������Ă݂�������
�����œǂ��ǁA�������܂��������M�@���̂���
�J�ݓ����̔��d���K�͂��炢���A���Ȃ�X�p�R���{�݂݂����ȓd�͎��v��
�������낤��
���̈ˍ����̒��g���M�@�łǂ�����ăL�[�C���O����̂��Ǝv������A
����ȃR�C�����g���Ă��̂�
����DC�Ń`���[�N�R�C����O�a�����ăC���_�N�^���X��ω������Ă��ł�����
����DC�p�̔��d�@���킴�킴�������悤��
3�Ă��{�R�C�����Ƃ��A�X�v���A�X���傫�������낤��
��M�@�⑪���̓s����
�m��悵���Ȃ���������������
�ΉԎ����M�@�ɂɂ���ha
�u�ΉԎ����M�@�v
�Ō�������ƁA
�w�����Ȋw��n�x�L�ڂ̋L����
�݂���܂��B
>>638
�ߍ����͉ΉԂƑS���Ⴄ���̂ł���
�Ƃ���ł��̃L�[�C���O�̉�H���A���̋C�ɂȂ��
AM�ϒ����邱�Ƃ��ł����̂��� >>639
�}�O�A���v�̓X�C�b�`���O���삾�������`�̕���s��Ȃ��Ɠ���Ǝv���B
���Ă�18k���x�̔����gAM���ĉ��l���邩�ȁH >>631
A�d�r�͒P1�A�P2���g���邯�ǃA���J�����}���K���̕����ǂ�(�����d����)
B�d�r�̓X�y�[�X�ɗ]�T�������6F22�d�r(9V)��5�`10����Ȃ�
�X�y�[�X�ɗ]�T���������23A�d�r(12V)��������Ȃ� ��1���W�I��g��ł���ǁA
2�i�ڂ̃R�C���̓A���e�i�R�C���ɑ��Ē��p�ɋȂ�������������ˁH
>>644
���U���邩���
�ł���V�[���h����Ȃ�V���[�V�̗��\�ɕ����ꂳ����Ȃ���Ă̂�������������� >>645
�T���N�X�B
�V���[�V�̗��\�ɂ͕�������ǁA����ł���������������������ˁH
�莝���̃R�C�����f���ɑg�ނƃA���e�i�R�C���ƕ��s�ɂȂ����Ⴄ���
�X�e�[����B >>646
�����������
�ł��邱�Ƃ͂���Ă����ׂ� 6EH7���g����0-V-0+LM386������Ă݂��B
�Z�g�тŎ����������傫�߂̃X�y�[�X���̃R�C���ł���Ă݂����A6BA6��6AU6�Ɣ�ׁA�^�b�v�̈ʒu�������ԉ��������B
�v���O�C���R�C���ő��o���h������ꍇ�AQ�͉����邪�R�C���͂Ȃ�ׂ����^�����z���������I�ɂ��Ȃ��ƁA�^�b�v�����͂��Ȃ���ɂ����Ȃ肻�����B
���x�́c����߂��ȁB�i����킪�Ȃ��̂�ry
����i5���X�[�p�[���C�����Ȃ��ǒf������IFT�̑����
�g�����W�X�^�pIFT��Ód�����ő�p���悤�Ƃ��Ă���A
�����R���f���T�͍��ψ��ł���Ηe�ʂ͉��ł������́H
���i���ɍs������1KV�ψ�100pF�̐ϑw�Z���R�����ŏ��e�ʂ�����
���܂�������
�Ód�e�ʂ̌덷�͈͂��傫��
���x����������
���x�ɑ��ĐÓd�e�ʂ������I�ɕω����Ȃ�
�o���ɂ��Ód�e�ʂ��ቺ����
���͖S���X�`�R���̂ق���IFT�Ɏg���ɂ�
�U�����ڂ������� tan��0.001
�Ód�e�ʂ̌o���ω������Ȃ��قڈ��
���x������-150ppm/���ƈ��
�����Ɏキ���c���Ă̔M�Ȃǂŗn������
������������v����Ȃ��ł�����
>>650
�^��ǎ��X�[�p�[���W�I�O��K�C�h����4p������
�ψ�500V�Ƃ̂��Ƃ����ǃg�����X���X�����炩�ȁH �W�����t����������荇�킹����x�łȂ�Ƃ��Ȃ�Ȃ��H
>>653
�����̓d�C�@�K�́u�ሳ�v�敪�̌��E������500V����������A�}�C�J�E�R���Ȃnj��X���ψ��͈̂�ʒሳ�p�K�i500V�ɂ�����ł͂Ȃ����ȁB
���������ȃP�~�R���Ȃǂ͂����ƌ����ɁAWorkVolts�^Sardge Volts�Ƃ��K�肳��Ă�B
�����Ă�AC350V���́u�����v�����ŁA���M�@��Â�TV�����o�͊ǂȂǂ��g����Ŋ���߂̖������Ă����B
CRT�̃A�m�[�h�͌��X�����Ȃ�ŁA����͂ǂ����������ŋ������̂��˂��H
���d�C�@�K�����d�C�H�앨�K��A���d�C�ݔ��Z�p��A�ʎY�Ȑ��߁��o�ώY�ƏȐ��߁B�d�C���Ɩ@�Ɋ�Â����߁B >>655
���Ⴂ���Ă�C�����邯�nj���̍�Ⴞ����@���]�X���Ęb����Ȃ���
�����P�Ƀg�����X�����Ƒψ�500V���Ⴞ�߂ȂȁH���Ă����� >>650
100PF����傫�����B
�����W���́A����0.01���炢�̃��x���ɂȂ�B
�����W���́A������H�̓����e�ʂɑ��錋���R���f���T�[�̊����Ǝv���Ă����B
���e�ʂ���ɓ���Ȃ��Ȃ�A���ψ��Ŕ핢�����߂̒P�c�����Ђ˂�̂��A�퓅��i�B�i�V���[�g�E���ʋ����ɒ��Ӂj
�s���Ȃ炻�̔����Ă��鍂�ψ���100PF�ƒ���ɂ��������邪�A�o�C�p�X�p�̃R���f���T�[�͌덷�����x�������ɒ[�Ɉ������Ƃ������̂ŁA�����߂��Ȃ��B
���Ȃ�A
1�F���ψ��i�^��Ǘp�j�̃}�C�J�R���f���T�[���Z���~�b�N�R���f���T�[��T���B
�i�Z���~�b�N�̏ꍇ�́A0���x�v���̂��̂Ɍ���B�E�E�ꕔ���������F����Ă���B�j
2�F���������e�ʁi��PF�j����ɓ���A�����B
3�F100PF�i���ψ��j������ȏサ����ɓ���Ȃ��Ȃ�A�����ɂ��ĒP�S�Ђ˂�ɂ���B
4�F���e�ʂ͎�ɓ��������ψ����Ⴂ�Ȃ�A��3�Ɠ��l�ɂ���B
>>651
���ψ��̃X�`�R���́A�������s�Ƃ����Ă������x���ł́H >>650
���i������o���Ȃ���Ή�H��P�����ɕύX������H
���\�͗����邯�ǁB
�f�����Ă��Ȃ����̃R�C����ϊ��ǂ̃v���[�g���ׂɂ���B
�ϊ��ǂ̃v���[�g����IF�ǂ̃O���b�h�ɂ͓K���ȃR���f���T�[�Ō����B
IF�ǃO���b�h���獂��R��AVC���C���ڑ��B �P�����ɂ���Ȃ珉�i�̂Ƃ���ɃZ���t�B�����܂���ΑI��x�I�ɂ͖���������
�Z���t�B���̓C���s�[�_���X���Ⴗ���邩�琮����H���ʓ|�ɂȂ�ˁB
�R�����Y�Ƃ��擪�Ƀt�B���^�������ĂāA���Q�_���v����IFT��IF�������Ȃ��ł��悤��
�Ȃ��Ă���
>>651
�X�`�R�����ē����ȃI�[�f�B�I�p�̍�����������H
>>657
�傫�����邩�c
���������Z���R�����S���ƌ����Ă����قnj������Ȃ����B
�P�c�����Ђ˂��i�����ǒP�c�V�[���h���ł������������ȁH
>>658-659
�ł�������H��ς����ɏC��������(���ŗ����ł��ĂȂ�����������w) 5��������IF�͐���ׂ�Q���グ�����Ƃ��낾�B
�g�����W�X�^�pIFT�ŒP�����ɂ��Ă�C���s�[�_���X�͎����ƒႭ���܂�Ǝv��
������Ǝs�̂�IFT�Q��g�ݍ��킹���Ⴊ����Ǝv�����玩���ɂ������̂�I��H
�X�`�R���͖����Ȃ��Ă��}�C�J�Ȃ炠���Ȃ����ȁH
>>665
�}�C�J�ł��܁A�������A
by �W���}�C�J�e�� ����Ȃ��Ƃ��������Ȃ�����?
����������I������
�}�C�J���A�Ə���������ƃN�X�b�Ƃ����̂ɁA�A�A
�킴�킴�u��I���v�������ɂ������Ƃ͊������Ⴂ������
�������̃R���f���T������300pF���x�܂łȂ炻��Ȃɉ��x�W��������邱�ƂȂ�
���̂�����̗e�ʂ�B�����Ƃ��܂��Ȃ��Đ��Sppm������100�x�ς���Ă�1%���炢�̕ω��������قǓ����C�ɂ���t�B���^�[�łȂ������Ȃɂ����Ȃ��ł���
�V�����ƁA�u���v�Ɂu��v���g���̂́A�c�������B�}���ȁB
Intermediate Frequency Transformer
���������AXtal�̃I�[�o�[�g�[�����Ă�
�؊NJy��̃��[�h�~�X�A�z���Ă����C�����Ȃ����
SAX�̃I�N�^�[�u�L�[���Ǝv������
>>678
���̊y�킾�ƍ����g���t�i���|���j�N�X�t�@�j�Ȃ�ď펯�I����B
�M�^�[�Ȃ�
12�t���b�g��2�{�i�{�P�I�N�^�[�u�j�A
7�t���b�g��3�{�i�X�x�{�P�I�N�^�[�u�j�A
5�t���b�g��4�{�i�Q�I�N�^�[�u�j�̉��ŁA
�y���\�L�́A�Ǝ���Arm.12�A�Ď���Hrn.12��Hm.12
�i���l�͉��������̃t���b�g�ԍ��j�B
�I�[�o�[�g�[���̏ꍇ���ɂ��[�q�Ɍ���Ȃ�������Ȃ�����������͓���ł����A
3�{�A5�{�A�����i������A���p�I�ɂ�7�{���x���g�p���E�B
�A���A�����{����͔����ȃY�����Ă���B >>680�@�@����
�~> �y���\�L�́A�Ǝ���Arm.12�A�Ď���Hrn.12��Hm.12�B���|���j�N�X�t�@
��> �y���\�L�́A�Ǝ���Arm.12�A�Ď���Hrm.12��Hm.12�B�n�[���j�N�X�t�@ >>680
�Ӑ}�������[�h�~�X�Ȃ�āA������l�^�Ɏ�����Ȃ�����܂����蓾�Ȃ��B �I���̃g�����y�b�g�́A�ǂ̔{�����邩
�����Ă݂�܂ł킩��Ȃ��B
�_�C�������ɍœK�Ƃ���Ă�O���������ĉ��Ԃ������́H
>>684
���Ԃ��ɂ��Ă��A�u�����v�͂��߂���w
�����ȑO�O�����̎������Ƃ��́A�N���V�b�N�M�^�[�Ɠ��l�̍����@�ۂ̎��������B
�_�C�������̑�p�ɂ���Ȃ�A�����łł��������B �I�N�Ŕ����Ă�̔���������������ˁB
�I�N�̂��i�C��������Ȃ������H
�V�i���������͉��̎��g���Ă��́H
9R-59D�̎������������ɃV���R�[�̂��o����Ƃ��Ń_�C��������������
��3���W�I���v�X�ɑg���ǒႢ���g���ōĐ��̊|���肪�����̂͂Ȃ�ł��ȁH
�Đ��R�C���̊����𑝂₷�����R���̗e�ʂ𑝂₵����H
�Đ����͊��x�������ǁA�g���Ă��璲���߂�ǂ��B
�����Œ������Ă�����H���ĂȂ��̂��ȁH
�s�����Ƃ��낪�A�[���X�g�����O�̃X�[�p�[�w�e���_�C���ɂȂ�B
�A�[���X�g�����O���Ă�������ˁB
���W�I�̉�H���������邵�A�F����s�m�ł�����
���Ďv���Ă���������܂���
�������W���Y�E�W���C�A���c�̈�l�Ȃ��
�w���́A�u�F���v�u�����E�ʐM�v�������̈��Ǐ��ł���
>>695
����ς肻�ꂵ���Ȃ��ˁB�T���N�X�B >>698
�����ߎ��̐V�^�̑�C�̔�������������
�ꗗ�̃R�s�y�������C������ �A���e�i�R�C���Ƌǔ��R�C�����芪�����삵�A
6wc5-6d6-6zdh3a-42��4���X�[�p�[���������B
�����ǂ͎�ɓ���Ȃ������̂ŃV���R���c�ő�p�B
6wc5��7�s���\�P�b�g������ł����A���������B
80BK�Ƃ����荢��ȁH
����������ST�ǁA�����͐^��ǂł��傤
>>703
�^��ǖ����������ŏ����̂͂ǂ��ɂ��Ȃ�܂��B
�^��ǐ���Ƃ��Ă͂ƂĂ���a��������܂� �g�����W�X�^�ł�IC�ł��������͈�a������܂��ˁ`
�ʼnY��6R-DHV1����1�{�ŕ�3�g�߂�炵���������悤��TV�����Ă���H
>>707
�R�Ɋǂ��R���j�b�g�̂͂��邪�R���p�N�g��������B
�\�P�b�g������B
�d��������Si�_�C�I�[�ɂ��đo�R�ɂ��g���H >>703
6.3V�̊����ɗ]�T������ΐ�����84/6Z4����������
�������O�`��T�ǂ̂�����̂Œ��� >>707
�f����6BM8�����̃q�[�^�Ⴂ��8B8,16A8�Ƃ��ō��
�����̂���6AB8�ō�� >>711
6GW8��14GW8�������ˁB >>707
�^��ǂP�{�ŃX�[�p�[��������Ƃ������Ƃ�������
�w�^��ǂP�������x�i���c�닅���A�}�C�N���}�K�W���ЁA2005�j
�Ƃ����{�����邩��A�Q�l�ɂ�����ǂ��ł��傤���B
�������A��k��1�O�N�ȏ�O�̖{�Ȃ̂Ŏ�ɓ��邩�ǂ���
�ۏ�̂�����ł͂���܂��B �̂̃��W�I��PU�[�q�̂悤�ɁA�O���b�h���g��G�̂Ƃ��փR���f���T�����
�I�[�f�B�I�M����������悤�ɂ��Ă����ƃA���v�Ƃ��Ă��g���ĕ֗�
�����W�W�C��������
�������^��ǎ
����ɂ��Ă����X�Ȃ��Ȃ�Ȃ��^��ǁB
�}�O�l�g�����i�d�q�����W�j�A�u���\���ǁi�����Ɠd�j�A�i�s�g�ǁi�q�������j�A�͓��������c��B
�������̃R���f���T�[�}�C�N�ɓ����̐^��ǂ����Ă܂�����l���B
���ً�`�ɒ��������\�A�̃~�O�����ă��[�_�[�W�Ȃ�^��ǂ͓��R�B����͈�ۑ��씭�\���Ȃ��B
>>717
�k�C���̃~�O�Ƃ��A���̘b����B >>718
�H�}�O�l�g�����͌����ŁA���܁A�h�R�̂����ɂ�����d�q�����W�̎�v���B�~�O�̃��[�_�[�������x���B >>719
��������̂܂܂Ȃ�A�A�r�I�j�N�X�܂œ����̂܂܂��Ǝv���Ă�N�`���B >>719
���������A�\�A�Ȃ�Ă���������B >>716
�䂪�Ƃ̐^��ǂ������Ȃ�Ȃ��B�^��ǂ����ӕ��i���������āA�H��ɐi�߂Ȃ��B���Ƀg�����X�Ƃ��B �I�V���X�R�[�v��CRT���܂��܂��B
�f�W�^���I�V�������ԗǂ��͂Ȃ��ė������ǁB
�܂��A�i���O�I�V���g���Ă�l������ˁB
>>717
�̂̓t�@���q�[�^�[����ȒP�Ȏ��v�܂Ŏg���Ă��u���ǂ�����
���X��LED��o�b�N���C�g�t���t���ɕς���Ă����Ă�������ł���^�����Ǝv��������
�ӊO�Ƃ��ԂƂ��c���Ă��� >>725
�����炭OLED�Ƀg�h��������� �u���\���ǂ͐����o��Έ����ȁH
�m���^�P�����N�u���\���ǂ݂����Ȑ^��ǂ��������
�M�^�[�A���v�̍�����͋��������B
���ƁA�~�O�Q�T�̋��̓��M�����[�^�炵��
�I�[�f�B�I�͂Ƃ��������W�I���������܂ő��������Ȃ�
AM�͂��̂�����g����B����FM���W�I�����邪�n�[�h���͏オ���Ȃ�
>>729
�����ő��M�@������2�{�V�ׂ�B
����̓A�i���OTV�œ������Ƃ���Ă��B �V�����J�������̂�����
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://korgnutube.com/wp/wp-content/uploads/images/omote.png)
>>731
����K�i�\����肵�����ǁA�C�}�C�`�g���Â炢�B >>726
����ȂɁH
���ʂ�LED�ƈႤ�́H >>725
�u�������v���ۂ���Ⴄ�I����́I���`��I�v�V�������y�Ȃ낤�B
���P�xLED�ł��f�U�C������Ő����Ȃ��̂��H�Ƃ͎v�����ǁA�܂��G��Ȃ��݂������˂��B �����A���̍����I�[�f�B�I����Ɉ�s�\���̃V���v���Ȍu���\�������B
�����ڂ̉��o�ɂ������
MAP-S1
>>735
���ׂ��������L�@EL�̎���
����Ɏ���đ�����͓̂����悾�Ǝv���� >>732
��i���Ŏg�p���Ɓ{�o�C�A�X�����ˁE�E�E
���߂ĕ��ʂɁ[�o�C�A�X�Ŏg����悤�ɂȂ��Ă���E�E�E �O���b�g�Ƃ��H�v���Ă���������Ƃ܂Ƃ��ȓ����ɂ���̂��Ǝv���������̂܂�܁B
�܂����������\���Ȃ̂ɁA���ʂ̌u���\���ǂ�荂���l�i�Ȃ���ȁc
����Ȃ烄�t�I�N�ň����V�Õi�����ėV�ق�����������
>>717
����͊j������EMP����������ɔ����̉�H���U�d���ō\����j���̂ɑ��Đ^��ǂȂ炻�̌��E�_����������
���Ęb�͂��邪
����A�����̿�ި�Ăł̔����̉�H��ɳʳ���Ⴍ�āi���ԃ��[�J�[����ʑ���ɐV���i���������������j���ΓI�ɐ^��ǎg�������Ă�
���Ă̂��������Ȃ� �����������̎���̓A�����J�ł��畁�ʂɐ^��ǂ����Ă�����
���[�_�[�̑�o�͂Ɏg���锼���̂ȂȂ��������M�������Ⴉ������
>>742
�ʂɂ��O��̗V�т̂��߂ɊJ�����Ă�˂���A���Ă�����l�͎v���Ă�������ł��傤�B >>743
���˔\�픘���E�����������̋��͂ȓd���g�E��r�I�����ł̓���E���ቷ�ł̓���Ɋւ��ẮA���ł������̂͐^��ǂɓG���ȁB
���������A�̂Qch�ŁA�������̏ꏊ�ŃZ���T�[�̏o�͂�6AU6�ŎĂ���Ƃ���̏C���]�X�̘b���������Ƃ�����B
���`��������Ƃ��ŏڂ����b�͂��Ă���Ȃ��������A�ꏊ�͂����炭�͌������R���ď����H�ꂠ����ŁA���ł��g���Ă���̂��낤�B �ŋ߂̓G�W�\�����ʂ𗘗p�����F���p�f�o�C�X�Ȃ��J������Ă�炵����
�d�ɊԂ����~�N�����Ƃ�������K�X�����Ƃ��͂��Ȃ��Ă����炵������
���������ΐ^��ǂ��ĉF����Ԃ��Ɗǂɓ���Ȃ��Ă����삷��̂���
�F����Ԃ̕���������Ƃ��Ă͗��z�I�ȋC�����邪�A
�n��ł��̐^��ǂ��������邽�߂̐ݔ�����|����ɂȂ肻���B
�F�����ƕ��ː����r���[�r���[�~���Ă��ē��삪���������Ȃ�Ƃ������̂���
>>751
�F���ǂ��납�X�p�R�����Ƃ��ɃP�`���ăG���[�����@�\�t���Ȃ�������N���r���Ńr�b�g���]�N�����ė�������̂��o���オ���Ă��肷��
�ŐV�̐l�H�q���ɐς�ł�d�q�@���20�N30�N���x���O�̐��\�Ƃ����������ĂȂ� >>752
E�e�����������ȁH
�����q�����̂�
�Â����W�W�߂Ă��Ă���Ɏg���Ă�p�^�[���̑e���̂�IC��
���Ă̌����L������� �R���p�Ƃ�������ό͂ꂽ��ł���Ă�̂���
>>747
���������֘A�͔F��Ȃ����G�Ŕς킵������A
���E���A���₨�H���Ƃ����̉��Ƃ����F�X��ς��낤��
���d�l���g�������Ă�Ƃ����邾�낤�� �����ۂ��\�A�͉��M���E�E�E���Ă̂͂���������
�L�l�F���D�͂��܂��ɃR�A���������g���Ă�낤���˂�
���M�̓J�X���o�ĈӊO�Ɗ�Ȃ��Ƃ����I�`
�͂�߂����Z�p���܂���Ȃ�
>>755
�����̌���ł́A�Ⴄ�Ǝv���B
�E�^��ǂȂ�A�ʏ�g����ȒP�ȍ\���i�����̈�i�A���v�H�j�œ������A�C�����ȒP�A���ː��ɑ��ē��ʔz������K�v���Ȃ��B
�E�����̂��ƁA���Ȃ茵�d�ɕ��ː��ɑ���V�[���h���s��Ȃ��ƁA�g�����ɂȂ�Ȃ��B
�܂��A�b�ɂ͏o�Ȃ��������A���Ӊ��x�������ꍇ�́A���炩�̃N�[���[���K�v�ɂȂ�B
���̕ӂ��l�����Ȃ��ƁA�Z���ԂŎ�芷����K�v���o�Ă��邪�A���ː��ʂ̍����ꏊ�ɂ��傭���傭�l���o���肳����킯�ɂ͂����Ȃ��B
�c�Ƃ����b�Ǝv����B
�܂�A�Z���T�[���邽�߂����̂��d��������̋Z�p�ł��ɂ́A�K�͂��傫���Ȃ肷���Ėʓ|�E�R�X�g���c�Ƃ������ƂȂ낤�B ���ɂ��܂��ɐ^��ǂ��g�p���Ă���Ƃ��낪����Ƃ�����������i�̓f�b�h�X�g�b�N�����Ȃ��̂��ȁH
����Ƃ��ǂ��������̈˗��Ȃō���Ă�낤��
�f���T���@�ɂW�O�W�T���������g���Ă��Ƃ�
�K�C�K�[�J�E���^�p�Ȃ�GM�ǂ͍����œ����̂Ő^��ǂŐv�����ق����ȒP�ł͂���B
������̃J�E���^��X�y�N�g�����[�^�Ȃ�V���`���[�^�┼���̂ł͖���������ȁB
�^��ǂ̓����͔M�d�q���ӎ�����̂ʼn�����ɋ߂��\���Ƃ����鏊�ƍ�������A
�����ēd�q���L�����A�ł��邱�Ƃ��ӎ����Ȃ����H�v�ł��鏊���낤�B
(�d�C�́{����|�ɗ����Ɗ��Ⴂ���Ă���l������)
����ɂ����Γd�����䂩�疳���AOPAMP�����߂Ƃ���قƂ�ǂ̊�b�͐^��lj�H���ŏ�������ȁB
�u�������H�Ɨp�ȂǗp�r�ɂ���Ă�LED�����������i�������ǂ��ꍇ������̂�
�u���ǂ͈���==���Y��~����Ȃnj��ߕt����̂͗ǂ��Ȃ��B
>>762
�u������LED�ɔ�ׂČ���(lm/W)�������̂Ɛ�����܂ނ̂������� >�K�C�K�[�J�E���^�p�Ȃ�GM�ǂ͍����œ����̂Ő^��ǂŐv�����ق����ȒP�ł͂���B
�m���������f�l������
�܂����ʂɃK�C�K�[�J�E���^�[��AVR�ŃJ�E���g���������ǂˁB
����Ɛ^��ǂ�B�d���ƈ���ăJ�E���g���͓d���h���b�v����l�ɂ��Ȃ��ƃJ�E���g�ł��Ȃ��B
�u�J�~�I�J���f�v�ŗL���ɂȂ������d�q���{�ǁ^2���d�q���{�ǂ��A�u�^��ǁv�ŁA��������A�ɁB
�M�A�ɂƂ͌���Ȃ��_�ɒ��ӁB
����͊e�u�z�Ɂv����A���ʂ̐��{�̓d�q����o�����ŁA
�ō��d���̃A�m�[�h�ȊO�͊F�u�A�Ɂv�݂����Ȃ��̂����ǁA�u�^��ǁv�Ƃ��ĖY�ꂿ��C�J���B
�J�~�I�J���f�̑��{�ǂ̌�i��H��^��ǂȂőg��
��������イ�̏�ł܂Ƃ��Ȏ������ʂ͏o���Ȃ��������낤�ȁB
>>762
���`�́u�K�C�K�[�J�E���^�[�v�́A���˔\�ʉ߂ɂ����d�p���X���J�E���g�����ŁA
���p�x����������I�Ȍv���͏o���Ȃ����A
���ː����x�ł̋敪�����������A�����Ƃ����ɉߋ��ٕ̈��Ǝv���Ă��������������܂��g���Ă�́H
���d������A��҂K�v������A�ǂ���������Đ�kHz�p�x���v�����x�B
50�N���炢�O������ː��ʉ߂ɂ��ő̒��̌u�������𑨂���Ƃ��������̗ǂ��ϑ����@�ɐ�ւ���Ă�͂��Ȃ��ǁB ���N�O�APET�̃V���`���[�^����Ōv���Ƃ����s������
>>769
��H�\�����ȒP�ŁA�u���������Ȃ����v�̊m�F�ɂ͖��ɗ��B
�J�E���g�����p�x�ȏɎ���O�̏ŁA�g�p����B �g�����X���X(�������͓d�r)��FM�g�݂������NJȒP�ȉ�H����H
�R�C���ނ͋���������g�����W�X�^�p���g��������
VHF�їp��10.7MHz�̐^��ǗpIFT�Ȃ�Ē��g��IFT�����荢���ˁc
TR�p���ő��Ɍ������Ȃ��������Ă��Ód�����Ŏg�������Ȃ�
�̂̉�H�����Ă��FM��80�`90MHz����Ŏg�����ɂȂ�Ȃ���
AM�X�e���I�`���[�i�[�͂���̂�FM�X�e���I�͌����݃g�����W�X�^
>>773
FM�ɂ����Đ�����́H
��H�C�ɂȂ�Ȃ��B���ɕ����ӂ� >>777
���Đ��́AAM��FM��������H�ŕ����ł���B >>777
������͑�R�l������ł���B
�s�̕i�ɂ͖����Ă�1�䂱������Ȃ牽�ł�OK�B
�g�����X���ȒP�ɂȂ��H�̓p���X�J�E���^�[�E�s�[�N�f�B�t�@�����V�����E
�N�H�[�h���`���[�E�Q�[�e�b�h�r�[���E���b�N�g�I�V���[�^�[�Ƃ����ˁB
���Ƃ͒��Đ��Ǝ����l���������ǃX���[�v���g���ȒP�B >>777
AM��2�g�X�e���I�͐^��ǎ���ɕ��y���}��ꂽ����
FM��MPX�X�e���I�͐^��ǎ���܂���̂̃X�e���I�V�X�e���͂قƂ�ǂȂ���
�Z�p���[�g�^�̃X�e���I�ł��I�v�V������MPX�X�e���I�A�_�v�^��ڑ�����ƕ����ł�����Č����̂�������������
�X�e���I�A�_�v�^�̉�H���T���ƎQ�l�ɂȂ邩�� >>777
�X�e���I���y�̍��ɂ͐^��ǂ͉��ɂȂ��Ă��Ă�����X�e���I�����̎Q�l�ɂȂ�̂͏��Ȃ����������ǁA�����̓J���[�e���r�̐F�M�������Ɠ��������炻���������g�����b�N������Q�l�ɂȂ邩���� ���Đ����W�I
�ȑOVHF�e���r��TVI�o�ē{��ꂽ��������UHF�n�f�W������e�����Ȃ��H�̂��ȁH
ICF-5800�������ケ���op���������ǂقƂ�Ǝg��Ȃ�����
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://tonota.air-nifty.com/photos/uncategorized/2008/09/28/sta5002.jpg)
�ケ��Ȃ̂��@�iMW������ꏊ�Ƀ��W�I�����Ă���g���Ď����ɁB�j
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://b9audio.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_19c/b9audio/m_135013SONY_TMR5-9d204.jpg)
���ł���FM�⊮�ǂ̂悤�ɁB�@����͒T���Ώo�Ă��邩���B >>783
�X�e���I�w�b�h�z���A�_�v�^�[���ăI�N�Ŏ��o�Ă邯��
����ǂ������g����������̂Ȃ́H �܂�Ƃ���w�b�h�t�H���A���v����Ȃ���
����A��������
FM���m�������W�I���嗬����������AMPX�[�q�Ɍq����FM���X�e���I�Œ������߂̃A�_�v�^
STA-50����������
�ꎞ���b��ɂȂ������ǁA������������Ă�����
>>786
MPX�[�q�̂Ȃ�FM���m�������W�I�ɃA�_�v�^���q�����߂ɁA
�f�E�G���t�@�V�X��H�̑O�Ɍq�����o��������B >>786
���ʂ̃X�e���I�A�_�v�^�[����Ȃ��ăw�b�h�z���p�̃X�e���I�A�_�v�^�[���Ă��Ƃł����H �w�b�h�t�H���A���v�������Ď��ŗ��������߂��낤�ȁB
�̂̃g�����W�X�^���W�I�ŃX�s�[�J�[�����̃X�e���I�A�_�v�^�[��
�I�v�V���������ɂȂ����@�킪����ق炵�Ă��邯�ǁA
FM���Đ��̐^��ǃ��W�I�ɂ��g����̂��ȁH
�g�����X���X5���X�[�p�[(�o�͊�35C5)�̃p�C���b�g�����v�ŕ����������Ƃ�������A
������35W4�̃q�[�^�[�^�b�v��50���̒�R�ƃp���œ����Ă郉���v�̋K�i��
6.3V0.25A�Ȃ���ǁA������6.3V0.15A������ƃ}�Y�����ȁH
���ʂ�0.15A�̓d���������悤�ȋC������
���̂ւ�̘b�́u�S���{�^��ǃ}�j���A���v�ɋL�q��
�����������H
���̖{�����Ă邯��
>>793
�d�����ꂽ����(6.3V0A)�l���Ă�낤����A��������Ȃ�ǂ��C������B >>794
0.15A�Ȃ�X�g�b�N�����0.25A�Ȃ�ēc�ɂ̕��i���T���Ă���������w
���Ȃ݂Ɍ^�ԕs���̃V���[�v���B�ꕔ�X�`�R���g���Ă邩�疖���̂��̂���
>>797
�g�����X���X���ăp�C���b�g�����v�ꂽ�琮���ǃ_���ɂȂ���ĕ���������c >>798
�V���[�v�̃g�����X���X��UC100�AUC102�AUC103�AUK70�������Ƃ��邯�ǁA
�d���͂U�D�RV�@�P�T�O��A�������l�ȋC������B �Ȃ��A�^�Ԃ��킩��Ȃ��Ȃ�^��ǃ��W�I�̃f�[�^�[�x�[�X�̊Ǘ��l�����
�����Ă���ƃ��[���𓊂���Ƃ�����������Ȃ��B
�����͎t���Ȃ��̂ł��ꂪ���ȂЂƂ͎g���Ȃ����ǁB
>>799
�^�Ԃ͉�����ꖂ��ă{���{���̉�H�}����ǂ����HR�Ŏn�܂�͗l
���Ɛ^��ǂ��Ȃ����S������/�}�c�_ >>793
�C�ɂȂ�Ȃ�56��68���̒�R���p���ɂ���H >>801 ���W�I�̊�A�b�v���[�_�[�ɂ�����Ό^�Ԃ܂ł킩��ꍇ���B
HR�@����Sharp�̉\����B HR-15���āAUK-70�Ɠ������ۂ��ȁB
�V���[�v���Đ^��ǃ��W�I�o���Ă���������
���O�̓V���[�v�^��ǃ��W�I���D�Ƃ̉���{�点��
�V���[�v���Đ^��ǂ̍��͑���d�@����������
�y�b�g�l�[���Ƃ��Ă̓V���[�v�𖼏���Ă�����
>>807
�\����Ȃ��c
���͏����A�N���E���̃|�[�^�u������ �V���[�v�_�C��
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.sharp.co.jp/100th/onlyone/1929/images/p01.jpg)
�V���[�v�͂��̃��W�I�~�������
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://jl4ens.world.coocan.jp/5s8511.JPG)
�̂̓��W�I���q�������ԑg���ėL������ˍ��̋���e���r�݂�����
���W�I�����Ȃ��������瓖����O������
�e���r��1�������m�ɂȂ�Ȃ�Ă������薳������
���ł�����������Ɖ������Ŏq���̑z���͓�������ԑg���L���Ă������̂ɂƎv��
���ăX���`���ȃX�}�\
FM���ƃ��W�I�h���}�Ő��N�����̍�i���ˁB
NHK���ł��͂Ȃ��łĂ����͂܂�����Ă�ȁB
���������ǎq����������Ҍ����ԑg���₷���Ƃɕ��匾���̂͌��ǘV�l�B
NHK���ꎞ����肩�͎�Ҕԑg���₵�����A�u�[�u�[�����Ă邾�낶�����ǂ��́B
���x�n�܂郉�W�I�ŊG�̂Ȃ��A�j�������Ĕԑg���V�l�͑������匾���͂�����
���ꂢ���ƌ����Ă����ێn�܂�ƕ��匾���̂��V�l
�ۈ牀�����Ȃ��̂Ɠ����\�}
>>812
�������������ɓ��@���ėǂ����b�o�Ă������Ă��B
���̎������Ă�������̂��T�����[�̃T�C�R���^���W�I�B GT��5���X�[�p�[���ă\�P�b�g�����������mT�ǂɍ����ւ��ł���H
�ł���Ή�H��M�炸�ɃA�_�v�^�[�ō����ւ��ł���悤�ɂ�����
�ł���B�i�������A�K�i�Ƒ��k�Łj
�́AST��/GT��/MT�ǂ̃\�P�b�g�����ڑ����ĕ��ׂāA
�ǂ̊ǂł��i�����Ă��j�g����A����L���������L��������B
>>819
����́w�����Ǝ����x�Ɍf�ڂ���Ă����A�u5���X�[�p�[���^��ǎ����@�v
�̋L���ł͂Ȃ����낤���B
���₵���^��ǂƗǕi�̐^��ǂ�����5���X�[�p�[�ɂ�����
�����ł�A�^��ǂ�OK�Ɣ��肷��Ƃ������@�B GT�ǂ̃n�J�}�����ɂ�T�ǂ̃\�P�b�g��g�ݍ��킹��Ƃ������A
�n�J�}�����������č��͓��荢��Ȃ낤�Ȓ��ׂĂȂ�����
�g���Â����@OMRON��MK��P�̃����[�B
�����[�@�\���O���Ďg��
�\�P�b�g���g����B![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://tonys.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/05/29/img_0117.jpg)
>>821
���V����GT�ǂ����ă\�P�b�g�������������p����
����Ă邯��
GT�ǂ̃\�P�b�g������MT�Ǘp�\�P�b�g���[�܂��Č��\��肭�o���� >>818
���W�I�͏�����DX-330
�^��Ǎ\����12SA7GT/M�A12SK7GT/M�A12SQ7GT/M�A35L6GT/M�A35Z5GT/M
mT�ǂ͕W���I��12BE6�A12BD6�A12AV6�A35C5�A35W4���g��������
>>822
�����[�̓W�����N���ŒT�������Ȃ����c���Ȃ݂ɂǂ�ȊO�ρH >>825�@�����̃|�[�^�u�����ƍ����������邩��A�P�[�X�����g���Ȃ��B
https://www.monotaro.com/g/00361669/
�R�C���Ă��Ŏg������ɂȂ�Ȃ��Ȃ��������[�̖{������苎����mT�\�P�b�g��
�v���O�ƃP�[�X��ڒ����Ă���l�W�͂�T�\�P�b�g�̐ڍ��ɓ]�p�ł���B �g���Â��������[�̓���o�H����������
GT���X�ǂ�MT���X�ǁACR�̒萔�ύX���Ȃ��ƃ_�����ĕ��������Ƃ���
�Ȃ����q�[�^�[����w
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://lostinanime.com/wp-content/uploads/2017/01/Ghost-Hound-3.jpg)
�����Ɛ�����ǂƂ��Ȃ�ł���
���łȂ�ăA�j���H
�V�i��6ZP1�ŁA�Ǖǂ��������Ă�������������
�Y�킾�����B
�������O�ɂ��薼�������Č����Ă��c
�u�_���Ghost Hound�v���Ă�ł�
���W�I�͉����̕������ȂƎv���������ł��Ȃ������ł��ˁB
�o���R���őI�ǂ��Ă�V�[�����������B
�v���[�g�̓����͐��ۂ������Ă邯�ǂȁB
���O���Ȃ낤���ǁB
�^��s�ǂ̃^�}�ŃO���b�h�����ɕ��d�������Ƃ�����
������MT�ǂɌ����邵YAHA�A���v�Ƃ����낤����
�܂����炩�ɂ悭�l���������点�Ă��
���̉�����LED�Ō��炵�Ă邾�������w
�A���v�ł͌��\����Ă�l��������B
����`�F�����R�t�������m���
>>838
���������A12AU7�������̋����킴�킴�ؒf���čH���āA��Ō��ʂ�ɂ��Ē���LED���g���Č��点��c�Ȃ�čH����l�b�g��Ō������Ƃ��������B
�ǂ����������ȁE�E�E�E�B �l�^�A���v�����ǃ\�P�b�g�̌��Ƀs�b�^���Ƃ��F�̂k�d�c���L������ŕt���Ă݂�
>>841
����������^��ǂ̃I�u�W�F�I�ȃ��m�������Ƃ����
MT�̃K���̒��ɃR�C���ƌ������o�l�I�Ȋ������ŏo�����l�^�i���{�b�g�j�������Ă�
������LED�̖�����ŏƂ炳���A���Ă�
���ɓ����Ă�̂��ȒP�ȃ��m�ł��A�^��ǂ̒��Ƃ���
�{�g���V�b�v�I�ȃo�C�A�X�ŗǂ����m�Ɗ����� ��C�ǂł��Ƃ�����������Ȃ��ˁB
�ł������Ȃ����Q�b�^�[�͔�����������
>>841 6E5M�̑�ւ�
�UE5�Ȃ炿������LED���~����ɔz�u���ăV�O�i�����[�^ >>844
����i�ł������u�Ԃɋ�C�����邩�甒���Ȃ�W���}�C�Jw 6BN8(VHF/UHF�������V�I���g�p�̑o2�ɁA3�ɕ�����)1�{�Ń��W�I�g�߂�H
2�ɕ��Ō��g����3�ɕ���AF��������������H�v�ł��Ȃ�����c
��炩�����c
1S5-SF�̃q�[�^�[���Ă��܂���orz
�e�X�^�[�œ��ʊm�F���������Ȃ̂ɐ�Ă��܂���
�e�X�^�[���P3�d�r2�{�d�l�Ȃ̂���������
�߂͐�N�T�͖��N
�������P���N�ڂł��������@�i-�l-�j�Ȃނ��`
>>847
�X�[�p�[���W�I�p��2-3�Ɋǂ��g����3�ɕ��ō����g�ƒ���g�̃��t���b�N�X��
2�ɕ��Ō��g���Ă̂��������E�E�E�E���A���ʂ�3�ɊǂŃO���b�h���g�������Ǝv���E�E�E >>847
����́A�_�C�I�[�h���Q�ɕ��ɕς����C���[�W�H
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://tuberadio.web.fc2.com/radio/REFLEX.GIF)
�Ƃ���ŁA�^��ǂ̃J�\�[�h����v���[�g��
�����M�d�q�̑��x�͂����炭�炢�H
�d���ɔ�Ⴗ��H
>>850
�O���b�h���g�̕��������́H >>847
�g�����W�X�^�[��1���t���b�N�X���Q�l�ɂ�����H
�J�\�[�h���ʁX�ɂȂ��Ă邩��ȒP���Ǝv�����ǁB �����͋C�ɓ����̂ŁA������Ƀ��X�B
MIX��7360���g������M�@����낤�Ǝv���Ă���B
�����ŁA�c�����ׂĂ��邢�����̃T�C�g�ɃA�N�Z�X�������A�݂ȃr�[������d�ɂ̕��ɐM������ꂽ�����ő����Ă����B
����́A���\����Ă���u�ϒ��p�v�̉�H�������Ȃ��Ă��邩��Ǝv����B
����ASSB�n���h�u�b�N�Ȃǂł̎�M�@�g�p��ł́A�M�����͂͂����ނ�G1�ƂȂ��Ă���B
�ǂ����ɁA���̕��̕����Řc���𑪂���HP�͂Ȃ����̂��B
�N���m��������A��������B
>>660
���̂��ア�`���`�Ƃ������Ă鉹�̎��H
����Ȃ�A�Z�g������M���Ƀt�F�[�W���O�Ă��������
�r�[�g�������Ԃ����ۂ̉��ł��ȁB
���ʂɃA�i���O�̃_�C������T�d�ɓ������Ă���Ƃ��ɂ悭�����
�����̃��W�I�ł��^��ǃ��W�I�ł��悭�����@��͂���Ǝv���B
�iDSP���W�I���ƕ����Ȃ����ȁj
�������A�Z�g��������B
�h���}�̃��W�I�iAM/FM���W�I�j�ł͂܂��������͂Ȃ����B �������ǁA�v���Ԃ�ɐ^��ǃ��W�I
�C���A���ǂ��邩�ȁB
25M-K15�Ƃ������A�Ȑ����ǂ��g�����A�g�����X���X�܋��X�[�p�[���I�N�ŗ��D�B�s���ׁ̈A�C���B
�o�̓g�����X�ꎟ���f���A�d���p�����R���f���T�̗e�ʔ����������A���i�����B
���̑��A3V 0.15A�̃p�C���b�g�����v���f���B����́A�A�L�o�ł���ɓ���Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠����6.3�u�ő�p�B
�ׁX�������Ƃ́A�܂����邯�ǁA����Ŏ�M���삵�n�߂��B
�ł��A�������50�g���n�����傫�߂̈�ہB
���̍��i1954�`1956�N���H�j�́A�Z�p�͏n������Ă��āA�R�X�g�_�E���̋ǖʂŐv���ꂽ���i�ƌ����B
���[�J�[�́A���{�R�����r�A�B
�W���I�Ȍ܋��X�[�p�[��H�ɑ��A�Ȃ���Ă��镔�i�������B�i➑̂ɉ�H�}�Y�t����j
�n������������B�@���������ꍇ�A�ǂ�������ׂ��H
�u�n���ɔY�ޕ��ւ̕������E�n���ގ��̃g���̊��v
��
�u������o��n���̑�v
���O�O���ƍK���ɂȂ�邩��
>>866
�O�ɃR�����r�A��5���X�[�p�[�C���������ǁA
����ς�n�����~�܂�Ȃ��ĔY��B
�^��ǃ\�P�b�g�̐^�̃A�[�X��
�ڐG�s�ǂɂȂ��Ă��̂������������B >>866
25M-K15�Ƃ�5R-K16�Ƃ�6R-DHV1�Ƃ������ɍ���V���[�Y�c �F����A���X���肪�Ƃ��B�@�Q�l�ɂȂ�܂��B
�I�V�������Ȃ���A�d�����C���ɏ���Ă���50Hz���m�F���Ă��܂��B
��ƂɈ��A����Ȃ�̉��ʂł���A���ꂮ�炢�̃n���͋��e�͈͂��Ċ����̎d�l���ȂƂ��v�����肵�Ă��܂��B
���낢�뎎���Ă݂܂��B
>>870�ł��B
�n���̌�����������܂����B
�����N��̉�H�}�ɂ���C���z���̐�ւ�SW�̐ړ_�s�ǂŁA
35C5�̃O���b�h���n�C�C���s�[�_���X��ԂƂȂ��āA�n�����E���Ă��܂����B(0.002��F�Ō�����ԂɂȂ��Ă��܂����B�j
����SW�́A�C���z����}���ƃC���z������SW�����J�j�J���Ɏ����Ő�ւ��\���ł��B
�Ƃ肠�����A���������Ă݂��Ƃ���A�n���͊F���ɂȂ�܂����B
�����A�R�X�g�_�E���ɂ��v�I���ł͂Ɛ��������������Ă��܂��܂������A
���̌o���s���ł����B�@�Â����W�I�̐ړ_�ȂǐM�p���Ă͂Ȃ�܂���ˁB
http://fast-uploader.com/file/7053958397506/ ���̉�H�}�̃P�[�X�A���e�i�ʒu���Ⴄ�悤�ȁB
�n�C�C���s�[�_���X�̃C���z���i�N���X�^���Ƃ��Z���~�b�N�j�͂Ȃ��̂�����A
�X�C�b�`���Ǝ���Ă��܂��̂��g�B
���ł̒��V���[�Y�̃W���b�N����Ȃ�3�{�̒[�q�̂����ǂꂩ���V���[�g����
�����X�s�[�J�[�I�����[�ɁB�@�V�����X�e���I�W���b�N�����ăR���f���T�Ő≏��
PH�|�W�V�����Ő�ւ���l�ɂ����AUX���͂̃��m�����A���v�Ƃ��Ďg����B
*�ǂ����V���[�g���Ă����̂�����10�N�ȏ�O�ɂ�����̂ŖY�ꂽ�B
>>872
���̒ʂ�B�����C���z������̉�H�͓P�����Ă��܂����Ǝv���Ă��܂��B
���Ȃ݂̂��̉�H�}�ɂ͌�肪����܂��B
35C5�̃J�\�[�h��R��200K���ƂȂ��Ă��܂����A����Ȃ��Ƃ��蓾�Ȃ��B
200���̊ԈႢ�ł��B���ۂ̃u�c�������Ȃ��Ă��܂��B
�P�[�X�A���e�i�̈ʒu�́A���ۂ̃u�c���ł����A
�u�Ⴄ�悤�ȁv�Ƃ����Ӗ��������Ă��������B�X�C�}�Z���ł��B >>873
30A5�̃J�\�[�h��R�͋K�i�\�ł�180���ƂȂ��Ă���̂�
200���ŗǂ� >>874
�Ȃɏォ��ڐ��ňӋC�����Ă�B >>871
12BD6�̃J�\�[�h�̃o�C�p�X�R���f���T���Ȃ��Ă�̂́A
�R�X�g�_�E���Ȃ�̂��ȁA����Ƃ��������R��������
�Q�C�����������Ă�Ƃ��Ȃ̂��ȁH �����Ȃ�ˁA�W���I�Ȍ܋��X�[�p�[��H���炢�������i���ȗ�����Ă���B
12BD6�����łȂ��A35C5�̃o�C�p�X�R���f���T���������A
12AV6�̌��g�o�͂̍����g�t�B���^�[���R���f���T1�ōς܂��Ă���B
�����͏I��ォ��̕����ǂ̓d�g�������P����āA���i�̐��\����������āA
����ŗǂ��I�ȂƂ��������̂��ȂƎv�����肵�܂��B�i�܂������������H�j
35C5�́A���܂肢�����@�Ƃ͎v���Ȃ����A���i��ߖA�҂����Ă�H�Ǝv����w
35C5�̃J�\�[�h��R�A200K�ɂȂ��ĂˁH
�g�����X�����ƃN���X�^��(�Z���~�b�N)�C���z���ŕ����̂�
�d�͑����̐^��ǃq�[�^�[OFF���ďȃG�l�ȒP�����ǁA�g�����X���X���Ɩʓ|���ȁB
���͂悤�������܂��B�{���̕����\��ł��B
�s�c�I���A�ؑ����D�̂ӂ邳�Ɣ����q�ɂē��{���}�A���䐽�Ɖ����݂������������܂��B
�K���̉��l�A���B
���z�M�͍��䐽�̃c�C�L���X���烊�A���^�C���Ŕz�M����܂��B�������������B
����29�N6��27���i�j
�َm�@�����݂����A���䐽�A�x�؍����A�r�����F �ق�
�I�������@���ԁA�ꏊ
8���`�@�����w���
11���`�@���[�c�n���ӏ���
15��30���`�@���̉w�����q
18��30���`�@�����q�w�k��
�������݂����㉇�
�����݂����@�����q�����̉�
https://m-okamura.japan-first.net/
�y�����O���[���ԁz�U���Q�S�i�y�j�`�V���P���i�y�j�@�ߑO�W���R�O���`�ߌ�W��
�y���[�ŏI���z�@�@�V���Q���i���j�@�ߑO�V���`�ߌ�W���܂� >833
����̂������A���W�I�ƊW����̂ł����B
�ςȑI���^���͂�߂Ă��������B
�����̃g�����X���X���W�I�ŋǔ��R�C����100PF�̃R���f���T���Ȃ��̂�����B
�ǔ��R�C���̊����Ⴄ�낤�ȁB
>>884
�Ȃ����Ƀ��X�����邗
�l�g�E�����E�U���̂ɂ͓��ӂ��邯�ǂˁB >886
���炵�܂����B
883�ւ̃R�����g�̂���ł������A
���������ԈႦ�đł��Ă��܂��܂����B
�܂������
>
>
8
3
3
�Ƃ��ł��ĂȂ����
>>885
�A�����J�̈����ȃ��W�I�ł���Ȃ�����
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://i149.photobucket.com/albums/s63/mtcm76/540Td.jpg)
IF�����܂ŏȗ�����Ă邩��A�ȈՉ��̃��x�����Ⴄ���E�E�E�E >>891
����ł��ϊ������͂��邩�獂1��2���W�I��肿�傢���x�������x�Ȃ璋�Ԃ̉������p�Ȃ�\���Ȃ�łȂ����� >>892
��������IF�ȗ��������Ă݂����A���[�J���ǂ��ɂ͏\���Ȋ��x�Ƃ����b�������� IF���������Ō��g������������
�g���Ȃ����͂Ȃ����Ǖ��i���܂邩�猋�Ǖ��ʂɖ߂�����(��)
�i�������Ȃ���AGC�̃_�C�i�~�b�N�����W�����ɂ����A���Ďv�����Ⴄ�B
�t�Ɍ����A�I��x�̗ǂ��Q���}���W�I���Ǝv���B
10MHZ�ȉ����ƊO���G�������������傫�����獂���g�����Ȃ��̃_�C���N�g�R���o�[�W�����ɒ���g������IC�ЂƂŏ\���Ȋ��x�Ȃ�Ȃ�
���g���ϊ����_�C�I�[�h�~�L�T�[�ɂ���ƃg�[�^���Q�C��40�`50dB
�A�N�e�B�u�~�L�T�[�Ȃ�60�`70dB���ĂƂ�����
�g�����X���X�܋��X�[�p�[����}�ɉ����o�Ȃ��Ȃ�A�g���u���V���[�e�B���O���B
���������q�[�^���_�����Ă��Ȃ��̂ŁA�ǂ����̋����q�[�^����N�����Ă���Ɣ��f�B
���ׂĂ̋��������������ăq�[�^�s���ׂĂ݂���A�e�X�^�[�ł͂���������ʁB
�����V���[�V�Ɏ��t�������A�d���I�ɏ�ʂ̃q�[�^�[�q����GND�Ԃ̒�R��}���Ă݂����������Ȃ��B
�i�g�����X���X�Ȃ̂ŁA�e���̃q�[�^�͒���ڑ�����Ă���B�j
���̏�ԂŒʓd���A�e���̃q�[�^�d�����v���B�q�[�^��H�̒��قǂɂ���12BD6�̃q�[�^�ԁi3pin-4pin)�ԓd����97V�B
�܂�A�����i12BD6)�̃q�[�^���f�����Ă���Ɣ��f�B
�f�����Ă���̂ŁA�q�[�^�ɂ͓d�������ꂸ�A�ꂽ���̃q�[�^�Ԃ�97V�̓d���������ƍl���Ă���B
�e�X�^�[�ɂ������d���ɂ�鑪��ł͓��ʂ��Ă��邪�A���ۓd���𗬂��ƒf����ԂɂȂ��Ă��܂����Ƃ��Ă���H
�q�[�^�[��H�̔z�����ꂽ
�\�P�b�g�̐ڐG�s�ǂ͊m�F���܂������H
�\�P�b�g�̐ڐG�s�ǁA�q�[�^�z�����m�F���܂������A�ُ�Ȃ��ł��B
���A�����12BD6�P�i�ɑ��A�茳�ɂ�����7.2V�̒����d���i�G�l���[�vx6�{�j�������Ă݂��Ƃ���A
��u�d���������̂ł����A���̒���ɕs�ʏ�ԂƂȂ��Ă��܂��܂��B
���̎��̓d�C��R�𑪂�ƁA��u���ꂽ��A���ʒ�R�����܂�A��L�̒����d�����O���ƌ��ɖ߂錻�ۂ��ł܂��B
�q�[�^�̐ꂩ������Ċ����ł��傤���H
�����V�i��12BD6�ƌ������Ă݂�w
���B�n��PCL86�Ƃ�ECC83�Ƃ��ŁA�ʓd����ƃq�[�^�[���߶�[���ƌ�����
����������ŕ��ʂȂ��w
���Y���Ə������߶�[������ˁB
12BD6����12BA6�̕���������Ȃ��H
>>903
�T�M�ǂ��Ă���ȂɌ�������H >>905
�t�B���b�v�X�AEi�Ȃ͂悭����������
����������Ȃ���́A���邭�Ȃ��Ă����������߶�[�ƂȂ�Ȃ����� �����������ƂȂ��Ԏ��͂Ȃ�Ƃ��ڐG���Ă邯�ǁA�ʓd�Ŗc�����ė������Ċ����ł�����
�U���Ă���e�X�^�[���ĂĂ݂���H
����Ȃ炻�̒��x�̐U���͖��Ȃ��͂�����
�l��30A5(���m�ɂ�30M-P23)P-P�d���g�����X���X�A���v�͓d��������A�������X�Ƀs�J�b�ƌ���B
���b�V���J�����g�Ńt���b�V������̂��t�B���b�v�X�n�̓���
���{���ł������̓t�B���b�v�X����Z�p�����������炱�̓������p���ł�
�q�[�^�[����ɔ�яo���Ă��ăy�J�[�ƌ���̂͗L�邯�ǂ��ꂶ��Ȃ���ˁH
��p��Ԃ���ʓd�������Ɉ�u�����q�[�^�[���߶�[�ƌ���B���̌�͕��ʁB
�g�����X���X����������Ȃ��ď�����6BA6�ł��������Ƃ���B
>>910
�Ȃ�����Ȏd�l�ɂ����낤���E�E�H�H >>911
���悠�����ł��B V1, V2�������߶�[



 @YouTube
@YouTube
Mullard���t�B���b�v�X�n�ł��� >>908
12BD6�̌������ǁA�U���Ă݂����ǏǏ�ɕω��Ȃ��B
���Ȃ݂ɁA12BE6���莝����9.6V�����d����ڑ�����ƁA
�ŏ���400mA�ʂɒB���A���X�ɓd���l���������Ă����A���ɂŗ��������B
12V���Ȃ̂ŁA�q�[�^�͔��Â��_�����Ă���B
������ɂ��Ă��A��莋���Ă���12BD6�̃q�[�^��NG�Ǝv���B
�ʂ�12BD6����蒆�B�������r���Ă݂��B >>913
�߶����ƌ�����Ă����������Ƃł���
���߂Ă݂܂���
���������̎����Ă���6DJ8�̓t�B���b�v�X�̓z�ł������̂悤�Ȍ�����͂������ʂɂڂ킟���ƌ���o���Ă���Ȃɖ��邭���Ȃ��ł� ���x�W���̑傫���t�B�������g���g���Ă�̂��Ȃ��B
�����オ��𑬂����邽�߁H
�t�B���b�v�X�ɂ��Ă������ɂ��Ă������͌��邵����Ȃ���͌���Ȃ��E�E�E
�ǂ����ĂȂ�ł���[�ˁH
>>914�ł��B
�V���ɓ��肵��12BD6�ɍ����ւ�����A����܂����B
12BD6�̒��r���[�Ȓf���������ł����B >>916
�Ȃ�ق�
���ɂ����������R�Ȃ痝�ɂ��Ȃ��Ă邩�� �g�����X���X�p�^��ǂ́A�q�[�^�[�̗����オ�莞�̓d��������
�ł��邾���������̂��g���悤�ɁA�Ƃ������ӏ������������悤�ȋL�����B
>>921
�Ã��W�I�̔���グ�ɗ����Ă邩�炱��ȏ����𑱂��Ă���̂��낤���ǁA
���Ƃ��������Ēʕ���PSE�̔������K�p����đ�ς����ˁB >>914�ł��B
�ӂƎv�������āA���X�g�A�����܋��X�[�p�[�̃X�s�[�J�z�����O���AALTEC�̃t�������W�X�s�[�J�iCF404-8A)�Ɏ��t���Ă݂��B
AM���W�I�Ȃ̂Ńi���[�����W�����ǁA�N�X�Ɨǂ����Ŗ�B�@
���̌�A�����ȃX�s�[�J���Ƃ������Ђ����������B
�����������̂�����t���Ă���̂��AALTEC����ԁB�������邢�B �X�s�[�J�[�������郉�W�I�H��p��肿����Ə㓙�Ȃ�Ɋ����邾���ł������ł���ˁB
OPT��2���������g���ďo�͊ǂ̃J�\�[�h�ɋA�҂������Ă����������ɂȂ�܂��B
���X�g�A�������W�I�͒��q�ǂ��ғ����Ă��āA�����������Ȃ��B
�ӂƎv�����āABluetooth�C���z����g�ݍ���ł݂��B�iBT�C���z���́A�A�L�o�I�[�Ŕ�����1200�~�̂�j
��H�}���A�b�v���܂����B�@���������Ȃ��A�̂̉����Œ�����̂��y������B
http://fast-uploader.com/file/7057530786454/
�g�����X���X�́ABT�p�̓d���i+5V�j�����Ƃ��낪�Ȃ��̂ŁA100V��USB�ϊ��d��������������B
�ϊ��d���̓X�C�b�`���O�d���Ȃ̂ŁA�m�C�Y�̏��Ȃ����̂�I�ԕK�v����B
���E�߂͏H���̃R���ihttp://akizukidenshi.com/catalog/g/gM-08312/�j �����͂������̃��W�I�ŋ��p�ł���悤��
���g���C�����X�}�C�N������ĉ����𗬂���悤�ɂ�������
�܋��X�[�p�[���W�I�̒������ɁA�����g����ƃr�[�g�������錻�ۂ��N���AIF�i�̔��U���Ǝv�����ׂĂ݂邪�A���̒���͂Ȃ��B
������Ǝv���A�X�y�A�i�ŃA���e�i�M�������Ă݂�ƁA455KH���t�߂ɂȂɂ��L�����A������B
���̎��܋��X�[�p�[�̓d����OFF�B�l�b�g�Œ��ׂ�ƁA�g�C���̐������u�̃N���b�N�H���R��Ă���Ƃ̏����A����̕��ׂ邪���Ȃ��B
���Ԃ�A�ߏ��̂���Ȃ̂�������Ȃ��B
���ǁAIF���g����440KH���ɒ������āA��ꂽ�B�@�{���ɂ���Ȃ��Ƃ���ˁB
http://fast-uploader.com/file/7058344455538/ ���ꂾ�Ƃ����Ă���AM���W�I���e���������Ȃ��̂����c
���̃g�C���̑��u�̂قƂ�ǂ��A���̎��g���̃N���b�N�������Ă��邩�͕�����Ȃ����A
���������ł���Ƃ͊m�肵�Ă��Ȃ�����A��ʓI�ɋN����Ƃ͈�T�Ɍ����Ȃ��ł���B
>>927 ���[�J�������ł��e������܂����H
���Ƃ����瑊�������ł��ˁB 455KHz��M�@�ƍ����FOX�n���e�B���O����Ă݂Ăق���
LED�Ɩ��łȂd�g�łĂ�̂��܂ɂȂ������H
>>930
���[�J���ǂł��e�������B
>>927�ŏグ���X�y�A�i�g�`�ɂ���590KHz�A690KH����NHK�̑��Ƒ��B
455KHz�t�߂̖W�Q�g�͂�����-10dB���x�Ⴂ�����B �ȑO���W�J�Z�w�����ă��W�I��������
�NJԂŐ����m�C�Y�B
���W�J�Z�������̂��Ƒ��̃��W�I�Ńe�X�g
��͂�m�C�Y���B
���鏤�X�X�ł������m�C�Y�B
���nj����s���B
���N�����������݂��̃m�C�Y�͂Ȃ��Ȃ����B
�����g�я[�d��̃m�C�Y�Ɏ��Ă�B
���̍��܂��g�тȂ������̂łȂ����̂��s�v�c�B
���g�тł��ׂĂ̋ǂ̎�M�����͂ɖW�Q���Ă���C���o�[�^�[��H�n�̃m�C�Y
����ǂ����������Ȃ�
�����Â��C���o�[�^�[�u�������Ȃ���o�Ă�
�u�����Ɍ����Ă͍ŋ߂̂͂����Ԃ悭�Ȃ�������
���\kHz����SkHz���x�̗h�炬�̂����`�g������P�Ȃ鍂���g�łȂ��́H
HAM�p�̃X�C�b�`���O�d�����m�C�Y�����\KHz�����ɓ��邯�ǎ��g��������Ȃ�Ɉ���Ȃ̂Ő�KHz���x�̕��ɂȂ��Ă邵�A
���g�����ςɂȂ��Ă邩��ړ������Ēǂ��o�����Ƃ��o����
��`�g��n+3n+5n+7n+9n+�c�Ƃ��������g�̊�{�����g�̍���
�����{����������ƎO�p�g
�S���̂����莕�g��������
�Ƒ����e���r���Ă�Ǝ����̕����̃��W�I�������ɂ��������肵���Ȃ�
�v���Y�}�e���r���Z�g�тɂ���`���ƃm�C�Y���o���Ă��Ȃ�
Tone Wheel
Leslie speaker
>>922
�g�����X�̃��K�[�ɂ��Ď��₳��Ă�����
������ĂP���ƂQ���̐≏�̂��ƁH
�≏��R���ďK�������ǃg�����X�̏ꍇ����
����200V�̃g�����X�Ȃ�A�P������200V
2�����ɃA�[�X��ڑ����Čv������Ƃ��H ���ԁA��-�S�S(�{�f�B�[)���B
5M-K9���ĂȂ�ł��ꂾ���q�[�^�[��5V�Ȃ�ł����H
>>951
�����ǂ̏ꍇ5V�͂��Ƒ����� 6.3V���Ɖ����s�ւ������Ƃ����낤��
�m��6.3V���Ă͓̂d�r�̓d�����������ˁH
12F�Ȃǂ�z�肵��ST�njn�̃p���[�g�����X���g����Ƃ������Ƃ���5V�̔��g�����ǂ��J�����ꂽ�Ƃ����b�����B
�t�B���b�v�X�ƒ�g���Ă����炩�ȁH
������ł�6CA4��5V�ɂ���5R-K16���g���Ă����c
�č�����5M-K9�͂قƂ�Ǐo����ĂȂ������B�@���{�K�i�����B
6X4�����ʂ���Ȃ������ȁB�@5M-K9���Əo�͂�6AR5�ł��t���Ɏg���Ƌꂵ���B
�č��ł�6AQ5���X�^���_�[�h���ȁB
5M-K9�A6W-C5�ȂǁA�^��ǖ��̓r���Ɂh�|�h�̓�����̂�
���{�Ǝ��̐^��ǂ��ƕ��������Ƃ�����B
>>958
���̂ق��ɃA���t�@�x�b�g�̎g�����ɂ�
�K���������� �S���{�^��ǃ}�j���A���i���a38�N���s5��1�����s�j�ɂ��ƁA���g�}�iRETMA�j�����A���{�W�������A���B����������炵��
�܂�1956�N�ȑO�ƈȍ~�ł��Ⴄ�Ƃ��Ȃ�Ƃ�
�Ƃŕs�J�����I�ɉ҂�����@�Ȃ�
�Q�l�܂łɁA
�ˁ@�w�����̃����C�G�E���x �Ƃ���HP�Ō��邱�Ƃ��ł���炵���ł��B
�O�[�O�������ˁw�����̃����C�G�E���x"
W5FQGR98ON
6X4���_�C�I�[�h�ɒu��������ƁA���̂܂܂���d�����������ȁH
6X4�̖{���̌`�Ń_�C�I�[�h���g��������ƍ����Ȃ�̂Œ�R��1�i���₷�B
5MK9�@�������B
35W4 �͂��̕��̃q�[�^�[�d�����l������K�v�����邪���X���B�d���œ��삵�Ă��邩��
�d�������������D���ʂɂȂ�Ǝv���B
������̏ꍇ�������������n�܂葼�̋������܂�܂œd���R���f���T�ɖ��������邩��
���̂܂g���Ă���ꍇ�������K�v(�ϓd�����߁A�����ǒ���̒�e�ʃR���f���T�̔����
�Ȃ�����A�n����ő�e��(20�ʁ�100�ʂɂ��Ă��悢�j�B
>>964
������Ŏ���ł����A�����Ă��������B
>���̋������܂�܂œd���R���f���T�ɖ���������
�Ƃ����͉̂��̂ł����B
���ׂ��y���̂œd���������Ƃ������Ƃł��傤���B >>965
��������
5���X�[�p�[�̉�H�}������킩�邪�_�C�I�[�h��������ɒu���������
�d���R���f���T�ɂ͑�AC�d���d����1.4�{�̓d����������
���̋������܂�܂�+B�d������d��������Ă����Ȃ�����d���g�����X�╽����H
�̒�R�ɂ�d���~�����Ȃ��̂œd���R���f���T�ɍ����d����������
���Ƃ��g�����X����AC�A�_�v�^�[�̏o�͓d���������ׂ̂Ƃ��Ƃ�ł��Ȃ������悤��
�_�C�I�[�h�����̏ꍇ�ɂ͑��̋����l�ɉ��܂�܂œd���R���f���T�ɓd���͂�����Ȃ� �s�̕i�ɂ��邱������6X4��p�i�݂������Ă����ƁA�{����6X4�ɖ߂����֗�
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://i.ebayimg.com/images/g/8Y4AAOxy83JRGuY5/s-l300.jpg)
���g�͒�R�ƃ_�C�I�[�h�������Ă邾���ł��B
�O���X����̂悤�ɃR���f���T�̑ψ��ɒ��ӂ��K�v�B >>966
5���X�[�p�[�ǂ��납�^��lj�H�̐v�̌o�����Ȃ��̂ł����A
>�d���R���f���T�ɂ͑�AC�d���d����1.4�{�̓d����������
���דd�����y�����̂���傫�����̂܂ŕϓ�������̂ł���A
�y����Ԃł����v�Ȃ悤�Ƀ}�[�W�����l��������ŕ����R���f���T�̑ψ���ݒ肷��
���̂ł͂Ȃ��̂ł����H �����Ȃ��ĂȂ��Ƃ��낪�̂̃��W�I�ł���܁E�E�E
>>968
DC�d����d���R���̑ψ���8�����炢�Ŏg���@�]�T�̂Ȃ��̂͋���
�V���R���_�C�I�[�h�͗ǂ��������ǎg�p���͓d���R���̗e�ʂ�
���ӂ��邱�Ɓ@80 6X4=10��F�@6CA4=50��F ���X >>964
�����ǂ��_�C�I�[�h�u���b�W�̗��g�����ɕς��āA
�i�˓��d����Ƃ��Ē���ɒ�R�����āj�A
�����R���f���T��100�ʂe�~�Q�ɂ����B
�������ŁA�n���͑S���������Ȃ��Ȃ����B
���Ȃ݂ɁA�u5���X�[�p�[�v�̕��͋C���c�����߂ɁA
�����ǂ́A�q�[�^�[�����_���Ă�B
��R���R���f���T���A�̂ɔ�ׂĂ��̂������������Ȃ����̂ŁA
��H��F�X�lj����Ă��A�V���[�V�[�̒��͏\���]�T������B >>971
>��H��F�X�lj����Ă��A�V���[�V�[�̒��͏\���]�T������B
6BE6��G3�ɐ�ւ��X�C�b�`��t���āA������H����藣����G3�ɃI�[�f�B�I�M����
�������悤�ɂ��Ă����ƁE�E�E�����Ƃ��ꂩ�����悤���E�E�E ��R����i���₷�A���B�v����Ƀ��^��H�łœd���ƒ�R�𑝂₹�Ηǂ��ƁB�d���͐����ǂł͖�������100�}�C�N�����炢�ł����Ă�OK�ƁB��R�l�́H200�I�[��3W�Ƃ���߂̂����Ƃ���ǂ��̂��ȁB
���t�I�N�Ŏ�ɓ��ꂽ�r�s�ǂ̂T���X�[�p�[���A��U�S���o�����āA
��R�A�R���f���T�A�g�����X�A�X�s�[�J�[��V�i�ɕς��āA�d����H��
>>971 �̂悤�ɕς��āA�����a�f�l����Ɏg���Ă���B
���v���A���W�I����蒼�����Ԃ����A�h�e��g���b�L���O�����̂��߂�
�e�X�g�I�b�V���[�^����鎞�Ԃ̕������������C������B
���Ȃ݂ɁA455KHz���U�ɂ́A���c�̃Z�����b�N���g�����B >>974
���������̐����ǂ��_�C�I�[�h�ɕς�����A�q�[�^�[�݂̂��y���ނ̂�
�ד����Ǝv���A455�Ǖ����U���Z�����b�N�Ƃ����̂��S���Ȃ� �܋��X�[�p�[�u���v���Ă��Ƃŋ��e���Ă�낤��B
���e�ȐS�������Ă��Ă���5�X�̉����Ƃ����l�����Ȃ�
�n����h�����ߐ�����H���_�C�I�[�h������
�����R���f���T��100�ʂe�~�Q�ɂ���ȂNj��̍����@���V��5�X��5MK9
����������i�ڂ�10�ʂe��i�ڂ�20�ʂe�łقƂ�ǃn���͋C�ɂȂ�Ȃ���
�I���X�[�p�[���������������A�ꗬ���[�J�[�ȊO�ɂ��g�ݗ��ăL�b�g��
�K���[�W���[�J�[���瑽���������ꂽ�@���ɂ���Ă͑f�l�g�ݗ��Ă䂦
�A�[�X�|�C���g���z�����̂��₵���Ȃ��̂�����@���������Ȃ�I���W�i����
����C�J���@�����ǂ̃q�[�^�[�����y���ނȂ�Ĕn�����Ă���
>>975
�u�e�X�g�I�b�V���[�^��455KHz���U�ɂ́A���c�̃Z�����b�N���g�����B�v
�̂ǂ����S���Ȃ���H�� ���ӗ͎U��������҂ɂ悭���鎖���ˁB
>>1�@�ɂ��ƁA�����́A
�u5���X�[�p�[����O�A���l�A��1�A0-V-1���A�^��ǂ��g�p�������W�I�̃X���b�h�ł� �v
�Ƃ��邩��A�u�T�X�v�ɂ������K�v�͂Ȃ��̂ł́H
�܂��A�����ȍl���̐l��r������킯�ł͂Ȃ����B �m���ɐ������_�C�I�[�h�ɂ��Ă��܂����猵���Ɍ����5����X�[�p�[�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă��܂���
�����ǂ��炩�Ƃ����I���W�i����`�ő�֕��i�͏o���邾���g�������Ȃ�
�^��ǃ��W�I�Ȃ̓y�[�p�[�R���Ƃ��ⓚ���p�Ō������Ȃ��Ɗ�Ȃ����i�Ƃ������邯��
���Ƃ��Ƌ@�\�����藧���Ă�����̂��������Ă��܂��̂͋C����������Ƃ��Ă��ł���������ɖ߂���`�ɂ�����
�q�[�^�[�����������Ă����̂��V�ѐS�Ƃ��Ă͔ے�͂��Ȃ����ǎ������l����Ƃ��������Ȃ��C������
FM�������W�I�ɂȂ��Ă���Ɛ�����V�I���g�ɐΎg���Ă����ŁA���X�ɂ������̂��B
�QSP�̃K���Œ�����V����ۂɂ́@12BE6�@12BA6(D6)�@1N60�@12AX7A�@30MP23(30A5)x2�@SD1
5��3Di�\���łȂ���ăX�e���I���O�����͂̂ݐ��K�̃X�e���I�ɂ��Ă��������B
�}�W�b�N�A�C�������ɐ������萔���Ȃ�������
��������Z����������4���X�[�p�[�Ƃ�����������ʂɐ����̓_�C�I�[�h�ł������Ǝv�����ǂˁB
�����gFM5���X�[�p�[(�}�W�b�N�A�C�͋����Ɋ܂߂Ȃ��Ƃ���)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://telefunken.pytalhost.eu/Gavotte1063/gavotte1063-537.jpg)
�r�s�ǂ̂T���X�[�p�[�S������1950�N��ɔ�ׂ�ƁA���͂`�l�������̂�
�������ǂ��Ȃ��Ă���B
�͕̂��i�������ŁA�Ⴆ�Δ��g�����Ȃ̂��d���g�����X�̓����������Ȃ�
���������߂����A�����p�d���R���f���T���A10�{20��F���n�����ƃR�X�g�Ƃ�
���ˍ����Ō��E�������Ǝv���B
���͕��i���������^������A�u�^��ǂ̉��v���u���̂������v�ŕ������߂ɁA��H��
�F�X�H�v����̂��A�����Ǝv���B
���ʂ́A�u�T���X�[�p�[�v���u�S���X�[�p�[�v�ɂȂ������ǁB
���́A>>971 �ŏ������ȊO�ɁA�o�̓g�����X�ƃX�s�[�J�[�̓I�[�f�B�I�p��
�����̂������̂ɕς��āA�o�̓g�����X������6Z-DH3A�̃J�\�[�h��
�y��NFB�������āA��������t���b�g�����Ă���B�C�x�ߒ��x�����ǁB
�Ȃ��A6Z-DH3A�̓�ɕ��̓Q���}�_�C�I�[�h�ɒu���������B ���ʂ̃A���v�݂�����6Z-DH3A�̃J�\�[�h�A�҂�����ƁAVR���i���Ă�
���g�M�����J�\�[�h���͂œ���̂ʼn��ʂ�0�ɂł��Ȃ��Ȃ����Ⴄ��ˁB
���g�����ɂ͂��������Ӗ����������̂��V���i���_
���̋Z�p�_�C�I�[�h�u���b�W
��ɊǂŃu���b�W�g��ł�̂��Ă������H
�����̓_�C�I�[�h�ł��������nj��g�͋�����Ȃ��Ɛ^��ǃ��W�I����Ȃ��Đ^��ǃA���v���Ă����ȋC������B�܂��A���t�@�C�����͔̂ے肵�Ȃ����ǂ��B
���g�����ǂ̃��W�I�Ȃ�_�C�I�[�h�u���b�W�ɂ��ł��邪�A����𗼔g�����ǂŃu���b�W����Ȃ狅2�{�v�邩��X�y�[�X�I�ɂ�������A�M�I�ɂ��������Ǝv�����疳�������Ǝv���B
���g�����ǎg����⍂���ȃ��W�I�̓g�����X��0V���_�̂���������Ǝv���B�_�C�I�[�h�u�������Ȃ�u���b�W�v�炸�A�_�C�I�[�h2�{�ōςނȁB�g�����X�̈Ⴂ�Ō��܂邩�ȁB
�����Ȃ�����UAR5�����点�邾���ɂ��ăp���[MOS�ɂ��Ă݂邩
�q�[�^�[�̂ݓ_���Ă��̂��������Ӗ�����ˁB�ܑ̖������B�����}���ĉ�����LED�ŏƂ炷���炢�����x�����̂ł�w
1000�Ȃ玀�}�W�b�N�A�C����������
lud20230201230523ca
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/denki/1457462785/�q���g�F5ch�X����url��
http://xxxx.5ch
b.net/xxxx �̂悤��
b�����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
TOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜
�@���u�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30�� �v�������l�����Ă��܂��F
�E�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����13
�E�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����14
�E�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����11
�E�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����15
�E�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����8
�E�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����2
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����542������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����552������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����559������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����541������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����553������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����551������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����550������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����547������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����555������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����545������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����540������
�E�X�[�p�[���{�b�g���OG�ŖG����X�� ����302
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����554������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����543������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����557������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����558������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����548������
�ELIVE HOME 2022 �������܃X�[�p�[�A���[�i2Days�I �����ށX ����1513
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����549������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����544������
�E�X�[�p�[���{�b�g���OG�ŖG����X�� ����305
�E�y����z�X�[�p�[���{�b�g��탿�����yDC�Łz����18
�E�X�[�p�[���{�b�g���OG�ŖG����X�� ����303
�E�X�[�p�[���{�b�g���OG�ŖG����X�� ����304
�E�X�[�p�[���{�b�g���OG�ŖG����X�� ����301
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����564������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����560������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����524������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����525������
�E�A�[�P�[�h�Q�[���֘A�̃I�[�N�V���� ����22
�E�y�X�p���{�z�X�[�p�[���{�b�g���DD ���[���h72
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����566������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����560������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����570������
�E�X�p���{OG�̎����Ɋ��҂��鎖 ����116
�E�y�X�p���{�z�X�[�p�[���{�b�g���DD ���[���h62
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����562������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����565������
�E�y�l�b�g�z�u���̋C�ɂȂ�X�[�p�[�t���[�N�Ŕ��E���ɂł�����ˁc�v�����T�������q�v�����X���[���^��킳��́u�v���ӎ��v�ɐ�^��2
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����575������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����567������
�E�X�P�[�g�����X�� ����19
�E�yC3�}�[�P�b�g�zC3TOKYO(���L�����z�r)�����X�� ����12
�E�y�o�X�P�b�g�z�����ۑI��F�c���\�̃p�X���A���E�[�v�@�\�t�g�o���N�VCM�ŃX�[�p�[�v���[
�E����m�q��(���A��A�O�c�A�]�A�X�p�[�N��)����17
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����572������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����569������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����573������
�E�y�X�p���{�z�X�[�p�[���{�b�g���DD ���[���h82
�E����m�q��(���A��A�O�c�A�]�A�X�p�[�N��)����15
�E����m�q��(���A��A�O�c�A�]�A�X�p�[�N��)����18
�E�X�p���{OG�̎����Ɋ��҂��鎖 ����119
�E�X�p���{OG�̎����Ɋ��҂��鎖 ����115
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����576������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����563������
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����571������
�E�X�p���{OG�̎����Ɋ��҂��鎖 ����118
�E�A�[�P�[�h�Q�[���֘A�̃I�[�N�V���� ����25 ����2
�E����m�q��(���A��A�O�c�A�]�A�X�p�[�N��)����16
�E�������X�[�p�[�h���t�B�[ ����537������
21:20:17 up 20 days, 22:23, 0 users, load average: 9.65, 9.27, 8.95
in 0.059337139129639 sec
@0.059337139129639@0b7 on 020311
|
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://a.pd.kzho.net/1458209363249.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://oldradio.qrz.ru/tubes/foreign/04/PC900.gif)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org867472.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/EGh3OYU.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/Ded9PrT.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/FMprot2-sch.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/11696ssch.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/nordmende/nordmende_carmen56_am-fm_radio_sm.pdf_1.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463243/23432455/oldies/egyeb/freed_eisemann_nr-5_nr-6_battery_receiver_sch.pdf_1.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/aa/Neutrodyne_circuit_-_modified.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/59/48/bea47990db16e67e6e257e7f6e719c09.jpg)



 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube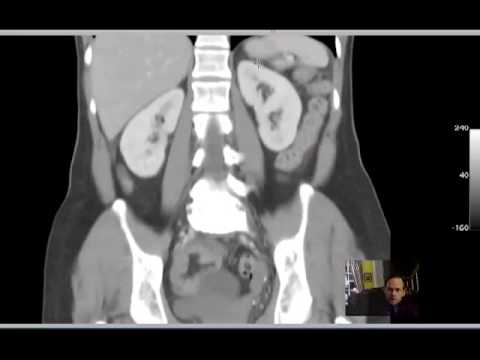

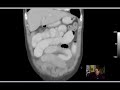
 @YouTube
@YouTube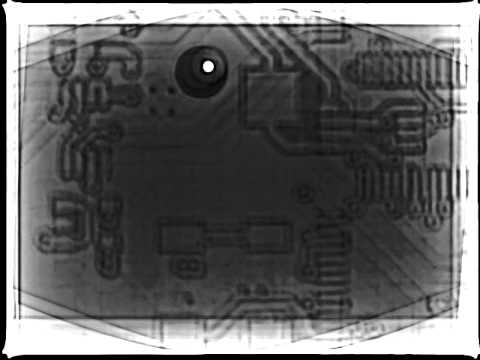

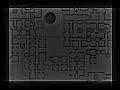
 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.japanradiomuseum.jp/images/11829ssch.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%8D%E7%94%9F%E5%9B%9E%E8%B7%AF#/media/File:Regenerartive_Receiver-S7300056.JPG)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://blogimg.goo.ne.jp/user_image/5b/01/8b3b6500910dc7e9533df45f8c9eab40.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.funkygoods.com/garakuta/3_tubes/namiyon_03.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://images.campyent.com/sites/default/files/schematics/rca_victor_co_inc_radiola_17_pg1-1.png)



 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.dotup.org/uploda/www.dotup.org1035435.png)



 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.tubecollector.org/equipment/proximity-fuse-valves.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://patentimages.storage.googleapis.com/pages/US3166015-1.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/b7qsCeZ.jpg)



 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://korgnutube.com/wp/wp-content/uploads/images/omote.png)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://tonota.air-nifty.com/photos/uncategorized/2008/09/28/sta5002.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://b9audio.c.blog.so-net.ne.jp/_images/blog/_19c/b9audio/m_135013SONY_TMR5-9d204.jpg)



 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://www.sharp.co.jp/100th/onlyone/1929/images/p01.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://tonys.cocolog-nifty.com/photos/uncategorized/2012/05/29/img_0117.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://lostinanime.com/wp-content/uploads/2017/01/Ghost-Hound-3.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://i149.photobucket.com/albums/s63/mtcm76/540Td.jpg)



 @YouTube
@YouTube![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](https://i.ebayimg.com/images/g/8Y4AAOxy83JRGuY5/s-l300.jpg)
![�y�^��ǃ��W�I�z 5���X�[�p�[ ����12 [���f�]�ڋ֎~]©2ch.net YouTube����>13�{ ->�摜>30��](http://telefunken.pytalhost.eu/Gavotte1063/gavotte1063-537.jpg)