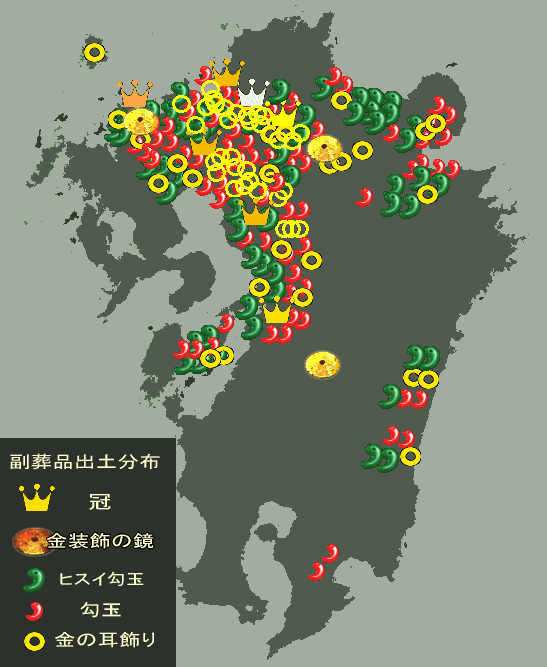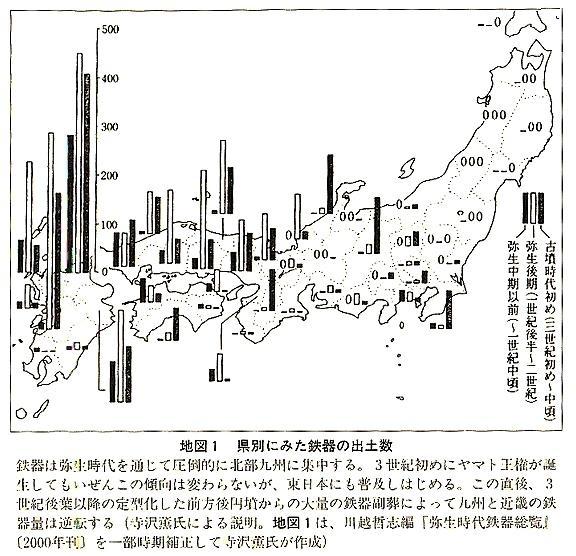1�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:31:47.27
�@�הn�䍑�_�̓S�A�E�����̃X���ł��B
�y���@�q�z
�E�R���I���t�ɂ́A�Õ����オ�J�n���Ă����B�i��10,FAQ10,43�j
�E�Õ��o�����i�K�ŁA�ߋE�������𒆐S�ɗK�͂̐����A�����`������n�߂Ă����B�i��2,4�`6�j
�E�k����B�����p�ݒn��́A���ɂ��̐����A���̎P���ɂ������B�i��7�j
�䂦�ɁA�`�����ږ�Ă̓s���������̂͋E���ł���B
�@�הn�䍑�_���������E���Ō����Ȃ̂Ń��}���͂���܂���
�@���҂̊ј^�������A�X�Ȃ�^����T�����܂��傤�B
�O�X��
http://2chb.net/r/history/1549730950/
���O�y �v�@�| �z�@�@�i�@>>2-12�Ɋe�_�A����ȉ���FAQ��t���@�j
�@㕌���Ղ̔��@������A�����ɂ͐����{�̍L��ɉe���͂��������@���I�w���҂��N�Ղ��Ă���A����͊e�n�̎ɋ������ꋁ�S�I�ɏW�ꂽ���͊�Ղ��������ł������ƍl������B
���̎��S�����͂R���I���t�Ƃ݂���B�E���ɒ����������}���ɐZ�����鎞���ł���B
�@������`�l�`�̋L���ƑΏƂ���ƁA�����R�Õ��̔푒�҂��`�l�`�ɋL�ڂ��鑂鰂ɔږ�ĂƌĂꂽ�l���ł���A㕌����הn�䍑�ɂ������`�����̋{�a���ݒn�ł���Ɠ���ł���B
�@�Q���I�̒n���K�͓I���≻�́A�_�Ɛ��Y�͂���������Љ�I���v����w���I�n�ʂ��߂�͏o�W�c�̐���������ɑ��i���A�퐶�I������J���I�������߁A���ˉ��������u������o������B
�@��������A�퐶���u��̋��剻�������Ȓn�悱�����A�퐶�Љ�ɌÕ�����ւƌ������\���ω��̒������n��ł���A�R���I�ɔ����I�ɍL�扻����G������Ƃ̒��j�ł���B���R���ω��ɋN������Љ�\���ω������ۂƂ���㕌��ɋÏW�����������ƌ�����B
�@�`�l�`�ɋL�ڂ��ꂽ�ږ�Ă̊������Ԃɑ������鏯�����s���́A�E���l���̓y�킪�Q�i�I�ɖk����B�ɗ������Ă��鎞���ł���A���Ƃɓ߉ϔ�b�n��ւ̐l���������}�g�債�Ă����B
�@�����p�f�Ղ��ΊO���̎���ɖ��o�邱�̎����ɂ́A�����{�e�n�̐l�X���ؐl��y�Q���l�ƒ��ڌ��ɂ����Ղ�����i�K�ƂȂ��Ă���B
�@���ł��������{�����؎Љ�ƓԂ̍������ĊJ���������A���̊O�I�h���ōł��ω��̐������n�悱���������̘`���̒����ł���B
�@�`�l�`�q�ׂ�Ƃ���́A�R���I�O�����ɑ�鰂ƒʌ������`�̏����͂ǂ��ɂ����ł��낤���H
�@����͍���s㕌��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B 2�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:01.09
���P�i�������s�j
�@�ޗnj�����s�ɏ��݂���㕌���Ղ��Q���I���ɐl�דI�E�v��I�Ɍ��݂��ꂽ�O�㖢���̋�����J��Ԃł���A�܂��k����B���܂ޗe�n�̕�������e���Z�����A�����đS���ɔ��M���钆���I�ȏ�ł��������Ƃ́A�g�ɒm���Ă���B�i��2,FAQ38�Q�Ɓj
�@���E㕌��w�߂��ɓ�������ɕ������A�����Čv��I�Ɍ��z���ꂽ��^�����Q�i�S���܂Ŕ����ς݁j�́A�R���I�O���̂��̂ƌ������\����Ă���B
�@���و�͍���������݂̂ł�����150m�A��k100m�O��̋K�͂������A�召���ꂼ��\���E�@�\���قɂ��镡���̌��������`�̍��Ɉ�ㅂ���Ă���A�d�v�ȌÓ��Ƃ��Ēm�������ɐږʂ��Ă���B����ɔ䌨������̂́A�퐶����ɑ��݂��Ȃ��͖̂ܘ_�̂��ƁA����܂Ō�������Ȃ��B��^�����̖T�i��^���J�y��SK-3001�j�ŏ@���I�s�����s��ꂽ���Ղ��������ꂽ�B
�@���̌����Q�́A�ʒu�W���猾���ĎO�֎R�y�є����R�Õ��Ƌٖ��ȊW�����@�����B�����p��̎����Ɣ����R�Õ����݊J�n�̎������߂����ƁiFAQ10�Q�Ɓj�����Ă���ƁA�O�֎R�ƊW�̐[���@���I�w���҂������ɌN�Ղ��A����ɔ����R�Õ��ɑ���ꂽ�ƍl����͍̂����I�ł���B���̑�^�����Q�Ɣ����R�Õ������ď���̈ʒu�W�́A�g�|���W�[�I�ə��z��鋎R�˂�z�N������B
�@�����R�Õ��́A���{�L��e�n�̑����ԓI�ɏW����^���Õ��̚���ł���A�������}�g�����̏��㉤��ƍl�����邪�A�푒�҂������ł���Ƃ����`���ɂ��M�ߐ��i���R�Q�Ɓj������@
�@�T���A���̑����̑��ԓI���i���珉�����}�g�����̏��㉤�͊e�n�̎Ɂu�����v���ꋁ�S�I�ɏW�ꂽ���͊�Ղ����҂ł���A�������ƍl������B���̎��S�����͂R���I���t�iFAQ30�Q�Ɓj�ł���B
�@���̒n�ɁA�����═��A�V���ȓy�؋Z�p��G��I�n�C����(FAQ21�Q��)�A�ɑ��݂��Ȃ������A���̉ԕ���(����2015)�ȂǁA�����������}���ɐZ�����鎞���́A��鰐W�ƒʌ����������Əd�Ȃ�B
�قړ�����j���ł���鰏����Γ`�`�l���i鰎u�`�l�`�j�̋L���Ə�L�̍l�ÓI��������ˍ�����ƁA�����R�Õ��̔푒�҂͑�鰂ɔږ�ĂƌĂꂽ�l���ł���A��2�`8�ɏڏq����Ƃ���A����㕌��������̏��s�ł���B
3�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:20.65
���Q�i�����R�Õ��Ɍ��鋤���̍\���Ɛ����I�l�b�g���[�N�̌`���j
�@�O�f�̑�^�������p�⎞�ɉ�̂��ꒌ�܂Ŕ�������ēP������Ă��邱�Ƃ́A�㐢�̑J�{�Ƃ̊֘A���l�����邪�A���̋{�̂�����ɏƂ点�A�����̎�̎����ɔ����p��ƍl���邱�Ƃɍ�����������Ƃ�����B���������āA���̌����̎�l�̊��������͔ږ�ĂƏd�Ȃ�B
�@�܂��A�����R�Õ��͂��̌����̐^��Q���i鰎ځj�ɗ��n���A������i����j�Ō����ȂNjٖ��ȊW��L���Ă���A���̌����̎傪�푒�҂ł���ƍ����I�ɐ��F�ł���B
�@�����ɂ�鑊�����������m���ȎЉ�ɂ����āA����̎���s������q���͎���p�����̌��F�E���������V���̏�iFAQ26�Q�Ɓj�ł���B���̏�Ō�������Ă���e�n�̑����́A����Ή����̒��ɂ�����e�n�̉e���͂̃o�����[�^�ł���B
�@�܂�A㕌��ɒa��������^���O����~���̂�����́A�������ꂽ�����߂��錠�͍\���̕\�ۂ��郂�j�������g�ɑ��Ȃ�Ȃ��B�����Ĕ����R�Õ��ȍ~�A�Õ��̒z����拤�L���A�������Ƃ̍��i���`������B
�@㕌��̎���A����ɉ����Čn���I�ɓW�J����剤�拉�Õ������n��I�Ɍ��Ă��A�����R��Ƃ��Đ��a�ˁA�s���R�A�a�J���R�Ɩ��m�ȘA�������F�߂��A��A�̐������K�͂ő��݂������Ƃ�����B�����̑剤�拉�Õ��Ƃ��ꂼ��z���������L���A�P���Ȑ�����ŏk�����ꂽ���Õ����A�S���ɓW�J�i�V�c1999�j���Ă��邩��ł���B
�@�z�����̋��L�́A�n���I�W�c�Ԃ̑��̌����ɂ����鑊�ݏ��F�W����Ƃ����A�[���I�e�q�����͌Z��I�����͊w�W�������Ă���ƍl�����A���ꂪ�d�w�I�Ɋe�n��ԗ����Ă�����ώ@�ł���B
�@���̌X�̕R�т̏W�ς��A���ߓI�S���x�z����}�����ȑO�́A����ɂ͊e�n�̎������������č���������ȑO�́A�`���̐����I���i�ł���B�����ł����d�w�I�Ƃ́A�Ⴆ�Α剤���Õ���4/9�̒z���������Õ��ɂ����ẮA�剤��2/3�̗͊W���������A�X�ɂ��̑��2/3�̗͊W��������悤�ȊW���Ӗ�����B
�T���A�剤��4/9�ɑ��Ē��ڎw���͂�����̂łȂ��A2/3���ʂ��ĉe���͂��s�g����悤�Ȍ`�Ԃ̍��ƌ��͍\���ł���B
�@���̎n���_���A�����͖��`�ł���n��I�����W�c�Ԃ̐����͊w�W������E�\�ۉ����Œ艻����鎞���A�T���@�\�I�ɂ͖��g�D�ŏ��㍑���̌l�I�J���X�}�Ɉˑ������v�����ƒi�K�i�������j���爽���̐����I�@�ւɂ��^�c����鏉�����ƒi�K�i�Õ�����j�ւƈڍs�������A�T���z���O���ɂ���Ƃ݂邱�Ƃ��o���悤�B
4�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:38.66
���R�i�����Ɍ����锢���R�Õ��̓��ِ��j
�@���̍s���R�A�a�J���R���Ƃ��ɒ鉤�˂Ƃ��ē`������A�����ƋK�͓I�ɓ����ł��锢���R���܂��u���ˁv�̖����`�����Ă���ɂ��S��炸�A�鉤�̛H�̕�ɉ߂��Ȃ��ƋI�ňʒu�t�����Ă���B
�@���̂��Ƃ́A�z���H���̑�K�͂���_�Ɛl�̋��Ƃɂ��z���Ƃ�����b���Љ��Ă��邱�ƁA�A�����ꂪ�I�̎��^����B��̗˕�z���L���ł��邱�Ƃ������Ċӂ݂�A�I�Ҏ[���́A�s���R�y�яa�J���R�̋K�͂�F�����Ă���ǎҎ��_�ɉ����āA���炩�ɕs���R�ł���B
�@�����R�A�s���R�y�яa�J���R�́A�Ⴆ�ʒu�W�y�ђz���N��̘A�����Պʼn߂��悤�ƁA���̈��|�I���ʂɂ����āA�����i�̎匠�҂��A���I�ɑ��݂����Ɛl�X�Ɉ�ەt�����ɂ͂����Ȃ��B
�@��������A��O�̎����Ƃ��ē��Y�˕���������Ă���ǎ҂ɂƂ��ċI�Ҏ[���_�Ŕ����R�Õ��̔푒�҂ɐ��_��i�s�ƕ��Ԓj���鉤���푒�҂Ƃ��ē`������Ă����Ȃ�A���s�̂悤�ɉ��ς��s�����Ƃ͍���ł��낤�Ƃ������ƁA�����Ĕ푒�҂ɂ��Ă̓`���������Ȃ��ꍇ�����s�̂悤�ɐV�K�n�삷�邱�Ƃ�����ł��낤�A�Ƃ������Ƃł���
�@�܂��A�����O�֎R�`���̗ތ^�v�f�ɂ��ċL�Ƃ̑���_����l����ƁA�㐢�ɓ��W��������ē��n�̐��͎҂ƂȂ����ƍl������O�֎��̎n�c杂ȂǂR���I�̎j���Ƃ͖��W�ȗv�f����A�̒n���N��杓��ƂƂ��ɐڍ�����Ă��邱�Ƃɂ͋^���Ȃ��B�O�֎R�`���ތ^�̐_�����b��V��ː_�b�ȂǁA�t�����ꂽ�^���̔Z���ȗތ^�I��������������ƁA���ψȑO�ɑ������Ǝv����`���̎c�������������яオ���ė��悤�B
�@�T���A�蔒���˂Ɏ��肳�ꂽ���a�˂Ȃǂ�薾�m�Ȍ`�ŁA�푒�҂��j���̒鉤�łȂ����Ƃ������`�����I�Ҏ[���ɂ����Ă����������Ȃ��������Ƃ��đ��݂����ƍl���邱�Ƃ��o���悤�B
�@�����푒�҂̂��̂Ǝ��肳��Ă��鑼�̋���Õ��ɂ́A���ÕP�i���_�@�A�i�s�\���j��蔒���i�p�̍@�A�Y���E�s�ӑ��j�Ȃǐ��Ƃ̌����I�p�����ɋ^�`�̂���剤�ɐ�������t�^���Ă���z��҂̂��̂Ȃǂ��ڗ��B�����́A�А_�i�_���j�Ȃǖ{�l���剤�����Ƃ����҂̂��̂�����B�����̐��i�Ɣ�r���Ă��A��͂蔢���R�̈ʒu�t���͈ٗ�ł���B
�@�I�̂��邷�p�\���̘`���ł̋t�]�폷�Ɋ֘A���āA�֗]�F�V�c�˂Ɣ��˂̓���o�ꂷ�邱�Ƃ��������A�����ē��ݍ���Ō����A�����R���l�Êw�I�m�����琄�@�����Ƃ���̎n�c����I�ȑ��݂ł��邱�ƁA���ޏ�����ł���Ƃ������Ƃ��A�����̖��O���m�����Ă���A�I�Ҏ[�����̐������������₂���Ȃ������Ƃ����������琬�藧�]�n�����낤�B
5�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:33:57.93
���S�i㕌��̒n���I�Ӗ��Ƙ`���̌`���j
�@㕌��͓��R�ƎO�֎R�œޗǖ~�n���k�ɓ��鉡�f���̓��[�߂��ɐ�n����B���̒n�͑��p�����a���k�サ�����˓��q�H�̏I�_�ɂ��āA�����X���o�R�ňɐ��_�o��͌��t�߂��瓌�C�q�H�Ɍ������N�_�ł���B
�@�����ɏ���ɖʂ��A�k���E�R�A�ɂ��������ʂ̗v�Ղł���B�T���A�O�֎R�������h�}�[�N�Ƃ���҂Ɋ֍ǂ̐_���J��n�ł���A�Â�����s�����B
�@�АM�ނ̗����搧�̏�������A�퐶����̖k����B�ł͑ΊO���͂œˏo���������̋��S�����������Ƃ��������Ă���A���̂����ɂ͒������АM����Ɛ�I�ɓ��肵�z�z���邱�ƂŁu�`���v�I�Ȑ����I�Z�܂�����o�����߂��Ɍ������҂��������B
�@�������Ȃ���A���ƌ`���ƌĂׂ鐅���Ɏ���ʂ܂ܐ��ނ��A�ŏI�I�ɂ͂Q���I���̑嗐���A�������АM�����胋�[�g�̓r����ȂāA���̗ɂ����鋌���E�̒����͕����B
�@����āA�C����������ɋN������Љ�s���̒��É��Ɛ����I���S�͂̑r���ɂ�镴���̉����ړr�Ƃ��āA���̒n㕌��ɐV���Ȓ����̒������\�z����A�{�i�I�ȍ��ƌ`�������ɏA���B
�@�����Ƃ́A�e�n�̑����ԓI�ɏW����^���O����~���ɕ\�ۂ���邱�ƂɂȂ鐭���I�W�ɂ����鋁�S�I�W��̏�Ԃ��A�����̒����̌�b�ŕ\���������̂ɑ��Ȃ�ʂƎv����B�����炭�͓����ɒ���̒�ł��������ꂪ�A�������̈АM�����^�ƍ��J�̋K�i���ɕ\�ۂ����Ԃ̃����P�[�W�̊j�ƂȂ��Ă����̂ł���B
�@����͎ƎX�̑��̌������d�w�������`�Ԃ��Ƃ�A����̑O����~���z����拤�L�Ɍq�����Ă����c�`�ƂȂ�B
�@��^���O����~���ɂ����鑒���́u���ԁv���v�f�̒��ŁA�ˏo���Ă���̂͋g���n���ł���A�k���������ѓO���Ă���E���\�g���͑������猩���������̐����Ƃ�����B
�@���Ƃ��E����u�l�����̕����I�Ĉꐫ�́A�𗬌��E�ʍ����Ƃ��ēZ�܂肪���݂������Ƃ�����
���̊��p�������Ƌg�����j�Ƃ��鐣�˓����Ƃ̍���́A���{���������c�т��闬�ʑ哮�����`�����A�����I�ɘ`�����̋A�����������Ƃ������悤�B
�@��i�ŐG��鏊�̊��≻�ɂ��C�����ቺ�ŁA�����̍��u��̍`�p�W�����p�₵���`�����v���ċ@�\�ቺ�𗈂��������{�C�q�H�ɑ��āA���˓��q�H�̉��l�͑傢�ɏ㏸���Ă����B㕌��ɒa�����������̓����ł��鋁�S�����A���̗��ʎx�z�̐����܂������̂ł��낤�B
�@���̈Ӗ��ŁA�`�l�`�ɓo�ꂷ��`�̍������Γ`���Œ��������ʂ�ʐM�Ɍ��y���Ă��邱�Ƃ́A���ڂɒl����B
�@�������}�g�����̐��i���A�A���t�B�N�`���I�j�[�ƒʏ��A���̗��ʂ��痝�����邱�Ƃ́A�L�v�ł���B
6�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:34:18.30
���T�i�`���̌`���ƋC��ϓ��j
�@�P�ɁA��d������͂Ƃ���E���n�Z�����k����B�ɈڏZ���𗬂��Ă���Ƃ݂����
�@�Q�ɁA�͓��Ƌg���̌𗬂̐[��
�@���̂Q�_���ӂ݂�A���C�n���i�����j�ɂ��e���͂����@���I�w���҂��A㕌��̒n�ɒn��ԕ�������̋@�\�Ƃ��ėi���������͂̒��j���Ȃ��̂́A�ėI���ՖԂ̍č\�z�Ɗg���ړr�Ƃ���A���˓��̊C���ʂ��x�z��������̗��v�����̂ł��낤�B
�@�����ɂ���Ēn���I�R�т̈�����L��̃v�����Ƃ��a�������B���̐��n�i�K�ł��낤�R���I�O�����ɂ́A�l������L���铝���@�\��s��̓����A�ʐM�Ԃ̐����Ȃǂ��ώ@����Ă���B
�@���ꂪ�X�Ɍl�I�J���X�}�̎������_�@�Ƃ��āA�z���O���ɁA�@�։����������V�X�e���̃t�F�C�Y�ւƐi�ނ̂ł���B
�@�Q���I�́A�Y�f�N��̊r���Ȑ��Ȃǂ�������z�����̕s�����ȏ����Ď���Ƃ���A���≻���i�����ł��邱�Ƃ��m���Ă���B
�@���̊��≻�́A���E�I�Ȋ����e�ʗ͂̒ቺ�ƂȂ��āA���鍑�̎�̉�������Â���_���̔敾�i���U���܂ށj��k�������̓쉺�������N�����Ă���A���I���t�̒����͓V���嗐�̎����ƂȂ���
�`���������̎����ł���B
�@���≻�ɂ��C�ނ́A���u�̔��B���ĊJ�����A���g���Ɉ��肵�Ă������u��ɓW�J���Ă����������̊C�l�W����p��ɒǂ����݁A���`�̋@�\�ቺ�Ƒ��ւ��č������ʖԂ̍ĕҁi�����{�C�q�H�̐��ނƐ��˓��q�H�̗������܂ށj�𑣂����B
�@�퐶�Љ���I���Ɍ����ē]�g�������Ă����C��ϓ��̑����Z�ł���B
������ȊC�ފ��ɂ͖��╨���w���A���g�ȊC�i���ɂ͈╨���N���X�i�w�����݂Ɍ`������Ă���A��Ղ̏�������������B�i�b��2008�j
�@�N���X�i�w�̎����͖퐶�O���`�����E�퐶�I���`�Õ��O���E�Õ�����`�ޗǎ���ł���A���̍��Ԃɋ��Ԃł��閳�╨���w�̎���������B
���������Y��ՁA�R�����L�Y�S���̕l��ՁA�y�䃖�l��ՁA�g����
�������V����ՁA�������ՁA���V����ՁA�䏰�������
���茧�ܓ��̉F�v������ՁA���]�s��l���
���������F�h�`��ՁA��q�����m�����
���Ő��������m�F���ꂽ�B
�����̎����́A���[���V�A�嗤�̊��≻�ƈ�v����B
7�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:34:39.26
���U�|�P�i���R���Ɖ����\������݂����ƌ`�����Љ�̓��ԁj
�@�������A���≻�ɑΉ����鐶�Y�͊m�ۂƂ����Љ�I�K�v�����A�J���⎡���E���̕���ő�K�͊J���s�ׂ��s���ɑ���J���͂��ʂɒ����ł���悤�ȋ����I�Ȓn���^��a�������������B
�@����́A���u��̋}���ȋ��剻�E���ˉ�����M�m�ł���B��������A���ˉ��̉��������n��ɂ͋}���ȒE�퐶�̎Љ�\���ϓ����N�����Ă���B
�@���I�ȋ�̗�Ƃ��ẮA������Ɍ������s����ȋC��z���鎞���A�g�����암�ő̌n�I�ȗp���{�݂��������K�͂Ȑ��c�J�����A���ˉ����ꂽ��K�͂œ��O�Ȗ����Ɍ���АM��n�ʂ�t�����ꂽ����̐l�X�̐͏o�Ƌ����I�ɐ��N�i����2014�j���Ă���B
�@�͏o���ꂽ����҂ւ̈АM�t���̏ے��Ƃ��āA���j�������g�ł��镭�u��ɕt�т�����̂Ƃ��āA�{���I�Ɍl���g�̂ɑ������镨�i�ɗR������АM���ɂ͐e�a�������锽�ʁA�l���L�ɓ���܂Ȃ��y��^�����Պ�͑O�r�������̂Ɛ��@�����B
�@����ɓ����Ċ��ɑޒ��ƂȂ��Ă�����^�̕���^�y�ъy��^������J�́A���L�͂Ȓn�擝�����ے�����Љ�I�j�[�Y�̍��܂肩��A���̖������������̍������˕��u��ɂ���đ�P����A���̎Љ�I�g�����I���Ɍ������B
�@�₪�Ēn��ԓ����̑j�Q�v���ƂȂ肤��Պ�̐��i�̍��ق��̏ۂ���K�v����A����^�̎��������������ʂɁA�y��^�̒������l�̑��`�I���������w�ɓ������Ĉ����p����A�Õ����J�̕t�їv�f�ɗ����i�g�c2014�j�����B
�@���߉������������̏ے��Ƃ��āA���^�ʼn����̂��铺�V�݂̂��V�퉻���ČÕ�����Ɉ����p�����B
�@���`���a��͎�ɐe���W�c��Ƃ��ċߋE�E���C�𒆐S�ɕ��z���A�~�`���a��͐͏o�w�̕搧�Ƃ��ĉ��R�ɕ��z�������A���̋��E�ł����d���ŗ��҂����������B
���̉�����ɁA�~�`���u��͖퐶����ɐےÁE�d�����爢�]�d�E�ۉ͐�E�O�g�암�E��a�R��A�ߍ]�ւƓW�J���A�����t�ɂ͎��a����������ω������ˏo���t���~�`���u��Ƃ��Ċ��p�n��y�ё�a�~�n�ɂقړ����W�J���A���ꂪ��a�ŋ��剻�̉�������O����~�`���u��Ɍq����B
�@��̕����̋��������d���őO����~�^���u��ƕ��`���a��̊Ԃ̊K�w�����������A���ꂪ�O����~�^���u�拐�剻�̗v���ƂȂ��Ċg�U�����\��������B�Ӊ����Ŕh�����������̕ω����A�E���Љ�����ɂ��i�s���Ă����K�w����������`�Œ��S���ւƃt�B�[�h�o�b�N���ꂽ�̂ł���B
�@���̕搧�̐����ߒ��ɂ́A�������y�킪����Z�@�A�Đ����@�Ƃ��ɍݒn�ȊO����̉e�����Z�@�̈ꕔ��������ĐV���Ȍ^����n�o���Ă��邱�Ɓi���F2006�j�Ƃ����ʂ�������������B
8�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:03.65
���U�|�Q
�@���ˉ��̐i�s����M�m�����Љ�\���ω��͊e�n��ŊT���������J�̏I���Ɗ�����ɂ��Ă��邱�Ƃ��m���Ă��邪�A���ƋE���Ƃ��ɑ�a�Ɋւ��Ă͗�O�I�ɁA�������J�̏k���ƍ��˂̔����i���j�������g�Љ�̓����j�ɑ傫�Ȏ��ԍ�������B�ނ��덂�ˉ��ɑウ�đ�u�l�����L�͈͂ɐĈꐫ�����Ă���悤�Ɍ�����̂��E���̓��ِ��ł���A�������͓I�Ȋj�̌��o���ɂ����퐶����E���Љ�̓����̉𖾂��҂����B
�@�����I�ϓ_����́A�퐶�Ζ_���������瓺�����z�������ċE����u�l���ƁA�ߐ��E���̑O�g���A�ȂƂ��Ċ��p����j�Ƃ��������˓���ㅃG���A���`�����Ă���B
�@�����ŏg�Ɏw�E�����E���퐶�Љ�̋ώ����̒�����}���ɋ���O����~���ɂ݂錠�͏W�����N�N�������Ƃ́A�ߑ�̃|�s�����Y���ɂ��ʂ�����̂�����B���͂̈�ǏW���ƌ������A��҂��ˏo�E�u�₷�邱�ƂƑ��҂��ώ��ł��邱�Ƃ́A�Η��I�Ɍ����Ă��̎��ǂ�����������̂ł���B
�@����A��B�ō��ˉ����N����Ȃ������̂́A���̐�i�����Ђ����Ē��ԊK�w���x�T�ŗL�͂ȎЉ�\���ł������ׂɁA�ˏo�������͂̔����ɑ��ĝy�I���傫��������ؓI�ł��������Ȃł���ƍl������B
�@���̊��≻���߂���ƁA���̌Õ���������J�n����܂ł̊ԁA���u��ɂ͍ĂуN���X�i�w�̌`�����n�܂�A�W�����Đ�����B�@���I���Ђ������͂��s�g�ł����w�i�ɂ́A���̂悤�Ȉꎞ�I���g���ɂ��Љ�s���̒��É��Ƃ�������������A�C��ϓ������J�҂̑��݊�����������Ӗ��ŗ\�蒲�a�I�ɓ������\��������B
�@���̃N���X�i�w���̈╨�ɋ�������̂��������s���̓y��ł���B
9�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:27.12
���V�i�k����B�ɂ�����l�̈ړ��Ɛ����I�����j
�@�R���I����������I�̎��ԕ����������s���ƌĂ�A�ږ�Ă̊������Ԃ��c�O�|���I�ɂ���ƊT�ˏd�Ȃ�B
�@�k����B�ŏo�y����y�Q�y��͏������s�����s�[�N�Ɍ����A�y�t�� IIB�i�z���O�V���`�z���h�Ñ��j���ɂ͊m�F�Ⴊ�Ȃ��i�v�Z2007�j���Ƃ��m���Ă���B����͒�؊��i���v�y�QIV���j��E�����y�Q���ċ����i���y�QV���j�Ɋ����ȑΊO������W�J�����̂��}���ɐ��ނ���A�Ƃ������������A���^�C���ɔ��f���Ă���B�iFA43�Q�Ɓj
�@�܂苌��S��Ƃ̌���IIA���i�z���O�Ñ����s�j�̒��łقڏI�����Ă������̂Ƃ݂��A�s�[�N�ƂȂ鏯�����̒���鰂ƒ���I��������������240�`248�N���ʒu����ƍl������B
�@�������s���́A��s����퐶V���Ɉ��������E���l���̓y�킪�Q�i�I�ɖk����B�ɗ������Ă��鎞���ł���A���Ƃɂ��̍ŏI�����ł���z���O���ɋ����I�ɐi�W����B���̗����͐l�I�ړ������̂ƍl�����Ă���A�����p�݂ɍL����A�͐�ɉ����ē����ɐZ������B
�@��ʂ̕���ɋE���n�y�킪��������鎖�Ⴊ�����A�R���I�O���̂����ɔ����߃m�Òn��̐����������퐶����ȗ��̏t���n�悩��E���n�F�Z���Ȕ�b�E�߉ϒn��ֈڂ邱�Ƃ�����A���̐Z���̐��i���`����B
�@�t�ɁA�Ō�܂ōݒn�n�̓Ǝ������ێ�����̂������n��ŁA���̋E���n�y��̎�e�ɋɂ߂ď��ɓI�Ȏp���́A���}�g�����ւ̐ڋߌX���������Ȕ����Ƃ͑��G�I�ƌ�����B
�@�O�`�ł��鍡�Øp�A���z���p�o���ɋE���n�̉�����������ɂ��S�炸���S�����ݗ��n��F�ŁA�ɂ߂ċ͂��̋����y�킪���J��\�Ƃ�����p�Ŕ��������̂݁A�Ƃ����́A����������͓I�ǂ̒��Őh�����Đ����I�Ɨ���ۏ���Ă���悤�ɂ����f��B
�@�P�ɁA�O����~���̐Z���i�O�`�F���n��ɋv�ZIIB���A���S�X�F�ˉ�ɓ�IIC���j�����̌�̈ɓs���̏I���ߒ���\�ۂ��Ă��邱��
�@�Q�ɁA�����I�F�ʂ�тт���嗦���l���̏��Ȃ��ɓs���Ɏ���u���Č��@�Ɩ������s���Ă���ƋL���j��
�@������ˍ�����ƁA�ΊO���Ղ̎哱����r��������̈ɓs���̎p���M�m�ł��悤�B
�@�k����B�̓y��ҔN�Ō����Δږ�Ă̐l���̑唼���߂鎞���̑�������v�Z�hA�E�hB���A�����͑ΊO���Ղɂ��čő勉�̒��S�n�ł���B���̂���A�����͋E���l�̗������܂ސ[���l�I�𗬂�����A�����l������c����J�̌`�Ԃ܂ŁA���̉e�����Ă���B
�@���̉e�������ݗ��n�Ɖe����^�����O���n�������E�W�Z���Ă���W�c�ƁA�O���n�ɑ��ĕ��I�ȍݒn�W�c�̊ԂɁA�O�҂���ʂƂ���W�c�Ԃ̊K�w�����w�E�i�a��1988�j����Ă���B
�@�����O�_�ԏ�n��Ɉ�萔�̊y�Q�l���Z���m��������Ă��邱�Ƃ��ӂ݂�A�`�������ƍ������ĊJ�����R���I���t�ɂ����āA�����͕K�������̏�����肵�Ă���ƌ��Ă悢�B�]���āA����鰉����͋E���ɂ������`�l�Љ�ő�̐�����m���Ă���ƍl����ׂ��ł���B�y�t��hB����鰉����ƍ����̂����������ɑ������邱�Ƃ͏����̈�v����Ƃ���ł���B
10�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:35:44.20
�@���̎����ɁA�z���̒�����ɔ�肳���߉ϔ�b�n��̓y�푊���E�����}�g�́u��ђn�v�I�W�J�Ɍ������Ă��錻���́A�הn�䍑��B���ɂƂ��Đ�]�I�ł���B
11�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:36:09.61
���W�i����j
�@���{�̑ΊO���́A�Â����ӓ��f�ՁA���Ō��m�Җf�ՁA�����Ĕ����p�f�Ղƈڍs����B
�@���m�Җf�Ղ̒��ڎ�̂����̃I�E�ł���A�����ɍł��e���͂������Ă����̂��O���O�_�̉��ł��邱�Ƃ��L���ł���B
�@���m�҂����C�����������p���ΊO���̎���ɖ��o��̂��A�������s���ł���B
�@���̓]���̍ŏI�i�K�ɂ́A��a��d������ڏZ���Ă����l�X�₻�̓��オ���|�I�V�F�A���߂�`�p�s�s�Ő����{�e�n�̐l�X���ؐl��y�Q���l�ƒ��ڌ��ɂ����Ղ�W�J���鎞��ƂȂ�
�@�O���O�_�̉��͐Â��ɕ\���䂩��ޏꂵ�Ă����B
�@�����p�f�Ղ̎���S�̂�ʂ��āA�߉ϐ�n��[����여��[㕌��͍������ʂ̑哮�����x����g���C�J�Ƃ��ċ@�\���A���̏����������I�Ɉ�v����B���ꂪ�`�l�`�L�ڂ̎O�卑�i�z�E���n�E�הn��j�A���C�A���X�ł���A�����p�f�Ղ���Ƃ���`���̐��̂ł���A���C�f�Ղֈڍs����܂ő��������ƍl������B
�@�k���āA����n���W���͖퐶����ɂȂ�ƒ�u�ˏ�ňꕔ�̈�ʐ����W�����h�q�I�v�f��тт��`�Ԃ��Ƃ�B
�@���̌��ۂ́A���≻���ۂɋN������Ǝv����Љ�ϓ��̑��݂�A���������≻�ɋN�����钆���̐���s���ɂ��АM���A���r��Ƃ��������I�v�f���I�ɔ��f����ƁA����������ɂ���u�`�����v�ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@���̎����ɍ��n���W��������B���瓌�C�A�k���ɂ܂œW�J����Ƃ��������́A�u�`�����v�����{���������L�͂Ɋ������Љ�ۂł��邱�Ƃ��B
�@�y��g�U�ɂ݂鉓�u�n�𗬂̊������ƕ�������A�Q���I���`�R���I�̏؋��́A���ׂď������}�g�����ƐV���`���̒a�����w�������Ă���̂ł���B�����K�����قƂ�ǎ�e���Ȃ��n��ł������E���i����1970�j�̕^�ϓI�Љ�\���ω��́A�S����I�����a���Ɍ������ٓ��ɂق��Ȃ�Ȃ��B
�@�����Đ��ł��������{�����؎Љ�ƓԂ̍������ĊJ�����Ƃ��A���̊O�I�h���ōł��ω��̐������n�悱���������̘`���̒����ł���B
�@�`�l�`�q�ׂ�Ƃ���́A�R���I�O�����ɑ�鰂ƒʌ������`�̏����͂ǂ��ɂ����ł��낤���H
�ȏ�̍����ɂ��A����͍���s㕌��ȊO�ɂ��肦�Ȃ��B
12�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:36:52.44
���X�@�Q�l (URL)
���l�b�g��ł�������A�E����������\�I�Ȋw�҂̂ЂƂ�
�@���V�O����ʌ����ɏ������_��
㕌��w�����@��P���iPDF�jhttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-1.pdf
㕌��w�����@��S���iPDF�jhttp://www.makimukugaku.jp/pdf/kiyou-4.pdf
���@�Q�l�i�s�̏��Ёj
�������x�[�X�̓���I�_��
���{���O�u�הn�䍑�ʒu�_���̊w�j�I�����v���{���I�����P�V����
�m�� �֎j�u�`���̐����Ɠ��A�W�A�v��g�u�����{���j�P����
���R���p�N�g�ŕ�I�ȊT����
�m��ЕҏW���ҁu�Ñ�j�����̍őO���@�הn�䍑�v
�����A�W�A�̍l�Êw�ւƎ�����L���������
�����u�הn�䍑�̍l�Êw�v
��
���P�O�@���N��ڈ��̎Q�l
�i�����_�ō����w�Z���{�j���ȏ��Ȃǂɍ̗p����Ă���N��ςƊT�˓����́A�ł��L���ʗp���Ă�����́j
���퐶������
�@�@�P���I��P�E�Q�l�����`�Q���I��R�l��������
�����������i�����O�`�R�j
�@�@�Q���I��R�l���������`�R���I�����@
��������O���O���i�z���O�`�P�j
�@�@�R���I�����`�S���I��P�l����
���Õ�����O���㔼�i�z���Q�`�R���E�V�i�K�j
�@�@�S���I��Q�l�����O���`�S���I��R�l����
���Õ����㒆���O���i�z���R�̈ꕔ�ATG232�`TK216�j
�@�@�S���I��S�l�����`�T���I����
�@�@�@�i�Ñ�w������@�X���A�O�D�A�c��2016�ɂ��j
�������R�Õ��͕z���O�Ñ��ɊY���i���V2002�j
���{�����V�́u�R���I����������I�̎��ԕ����������s���v��
�@�����O�����������O�Ƃ��Ė퐶����ɕ��ނ���l�����ŁA���N��ς͓���ł���B
�@���l�ɁA�z���O�������ɕ��ނ���l���������N��ςɈႢ���Ȃ��B
�@�������s����퐶����ƌĂԂ��Õ�����ƌĂԂ������N��ς̑���łȂ����ƂƓ����B
���k����B�ҔN�i�v�Z�j�Ƃ̕��s�W�i�v�Z2002,2006,2010�j
�@�hA���[ ��a�����O�`�P�@�[�@�͓������h�`II
�@�hB���[ ��a�����Q�`�R�@�[�@�͓�����II �`III�@�@��㕌���ˁA����R�A�z�P�m�R�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@ IIA���[ �z���O�Ñ��@�[�@�͓�����III�@�@�@�@������A�����R51��
�@ IIB���[ �z���O�V���`�z���P�Á@�[�͓�����IV�`V�@�@�����a�A���ˁA���䒃�P�R�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Y�Ԓ��P�R�A��������
�@ IIC���[ �z���P�����`�z���P�V�@�[�͓�����IV�`�z���h���ֈ��ˎR�A�_���_�ЁA
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���X���R�A�s���R�A�_���R 13�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:16.41
���P�P
���e�`�p 1
�p�F�`�l�`�ɂ͋�B�̂��Ƃ��菑���Ă���ł͂Ȃ����I
�`�F��B�͘`���̈ꕔ�Ȃ̂Ŗ��Ȃ��B
�@�S�g�͈ɓs���ŏ�ɒ�����̂ŁA��B�̂��Ƃ��悭�ώ@����Ă���͓̂��R�̂��ƁB
�@�t�ɁA�ɓs���̑����锎���p�ݒn��Ɍ����Ȃ�������Y���i�܍��m���O��j���L����Ă��鎖���́A�`���̒n��I�L����𐄒肷�邤���ŏd�v�ȏ��ł���A�A���A�`���̓s�������p�ݒn��ɂ͖������Ƃ��B���ꍑ�ł͊ώ@���ꂽ����s�悭�ώ@���Ă����o���Ȃ������������A�`���S�ʂ̕����ƋL�^���邱�Ƃ́A�����I�s���łȂ�����ł���B
�@�E���͎�̐��Y�n��i���Ă���A����͂R���I�̋�B�Ɍ����Ȃ����̂ł���B����鐸����\�͎O�d�̒O���̓V����Ղ�X�Y��ՁA�F�ɂ̒O���͏オ�ꕶ�A���Ì��E���������퐶�����ŋ{�Ök���z���O�ƁA�Â����痘�p����Ă���z�����ݒn�ߕӂɓ_�݂���B
�@�����̌@��Ղ��̂��͖̂������ł��邪�A�O��ԍ⍡�䕭�u��i�퐶�I���j�o�y�̐���邪���炩�ɒO���z�R�Y��̓����������i���2008�j�A�z�P�m�R�̐�����Mn,Fe�̊ܗL�ʂɉ��đ�a����z�R�Ɠ������ِ��i���2001�j�������B
���䒃�P�R�i�R���I��R�l�������`��S�l�����j�o�y�̐���邪��a�Y�ł��邱�Ƃ͐���A�����y�щ����ʑ̔䕪�͂ɂ���Ĕ����ς݁i���2013�j �ł���B�����̏���A�R���I�̉F�ɂ�O���ɒO�R���L�������Ƃ͊m���������B
�@�k����B�̌Õ��o�����ɂ́A�ÌÐ��|�Õ��ȂNjE���Ɗ֘A�̐[���ꕔ�̌���ꂽ������E���Y�̐���邪��������i�͖��2013�j�Ă���B�푒�҂łȂ������{�݂Ɏ{�邷��̂͋�B�ł͖w�nj����Ȃ��V��i�u��E�J��2012�j�ł���A��������̉e���ƍl������B
�@�܂��A㕌���Ղ���o�y�����m�����`�l�`�̋L���ƍ��v����B�iFAQ51�Q�Ɓj
�@�`�l�`�Ɏ�����Y�̍d�ʃq�X�C���o�ꂵ�Ă��邱�Ƃɂ��^�`�̗]�n�͂Ȃ��A�����̒����l���F������`���͈͓̔͂��{�K�͂ł���B
���e�`�p 2
�p�F���s�Ƃ͉͐���s�����Ƃ��I
�@�@鰎g�͋�B���o�Ă��Ȃ��ł͂Ȃ����I
�`�F�C���s���Ƃ����u���s�v�ƋL�ڂ��ꂽ���Ⴊ����̂ŕs�����B
�u���s�v�Ə�����Ă��邪��ł��邩�C�ł��邩�������Ȃ��P�[�X���A��Ɣ��f���闝�R�͖����B
�@�t�ɁA���m�ɉ͐���ړ����Ă���P�[�X�Œ����u���s�v�Ƃ�����b���g������͖����B
�i��j
�@�@�u�����v���U��
�@�@�u���i�{�ŗL�����얼�j���V��
�@�`�l�̒n���嗤�Ȃ�ʑ�C���̓���ɏ��݂��邱�Ƃ͗\�ߖ�������Ă���B
�@�`�l�`�ɂ�����u���s�v�̏��o���u�z�C�݁v�ƕ����I�Ɍ`�e����Ă���ȏ�A�ȍ~��10����20���ɋy�ԁu���s�v�����̏ȗ��`�ł���ƌ����Ƃɂ͍�����������B
14�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:35.59
���e�`�p 3�|�P
�p�F�s���_���猾���āA�E�����͖����ł͂Ȃ��̂��I
�`�F�`�l�`�̋L���s�����L�ڒʂ�ɒH��A����{���t�߂̓�C��i��FAQ40�Q�Ɓj�ƂȂ�B�j���ɂ����Ȃ���߂��{���ď�L�ȊO�̔��n�����߂Ă��A����̓e�L�X�g�̉�₂������͕����ɑ��Ȃ�Ȃ��B
�@�u�c�݁v�Ƃ�����@����́A�M�҂���������`�l�̍�����m����i���E���B�s�ߍx�j���ɓ���ł���Ƌ�̓I�ɐ��v���A�`�l�̓���I�����Ƃ̐������m�F���Ӑ}�������Ƃ����炩�ł���B�i�֘A�F��FAQ 40�j
�̂ɁA�u���S���������v�́u�ݓ���P���v�͘`�l�̍�����m����قǂɓ���ł���ƌ����M�҂̔F����[�I�Ɏ����Ă���B
�@�ȏォ��A�`�l�`�̗����y�сu��v�Ƃ������ʋ�ɒv���I�Ȍ����܂ނ��ƁA���тɕM�҂��P����1,800�ڂ�p���Ă��邱�ƁA�̓�_�ɋ^��̗]�n���Ȃ��B�i�������j
���ۂ̘`�l�̍��X�̑�����`�n�͉�m�R�A�͂��납鰓s�����ɉ����炸�A����قǂ�����łȂ��A㕌��Ɏ����Ă͗��z�Ƃقړ����k�܂ł���B
�@�O�C���n�C�͊T�˂̒�_�邱�Ƃ��\�Ȃ̂ŁA�����ɍ��낪���邱�Ƃ����炩�i��FAQ19�Q�Ɓj�ł���B�����āA��B�{���œ�[�͉�m�R�A���P�ٖk���ł���B�܂��A�����̂P/�T�قǂ̉ˋ�̂P����z�肷��Ȃ�A�y�Q���u雒�z���k�ܐ痢�v�Ƃ���n�����ɏƂ炷�Ƙ`�n�͗��z�̗P�ٖk�ł���A�`�l�`�L���ƑS���������Ȃ��B
�@�M�҂̔F�����������]���̐����A�y�сu�쎊�הn�㚠�v�̕��ʁu��v�B���̑o���ɍ����F�߂Ȃ�����A�u�c�ݘ��m�����i����u��v�j�V���v�ƋL�q����邱�Ƃ͗L�蓾�Ȃ��B�܂��A����̌v�Z�ł��邩��A����́u���v�̕��ʂɌ덷�͂��蓾�Ȃ��B
�����āA�������L�q�����{�l�����v�����ʒu����m�R�A�ȓ�ł��邱�Ƃ́A�ꕔ����l�̑z�肷��ُ�ɒZ���ȗ��P�ʂ̕s���݂𗧏�����̂ł���B
�@���ۂ̒n����R�C���̊Ԋu���������łȂ����Ƃ͂��Ƃ��A�`�l�`���ڂ̂Ƃ���̍s����H�����̂ł́A�ɓs���ł��邱�Ƃ��m��������鎅���O�_�ɂ��A�z������ׂ������E��b�߉σG���A�ɂ����B�ł��Ȃ����Ƃ͎����ł���B
�@���̂悤�ɁA�s���L���͕��ʁE�����Ƃ��ɒ�����������܂ݎ��p�ɑς��Ȃ��̂ŁA���ݒn���ɂ͍̗p���Ȃ��B���ɂ̂ݗp����i�֘A�F��FAQ8,17,18,19,20,57���Q�Ɓj
�i�{�� �����j
15�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:37:54.01
�i���O�j
���e�`�p3�|�Q
�����@�Ñ㒆���̒n�����o�i�������n���u���L�ɂ��j
�@�ɓ��S�F雒�z���k�O��Z�S���@�y�Q�S�F雒�z���k�ܐ痢
�@�\�͌S�F雒�z���玵�S���@�@��C�S�F雒�z�쎵���S��
�@����S�F雒�z��Z��l�S��\���i�h�j���A�M�́u�����v�ɋ����雒�z��痢�j
�@�i雒�̗p����芿�㌴�j���Ɋ�Â����̂Ɛ���j
�@�`�l�`�]������12,000�]������������4,000���ł��邩��A�����������9,000�����x�ƂȂ낤�B�y�Q�����k5,000����������������T��3,000�����x�ƌ��ς���ƁA
�y�Q����A�R�A�����c���ɏ��݂���\�͂܂œ�k��6,000���ȉ��A�L���܂�10,000�����x�ƃC���[�W�ł���B
��L��9,000���͑ѕ��`���E���B�s�Ԃ̓�k�����Ƃ��Ė������Ȃ��B
�M�҂��`�l�̕�������m�Ȃ�тɎ�R�Ɣ�r���Ă��邱�ƂƂ���������B
�@�܂��A12,000�]�����������������9,000�����x�ƂȂ�ƕ��ʂ͒�������쓌�ɕ��A�`�l�`�`���Ɍf����u�ѕ�����v�Ƃ��ꗂ���ł���B���̂��Ƃ��u�쐅�s�v�̕��ʂɍ����F�ނׂ������ƂȂ낤�B
16�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:14.07
���e�`�p 4
�p�F㕌���Ղ́A�����˂��Ƃ����הn�䍑�ɂ͏���������I
�`�F�N���A㕌���Ձ��הn�䍑���ȂǂƁA�咣�͂��Ă��Ȃ��B
�@㕌���Ղ́A�ޏ����̋������s�ł���A���ł͂Ȃ��B
�@�܂��A�u�הn�䍑�͑�a���v�ƌ����\����p���鏔�����A�����͎הn�i�̌ꌹ�i���ʌ��j�ɂ��Ă̌��y�ł����āA�̈�Ƃ��Ă̗ߐ���a���Ƃ�����`���咣���Ă��Ȃ��B
�@�E�����ɂ����ẮA�הn�i���a����̉��E�Ƃ��������Γ�̌����i����1910�j�ȗ��傫�ȃu���͖������̂́A�ߐ������d埸�ƂR���I�Ƃł͎��ԍ��ɂ��ٓ��������ł��Ȃ��B����āA�הn�䍑�̌����Ȕ͈͂ɂ��Ă͍ޗ��s���ł�����̂́A�ߐ��܋E�̊T�O�ɑウ�āA�l�Êw�I�ϓ_����T�˂Q���I���t���_�̋ߋE��u�l�����z���z�肷��B
�@�܂��A�הn�䍑�Ə����������łȂ����ōl�����ꍇ�A㕌���Ղɔ����ʂ̑��������_�o�여�擙���͂��߂Ƃ���E�����������܂��A�������Ɋ܂܂��\�����l������K�v������B
���e�`�p 5
�p�F���ʂ��Ԉ���Ă����Ȃ�C����n�ꂸ�����I
�`�F1719�N�ɒ��N�ʐM�g�̈�s�Ƃ��ė��������\�ۊ˂́A�Δn�œ쉺���Ă���̂ɓ��������Ă���ƌ�F�����B����ɑΔn�͓����ɒ�����(������O�S���C��k�͂���1/3)�ƒ����w�C���^�x�ɋL���B�i�u�����O�S���A��k�O�V�ꕪ�v�j
�@���{�Y�i���E�Δn�s�㌧�����{�ށj�͑Δn�̖k���[�A�{���i���E�����j�͂������瓌(���ۂ͓�)��S�Z�\���Ə����B
�i�u�����������R�l�S���\���A��������{����S�Z�\���v�j
�@���D�z�ł́A���ۏ��钩�������Ă���̂ɁA�ˑR���ɐi��ł���ƍl���Ă���A�ނ̒n�����͂��傤��90�x�����Ă���B
�@�Δn���猩�Ċ��R�𐼁A��㋞�s��k�A����𓌂ƔF�����Ă���B
�@�Ƃ��낪�A�Δn����̋��s���̕��ʂɂ��đ傫�����낵�Ă���ɂ��S��炸�A�]�˂͋��s�̓���O�S���Ɛ������c�����Ă���B
�@�ނ��Ȃǂ����A�����Ɠ����������Ă���B
�@���̂悤�ɁA�g�҂����ʂ���F���Ă��Ă����S�ɉ��҉\�ł��邱�Ƃ̏ؖ������݂���ƂƂ��ɁA�����ₓ��ɂ���đS�̂̐������͈ՁX�Ƒr�����邱�Ƃ����炩�ł���B
���e�`�p 6
�p�F�E�����ł́A�ږ�Ă͋L�I�̒N�ȂH
�`�F�L�I�̉����������̂܂j���ƌ��Ȃ����߁A�ږ�Ă��L�I�̒N���ɂ��̂܂ܓ��ěƂ߂Ȃ��B�ߔN�̗��j�w�̂�����ɉ������l�����ƔF�����Ă���B
17�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:33.00
���e�`�p 7
�p�F㕌������B�̓y�킪�o�Ȃ��ł͂Ȃ����I
�@�@㕌��͋�B�הn�䍑�ƌ𗬂̂Ȃ��ʂ̍����낤�H
�`�F���̂悤�Ȏ����͂Ȃ��A���R�𗬂��������B
�@�E����V�l���A�������A�z�����݂Ȏ��n��ɉ����Ėk����B����o��i�{�����V�Q�Ɓj���A㕌��ɂ����Ă��}���Ő��삳�ꂽ�����P�i�v�Z2006�j���o��B�E���Ɩk����B�����ԊC�H�̏d�v���_������E���n�E�g���n�̓y�킪���������B�i��FAQ31�Q�Ɓj
�@���̂��Ƃ́A�������Ă����̂��E���n�E���˓��n�̐l�Ԃ��������Ƃ������A�E���Ɩk����B�̕Ж��I�W����������B���E���n���Љ�I�ɏ�ʂł���B�i���V�Q�Ɓj
���e�`�p 8
�p�F�u���������n�C���P���A���L���A�F�`��v
�@�@�Ƙ`�l�`�ɂ���B�E�����͓�𓌂ɓǂݑւ��邩��A����͖k���ȁH
�`�F�ǂݑւ��Ȃ��B
�@�s���_�Ƃ͕ʂ̕��@��㕌���`���̓s�Ɠ��肵�����ʁu�쎊�הn�㚠�v�̓�́u���v�̌��Ɣ��������B�܂�A�s���_�Ŏהn�䍑�̈ʒu���肵�悤�Ƃ����B���̑����Ƃ͘_���̌������t�̕��@�_�ł���B
�@����͑��̉ӏ������ǂݑւ���Ƃ����咣�ł͂Ȃ��B
�@�Â��͈ɓ������_�Ó��Y�̍��j���O�d���܂ŗ��ʂ��Ă���B�l�ÓI�╨�̕��z������A�×��S�D�̓n���ɐ����O���x����ɓ�֓��Ɏ���C���ʘH�̑��݂����炩�ł���u���������n�C���P���v�̏�Ƃ��Ē��ڂ����B
���e�`�p 9
�p�F��z���͂ǂ����H
�@�@���������������̂������{���悤�ȍL�悾�Ƃ�����
�@�@�����ɑ������t�ɋ��������̐��́A��z���Ƃ͉��҂��H
�`�F�r���P��P���g�U��Ȃ�тɑ��E���V���z�悪��������k���A�֓��ɋy�ԍL��ɑ��݂����B
�L�͂Ȍ��ł���B
�@����B�𒆐S�Ƃ����Ɠc�����z����ʐϓI�ɂ͋������A�`���̑ΊO����j�Q����\���Ƃ������ʂł̊댯�����l������ΑR���͂Ƃ��ĕ]���ł���B
�@�`�����ږ�Ă͓�S�̑Ίؐ���ɋ��͂����`�Ղ��Ȃ��A���̌�����ɋ�z���̋��Ђ��������ꂽ�\��������B
�@���Â�ɂ���̖M���Ƃ��������Ă���j�I���W�i�K�ɂ͂Ȃ��A�����́u���v�͕����̐����I�n��W�c���_�Ɛ��Ō��ꋮ埸���s�����ł������ƍl�����邱�Ƃ͔O���ɂ����K�v������B
�@�����̔ږ�|�Ă��̍��Ɨ����������ł͘`���Ɠ��ꕶ�����ɑ�������̂Ɖ�����̂ŁA�ږ�Ă̋����ɑ��ĕs���ȕ��h�Ƃ������߂����蓾�悤�B
18�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:38:52.90
���e�`�p 10
�p�F����͋{�����Ǘ��̗˕�Ŕ��@�ł��Ȃ������I
�@�@�N�オ����Ƃ����l�Êw�҂͂��������ł͂Ȃ����I
�`�F����i�����R�Õ��j�����ō̎悳�ꂽ�y�푊�͋{�������˕���������o�Ă���A���̐��ʂ��퐶�����t����A�����鎞�Ԏ���ł̎w�W�ƂȂ��Ă���B
�@�˕�w�肩��O�ꂽ���u���A�n���A�����͔��@����A���̋@�ւ��琳���̕����o�Ă���B
�@���y��z�����y��茊��Ŕ������ꂽ�y�퓙���H���J�n��������Œꕔ�ɖ��v�����y��ł����Ċ�������̎��_�������Ɣ��f����A�z���O�Ñ��͈͓̔��Œz�����ꊮ�������Ɣ��肳��Ă���B
�@�������Ȃ��畕�y�ȑO�ɂ͒n�R��o���H�������邽�߁A���H������Ɏ�k��\�����ے�ł��Ȃ��B
���e�`�p 11
�p�F�`�l�`�̍��͗��߉��̌S�قǂ̋K�͂��낤�I
�@�@�����̍����R�O�����x�Ȃ�A�}�O�E�}��E��O�O�����x�̋K�͂ɂȂ�Ȃ����H
�`�F�`�l�`�̋L�q����́A�T��˖����̏����ƁA���P�ʂ̑卑�ɓ�ɕ������Ă�������Ď���B
�E�O�҂��A���R�������ɑj�܂�ċK�͓I�ɖ퐶���_�W���̈��E���Ă��Ȃ��u�N�j�v
�E��҂��A�͐여��╽�쓙�̒P�ʂ̑傫�ȓZ�܂�ւƐi�������A�V��������́u���v
�Ƃ݂���B
�@��҂ɑ�����z���̈ʒu�́A�����p�ݒn��ő�ł��镟������ɋ��߂邱�Ƃ��Ó��ł���B��埸�ɂ͒}�O�^�����P�̔g�y�͈͂�z�肷�邱�Ƃ��o���悤�B
�@�g��ʂ���R�O���̂������҂̍\����͕s�������A���ׂĂ��S�P�ʂƌ��͕̂s�����ł���B
19�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:12.05
���e�`�p 12
�p�F�`�l�`�ɂ́u���p���v�Ɩ��L����Ă���I
�@�@�E�����͘`�l�`�ƍ���Ȃ��̂ł͂Ȃ����H
�`�F���Ƃ����l�Êw�p��͌Ñ㒆���l�̔F���Ƃ͈قȂ�B����Ĕ��f�ޗ��ƂȂ�Ȃ��B
�@�������ɂ����Ă��A�R���I�O���Ɗm�F�ł���S���͂ЂƂ��o�y���Ă��炸�A�����͓����ł���B
�@�퐶����ɓ������ꂽ�����́A�V�퉻�������Ŏ��p����Ƃ��Ĉꕔ���S�퉻�������A�w�Ǖ��y���Ȃ��܂ܖ퐶�����ŊT�ˏ��ł��� �B
�@�ȍ~�A�Õ�����ɓ����āA�R���̓ˌ����}�������߂̎O�p���^�̕������ˎh���큁�������s����܂łقړr�₵�����R�́A���p����Ƃ��Č��S���̗v����������S������荂���A�����i�ł��铺���Ɠ����̑ܕ�\����S�̒b���i�ō�邱�Ƃ��o�ύ������̏�œS���ɗ�サ�����߂ƍl������B
�@�����̑��͒����ȍ~�̂��̂Ɨe�e�����قɂ��Ă��āA����̕����S�̔f�ŋ���Ŏ��Ŋ��������œh�肩���߂ČŒ肵�Ă���A�g�p�@���`������̌�p�i�ł������Ǝv���� �B
�@�R���I�ɑ�����S�g�̔�����ł͐������˂�����A�S���⌦�D�����̈╨�Ƌ��ɔ��@���ꂽ�B
�@�`�l�`�ɕ`�ʂ��ꂽ�R���I�O���͖��̕��������s�������n���Ƒ��G�I�ɁA�{�M�ŐM���ɑ���S���̏o�y�Ⴊ�����Ȃ������ł���A�����̘`�l�Љ�Ŏg�p����Ă��钷������́A�����Ō������ł���B
�@�`�l�`�ɂ������p����́u���v�̎��̂́A�`�l�`�������̕҂��ڌ������Ƃ���̘`�l�̕���A�T�������̍l�Êw�҂����ƌĂԈ╨�ł���\�����ʼnE���Ƃ����邾�낤�B
�@�����̒����Łu���v�Ƃ��������͒���������w�����̂ł͂Ȃ��̂ŁA����l�̌����R���I�����̑����������������l�������\�L�����\���̂����b�����Ɍ������炸�A���������̎Љ�ōł��ގ���������̖��O�ŌĂƂ��ĉ���s�v�c�͖�������ł���B
�@�Ȃ��A�u���{�l�Êw�̏K���ŕ��Ɍs��������̂������A�ܕ��ɕ����������ނ��̂��z�R�Ƃ����Ă��邪�A����͌���l�Êw�̕X��̋�ʂɉ߂��Ȃ��v�i�u�퐶����Õ��O���̐킢�ƕ���v���{�̌Ñ�U�j�Ƃ������B
�@������
�u�w���p���|�؋|�B�|�������V�B�x�Ƃ���́A��v�����n���u��儋����R�̋L�����P�p����B������鰐l�̑z����趂ւČÏ��̋L���鏊�ɕ��������萄���ɁA�e�������o�ł��ɂ��炴�邱�Ɩ��炩�Ȃ�B�v�i����1910�j
�@�̎w�E�͍������L���ł���B
20�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:31.04
���e�`�p 13
�p�F�`�l�̕�́u�L�����v�Ɩ��L����Ă���I
�@�@�Õ��ɞ̂���E���͘`�l�̍��ł͂Ȃ��I
�`�F�Ƃ���������{�̍l�Êw�p��́A�Ñ㒆���l�̌�b�ł���i�{���̞j�Ƃ͈قȂ���̂ł���B����Ĕے�ޗ��ɂȂ�Ȃ��B
�@�����u�v���Ñ㒆���̂���Ƃ�������Ă��邱�Ƃ͔S�y���I�ȂnjÑ㒆���ɂȂ��ď̂�p���Ă��邱�Ƃł������ł���A�l�Êw�҂̊Ԃł��ᔻ�I�ӌ��̂���Ƃ���ł���B�i�֓�����j
�@�Õ��̒G�����Ύ����܂��Ñ㒆���l�̉]���̊T�O�Ƃ������ꂽ�`��E�\���ł���A����鰐W�l�ɞƔF�������\���͖����ɓ������B
�@������{�l�Êw��Ŗ؞ؕ�ƌĂ�Ă��閄���p�n���\�z���́A�퐶����ȍ~��ɖk����B�𒆐S�ɕ��z���Ă���A�����I�ɂ݂Ċy�Q�؞ؕ�̕����I�g�y�E�ԐړI�e���Ǝv���͂�����̂́A�z�P�m�R����܂ߌ��`�Ƃ͎��Ă������ʌ`��ł���A�Ñ㒆���l�ɖ؞ƔF�������Ƃ͍l����B
�@�E���ň�ʓI�ȕ�͖؊������Łu�L�����v�ɓK�����Ă���B
�@�t�ɁA�k����B�ɑ��������Ί��͒����l�ɞƔF�������\�����ے�ł��Ȃ��B
���e�`�p 14
�p�F�E���̐������A�{�����������ꂽ��B�ɓs���ɏ������݂���悤�ȋ����͂����@�ւ�u�����Ƃ͍���Ȃ̂ł͂Ȃ����H
�`�F�k����B�ő吨�͂̓z������ɋE���n�Z������������A�z���ƋE���͖��ڂȋ����W�ɂ������ƍ����I�ɐ���ł���B���̐l�I������w�i�Ƃ��āA�ɓs���̊O�`���Ǐ�����ʒu�Ƀ��}�g�����������I�ȊĎ@�҂�u�����Ƃ͏\���ɉ\�ł������Ǝv����B
�@�ɓs���̉��s��Ƃ����O�_��Ղ��獡�Øp�ɒ������~����̉͌��t�߂ɂ́A�����ݏZ�̋E���n�Z�������������Ƃ݂������ȋ��_������B
�@�����͈��Ƌ����p�C�v��L���Ă������Ƃ���A�퐶���E����ɂ����đΊO�f�Ղ̗���Ɛ�I�ɋ��Ă����o�܂��A�╨����M�m�����B�k����B�ɂ����Ă��АM���̔z�z�ɉ����Ė��炩�Ɋi���̂��鈵�����Ă����Ӊ����̎ɂƂ��āA�ΊO�f�Փ����҂̗����Ɛ�𐧖鋭���I�ȊĎ��҂̑��݂͗L�v�ł���B
�@���̂悤�ȏ��ŁA�E���o���̗������k����B�ɂ����āA�������݂���悤�ȋ����͂����@�ւ��哱���邱�Ƃɂ́A����Ƃ���������F�߂��Ȃ��B
21���{�������j����2019/02/13(��) 12:39:34.56
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
22�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:39:51.20
���e�`�p 15
�p�F�S��̖R�����E���̐������e��������͖̂������I
�`�F�`�l�`�̕`���ꂽ�ږ�Ă̐����͔e���I�łȂ��B
�@�@���I���Ў҂��j�ɁA�e�n�̎�����I�p���Ő����͂����S�I�ɏW��i�����j�������̂ł���A�l�Êw���𖾂����R���I�̏Ƃ悭��������B
�@����A���̗p�Ε��̌�������S��̕��y��Ԃ𐄑�����ƁA��B�ƋE���ł��ɒ[�Ȋi���������B���\���D�i�v��F�����V�j���͂��߂Ƃ���ؐ��i�̉��H������݂Ă��A���ʂ̓S�킪���y���Ă����Ǝv����B
�@�⑶��ɂ͑�|����Ղ̓S���i�퐶��������j�Ⓜ�Ì�40�������̔�S���A���Ղł͉������Y1�����a��̓S���ɂ�锰�̍��Ⓜ�Ì�SD-C107�S�����A㕌���Ճ��N���n��̑�^�S������������Ɛ��肳��Ă����ʂ̓u�i�R���I�O���`�����j�ȂǁB
�@�b�����\��㕌��Β˂̖k��200m�ߕӏo�y����H����S�擙�i�R���I�㔼�j�A����E�j�쌗�Œ��b��Ձi���s�R�ȁC�퐶��`�Õ����j�A�����Ɉ�Ձi���s�s���C�퐶��O�j�A�a������Ձi�E����C�퐶��`�Õ����j�A
�����Ձi�����s�C�퐶��O�j�A���]���ŒJ��Ձi���C�퐶��j�A���Z�R�p�����w��Ձi�����C�퐶���j�A�����u��Ձi�����C�퐶���j�A��ˎR��Ձi�����C�퐶���j�A�ؒÐ쌗�œc�ӓV�_�R��Ձi���c�ӁC�퐶��`�Õ����j�ȂǁB
�@㕌��ł̓S���p�ɂ��ẮA��^����D�ׂ̑�^���J�y��SK-3001���o�y�����q�m�L�ށi�����R�j�̕��͂ŁA���̉��H���y�ю��ӂŐA���㏭�Ȃ��q�m�L�̑��p�Ƃ�������
�u�W���������H�l��ƏW�c�̔��B���Ȃ���A�S�킪��ʎg�p�܂��͎g�p�ł���W���v�i���� 2011�j
�@�ƌ��_����Ă���B
�@�퐶�I�����i�����V���j�̋E�������ɉ��Ĉ╨�����ړy��ƐڐG���ɂ����搧�����y���n�߂�Ɠ����ɉ₩�ɖL�x�ȓS�킪�o�ꂷ��Ƃ������ӂ݂�ƁA�E���̓y��̓������S��̈⑶��Ԃɑ傫���e�����Ă������Ƃɂ͋^��̗]�n�������B
���e�`�p 16
�p�F�L�I�ɂ͔ږ�Ăɓ�����l�����o�ꂵ�Ȃ��I
�@�@��B�̎הn�䍑�Ƒ�a���삪���W�����炾�낤�I
�`�F�R���I�̎j�����A�W���I�ɏ����ꂽ�L�I�����ꒉ���ɔ��f���Ă���Ƃ͊��҂��ׂ��łȂ��B
���ƂɁA�L�I�̐������������̍����͎��V���V�c���O���ɒ��v�������j��e�F���Ȃ��B
23�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:13.38
���e�`�p 17
�p�F�O���u�̓��̕����͒Z���ŏ�����Ă����̂��I
�`�F���ꏑ�̒��Ő������Ȃ��A�����̕ʒP�ʌn�����p����͕̂s�����ł���B
�@�܂��A�`�l�`�̗����������̒n���Ɠˍ������L�ӂȋK�����́B��������ĂȂ��B
�@����ĒZ���Ƃ����P�ʌn���A�[���邱�Ƃ͕s�\�ł���A�Z���͑��݂��Ȃ��ƌ�����B
�@���̂��Ƃ͔����ɋg(1910)�ȗ��~�X�w�E����Ă��邪�A�L���Ȕ��_���Ȃ��B
���e�`�p 18
�p�F�R���I�̉Ȋw�ł́A�ڎ��o���Ȃ��������̒����������V���ɂ���ċ��߂邱�Ƃ��o���������I
�`�F�����Ȃ�j����ɂ��A�R���I�ɑ��̂悤�ȑ�����{�̋L�^���Ȃ��B
�@������ɂ����̂悤�ȑ��肪�L�����Ȃ�A�`�l�̍��X��鰂̋��s���牓����ʒ��x�̓���ɉ߂��Ȃ����Ƃ����炩�ɂȂ�̂ŁA�`�l�`�̋L�����ꗂ���B
�@���������đ���͑��݂��Ȃ��B
�@�܂��A鰑�̎O�p���ʋZ�p�����������̎j����ł͂P����1800�ڂł��邱�Ƃ����Ăł���i�w�C���Z�o�x���J�CA.D.263�j�A�����o�y���Ă���ڂ̌����Ɠˍ�����A�ُ�ɒZ���ˋ�̗��P�ʌn�����݂��Ȃ����ƁA���ꖾ�炩�ł���B
������ɂ̓͟�q�i�̓쉤����B.C.179�`122�j�Ɂu�ꗢ���ݔ��琡�v�Ƃ���A�����H�ݎu�́u�Z�ڈו��v�Ɛ�������B
�����������ƍl�������鏎Z�S�ɂ����Ă�
�@�u�����n�a��\����D���Z�\�O���D�ߑ�����Ȑ���
�@�@���ʌa��S��\��ڎ����ܕ��D�����O�V�D�O�S�Z�\�ڎl���ڔV��v
�Ƃ���A�P����1800�ڂ��ێ�����Ă���B
24���{�������j����2019/02/13(��) 12:40:17.73
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
25�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:33.80
���e�`�p 19
�p�F���R�`�Δn���邢�͑Δn�`���̋����́A�M���ł����ł͂Ȃ����I
�@�@����Ɋ�Â��������_�ŁA�הn�䍑�͋�B�����ɋ��߂���I
�`�F�P�`�Q�Ⴉ��P�ʌn���A�[���邱�Ǝ��̂���@�Ƃ��Ĕ�Ȋw�I�ł���Ƃ������A�A�[�̕��@�_�ɔ�����B�܂��Ă�A�C��̋����̂悤�ȑ��荢��Ȓl����A�Ñ�̒P�ʌn���t�Z���邱�Ƃ̓i���Z���X�ł���B
�@�V�������̂ł́A1853�N�́w����{�C�ݑS���x�ɂ܂Ŋ��R�`�L�Y�i�Δn�k�݁j��48���Ə�����Ă��� �B�]�ˎ����48���͖�189km�ł���A�C�ې��H�������\�Ɋ�Â����R�`���{�ފԂ�34�C���i��63km�j�ł���B
�@�]�ˎ���ɂP������1,300m�Ƃ����u�Z���v���������ł��낤���H�@�ہA�Ԉ��������������������ł��� �B
�@�܂������M�����̂Ȃ�����p���ē����הn�䍑�̔��n�́A���R�Ȃ���M�ߐ��������B
�@�t�ɁA�S�g�́u�폊���v�ƋL�����ɓs������z���̋����u�S���v���A�L�������ꌅ�i50�`150���j�͈̔͂ŎO�_��Ղ���������z���Ŕ������Ղɓ�������܂ł̎�����20km���Ɠˍ�����ƁA����Ȓ����̒P�ʌn�i�P����1800鰎ځj�ŏ\���ɉ��߉\�ł���B
鰐l�����͊y�Q�l�̎��������\�����ł������n��Ō��������鐔�l�������Ă��邱�Ƃ́A��z��̒P�ʌn��O��Ƃ����הn�䍑�_�̋�����Ă��悤�B
���e�`�p 20
�p�F�`�l�`�̗����͂��ׂĊT�ˎ�������1/5�`1/6
�@�@����������t���I
�`�F���̂悤�Ȑ������͔F�߂��Ȃ��B
�@�l�Êw�I�m������A�ѕ��S���͖P�R�S�q�����̓��y��A��͋�������ɔ�肳���
�@�Δn���W�͕s�m��Ȃ���A��x���W�͌��m�ҁA��Ḃ͓��Îs�����t�߁A�ɓs�͎����O�_�A�z�͓߃m�Âɋ��߂邱�Ƃ��o����B
�@�M���ɑ�������Ɋ�Â�����`�l�`�L�ڂ̗����ɂ͗L�ӂȋK�������F�߂�ꂸ�A�`�l�`�̗����ɂ͑����̊ԈႢ���܂܂�邱�ƂɂȂ� �B
�@�S�����B�{���Ɏ���܂ł̋����́A���傤�ǂP�����ɂȂ�悤�Ɋ���őn��Ȃ��������ɒ������ꂽ���̂ł���ƍl������ɑÓ��������낤�B
�@��B���̏d�����锒���q�g���A�����̒n���Əƍ����ė����ɗL�ӂȋK���������o���Ȃ����Ƃ��Ȃė����Ɋ�Â����הn�䍑�ʒu�_�̝e����i����1910�j���Ă��A����100�N���o�߂������A�L���Ȕ��_�͒�N����Ă��Ȃ��B
26���{�������j����2019/02/13(��) 12:40:36.86
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
27�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:40:54.33
���e�`�p 21
�p�F����̎�������n��o�y���Ă���I
�@�@����̒z���͂T���I�ɋ߂��Ƃ݂�ׂ����I
�`�F����i�����R�Õ��j�̎������@�\��~���Ė��v����ߒ��ő͐ς������H�y�w���A�p�����ꂽ�ؐ��֓����z���P���y��ƂƂ��ɔ�������Ă���B�܂�������@�\���ė������ʂ��Ă��������ɃV���g�w���͐ς������ԕ��ɑ����ĕ��H�y�̑͐ς������ԕ�������B
�@�����R�Õ��̒z����z���O�Ñ��̂R���I��R�l�����A�z���P�𐼗�300�N�O��}20�N���x�Ƃ�����N��ςƖ������Ȃ��B
�@���̂悤�Ȗ��C�I�Ȉ╨�̑��݂́A鰐W����㕌��̏������}�g�����̌𗬂ɂ��f�ГI�Ȕn�C�����̗����Ɠr����������̂Ƃ��č����I�ɗ��������B
�@�����{�y�ł͑O����_��ȁu�V���v�i�e���j���̓��ڂ̕Г��A�����ł͌Γ�Ȑ��W��̓��ڕГ��i����302�N�����j���ŌÔ�����ŁA�����͐���340�N�͓̉�ȏo�y��܂ō~��B
�@�O���u�ɂ͘D�l�����n����ۂɑ������Ƃ��x�����L�q������A�Ƃɑ������ꂽ���~�p�Г��ɑ̏d�������ĈƂ��X���̖h�������M����B
�@����302�N���_�ŋR�n�ɏ]�����Ȃ����H�����m�ɕ`�ʂł�����x�ɂ͕��y���L�����ƌ��邱�Ƃ��o���邱�Ƃ�����A�S���I�����ɓ��{�Ō������o�邱�Ƃɕs�����͂Ȃ��B
���e�`�p 22
�p�F��AMS�@�ɂ��y��t���Y������C14�𑪒�A����̒z���N��𐼗�240�`260�N�Ɣ��\�����I�@����͐M�p�Ȃ�Ȃ��I
�@�@�����w�ʂ���o�y�������j��100�N��V�����N��������Ă���A�����炪�M�p�o����I
�`�F����i�����R�Õ��j�Ŕ��@���ꂽ���j�̂ЂƂ��P�А���380�`550�N�Ƃ������l�������Ă��邪�A2�Ђ͐���245�`620�N�ł���B
�@��������P�А���110�`245�N�ł���A�y��t���Y�����̐��l�Q�Ɛ�����������B
�@�܂�A���j�̑���l���n���I�ɐV�����N��������Ƃ������̂ł͂Ȃ��B
�@�l�Êw�I�펯��傫����E������ُ̈�l��ӐM����͔̂�Ȋw�I�ł���B
�@�Y�����̑��E�������z���͂̓R���^�~�l�[�V�����̃��X�N�����Ƃ��܂߁A���v�I�ɐM���ɑ���ʂ̑����W�ς�҂ׂ��ł���B
�@�t�ɁA��ˌÕ������R�w�ʏo�y�̓��j�Q�iNRSK–C11�y��12�j���тɓy��t���Y�����P�iNRSK–6�j�́A�����ĂR���I��Q�l�����O�����s�[�N�Ƃ���l���Y��Ɏ����B

�@������A���j�Ȃ�M������Ƃ����咣�ɑ����ď����R�̒�_�Ƃ��ĐM�p�����ꍇ�A�㑱����z���O�Ñ����R���I���t�Ƃ���������������t����D�ޗ��ƂȂ�ł��낤�B
��^���J�y��SK-3001�o�y���j���⑶�̂̑��茋�ʂ�������������t���錋�ʂ��o�Ă���B�i����2018�A�ߓ�2018�j�@�ꕔ�ɓy��t���Y�����̑���l���n���I�ɌÂ����l�������Ƃ����ӌ������邪�A�����Œ���Ă����쓞�B�ȑO�̖k�C���̑����͊C�Y���R���̃��U�[�o�[���ʂŐ����ł���B��N���ł���č��̐������𑪒肵����Ɠ��ꎋ���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B 28���{�������j����2019/02/13(��) 12:41:01.00
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
29�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:14.00
���e�`�p 23�|�P
�p�F�ږ�Ă̙n�͉~���Ȃ̂����產��ł͂��肦�Ȃ��I
�`�F�u�a�v�͉~�`�ȊO�̂��̂ɂ��p������\���ł���iex.�T��̕��̐n�F鰏�18�j�̂ŁA�~���Ɠ��肷�鍪���͂Ȃ��B
�i�͓�ȓ�z�s�o�y�w����ɐ}�x��蕀�@鰐W��j�@
�@�܂��A�z���ߒ��Ŕ����R�Õ��͉~�u�Ɗ�d���݂̂̑O�������琬���Ă�������������B
�@��d���͐����������猩��Ɨ��N���Ă��Ȃ��B
�@����āA��d���̒z����悪�������O����~�^�ł��鎖���́A���u��t����ے�ł���ޗ��ł͂Ȃ��B
�����R�Õ��͈ȉ��̉ߒ��Œz�����ꂽ�Ɛ��肳���B
�P�j�n�R���͂�n���`�Ɍ@�荞�݊�d���Ǝ���A�n��瓙�����o���Ő��`�\�z
�Q�j��d��~����ɉ~�`�ɒ��̓y�ۍ\�z�@
�R�j���̓����߂ĉ~�u�̒i�z����i�����A�Q�j����J��Ԃ��~�u������������B
���@���̎��_�ŁA��d�O��������~�u����Ɍ����ăX���[�v������B
�S�j��̕����\�z���X���[�v��芻��������A���u��ő����V����s���B
�T�j�O������d��ɐ��y�ƕ��u���\�z���Ċ���
�ȏ�̒i�K�P�`�S�ŕ��u�����݂��Ă��Ȃ��B
�@�P�j�͊�d��������̓n��炪��̂ɒn�R������o����Ă��邱�Ƃ���
�@�Q�j�R�j�͒ֈ��ˎR�̎���i�����G�R�钬����1999�j����
�@�X���[�v�ɂ��Ă̓A�W�A�q���ɂ�郌�[�U�[�v���Łu���N�Γ����v�̑��݂��m�F���ꂽ�B������������X���[�v���̂��́A�T���͕�ۂɒ��������Ɨp�擹��핢���ď�ˋV�T�ɕ����ɕ������ߑ������ꂽ�ʘH�ł���B
�@���N�Γ��́A�����R�Õ��ł͑�S�i�e���X�ɐڍ����Ď��p�����F�߂���̂ɑ��A���オ�~��ƂƂ��Ɍ`�[�����Ă���B
�����N�Γ��@
�@�O����~���̔����ߒ����l������A�~�^���a��̎��a��S����������������茇���c�����̂��O����~�^���u��̑c�`�ł���A�O�����͕��u�Ɏ���ʘH�ɗR������Ւd���ł���B
�O�����˒[����X�ɍ��s�����邱�Ƃɂ́A�擹��ǂ��Č��E���`�����邱�Ƃŕ��n������������ے��I�Ӗ������o�����Ƃ��o���悤�B
�@���u�z������o�ł���Ƃ������f�͈ȉ��ɋ���B
�i�{�� �����j 30�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:36.67
�i���O�j
���e�`�p 23�|�Q
�� �����R�Õ��̌�~���ƒi�z���ڍ����Ȃ��i�X��2013�����j����
�� �����R�Õ��̉~�u����~��Ă���X���[�v�i���N�Γ��j�����u���тꕔ����O�������̈ʒu�ŁA�O�������y�ɎՂ���`�ŏ������A�����ɒB���Ȃ�����
���@�����Õ��̕�ۍ\�z�͒n�����܂ސ����̋V�������O�ɍs����̂��ʗ�ŁA�X�Ɋ��̈��u���疄���͎��������̑��ʋV�炻�̂��̂ƒ�������ƍl������B�i���J1964�C�t��1976�j���p�����E�Q���l�����ɏ��Ȃ��Ȃ��B
�� �����E���������̑O���Õ��ł��鍕�˂�ֈ��ˎR�ŁA�O�����ƌ�~���ő����ɗp�����y���̑��Ⴊ�m�F����Ă���A��̎{�H�łȂ�����
�� �����̒��R��˂ł͑O�����ƌ�~���ŕ��̍H�@���قȂ�A�����тꕔ�Ō�~�������O�������y�̉��܂Ŏ{�H����Ă���A�z���ɑ����̎��ԍ����z�肳��Ă��邱��
�� �H����Ō�~�����u����s���锭�@�����m�F���Ⴊ�������邱��
�@�E �X���R�ˁ@�@�@�F�Ȗ�[�쐼 I ���i�1985,86�j
�@�E �O�����R���@�F���
�@�E ���˓��@�@�F�㑍
�@�E ����䎵�����@�F�㑍
�@�E �R����ꍆ���@�F�㑍
�@�E �����������@�@�F����
�@�E �����܍����@�F�\�o
�@�E ����R�ꍆ���@�F�A�n
�@�E ����g16�����@�F�����@
�@�E ��퐼��l�����F�����@�����L��
�@�E ���@���@�@�F����
�@�E ���q�ˌÕ��@�@�F�}�O
�@�E �_������ˌÕ��F�}�O�i�ȏ�@�A��1984�j
�� �͓���˂Ȃǒz�����ɒ��f�������ꂽ�ƍl������Õ��őO�������y���@�����邱��
�� �����R�Õ��~�u��ɋg������여��̑ٓy�Ő��삳�ꂽ�����䂪�A���u��ɍݒn�Y�̓�d�����₪���ꂼ��z�u����i���˕�2018�j�A�����J�̎��{�����T�����{��̂ɑ��Ⴊ����\�����������Ɠ�
���e�`�p 24
�p�F�|�ʕ��g�͋�B�̏K���ŋE���ɂ͖������낤�I
�`�F�|�ʕ��g����B���̍����Ƃ��邱�Ƃ͕s�\�ł���B
�@�|�ʓy��̕��z���猩�āA�퐶����I�����珯�����s���ɂ��̏K�������ɐ��s�����͉̂��R���y�ш��m���i�݊y1989�j�ł���A��B�ł͂Ȃ��B
�@���n��Ɛ[���𗬂̂�����㕌����|�ʂ̐l�X���������Ƃ͊m���ł��낤�B
�@�Õ�����̋E���ɂ��A���̏K�����Z���ɑ��݂������Ƃ͏��ւ��疾�炩�ł���A
�@���̂悤�ɁA�`�l�`���|�ʕ��g�L���͋�B���ɂƂ��ĕs���ȋL�q�ł���B
31�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:41:58.22
���e�`�p 25
�p�F��B�ɂ������`���͑�a�̓��{�Ɏ���đ���ꂽ�I�@�������ɖ��炩�ł͂Ȃ����I
�`�F�V���I�����͂���ȑO�̎j���𖾂��A���{�ƍ����̂Ȃ��P�O���I�̌�W�ŏ����ꂽ���j���̐V�o���݂̂Ɉˋ�����̂́A�w��I�łȂ��B
�@�������ł͘`�E���{�ʍ����Ƙ`�����{�����������_���L����A�������̔F���̍����������B�ȉ��̊e�����ɂ��A�ʍ����́A�p�\���ɗR�������a�`���Ƃ݂ğ|�����Ȃ��B
�E���㐬�������炩�Ȏj�����A�݂Ș`�����{�ƔF�����Ă��鎖��
�E����v�i�`�����{�ƔF���j�ɂċ������ɂ��������̔����ߒ������n��I�ɔc���\
�E�˙Γ`�œ��ꍑ�ِ������u�ʎ�v�ƕ\�L���Ă��鎖�Ⴊ�m�F�\
�@
�@��W�͋͂��P�O�N�����������Ȃ������Z�����ƂŁA���ς̕p�����钆�A�������͕ҏW�ӔC�҂��]�X�Ƃ���ߍ��Ȋ��̂��ƂɕҎ[����A���ƖŖS�̒��O�ɑQ���������݂��B
�@���̂��߂��A�`�Ɠ��{�����ꍑ�ł���Ȃ���`���d������s�̍ق�悷�݂̂Ȃ炸�A���ɂ�����l���̓`������d������ȂǁA���̎j���ɗ�����Ȃ��m��������Ă���B
���e�`�p 26
�p�F�Õ�����ɂ����Ă��O����~���̊�悪�ꗥ�ɓW�J���Ă���킯�ł͂Ȃ��I
�@�@���}�g�ɓ��ꐭ�����������Ȃnj��z�ł͂Ȃ��̂��I
�`�F���{�ɂ����鍑�ƌ`���͖퐶�I������}���ɐi�W���A�������̂����Ƀ��}�g�̉����_�Ƃ���G������Ƃ̕R�т��������ꂽ�Ƃ݂���B�������A�̖M���Ƃ̒a���͖����y����ł���B
�@���ꐭ���Ƃ�����b�ɁA���ߎ���������킷��ߑ�I�Ȓn��I�����W�c���C���[�W����̂́A���炩�ɊԈႢ�ł���B
�@���u�n���m�̖���I���A�[���I�Z�툽���͐e�q�I�����Ŏ�ɒʏ����[�g�ɉ����ăl�b�g���[�N���\�z���A�Ԃ̖ڂ��̉ߔ��������_�ł��A�����_�Ɛ��̍��Ԃɂ͊e�̖���I�ɂ͊e�n�e�̓G�Ύ҂�����ł��낤���A�����I�ɋ�����ۂ҂�����͓̂��R�ł���B
�@����ɂ́A���̃l�b�g���[�N�̍\���v�f����ʓI�W���A������Ȃ�����P�Ƒ��̕s����ȊW�ł������ƍl������B�Ȃ��Ȃ�A�푒�҂̈�`�I�`�����琄�肳��铖���̐e���\�����猾���āA�����I�����W���e�n���̈���I�p����ۏ����Ă��Ȃ�����ł���B
�@�䂦�ɂ����A���̌p��������Â���Õ��̕������J�ɂ����āA���̃X�e�[�W�̑����V���̏���ŁA���̌p����ۏ���]���҂̕��������i�p�j�ƂƂ��ɁA��ʎ҂▿�F�Ɋւ���O���W�̌p�����錾���ꂽ�̂ł������ƍl������B
�@�Õ��̒�^���͂��������������I���W�̌������܂ޑg�D���E�K�i���ɂق��Ȃ�܂��B
32�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:17.36
���e�`�p 27
�p�F���}�g�Ƃ����n�����A�ޗnj��ɌÂ����炠�����ŗL�̂��̂Ƃ����m�Ȃǂ���܂��I
�`�F���}�g�A�J�n�`�A���}�V���A�A�t�~�ȂǁA�����n���I������������Ă���n���́A�×��̃I���W�i���ƍl���Ďx�Ⴆ�Ȃ��B
�@���ƂɃ��}�g�ƃJ�n�`�͑ΊT�O�ł���A�m���ɃZ�b�g�ŃI���W�i���̌Òn���ƍl����ׂ��ł���B
���e�`�p 28
�p�F��B�ɂ͕����P�����_���R�Õ��Ȃǂɏ}���̗Ⴊ���邪�A�E���̌Õ��ɂ͖����I
�@�@�ږ�Ă̕悪����̂͋�B���I
�`�F�����P����A�_���R�Õ��Ƃ��Ɍ����������͏}����̑��݂�F�߂Ă��Ȃ��B
�@�܂��A�}���̓z�X�������ږ�ęn��ɖ�������Ă���Ƃ��镶���I�����͖����B
�@�Q�l����ł��邪�A�n�c��˂̔����B�͂��̑������n�ǂ��납�ˉ��O�ɂ���B
�@���{�̌Õ��ɂ����Ă����̔F���͗v�����ł���A�܂��Ă␂�m�I�̂悤�ɏ}���҂̈�̂���������̂ł�����Ղ���������ł���B
�@���u�{�̂ł̏}�����̗L����ږ�ęn�̔����ɂ���l���ɂ́A�������������B
���e�`�p 29
�p�F鰂ւ̌���i�Ɍ����i�����邾�낤�I�@�퐶��������̂͋�B�̂݁I
�`�F����i�Ɋ܂܂�Ă��鍂���x���D���u縑�v�͖퐶���ł͂Ȃ��B
�@�����x���D���͖퐶����̋�B�ɂ͑��݂����A�ޗnj����r�R�Õ��i�z���P���Òi�K�F�R���I���j�����o�ŁA�i���̌��g�����サ���Ǖz������Ɛ���i�z��1999�j����Ă���B
�@��B�̖퐶���͐D�薧�x�̒Ⴂ�e���i�ŁA�퐶�����̔����Ⴊ�������A�퐶����ɂ͐��ނ���B�퐶�����͂킸���Ȕ�����݂̂ŁA�i���I�ɂ��Ⴍ�A�D�薧�x���ቺ���Ă���B
�@����ŁA�Õ�����̌����Y�͓`���I�ȔQ�莅��p���Ȃ�����A�퐶��B�Ɣ�r�ɂȂ�Ȃ������x�̐D�z���s���Ă���_�ŁA�Z�p�I�n�����s�A���ł���B
�@��B�ƋE���̌����Y�͒����������̗l���ƍ����������ڂ������Ă���ƌ����悤�B
�u縑�v�ɓ����I�ȁA�o���ƈ��ɕ�����������Z�p�ŐD��ꂽ�喃���D�z���퐶�����̓��Ì��Ŕ�������Ă���A�퐶����ɂ�����z�̐D�薧�x�Ƃ��Ă͋L�^�I�ɍ����l�������B�i21�E23���T��j
�@���n�l�N�ɘ`�̌��サ���K��縑�͐ԐF�������x�j�o�i�Ő��F���ꂽ�u縑�v�ł���A������㕌���ՂŃx�j�o�i�͔̍|�T�����F��Ƃ���������(����2013,2015)�ƈ�v����B
�������Ӗ�����u蒨�K�v�̌�b���ʓr�g�p����A�P�Ƃ́u�K�vdeep red�̓x�j�o�i���Ɖ������B
�@�ȏォ��A�R���I�O���ȑO�̋E���Ō��D�������̉���I�Z�p�ϊv���������Ǝv����B
�@��B���ɂƂ��ĕs���ȏ����ƌ�����B
33���{�������j����2019/02/13(��) 12:42:37.20
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
34�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:38.38
���e�`�p 30
�p�F�ږ�Ă����̂͂R���I���t�ƌ����Ă��R���I�O���̂������I
�@�@����̒z���Ǝ��ԍ������邾�낤�I
�`�F���n�W�N�͑ѕ��̐V���炪���C�����N�ł���A�ږ�Ă͂��̒��C��m���ČS�ɏ̌��g�������ƍl����̂��Ó��ł���B����Đ��n�W�i����247�j�N�͔ږ�Ėv�N�ł͂Ȃ��A�����̍ŏI�m�F�N�ł���B
�@�u�N�̐E�v���r�₵�����̎�����u�y����쑊�A�������v�i�W�����Θ`�l�j�Ƃ���i���S�i263�j�N�܂ł����Ƃ��đ�����ƁA�ږ�Ă̖v�N�͂R���I��R�l�����̑O�����ŁA����J�n������ɑ������̂Ƃ݂邱�Ƃ��ł���B
�u�ږ�ĈȎ����n�v�Ƃ���̂ŁA�ږ�Ă̎��Ɓu���n�v�̊Ԃɂ͈��ʊW���F�߂��A���˂ł͂Ȃ��Ɣ��f�ł��邱�ƂƁA�ږ�Ă̎��̐旧���Ē����̓n�`�ƞ����g�Ƃ��������I���J�n���Ă��鎞�n������Ă������ʂł���B
�@�ȏォ��A���n�̎����Ɣ����R�Õ��̒z���Ƃ����z���O�Ñ��̎����Ƃɂ͐�����������B
�@�Ȃ��A�u�Ȏ��v���u�ߎ��v�ƒʗp�����Ă��̎������J��グ�čl���錩�������邪�A�ʏ�́u���v�̈Ӗ��ɉ����邱�Ƃɔ�ד���ȉ��߂ł�������͂������B
�@�܂��A�u�߁v�Ɖ����Ă���b���̔��b���_��k�邾���Ȃ̂ŁA�n�̕��ł���{��ł͈Ӗ����Ȃ����߁A�`�l�`�̓��Y�L���̋L�q���������n�łȂ��悤�ɓ���ւ��ēǂލ����Ƃ��Ă͐Ǝ�ƌ�����B
�@���̂��Ƃ͖ڑO�̗p�Ⴉ������炩�ŁA�u�ߑ��A���ƌw�����U���A�Ȕ@�����v�́u�߁v�����O�s�́u�n����r�\�P���A�c���s�H���A�r��L���A���l�A�̕��Z���v�Ǝ��n������ւ��Ȃ����Ƃ͒N�����m��Ƃ���ł���B
�@���ߏ���A�J��グ�Ĕږ�Ă̎��𐳎n�N���Ƃ���ƁA�����Ě��o�̏����g���k�邱�ƂɂȂ�A�s�����ł���B
�u�c沈��|���n�v�i鰎u����j�A�u騭�Ȏ��Ɓv�i��騭�蒐���������j�A�u�V�Ȏ���v�i�㊿���k�V�j�Ȃǂ̗p��ɏ]���A�u�i��i�j�ȁi�����j���i���ʁj�v�̎��n��œǂނ̂������ł���B
�@�Ȃ��A�`�l�`���̂ɐ��n�W�N�ȍ~�̔N���L�ڂ��Ȃ������炩�ɂ���ȍ~�̋L�����ڂ��Ă��邱�Ƃ����Ă���ƁA�����h���Ɋւ����A�̋L���͉Õ����f�_�Ɋ�Â��ď����ꂽ�����ȍ~�̎����ł���\���������B
35�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:42:55.90
���e�`�p 31
�p�F���n���͂ǂ��ɔ�肷��̂��H
�`�F�E�����̏ꍇ�A���n�����g���ʓ�������ۂ��邢�͏o�_�ɓ��Ă�����]������m���Ă���B
�@�l�Êw�I�Ɍ��ĂR���I�ɂ͐��˓��q�H�����ʘH�ł������ƌ��闧��A�y�я������}�g�����̌`���Ɛ��͊g��ɋg�����傫���ւ���Ă����ƌ��闧�ꂩ��́A������ې��˂��ۂ̉Y�Ȃ��ہi�D���̕��ʖ��́j���܂ޒn����ʓ��E�ʖ�Ȃlj��C�I�ɋߎ�����n�����������z����Ƃ���́A���˓��q�H�ɐ[���֘A����n��I�����W�c�̘A���̂Ƃ݂錩�����A�������̏�ŗL�͎�����悤�B
�@���Ƃ��A���Ճ��[�g�L����͗��Q�����L���Ղ��A���łȃM���h�I�A����g������C���Z���e�B�u�����݂���B
�@�������̏�ł͏㓹���E�������̑c�Ɍ�F�ʂ̖��������邱�Ƃ������[���B
�@�퐶�I������Õ��O���̊��ʘH�ɂ́A�g���`�P�̕��z�`�Ԃ���A�����p���݁����h�偨���R����E�������쁨���㓌�암���g�����d���E�ےÉ��݁����p���͓�����a�쁨��a�Ƃ������[�g������i���R2009�j����Ă���B
�@�@�@
�@�܂��͓��Y�����P�̓`�d�o�H���A�i�d���`�ےÁ`�͓��j�Ԃ𗤘H�Ƃ��ĊO��Ɍ��錩���i�ēc1997�j����L�𗠕t����B
�@����琣�˓����[�g���́A�C�����ቺ�ɋN��������{�C�q�H�̋@�\�ቺ���ӂ݂�ƑÓ����������B
�@�D��ċK�i���E�Ĉꐫ�ɕx�g���`�P�̕��z��́A�����p��ւ̑�ʔ�����ʂƂ���ƁA���ɂ����Ă͗K�ې여��ŋE�����u�l�����Əd�Ȃ�A���ɂ͌|�\�E�h���̕������Ɨ\�B�ŏd�Ȃ�B�ɗ\�Ȑ����甎���p�܂ł͋g���`�P�A�����P�y�ѕz���P�݂ȑ傫�ȏW�����Ȃ����ݕ��ɓ_�݂��Ă���A�g���E�ɗ\���j�Ƃ��Ċe�n���ݕ��̏��������I�Ɍ��Ճ��[�g���ێ��������p�ɓ��B���Ă������M�m�����B
�@�g���͑��V�p��䕶���̒��S�ł���A���˓��E�E���͖ܘ_�̂��Ɛ��o�_��A�O���ɂ܂ʼne�����y�ڂ��Ă���B
�@�퐶�������Õ��O���ɂ�����g�����암�̐l�����ԁi����2014�j�ƁA����여��ɂ����镭�u��̑�z�����猩�āA�����˓��ɂ�����`�Ð���L�����v�͐삲�Ƃ̘̎A���̂̒��j�͂��̒n���z�肷��̂��Ó��Ǝv����B
�@�E���F�ɐ��܂��Ĉȍ~�̓߉ϐ�n��ƁA����여��A�Ȃ�т�㕌��Ƃ����R�G���A�̏����������I�Ɉ�v���Ă��邱�Ƃ͒��ڂɒl���悤�B
�@�����`�l�`�L�ڂ̎O�卑�i�z�E���n�E�הn��j�̃A���C�A���X�Ƃ��ė������A�����p�f�Ղ���Ƃ������̂����C�f�Ղւ̈ڍs�ƂƂ��ɉ�̂�����̂ƊT�O�c������̂ł���B 36�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:15.81
���e�`�p 32
�p�F�E�����͂Ȃ��L�I���d�v�����Ȃ��̂��H
�`�F�����Ȃ�j�����j���ᔻ���������Ȃ��B
�@�R���I�̎j���𖾂ɂƂ��āA���j�����琬�����U���I��k�錩���݂̖R�����j�����g�p���邱�Ƃ́A�l�ɗv����J�͕��S���ߑ�Ȋ��ɐ��ʂ̊��Ғl���Ⴂ�B
�@���ꂪ�����I���p�ɗ��܂鏊�Ȃł���B
���e�`�p 33
�p�F�u���������n�C���P���A���L���A�F�`��v
�@�@�Ƙ`�l�`�ɂ���I
�@�@�C��n��Ƃ͗������łȂ��ꏊ�ɍs�����Ƃ��I�@�������͖{�B�ɂ���E���ł͂Ȃ��I
�`�F�������̏ꏊ�ւ��n�C����B�ɐ����牓�x�������ւ̓��C�q�H�ƌ��Ė��Ȃ��B
�@�u�ĘZ���C�ȗɓ����B�������n�C���ČS�E�v�i�O���u�O����j�ɓ��F�x�t�߁��R������
�@�u���n�C�����V���A���k�n�ɐ������c�B�A��n�C�����S�ρv�i��������j�k���N���؍�
37�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:36.60
���e�`�p 34
�p�F��������̍��ȕ����i������I
�@�@�ɓs���͗����̂��Ȃ��ł���I
�`�F�����P�����`���a��̒z�������͖퐶�㔼�`�퐶�I���Ƃ���邪�A���ڍׂɂ́A���v�̊J�n�������a���w�o�y�̓y�푊����A�퐶�I���i���V�����O�j�ƈʒu�t������B�i���c2000�j
�@���̒Җf�Ղ��I���ɂ��������莅�����ΊO�f�Ղ̃A�h�o���e�[�W��r�����邱�ƂƂȂ鎞���ɓ�����B
�@�����i�͒������������܂܂Ȃ����Q���S�ō\������A�g�p���ꂽ�����f�ނ́A�����ʑ̔䕪�͂Ɋ�Â��Έꐢ�I�قǂ��O�ɓ��肳�ꂽ�A������̃X�N���b�v�ł������\���������B
�@�����͊y�QIV���i��؊��j�ɂ����芿���U���̊������ڕi�����ꂵ�Ă��������ŁA���ڋ��̑��������ЂƂ��Č�������E���{���ė��p����Ă����B
�@���Y�̏��^仿�����͊����U���̔j�Ђ������Ƃ��ė��p���邱�Ƃ����킸�A����ȑO�ɔ��ڂ��ꂽ�����O�����^�C�v�i�n��W�̈�j���i�̃X�N���b�v�����ޗ��Ƃ����ƍl�����邪�A�����o�y���̖��������Ɠ����f�ނō싾����Ă���B�����͊����S���̔��ڋ��f�ނɋ߂������������Ă���B
�@�c�蔼���ɂ͏�L�̈���͂ݏo�����f�ށi��WH�̈�j���p�����Ă���A�����s�����َ����X�N���b�v�Ȃ����َ��̔��~�ŕ�U�����\��������B�����ɂ͎R���ȏo�y�̐퍑���╨�ɋ߂��������F�߂���B
�@��ʒ����̒��r�ňَ�̋����f�ނ��lj����������悤�ȏ́A�r�_�J�̓����Ŋώ@����Ă���B�i�n����1991�j
�@�㊿���ɗp����������f�ނ́A�����T���̑��������ɏ����O�����^�C�v�i�n��W�̈�j����㊿���^�C�v�i���d�̈�j�Ɉڍs���Ă���B
�@�����P���o�y�̑�^�T�����^仿�����Q�́A�����S���y�тT���̖͕��ł���A���㊿���^�C�v�̋����f�ނ��g�p�����A���܂��k����B�Ŋg�U���邱�Ƃ��Ȃ��B
�@���Â���Õ������仿�����╜�Ë��Ƃ͒f�₪����B
�@�㑱����Q���ȉ��ɂ͂߂ڂ��������i�͔�������Ă��炸�A�K�͓I�ɂ��ޒ������炩�ł���B
�@���̂悤�ɁA�u���v����ŁA�嗤�n�����̓���o�H�ƁA�`���̑�\���邱�Ƃ̔w�i�Ƃ��Ă̊����̈Ќ������X�r�Ȃ��A�܂������p�f�Ղւ̈ڍs�ɂ���Čo�ϓI��Ղ��r�����Ă����Ԃł���B
�@�ȏ���A�����P���́A�ɓs�������҂ɂƂ��Ď��������̒���������I�Ƃ����F���̂��ƁA��K�͂Ƃ͌����Ȃ����u��̔푒�҂̂��߂ɔN���ۗ̕L���Y���v���蓊�������揊�A�Ƃ����l����悵�Ă���ƌ��邱�Ƃ��ł���ł��낤�B
38���{�������j����2019/02/13(��) 12:43:53.97
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
39�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:43:55.05
���e�`�p 35
�p�F�����̏o�_�ɂ͓��{�C��������悤�ȑ�鍑���������̂��I
�`�F�l���ˏo�^���u��̕��z��͈ꌩ���ĎR�A�E�k�����������Ă��邩�Ɍ����邪�A�搧�̈قȂ�A�O���ł��Ƃ��瓌�������f����Ă���B�������_���Ɖz�A����Ɉ����ɂ��قȂ�n�搫������A���u�K�͓I�ɂ����o�_�̐��J����Q���u�₵�đ�z����Ƃ͌�����B
�@���Ƃɐ��o�_���J���Ő����ɂ����Ĉ����̐��j���������𗽂��K�͂ł��邱�Ƃɉ����āA���V�p���̕������g�����璼�ڗ������Ă���̂͐��J�݂̂ł���B
�@�ȏ���A�e�n��̎��含����n��I�Ɨ������𐬈��Ƃ��ē���I�w���҂Ȃ��ɂ₩�ȓ����W���������\���A�Ƃ����ȏ�̑z��͍���ł���B
�@���Ƃɉz�n��́A�_���Ƃ̐����I�A�g���������`�Ղ��ł��邱�Ƃ��w�E����Ă���B�i�O�c1994,2007�j
�@����ŁA���o�_�̐��J����Q�́A���c�R�i�퐶�����t�E�|�z���u��╽���P����Ɠ������j���瑐�c�T�i�����㔼���s�A�z���O�܂܂��j�̎����ɍŐ������}�������Ƌ}���ɐ��ނ���B
�@����ł��퐶�����ȗ��̕����I�`����ێ������܂܁A�Õ�����ɓ����Ă����}�g�̕������ɓە����ꂸ�ɁA�Ǝ�����ۂ����n���Ƃ��ĉi�������������قȒn��ł���B
�@������̐_�b�́A���}�g�ɏ]���I�Ƃ͂��������W�ł������n�������i���j���A�T���I�ȍ~�ɕ��f�E��̂̈��͂ɎN����@�_���J�̑����ۏƈ��������ɓƗ����������������Ă����A�Ƃ��������I�f������㏊���̋���I��b�ƍl����ׂ��ł��낤�B
�@�퐶�������Õ������̎j����Nj�����ɂ������āA�L�I�Ɋ�Â��ďo�_���ߑ�]�����邱�Ƃ͔��I�ł���B
�@�����ɁA�k����B���͓��ɕ��f�I�ɐ������ꂽ���Ɖߏ��]�����邱�Ƃ��A�S�����I�ł���B
���_���_�Ёi�����R�Õ��Ɍ㑱����R���I�㔼�A�O�p���I�N�����𑠁j���l���ˏo�悩������ɑލs��������i�K�ƕ]���ł���B
40�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:15.36
���e�`�p 36
�p�F�퐶���`����ɗ������ւ����ɓs���́A�I�����ɂ����}�g���������Ɋւ��ċ����C�j�V�A�`�������Ă��锤���I
�`�F�ɓs���́A�R���I�O�����甼�ɂ����k����B�ŋE���n�y�킪�g�U������ɂ����āA�ɂ߂ĕ��I�ł��������Ƃ������ł���A�ɓs�����������I�ɗL���ȗ���͊ώ@�����B
�@�������ʂŊO���n�ɑ��ĕ��I�ȍݒn�W�c���W�c�Ԃ̊K�w���ɂ����ė�シ����ӂ݂�K�v�����낤�B�i���V�Q�Ɓj
�@�����ʂɂ����Ă��A�ł�����^�C�v�̓������J�͏]�O�����ɗe�n�ɔg�y���Ă��邱�Ƃ���A���̕������k����B�ł����Ă��E���ɑ��ĉe���͂�L�����Ƃ͕]���ł��Ȃ��B
�@�܂��A�E���Ŏ嗬�ƂȂ�아�I�p�r�̊������J�i��ㅌ^���Ƃ��j�Ӎ��J�j�͋E���Ŋ����������̂ŁA�ɓs���̉e���ł͂Ȃ��B
�@�g���[�E���Ŏx�z�I�Ȋ����J����B�Ɍ����Ȃ����ƁA�����O���ɂ����J�͋E�������B�ɓ��������Ɠ������Ă��A�@���ʂňɓs�������}�g�����ɐ��I�ł���Ƃ͌����Ȃ��B
�@�Ȃɂ��A�����U�������i�K�ł͊��Ɏ����n��i�ɓs���j�͊������ʂ̊j�Ƃ��Ă̋@�\���~���Ă���i�ғc2007�A���2014�Ȃǁj�A仿�����̐���҂Ƃ��Ă�����𗬒ʂɋ����ĈАM�������҂Ƃ��ĉe���͂��s�ׂ��邱�Ƃ��Ȃ��B
�@�߉ϐ여��i�z���j���K�͂��k�����Ȃ�������^仿�����̐��Y�Ƌ������ێ����Ă���̂ƑΏƓI�ł���B
�@�ɓs���̕����I��i���́A�Õ������ɏ����z�����ꂽ�����̈�Ƃ����ȏ�̕]���͓���ł��낤�B
���e�`�p 37
�p�F����̐�����l�Êw�I�ɑ��݊m�F����邱�ƂȂǖő��ɂȂ�
�@�@㕌�����B���͂ɐ������ꂽ���Ƃ��l�Êw�I�ɔے�ȂǏo���Ȃ������I
�`�F㕌���Ղ́A�y�푊�E�������ɋE���ƕ����Ӊ��n��Ƃ̑��ݍ�p�ɂ���ėݐi�I�ɔ��W���Ă�����Ղł���B
�@�O���̓���n�悩��̎x�z�I�e���͔͂F�߂��Ȃ��B
�@���ꂪ���ԓI�E�L�}�C���I�ƌ����鏊�Ȃł���B
�@���Ƃɍ��ˉ��̊ł������k����B�ɂ��ẮA���{�I�ɎЉ�\��������Ă����ƌ����A�E��������т��Ėk����B�̐����I�l���ɉe����^���鑤�ł���B
�@�Õ�����̃��j�������g�^�Љ�̍������`���ˏo���t�~�u�̕��^���܂��Q���I������E������ق��Ă������q�̎j�I�W�J�o�H��ɂ���A�����R���琼�a�A�s���R�A�a�J���R�Ƒ剤���Õ����A������B
�@���}�g�������Q���I���̌`��������S���I���t�܂ŁA�O������N�������邱�ƂȂ����̒n�ɘA���I�ɑ��݂��Ă������ƂɁA�^��̗]�n�͂Ȃ��B
41�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:37.10
���e�`�p 38
�p�F㕌���Ղ͈�ʐl�̏Z�ޒG�����Z�����Ȃ��A��s���蓾�Ȃ��̂ł͂Ȃ����I
�@�@�d���Ă���͂��̑����̎�����x��̕��m�͂ǂ��ɏZ�ނ̂��I
�`�F��ʐl�̋��Z��Ԃ��{�����ㅂ��钆�����̏�s�͎�������҂��˂Ȃ�Ȃ��B
�@�Ӑ}�I���ɂ�茚�݂��ꂽ㕌���Ղ́A���Z����W�Z���̚����ɂ���퐶����̑�W���Ƃ͈�����悵�Ă���A���s���Ɨ����{�a�y�ы։��悪���������G��I������s�ƕ]���ł���B
�@�����́u�{�v�����s���镡�������ƈ�ㅂ�����`_����Ȃ钩����Ԃ��ی`���Ă��邱�Ƃ�����A��@�Ɖ�L���̉��O��Ԃ����̑�^�����Q�͋{�a�̗v����������Ă���Ƃ����悤�B
�@�×������̋{�s���c�͉͐�̗��p�Ɖ��ς��̂���ŁA�����̏ꍇ�ɑ������J�w�����B
�@���̓_���A��Ō�ݍH�����{��������ȑ�a�̌@��ŊJ�n����㕌���ՂƂ̗ގ������F�߂���B
�u�����ȗ����L���ҁA�țX��l�����A�B�L�j�q��l���Z�H�`���o���B�v
�@�Ƃ���Ƃ���A�ږ�Ăɋߎ�������̉Ǐ��ŁA���̋�������ʐl�̋��Z��Ƃ͊u�₵�Ă������M�m�����B
�@㕌���Ղ̎�����_���E�Z��Ԑ��A���J��Ԑ��Ƃ��������i�ƍ��v���Ă���ƌ����悤�B
�@��I�З͎҂ƐM�����Ă���҂���ʐl�ƎG�����Ȃ����Ƃ͖����I�ɍm���邪�A�퐶���ɋ��_�W������̂��ē��s�����ق��ׂ����`���Ƃ��ēƗ������Ă���X���Ƃ������������B
�@��a�̌��݂�A���y�̉^���ʂ��ܕS�`��l���~�\�`�ܔN�Ƃ������锢���R�Õ����͂��߂Ƃ���y�؍H���Ղ́A�����̐l����㕌��ŘJ�����Ă����؍��ł���B
�_���^�W���łȂ��ɂ��S�炸���و扺���̐��H�ő��ʂ̃C�l�ȉԕ�����������Ă��邱�ƂŁA�����G���ȂǍ��ނ̏W�ϓI���������������Ƃ��������Ă��邱�Ƃ��A��������x������B
�@�ɂ��S�炸��K�͂ȑq�ɌQ�������o�ł���i�L��2018�j���Ƃ́A������̐��^���L�V�A�����̒��Ԑl���̎Q�W���\�Ȍ�ʊ����ӂ݂�A�퐶�I��^�W�������W�I�ɕ��U�E��̂����Ƃ���邱�̎����A㕌���Ղ̋ߖT�ɍx�O�I���Z�����W�J���L���ɋ@�\���Ă������Ƃ��m���ł���B
�@�N���o�H�̌��肳���ޗǖ~�n���̂ɖh�q��̗��_������A���l�ʔ��B�̌�ʗv�Ղł�����B
�@�V�������`���̎�s�Ɩڂ���ɑ���������ՂƂ����悤�B
42�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:44:56.51
���e�`�p 39
�p�F鰎u�ɂ��Δږ�Ă̓s������͎̂הn�㚠�ł���I
�@�@�הn�䍑�ƌĂяK�킷�̂͋E���̑�a�ƌ��т�������ׂ��낤�H
�`�F�`�l�`�̋L�ڂ���`�l�ŗL��ɂ͓��{��̂��J���ߌ���̓������悭����Ă���A���߂ł��邱�Ƃ�������������d�ꉹ�ƂȂ�u�הn�㚠�v���A�㐢�ɔ��������ʖ{�Ԃ̌�ʂł��邱�Ƃ͊m���ƌ�����B
�@�������s�̗p���ɂ��Ă͂P�Q���I�����Ɂu�i�v����u��v�ւƈڍs���ĝB�R�Ƃ��Ă���A��ʂ̔����������T�˖��炩�ł���B
���e�`�p 40
�p�F�`������͉̂�m�u�����v�̓��ł���I
�@�@��B�ł����ł͂Ȃ����I
�`�F����ɔs�ꂽ��m���牤�N���u�����v�i�� ���˕��� ��v���u��꤁v�{�j�ւƔs�����Ă���B
�@�@
�s���悪����̌i�� ���B�s��R��Ձj�ł��邱�Ƃ͓��s������|�Ȃ�тɒnj�������Ă̓`�A���т�閩�z�̒n�ƋL���蒐��������t�H�ɂĖ��炩�ł���B
�@���B�s�̓��͉���ł���A�`�l�`�̗����L���Ŏהn�䍑���ݒn�_�������邱�Ƃ̖��v��������
�@��FAQ17�ŐG�ꂽ�Z���Ȃ���̂�z�肵��؍��ł�����B
�@��m����́A�u��m����܌��v�i�C�Г`�j�Ƃ����p�Ⴉ�������Ƃ����m�S���茧�̈Ӗ��ł͂Ȃ��A���S�암�̒ʏ̓I�n�於�i�������������ɖ茧�łȂ��j�ł���B
�@���v���u���@怚��S�H�c���C�����������s�сA����B��������Y�͈��A�Ȗ藧���B�v�i�����ʊӏ������j�Ȃǂƕ���킵���A���{�Ƃ����Ɩ�̍��p�������B
�@���i�́E�茧�j��鰑�E�����͒P�ɌƏ̂���A�̂��ɉ�m�S�������S�̑��ƂȂ���
�@���̂��߁A�����O���u�����M�����Ƃ���鑾�N�N�Ԃɉ�m�S���茧�����݂��Ȃ����Ƃ��Ȃē����͉�m����ƕʂł���Ƃ��鏭���ӌ��́A�s�����ł���B����������m���肪�S�����łȂ��݂̂Ȃ炸�A儋����R�ȂǐW��ɂȂ����j�I�n���������`�l�`�ɗp�����Ă��邩��ł���B
�@�{�_�L��啽�L�L�ɓo�ꂷ��u�����v���S�Ė茧���w���B���E���B����������u�����v�ƋL���ꂽ�B���ł���A�B��́u�����v���n�ł���B 43�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:16.32
���e�`�p 41
�p�F�����P��������I
�@�@��B�ɂ͌Â�����O��̐_�킪����I
�@�@��a����͋�B���͂̌���Ȃ͖̂��炩���낤�H
�`�F���̎咣�́A�o�����Õ������E���݂̂ŋʂ����������ɂ���Ĕے肳��Ă���B
�@�o�����Õ��́A�������Q�`�R����͋ʂ��ɗp���Ȃ��E���̏K�����p�����Ă���A�����I�������i�ނɂ͖������Ԃ�v���Ă����B�ʂ����镶�����̏o�g�҂͓�������͏������}�g�����̒����ɎQ�^���Ă��Ȃ��Ɣ��f�ł���B
�@�܂��A�����̏ے����郌�K���A�́A���E�j�I�Ɍ��Ĕ퐪���҂��琪���҂Ɉړ]����X���������B
�@�L�I�ɂ����Ă��A��ɓ`��ł��鋾�E���E�ʂ��������Đ����҂��}����~���V�炪�L����Ă���B�i�i�s�I�A�����I�j
�@�E���n�y��́A�������J�̋����y��Ƃ��āA�Õ�����Ɍn��I�ɓW�J����剤���Õ��ɍ̗p����Ă���B�����̎�e�ɋɂ߂ď��ɓI�iFAQ36�Q�Ɓj�ł������O�_��Ղ̎x�z�҂��A�������}�g�����Ɛ������͂Ƃ��ĘA�����Ă���Ƃ����z��ɂ́A���o�����������Ȃ��B
�@�퐶����ȍ~���s�������^仿�����͎�ɓ��s�ԕ����Ɠ����A�ʕ����n��ɑ������A�퐶����̂����ɕ��z���E�����܂ŒB���Ă���A���̋����n�͓߉ϐ여��ɋ��߂���B
�@�����̔��t����仿�����Ƃ��ēƎ��̊ȉ��Ɣ�剻�𐋂��Ă���A�n�����ł͌Õ��o�y���̌n���Ɍq����Ȃ��}�t�ɑ�����B��������X�q�������i�a27.1cm�j���ٌ`�̓��s�ԕ����ł���B
�@����ɑ��A�Õ��o�y�̍��Y��^���s�ԕ����͍ו��̎d�l�ɘ`�L���������A��{�̊I�v�����i���j�𔕍ړ��s�ԕ������瓥�P���Ă���A�n���I�ɕ����ƒf�₵�Ă���B�����o�y���ƌÕ�����ɐ��s������s�ԕ��n仿�����Ƃ̊Ԃ̃q�A�^�X�͑傫���Ƃ����悤�B
�����s�ԕ����̊I�v����
�~��8�������A�~���ɓ��ڂ��鐳���`��B
���̐����`�ɓ��ڂ���~���A�_�����тƘA�ʕ��̊���Ƃ���B
���̊���̂P�^�Q�a�̓��S�~�����т̊���Ƃ��A���̓����Ɋ`�������z���B
�@���́A�R���p�X�ƒ�K������⛏�ɕ`��ł���v�������A���ڂ̒��X�q�����s�ԕ��������^仿�����s�ԕ����i���{��ˁA���r�R�Ȃǁj�Ɍp������Ă���A�������ƈٍ��ł���B����炪��⛋��������Ȃ����Ƃ��������ƈَ��ł���B
44�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:35.26
���e�`�p 42
�p�F�����̕z���������������ŌÎ��V������y��ƈꏏ�Ɍ������Ă���ł͂Ȃ����I
�@�@�V���̌����̍��܂Ŏ��オ����̂����瓖�R����͂S���I�̌Õ����I
�`�F�Î��V������y��Ƃ͐V���≾��Ƃ������̓y��ł͂Ȃ��A�V���Ɖ���̒n�搫����������ȑO�̎���̓y����w���p��i����1985�̒�`�ɂ��j�Ȃ̂ŁA�P���Ȍ���ł���B�ْC��V���i��������y��j�Ɍ㑱����N��̗l���Ƃ���Ă���A�����R�Õ��̔N��Ƃ��������Ȃ��B
�@�ْC��V�������̗Ǔ���162�����ł͍ŏI�i�K�̖퐶���^仿�����Ɗ����U������������B
�@�\�h�K�͕�e�N�ڂɂ��}�]�̕���ɋN�����鎖�ۂƂ��Ė؞ؕ� II�ނ̐����𑨂��đ听��29�����̎��N������߂����i�\1993�j�A�������߂Ƃ��Đ����͂��鍪���Ƃ͕]���ł��Ȃ��B�����������t�����Z���̐����𐼐W������̉e�����ɂ�����̂Ƃ����\�ҔN�ɂ͐����͂�����A�R���I��S�l�����Ɉʒu�t���錋�_�ɂ͖�肪�Ȃ��B
�@��p�����V�̕ҔN�ɂ��ֈ��ˎR�i�z���P�j�����̒���̔N��Ɉʒu�t������B
�@�\�ҔN�ɂ��听��29�����̓����y���������h���͋v�Z IIB���ɕ��s���邪�A�\�������h���Ɋ܂߂��Ǔ���235�����͑O�i�K�ł���ْC��V���ɕҔN����Ă���i���v1999�j�s�����ł���B
�@�Ǔ���235������؞ؕ�h�ނƂ݂����\�́A���̓����y��ҔN�����ڍׂ�10�i�K�ɍו����ē����y��̏�����������i�K�Â��R���I������i��2011�j�Ƃ����B����͒������n�����y�����������������a��̏��� II�`III�i�v�Z�hB�` IIA�j��A�v�̊����y��i�ْC��V���j�͕�i�̔N��Ɛ�����������B
�@�Q�l����ɐ���250�N��Ƃ���鏹���O����2���Ί���ɕ������ꂽ�d���i�����j�y��Z���i���R���q��w��1984�j������B
�@���̓����y�킪�`�ԏ㐼�W������̉e�����ɂ���Ƃ���O��́A����S�ɋߐڂ��钉�����n�̓����y��̋N����������i�K�Â��Ƃ��铮���Ɛ�����������B
�@���̂悤�ɓ��̌����ҔN�͔N�X���k�����A�ʐ�����������Ă���B
45�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:45:55.02
���e�`�p 4�R
�p�F�������Q���I�����Ƃ����͉̂��̂��H�@����͉��̂R���I���Ȃ̂��H
�@�@�Y�f��N�ւ͐M�p�ł��Ȃ������͓`�����Ă��邩���m��Ȃ��I
�@�@�m���ȍ����ȂǂȂ����낤�I
�`�F�y�Q�E�ѕ��S塼����͕��ށE�ҔN�����
�@1B II�^���� 1BIII�^���� 1BIV�^���ƑQ�ړI�ɕω����Ă���B
�@�܂��A1C�^����1BIII�`IV�^���̎����ɘj���ĕ������Ă����B
���̒z���N���[�I�Ɏ����I�N��塼��
�E1B II�^���V�i�K�̒�擴31�������狻���Q�N�i195�j��
�E1C�^���̖P����1�������琳�n�X�N�i248�j��
�E1BIII�|1�^���̃Z�i�����Õ�����Õ��l�N�i252�j��
�E1BIV�^���̞��˗��Õ����瑾�N�l�N�i283�j���ł���
�ȏォ��
�@1B II�^���V�i�K�i�Q���I���`�R���I�O�t�F塼����Ő����j
��1BIII�^���i�R���I���t�F���ފ��j
��1BIV�^���i�R���I��t�ȍ~�F�����j
�Ƃ������N�オ�����Ă���A���̂���塼����1B II�^���V�i�K���y�Q�؞ؕ�V���ƕ��s����B�i���v2009�j�}�����������S���x�z���ĕ҂��`�Ƃ̐ڐG���������Ă���A�`�l��鰂ւ̒���E�v���r�₷��܂ł̊y�Q�S�ċ����ɓ�����B
�@�y�Q�؞ؕ�V���͉���G���Ɍ㑱���鐼�V�i�h���j�y�я����ƕ��s����i����2001�j
�@�܂���������y��̓o��͐��V���Ɠ������ł���i�����2008�j
�@����Đ��V�����O�̕����P���悪�Q���I���ɁA�z���O�i��a�����ŐV�w�j�̔����R�Õ����R���I���t�㔼�ɑ�������B
46�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:14.46
���e�`�p 44
�p�F�O�p���͑��݂��Ȃ��N����������Ă���I
�@�@���Y�Ɍ��܂��Ă���I
�`�F�i���O�N���琳�n���N�̉���������ӂ�ɁA�i���l�N�͎��݂����ƍl������Ȃ��B
�@�j����Ŗ��E���ꂽ�N���͒������Ȃ��B
�@���̂悤�ȓ����҂����m�肦�Ȃ������́A�������̏؋��Ƃ��ėL�͂ł���B
�@�����c��̑��ʂ͌����Ƃ������N�����ł���A���ʌ�ŏ��̐����ɉ����Ƌ��Ɍc��̑��Â���邪�A鰖���͌i���O�N���������Ɏ����������߁A���ʏj��Ɗ������d�Ȃ鎖�ƂȂ����B
�@���̖��̉����@�Ƃ���鰒��́A����̐��i�����O����v�z�������Ĕp�Ăɂ��A�ĂщĐ������̗p���������ꃖ���̂��Ɉړ��������B�i�v���u���j
�@�ŏI�I�Ɍ�\�Ƃ��ĉ[�������ƂȂ邪�A�����ƐV�N�̑剃���y��������ׂɂ͌i���l�N�����̎��݂��K�{�ł���B
�@���̉���c�_�͊������O�̏\�ɓ����Ďn�߂ċc�_���n�܂��ċ}篌��肳�ꂽ�����ł��邽�߁A��̉^�p�ɓ������č�����������͎̂��R�ł���A����̋L���ɂ��̍��Ղ𗯂߂Ă���B
���Ƃ��āu�t���N�A�����������ė����A���������ߑ������E���R��v�B�v�̋L���́A�i���l�N�i�����p�ߍ�j�łȂ���Ί��x������Ȃ��B
�@�i�����̘`�������g���琳�n���N�̍����g�h���܂ł̊ԁA�i���O���i���l�����n���e�N���̓������Q�������삳���̑z��͌����I�ł���A
�]�����l�Êw�҂����肷�鏊�́A���݂ɘA�g���������H�[�œ����i�s���}���ŏW���I�ɐ��삳�ꂽ�Ƃ����O�p���_�b����P���b�g�̐�����ƍ��v����B
47�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:34.28
���e�`�p 45
�p�F㕌���Ղɒ����ƒʌ��������ՂȂǂ���̂��H
�`�F���P�ŗ��q�����Ƃ���ł���B
�@�z�P�m�R�Õ��́A�R���I�ɐ��삳�ꂽ�㊿����鰋��A�f���品�Ȃǂ̕�����i�ɑ�����B
�@�����R�Õ��́A�I�Ȑ��~��z���y�؋Z�p���p����ꂽ�ŏ���ł���O���̋Z�p�ł���B
�@���̎�������͖G��I�n�C�����̍��ՁiFAQ21�Q�Ɓj�����o���ꂽ�B
�@�`�l���㌣�����Ǖz��`�т������K��縑�iFAQ29�Q�Ɓj���d�v�ł���B
�@�x�j�o�i�y�уo�W���Ƃ����A����܂ŗɑ��݂��Ȃ������A���̉ԕ����i����2015�j�́A���N�����ł̔����Ⴊ�����A�����{�y�Ƃ̒��ڌ��̌��ʂł���ƌ���̂��ł��Ó��ł���B�A�������͏����R���i㕌�61���F���c�n��a1-A�A���{2008�j�Ƃ����B
�@�������ԕ��̑�ʌ��o�ɂ���đ�^�����Q�̋ߖT�ɓ��������������Ƃ��m�F����
�i����2011�j�ASK-3001�o�y�̓��̑�ʋ�������ƕ����A鰎u��Œ��D�̋��c�Ɠ����u�S���v�Ƃ����ď̂�p�����Ă���ږ�Ă̏@�������������̉e�������V�@���ł���Ƃ��錩���ɂ��ė��t��������ꂽ�B
�@�܂��A㕌���Ղ��牓����ʊ����̉��r�R�Õ��i�z���P���Òi�K�F�R���I���j����́A�����ɂȂ�����^���Y�������[���邽�߂́A���Y�ł͂��蓾�Ȃ�������̚��I���e�킪�o�y���Ă���A�����ɓ��������Ƃ����l������ώ@����Ă���B�i�͏�2008�j
�@���̓��莞���͓�S�Ƃ̒ʌ����r�₷��ȑO�ɋ��߂���Ȃ��B
���e�`�p 46
�p�F���z�W�悩��A�ʕ����啍���̊Ԃɉ~�`�̂�����s�ԕ������o�y���Ă���I
�@�@���ꂪ鰐W�����낤�H
�`�F���z�W�悩��͓������⏺�����ȂǑO�������o�Ă���A�{�����`�������㊿���ƌ��Ă悢�B
�@�Q���I�̋��ł���B
�@���s�ԕ����S�ʂɂ����āA�A�ʕ����啍���̊Ԃɂ��錗�т�
�@�@�����ɋ����������с����������ȗ����ꌗ�т̂݁������ɑމ������ׂď���
�@�Ƃ������Ɋȉ����Ă����A�����U���i�Q���I�j�ɂ����Č��сA���͌����̂�����́iVA�j�Ɗ��ɏ����������́iVB�j�Ƃ���������B
�@�啍�����s�ԕ����̏ꍇ�́A���т̂�����̂��h�^�A�������̂� II�^�ƌď̂����B
�@���̑O���^�C�v�h�^����������╨�̋I�N���ɂ�
�@�@A.D.94�i���z�ߍx�o�y�j,105�i�����o�y�j,191�i���z�o�y�j
�Ȃǂ�����B
�@�Q���I�����_�Ŋ��ɓ`�����ł��낤�B
�@�_�����̂Ȃ��l�t�����s�ԕ����̐������銿���U���̎n�����A�����Ɩ��m�ł���B
48�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:46:53.58
���e�`�p 47
�p�F鰎u�ɂ��u�����v�ɂ͂Q���I�O������j�������݂��Ă���I
�@�@�Q���I������n�܂�Z����Ղł͖����ł͂Ȃ����H
�`�F�f���A�u�����v��㕌���Ղƍl����҂͋E���_�҂ɂ͎����ア�Ȃ��B
�@鰎u�L���j���́A�ِ������邪�A�㊿����������i�����N��������Ƃ���́u�`�����������v�Ƃ��A�����`�l�̊O����������Ƃ�Z�߂闧��ɂ������ɓs�����ɓ��Ă錩�����L�͂ł��낤�B
�@����ɘ`�����Ə̂��ׂ����Ԃ������Ă������ۂ��ɂ��Ă͔J��ے�I�ɑ�����K�v������B
��̉������㊿�鎺�ɂ͓��Ή��x�C����ϋɓI�ɋ��߂铮�@������A�����u���v�Ƃ����\������͘`���������̑��Ɗu�₵���҂Ƃ��Ĉ����Ă��Ȃ������̎p�����M�m�ł��邩��ł���B
�@���Ȃ��Ƃ����̐����̐��́A�n��I�����̕s������P�����z��̏k���A�����U�����̌����Ȃǂ��猩�Ċ��ɐ��ފ��ɂ���A�Q���I���ɂ͊���������퐶��̏I���ƂƂ��ɍŏI�I�ȕ�����}�������̂Ɛ��肳���B�iFAQ34,36�Q�Ɓj
�@�`�����������ɓ������ږ�ċ����ƐV���`���̍��ƌ`���͂���Ɩ����ł���A�����̓s���鏊������s㕌��ł��邱�Ƃ�W���Ȃ��B
���e�`�p 48
�p�F��������㕌���ՂƂ͂ǂ͈̔͂��w���̂��H
�@�@�l�Êw�I�Ɋm�F����Ă���̂��H
�`�F㕌���Ղ́A�l�Êw�I�Ȕ͈͊m�F�����ɂ��A���G�c��͓����狌㕌���͓��̊Ԃ̐��n�ɏ��݂��镡���̔����n��ɓW�J�����ՂƂ���Ă���B
��Ռ��݂̑��������ɑ�^�̉^�͂��J�킳��A�܂��Ɨt���n�̉ԕ��ɑ��芣�������l�גn���D�ޑ��{�̉ԕ������o�����悤�ɂȂ��Ă���A�v��I�ȊJ���s�ׂ���K�͂ɍs���Ă������M�m�����B
�@����s����ψ���͋��G�c��͓��k�݂ɂ�����Ղ��L����\�����w�E���A�V���s�ɂ܂�����l�Êw�I�z��Ɋ�Â�����ՑS�̐}�������\���Ă���i����s����Օۑ����p�v�揑2016�j���A���{���y�яa�J�����ŘA�������Ղ͌���ł͊m�F����Ă��Ȃ��B
�@�L��Ȉ�Ղł���A�{�������܂߂Ēn���҂��c��Ȑ��ɂ̂ڂ邽�߁A�����ɂ͕������ی�@��l���R���͂��ߎ�X�̐�����B
�@���̂��ߒ������y��ł���͈͂͌���͖����S�̒��̋͂��ȕ����ɉ߂��Ȃ����A�䂪���ɂ����鉤���a���ւ̓���H����ՌQ�Ƃ��ċɂ߂ďd�v������Ă���B
49�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:11.41
���e�`�p 49
�p�F������������������ϓz���̓C�g���Ɠǂނׂ��ł͂Ȃ��̂��H
�`�F�Ñ㉹�C�j�������B�ł���������̕T���ł���A�ߋ��̈╨�ł���B
�@�����̒���ł́u�z�v��do�Ƒ���̂��@���������ł���P���I�̔����Ƃ��Ă��蓾�Ȃ��B��É�nag�������ł��낤�B
�@�܂��A䗞@�㊿���ɐ�s�����͍G�i���W�j�㊿�I������I�ɂ��u�`�z���v�Ƃ��Č���Ă���A�u�ρv���u�`�v�Ɠ��`�ł��邱�Ƃɋ^��̗]�n�������B
�@�D����`���ςƂ��\�L����邱�Ƃ�����ʗp�����炩�ł���B
�@�@�u��� ���`�B�ꖼ�ځB����ρB�����q�B�v�i�m�a�����`���j
�@����Ɂu�ρv�A�u�`�v�̎q����w�ł���A�ɓs����y�ł���̂őS���������قȂ�B
�@�ł��������ɂ͛߂Ɂu�`�l�v�Ƃ������������m���Ă���A���̕������`�l�̍����\�L�ɁA�������Ƃ��Ă̘`�Ƃ�����`���܈ӂ������ɌŗL�����u�`�z�v�Ƃ��ėp���邱�Ƃ��A�A�������̈قȂ�\�������Ƃ��Ďg�p���邱�Ƃ��A�}������ȗp���Ƃ͍l����B
�@�܂��A�����̍�����������ł���P�[�X���u�i���Ɏ�j㳁v�u�Ԏt�㕔�v�Ȃǒ������Ȃ��B
���e�`�p 50
�p�F㕌��̑�^�����Q�͂���قlj���I�ŋ�O���Ȃ��̂Ȃ̂��H
�@�@�ǂ��ɂł����肻�����B
�`�F�����Q���召�Ƃ����S�������L����K�i����L���邱�Ƃ͉���I�ł��邪�A�v��I�z�u�Ƃ����_�ł͈ɐ���ՂƂ�����s�Ⴊ����B
�@����I�ƌ����Ӗ��ł́A�����y�ш�ㅍ����Ԃ��u��@�Ɖ�L����Ȃ钩��v�I��Ԃ�z�N������_�́A�ږʂ��銲�����H�̎��Ƒ��ւ��āA�����q�ɌQ�ƈ�����悷�B
�@㕌��S�̂̋K�͂ƌv�搫���ӂ݂�A�K�R�I�ɔ�r�Ώۂ͔��̋{���ƂȂ낤�B
�ܘ_�A�����R�E�a�J���R�E�s���R�̋K�͂��l����Η_�c�R�E���ɑΉ����関�����̋{��������ʂł��邱�Ƃ͗\�@�������̂́A����ł͔���̋{���ȑO��㕌��̑�^�����Q�ɔ䌨����悤�Ȓm���͂Ȃ��B
�@�P�ɏ��ʐς̂ݒ��ڂ���Ύ���I�Ɍ㑱���鎵���̖��s���SB02�i�z���O���s�j�͑�K�͂ł��邪�A���n�Ȃ�тɍ\�����猩�ėp�r���{���ł͂Ȃ��̂ŁA��r�ΏۊO�ł���B
50�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:32.41
���e�`�p 51
�p�F�m���͋�B�ɂƂ��ĕs���ȏ����ł͂Ȃ��̂��I
�@�@����L���C���݂Ŕ������Ⴊ����ł͂Ȃ����I
�`�F��B�����`�l�`�ɏƂ炵�ĕs���R�ł���A�Ƃ������_�����o�Ȃ��B
�@�܍��m��͘`�l�S�ʂ̏K���Ƃ��ċL�ڂ���A�l�Êw�I�m���ƍ��v���Ă���B
�@�S�g�����폊���Ɖ]����ɓs���ł��̏K������������Ȃ��̂ł���A���d�v�Ș`�l�̋��_�[�[�Ⴆ�Ώ������s�̂悤�ȁ[�[�Ŗڌ����ꂽ�Ɛ��@����̂����R�ł��낤�B
�@���Ŗڌ�����A��ق䂦��ۓI�ŋL�^�Ɏc�����Ƃ���Ȃ�A��x���̏��ɓ��L�����̂������ł���B
�@�퐶����̖m���̔�����͂Q�O�s�{���T�O�]��Ղɋy�ԁB
�@���{�C���[�g�Ŕ\�o�E���n�ɁA�����m���[�g�œ��C�E��֓��ɔg�y���A�퐶�Љ�S�ʂɍL�����z�����K���ƍl�����邪�A���R���E��C���y�ы�B�{���Ŋł���B
�@�m����n���I�ɒH��Δ������̓`�d�ł��邪�A�����p�ݒn��Ɉ⑶�Ⴊ�����A�������ň����̐J�㎛�n�Ƒ�a�̓��Ì��̓��ՂɏW�������邱�Ƃ́A�C���ʃ��[�g�̗��j���l�@�����ł������[���A���̏K���ƊC���ʂɏ]������E�\�W�c�Ƃ̊W���M�m�����B
�N��I�ɐ��ڂ�����ƁA�퐶�O�E�����Ɉ��[�R�A�[�E���Ɠ_�݂��A����ɐ��˓��[�E�������シ�邩��ł���B
�@���ƂɁA���Ì��Ŗ퐶��������ɐ��������ƍl������m��̋Z�p�̌n�^�C�v���A��������܂łɋ�B���܂ޑS���ɔg�y���Ă��邱�Ƃ��A�����[���B
�@�܋E�ł̏o�y��͈ȉ��̐ۉ͘a�e���
�@�@�V���E�X�V�{�i�ےÁj
�@�@�剮�E�S�Ր�E�T��i�͓��j
�@�@���Ì��E㕌��E�l���E�؈�啟�i��a�j
�@���Ƃɓ��Ì��ł͖퐶�O���������܂ŘA�����ĕ������݂���B
51�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:47:53.66
���e�`�p 52
�p�F㕌����ތ�Ɏהn�䍑�͂ǂ��Ȃ����̂��H
�`�F�o�n���Љ�ł͕����Ȓn�ʌp���ł�����n�Ղ��n���I�Ɉړ����邱�Ƃ��L�蓾��̂ŁA�l�Êw�I�Ɍ������S�n�̈���ړ��͕K�������������Ƃ͒f�����Ȃ��B㕌��̐��ނ́A���W�ŏq�ׂ��o�ϊ�Ղ̕ω��̂ق��A���J�^���傩��̎��I�ω����܈ӂ��Ă���\��������B
�@�ޗǖ~�n���ł��L�ӂȒn��W�c�́A���̂ق�����ƓY������B�剤���Õ��̏������猩�āA㕌��i���j�ɂ������{�s�͓Y�̕���{���w���L�͌��n�ƂȂ낤�B��R��E�ߍ]�Ƃ̊W�������[���B�i�Q�l�F�ˌ�2012�j
�@����W����\�̊m�F����Ă��銋��n��͑Ή�����剤���Õ��������Ă���A�͐�Ƃ̊W�ɂ����čX�Ȃ�T����v���B
�b�h�ۗL�`�Ԃ���}���̘V�i�E���藼�Õ����E���̑O�������ɋ߂��������̒n���ŁA�E���̒�����������͔J�댡���Ώۂł������Ƃ��镪�́i���c2015�j�ɂ́A���E�Y�Ɖ͐�E����̊ԂŖ���n���̕s�A������������Ă���B
���e�`�p 53
�p�F��嗦�͏����̕G���ŁA���̈Ќ��̌��Ɍ������������̂��낤�H
�`�F�������݂����ނ�悤�Ȑ��͎҂����u����A���̎������ɓs���ɍ݂邱�Ƃ́A�����p�݂������̓s����͒��ړ����̗e�ՂłȂ����u�n�ɂ��邱�Ƃ������B�����͍ł����ӂ��ׂ����@�ΏۂɎ������߂��Ɨ�������̂����R�ł��낤�B
���́u�嗦�v�̗p���┭�����u�P�ÕF�[��������v��u�}�����v�ƒʒꂷ�邱�Ƃ͋����[���B
�@�h�j�͒������h�����Ēn���ɒ��݂��钺�C���ł���A�C�n�̏B�Ɏ�����u���n�����l�����O���{���o���c��ɊN�t����h���̗��ł���B
�����t�͓������ɍݒn�o�g�̏�v���j�̐E���i�������������ϊ��I�A�������S���u�B�S�j�ւƍ������i�u�B�q����҂�đt�������f�v������I�j���v����Ă���B
�@���\�̌y�d��n���s���ւ̊֗^�x�͔N��ɂ��قȂ邪�A�Ď@���E�R�Ă̐E�\�ƍc��̎g�҂Ƃ��Ă̐��i�͕ς��Ȃ��B
�@���̎h�j�ɗޔ䂳��邱�ƂŁA�嗦�����u�n�ɕ��C���ė��������ł��邱�Ƃ͖��Ăł��낤�B�A���A���̗l�Ȓn���]�o�҂��e�Ղɓy�����čݒn�����邱�Ƃ́A�㐢�̏��Ȃǖ����̗�Ɏ������Ȃ��B
52�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:15.19
���e�`�p 54
�p�F��嗦�͏������Ȗk�ɒu����Ă���I
�@�@�Ȗk���Ă��Ƃ͏��������܂ނ��I
�`�F���ۂ̗p��ł͂����Ȃ�Ȃ��B
�u�n�E�k���ȓ����Ɂc�ד����A�n�E�k���Ȑ�����J�ג����c�n��J�Ȑ��������c�א����v
�@�@�@�i�O���u����鰏��N�ځj
�u���d�d��R�̈Ȑ����y�Q�A���̈ȓ������s�ю�V�v
�@�@�@�i�O���u���Γ`濊�j
�u�������A�����N���ԗL�p�ȓ�r�nਛ���S�v
�@�@�@�i���ؓ`�j�@���ԗL���͊y�Q�ɑ����B
���e�`�p 55
�p�F�͘`�Ɓu�ځv���Ă���B�n�������B
�@�@��؍��͘`�l�̍��̈�����I
�`�F�u�ڏ�v�Ƃ���Βn�����ł��邪�A�u�ځv�����ł͍����ɂȂ�Ȃ��B
�O�ڗɓ��A���^�n�V���i�������E�Z�j
�@�@�@�@�R���Ȃ̎h�j���ɓ��Ɓu�ځv
�d�˚��A�ݓ���C���F�㋏�A���o�k���A���o�֔k�o�A�k�o�^�c�ځi��������j
�@�@�@�@�C���̓������J���{�W�A�Ɓu�ځv
�@��ׁi����j�͋������A���ׁi�����j�͙����S�ƁA�R���I�Ɏ�v�Ȉ�Ղ̂��锼����ْ݂͕C�̏��؍��Ő�߂��A3���I�O���ْ͕C��V���̕������ł���B�i���v1999�C�v�Z2006�C�p2007�j
�`�l�̍��ł͂��蓾�Ȃ��B
53�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:34.94
���e�`�p 56
�p�F�u���L�v�́u��X�v�Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B�u鰂̎����Ɂv�Ƃ����Ӗ����I
�`�F�u���L�v�ɂ́u��X�c�v�Ƃ����Ӗ��ƁA�u���Ԃɂ́c�v�u���̍L�����E�Ɂc�v�ȂǂƖׂ��p�Ⴊ����B�u鰂̎����Ɂv�Ƃ����Ӗ��͂Ȃ��B
�u���ԂɁc�vin the world �̗p��
�E�u���L�l����q�@�ǎҌ��H�v�i鰎��t�H�`�N�j
�E�u���L�m�l�A�ᖢ�V���B�v�i�挫�s��j
�E�u���L�v�w�a��ҁA母������I�v���s�o��B�����������C�v�����ӁB(鰗����v)
�E�u���L���l�������@�v��g�@���C�A������s�{�l�_�V���A
�@�u�����M�ɘC�V����i�m�E�q���j
�@�@���͈͂͑S���E�A�����鰒��Ɍ��炸�A���̎���ɂ��s��
�@�@�������͕s�����someone�̑��݂����������ł���B
�u��X�c�v�̗p��F
�E鰈����@�A��@�V�j�A�F�@�p���A���v�l�ȉ��A���L�����B
�@���c�����A�n�����@�A�����ܓ��c�i�@�ܙB��܁j
�@�@����������鰉��̍�����鰒��܂ő�X�ύX���d�˂Ă���B
�E���L���߁A�㐢�����J�B�i���q�ǔJ�j
�@�@���c�Ă��������ǒ��̎q�����A����ɖk�C�ʼnƂ��ċ����Ă���X��ڂ��ǔJ
�E�͎��q�����L���ʁA�M�B�����B�i�蒐�͟Ёj
�@�@���͟Ђ̕��͊����̎i�k�A�Ђ�鰕��ɏd���A�q���������ɒB���W���Ɏ���B
�E�����l���L���j�i����j
�@�@���̂�鰂̎i��ƂȂ鉤�₪�q�Ɖ��Ɍ��P��
�@�@�@��̔����_�͊��왱�z���Y���A���V�͑�S����A�Z�ʼn��̕��@��鰓��S����
�@�@�@���R�Ȃ����l�͉����l�̂��Ƃł͂Ȃ��A���c��X���w���B
�E�b�v�V��A�������S���A嫐��L�m�ҁA�匪�����t���i�|�ʙB�j
�@�@���S���ɘj���đ�X��z��
54�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:48:53.49
���e�`�p 57
�p�F�퐶����ɑO�j�������Ȃ�㕌����Ȃ��{�s�̒n�ɑI���̂��H
�@�@�K�R�����Ȃ��I
�`�F�ޗǖ~�n�͌Óޗnj̏����ߒ��ɂ���A�͓����ӂ̖������n���������̔_�n�ւƁA�ؐ��_��ł����e�ՂɊJ���\�ł������B
���̓����ɂ��A�ޗǖ~�n�͍����l���z���͂�L���A�ږ���U�v���₷���A���͂̐L���i���U�Q�Ɓj���\�Ƃ��闧�n������������Ă����B
�@�@�����t�߂Ⓡ�̎R�Õ��̓����ɖ퐶��Ղ����z���Ă��邱�ƂŁA�������ɌÓޗnj̍��Ղ͋ɂ߂ċ�襂Ȏc�������������݂��Ă��Ȃ��������Ƃ͖��炩�ł���-
 �u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016
�u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016
�i �ޗǖ~�n�̖퐶����̈�Օ��z�Ɗ�b�n��@�w�Z���w���� 4�x p6 �}2�j
-���A�͍����̐썇�l���̒n���������������Ƃ���A�ޗǖ~�n�e�n���c���Ɍ��ԑ�a�쐅�n�̐��^�͋ߐ��܂Ő���ł������B
���Z�ɓK���������n�𐅈�k��ɓK������n���͂ޒP�ʏW���������ɔ������A����炪���^�Ō���邱�ƂŁA���R�����ɋnj�����Ȃ����ƌ`�����x����C���t�����\�ߏ�������Ă����ƌ�����B
�@�����āA�O�֎R�[�͌�ʂ̗v�Ձi���S�Q�Ɓj�ł���B���CS���P�̊g�U���[�g�ł��铌�R���Ɉˑ������Ɍ��Ճ��[�g�𓌂ɐL���ɂ́A�����X�����璆���ɔ����ĊC�H���m�ۂ���̂��v���ł������B
��a�쐅�n�ɑ����A���A����ŗ��쐅�n���o�ĐےÎR�w�E�����E�k���E�A�O���֒ʂ����ʖԂ̑��d���ߓ_�ł��铖�n�ɂ́A�ǂ̐_���J����K�R��������B
�@�E���y�т��̗אڒn�e�n�̎�����A�����ْ̍���ޏ��ɋ��ꏊ�Ƃ��ẮA�ߗ̐F���t���Ă��Ȃ�㕌��̒n���K�ł��낤�B 55�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:13.18
���e�`�p �T�W
�p�F�s���_�Ō�����ƁA�E�����͖����ł͂Ȃ��̂��I
�`�F�s���L���ɂ́A���ʁE�����Ƃ��Ɍ��܂܂�Ă��邱�Ƃ����炩�Ȃ̂ŁA���ݒn���ɂ͍̗p���Ȃ����A���ɂ͗p����i�֘A�F��FAQ3�j
�u���S���������ݓ���P���v�̂����A��B�{�������܂ł����P�����������ς݂ł���̂ŁA�s�����߂œ`���I�ȘA���������͕��ː��̛x��Ɉˋ����Ă��A�c�]��1,300�`2,000���ƂȂ�B
�����鰎�24cm�~1,800�ځ��P鰗�432m���Z�ŊT��562�`864km�ɑ�������B
�@�Q�l�l�Ƃ��Ĕ����`���ޗnj�����s�̎O�֎Q�������i�咹���O�j�܂Ńt�F���[�q�H�ƌ���̓��H��̒ʎZ������ƁA���s�q�H�̏ꍇ�T��620km�A��`�n11�ݒ�̏ꍇ�T��793km�ƂȂ�A�Ó��Ȕ͈͂Ɏ��܂�K������B
�u�쎊���n�����s��\���v�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v
�@���A�A�����Ɉˋ������p������ʎZ�����ꍇ
�u��ɕ{�C�H�����v�i���쎮�ɑ���l��v����j�Əƍ����Đ��s�������Ó��ł���B
�@�܂��A���ËI�����萢���̗������
�u�Z���p�ЍC�A�q��������g�ÁB�������R�D���z�}�q�����]�����u�V�ځv
�u�H�����h�N��ᡉK�A���q�����B�������R�R���\�ܕD���}���q���C�Ξ֎s�ˁv
�@�ȏ�48���o�߂ł���B�O���g�ߗ����̗ޗ�ɏƂ炵�A���s�������Ó��ł���B
�@����ɁA����1,300�`2,000����������v60���ŏ�����Ɩ�22�`33�������Łu�t�s�O�\���v�i�����������j�A�u�t���s�O�\���v�i�����g�`�j���Ɛ�����������B
�@�܂��A���m�̓������狗�����t�Z�����Ɛ��肳���ޗႪ�J���[�V���e�B�����i�O���`����j���Ɍ��o����B��L�ʎZ����60����30���������悶��1,800�����A25�������̏ꍇ1,500����������B
�@�ȏ�A���_�Ƃ��Č��ɑς���B�A���A���̎��Z�͎הn�䍑�̈ʒu���Ɏg�p���Ȃ��B
56���{�������j����2019/02/13(��) 12:49:22.97
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
57�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:34.37
���e�`�p �T�X
�p�F�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v
�@�@�̋N�_�͑ѕ��S�ł���I�@�E���ɓ��������Ȃ��I
�`�F�s�����ł���B
�u�쎊�v���u�`�l�ݛ�������C�V���v�Ɩ�������B
�܂�
�P�u�쎊���n�����s��\���v
�Q�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v
�͍\���������ł���A�u�쎊�הn�㚠�v�̋N�_��ѕ��S�Ƃ���Ȃ�u�쎊���n���v�̋N�_���ѕ��S�ɂ�����Ȃ����A���n���ɂ͐��s�݂̂œ���������B
����Ċؒn���s�����A�邵�A���s�������ؒn�Ŕ�������Ȃ����ߑѕ��S�N�_���͐��������Ȃ��B
���e�`�p �U�O
�p�F�u�쎊�הn�㚠�A�����V���s�A���s�\�����s�ꌎ�v�̂悤�ȓ����\�L��
�@�@�u���s���s�\���S���v�̂悤�ȗ����\�L�ƍ��݂���̂͂��������ł͂Ȃ����I
�@�@���p������ʂɋL�����̂��B�����̋N�_�͑ѕ��S�ł���I
�`�F���݂͒������Ȃ��B�P�ɏ��̐��x���Ɖ�����̂��Ó��ł��낤�B
�i�������j�������Z�甪�S��\���B�c���k���s�쎡������S�\�����A
�@�@�@�@�@�k�ڈ�ಁA�쎊�����O���s�A�c���ʐ����痢�B
�i���⚠�j���������甪�S��\���B�c�k���s�쎡����玵�S��\�O���A
�@�@�@�@�쎊�^Ḛ��l���s�A�c���ʁu��ɘ��v�\�l�S�Z�\���B
�i�P�C�o���j�������ݓ���S���B�s���s��B
�@�@�@�@�c���k���s�쎡���Z�甪�S�l�\���A�����G�u�ѕɑ�̝Ӂv������S�\���A
�@�@�@�@���k���������s�A���k�o�匎���A�����o�G�T�R���ځB
�i�G�T�R�����j���������ݓ���S���B�s���s��B
�@�@�@�@�c���k���s�쎡���Z�\���s�A���o�P�C�o�A�k�o�o���A
�@�@�@�@���oಁu�v�ɘ��v�E���x�ځB
�@�@�@�@�s�S�P���A�T�����x�B�c�����x�������s�A�S�P���A�ߓ������]�B
�i�匎�����j�������݈��Z�S���B�s���s��B
�@�@�@�@�c�����s�쎡���l�玵�S�l�\���A���������l�\����s�A���o�P�C�o�ځB
�i�Ɩn���j�����������S�\���B
�@�@�@�@�c�����s�쎡������\�ꗢ�A�쎊��闐�n�s�\�ܓ��A�k�o�G���ځB
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�ȏ�A���������j
58�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:49:55.29
���e�`�p �U�P
�p�F�u�����k��ؚ��A�����P���v
�@�@����͎��������Ƃ����l�����Ȃ��I
�@�@���Ƃ����Ȃ��肪�����������R�𖾂炩�ɂ���I
�`�F���m�̒P�ʌn�����݂���ƋA�[�I�ɏؖ�����Ă��Ȃ��ȏ�A鰎ڎ����ɏƂ炵�Č��Ƃ���ق��Ȃ��B���딭���̌�������͍Ĕ��h�~�ȊO�̈Ӌ`��F�ߓ�B
�@��ʕ͏\�{�ɂ��Č��\����K��������u��S���Ŋv�̐�ʕ��֒�����Ă��ĕs�v�c�͂Ȃ��B�@�u�j�������A�p�Ȉ�\�v�i�����`�j
�@�����́u���l�������v���u�l���������v�Ɠ��`�Ɏg�p����邱�Ƃ�����A���p�ɂ�������L�蓾��B
�@�܂��A�`�z�����̒��v�������̉����ƌ������ꂽ�`�Ղ��L�V�A���ꂪ�K��l�Ƃ��ČŒ肳��A�n�C�R��ƈ����ꂽ�\�����l������K�v������BFAQ58�ɏq�ׂ���2,000���ƍ��Z����Ɩ���痢��������B
�u�����V���c���ɓ������肜��讋�k���ߍs�C�\�A����濊滁E�`���ݗ����فv
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�㊿�����j
�u�@�n�ϖʁA�ݛ�������ݗ��v�i�@�~�j
�@����ɂ́A�哯�]�͌��̒���Y���m��E�؉Y�E�퐅���o�R���Ċ��R�Ɏ���q�H��1,296km�i�����\S22�j�ł���B������ꗢ��400m�Ŋ���߂���3,240����������B
�����̑D���͍q���������Z���������ߌ���̍q�H����`�n�������I��H���̋�����L�т��傫�����ƁA�]�ˎ��㖖�܂őΔn�C������R�{�Ɍ�F����Ă������j�I�������ɏƂ点�A�\���ɋ��e�͈͓��̍���ł���B
�@���̂悤�ɁA�`�l�`���ڂ̔��I�ȗ����̔����ɂ͊��ł������̑z�肪�\�ł���B�������Ɍ���闼��鰐W�̓x�ʍt�ɏƂ炵�đ���炪�ԈႢ�ł���Ɣ��肷��ȏ�̑F���͕s�v�ł��낤�B
59�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:50:15.31
���e�`�p �U�Q
�p�F�ѕ��S���؍����ǂ��ɔ�肵�Ă���̂��I�@���m�ɂ���I
�`�F����ɏ]���B
�@���Ε����ɂ��A�y�Q�S��������s�y�Q��y�闢�A�u�i���ɚd�j��������S��i�R�Ɍ��j���y��B��Y�s�]�����闢�͌������ځB
�@�ѕ��S�����P�R�S�q�����y��A�S�̊O�`�ƍl�����������邪�u�I�S�_�闢�y��i��Y�̑Ίݕt�߁j�A���암�s�ю��̏������邪�M��S�k���ʐR�y��A�������邪�M��S�M��W�A�����邪���x�S���闢�ɔ�肳���B
�@��S�͛x����哯�]���n�ɓW�J���A��Օ��z���A�ѕ��S�͎x���̐����]�E�ڔJ�]�y�ѐ��]���旬��A�k�����ߎR�A���ň��R���̒����R�܂ō����@�E�P�R�S�E��g�S�E�َR�S�A�����ڔJ�S�E�V�@�S�E���S�E���x�S�E�M��S�E�u�I�S�E�O��S�E���ьS�̋��B
�ߑ�I���H�����������܂Ŗň��R���͉I�˂Ȃ炸�A���R���ȓ�ŕ搧���قȂ�ɏ�S�E�C�B�s�͌S�̈�O�ł��낤�B
�@�ȉ��A���n�╨�𑽐��o�y����،n��Ղ��A���ύ��Ƃ����\�E�����[���E��������A���x���Ɩڂ����V���������A�����ğ����ӓ��A�`�����˗��A�n�R���o�ċ��C�܂ŊC�H�Ō���Ă���B���C�Ǔ����y�ё听�����ْC��ׁi��j���ɑ�������B
�@�y�Q�ƔZ���Ȍ����т̂�����Ջ��_��Ղ����ݕ��Ⓡ�ו��ɓ_�݂��邱�Ƃ���A���C�q�H���d�v�Ȓʌ����[�g�ł��������Ƃ����炩�ł���B
�@
���e�`�p �U�R
�p�F�������Ɂu�`���ҌØ`�z����v�Ƃ���I�@�`���͋�B�ɂ������`�z���̌�g�Ȃ̂��I
�`�F�u�Á�����v�͐����I�A����\���Ȃ��B
�����������Ɂu�i�b�Ɋ�j���@���p�A��郇����v���Ƃ���̂Ɠ����ł���B
���͓̉����i�b�Ɋ�j�����́A����̕P���ł�����郇�����퍑����ɖłсA�ϓ]���o�Ċ���ɌS���ɕғ����ꂽ�n�ł���A�P��郇������̐����j�I�E�n���_�I�Ȋ֘A�͖���
���e�`�p �U�S
�p�F���ϐg����160cm�̏W�c�ő��肵����������73cm�Ƃ���������I
�@�@�a�S�]���ł���ږ�ęn�́A100m�����̌Õ��ł͂��蓾�Ȃ��I
�`�F��b�m���̌��ł���B
�@�@������{�l�̂�������́A�Ñ㒆���ł̓P�C�i���Ɍ\�j�ƌĂ�A����͈ꋓ���Q����w���B��L�̕������������͍l�Î�����鰎ڂU�ځi������j���Y��Ɉ�v���Ă���A���̕S�]���͔����R�Õ��ȂǁA�剤���Ƃ���鏉���Õ��̌�~���a�ɍ��v����
�P�C�A�ꋓ����B�{�P�C���V���B�i������j
�l�H�O�ږ@�V�n�l�A�ċ�������隂�z��B�i���Ւʁj
60�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:50:34.34
���e�`�p �U�T�|�P
�p�F�����P����o�y�̔��t���͎������W�@�ɑ�������I
�@�@�`���̉������ے�������j�I�╨�ł���I
�`�F�j���I�����A�l�Êw�I�����Ƃ��Ɍ������������ł��낤�B
�l�ÓI�╨�ɂ��ڂ�
�@�u���F��P�Ucm
�@�����F��Q�Ocm
�@�퍑�`���͐V�F�Q�R.�Pcm �i����I�j
�@�㊿���`鰐W�F�Q�Scm�O�ォ������X���@�i䤙����Ĕ����j
�@��k���`�@���F�R�Ocm��
�ƕϑJ���Ă���A�ٖ��������̌������������u�Ɠ�k���ɕϓ��̉��������B���u���͏����̎Љ�I�n�ʉ����ɓ���������A�ߍH�ڂ̎Љ�I�e���͌�ނ���m�ł���B
�@��`�`�����̒��w�l�͐g���P�U�Ocm�����A�蒷�P�Ucm��şu���ڂƊT�ˈ�v�i��c1995�j����B�㊿�����_�Łw�����x�Ɏ��ڂ̂W���ƕ\�L�����\��������̂́A�ߍH�ڂƂ��Ĉ⑶�����u���ڂƐ�������ڂ̊W�ł��낤�B
�Q�l����ł��邪�A�D�ǎڂƌ���ڂ̊W���P�O�F�W�ɋ߂��B
�@�㊿�ڂ̂W�����P�@�Ɗ��Z����j���I�����͂Ȃ��A���w�l�蒷�̎��ԁi�j��18cm��A����16cm��F��c�O�o�j�Ƃ��ꗂ���B�܂��Ɍ��s�̌���ڂȂ̂ł��邩��A�u�퍑���ォ��g�p����Ă����̂Ŏ��ڂł���v�Ƃ����ٖ����s�����ł���B
�u�@�v���v���P�ʂƂ��Ďg�p���ꂽ����������Ă���A��Â̊��Z���݂̂��`�����ꂽ����ƍl����̂��Ó��ł��낤�B
�@�܂��A�L�I�ɓo�ꂷ��u�@�v�͎j�������N�ォ��݂Č㊿�ڊ�ƌ��Ȃ����������Ȃ��B�p���̂��ʂȈٍ��̒P�ʌn�ł��낤�B
�L�I�ɂ����锪�@���͉����ƊW�Ȃ��g�p��������Ȃ��Ȃ��A���@�ł��邩��`���̉������ے�������j�I�╨���A�Ƃ��鍪�����Ȃ��B
�@�܂��Ă�A���̑傫���������ŕ\�L����������Ȃ��A����I���w���}���̎Y���ƌ��킴��Ȃ��B
�s�Ñ㒆���̒j���g���y�ю蒷�F��c�O�o�j
�\�\�\�\�\�\�\�\�\�\MAN------------FRAU------
4500-3200B.C._____166.8 18.1 155.5 16.7
3000-2000B.C._____165.3 18.0 154.2 16.6
2015-1900B.C._____168.8 18.3 157.3 16.9
A.D.1979-__________170.3 18.5 159.0 17.1
�i�{�� �����j
61�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:50:54.85
�i���O�j
���e�`�p �U�T�|�Q
�@�w�X�L�x�����ɂ�
�@�u�ÎҁA�Ȏ����ڈו��A���Ȏ��ژZ�ڎl���ו��A
�@�@�ÎҕS���A�c�����c�S�l�\�Z���O�\���A
�@�@�ÎҕS���A�c���S��\�ꗢ�Z�\���l�ړv
�Ƃ���A���ڂ̂����ł��V�ÔT���召�̓��̑��݂��M�m�����B
�@�����ŁA�S��\�ꗢ�Z�\���l�ړ�218,164.22�ڂł���̂�
������ÎҎ��ڂ̕S���i2,400�ځj�Ŋ���߂���1.10009�����ځ��P�`���ڂ������A�u���Ȏ��ژZ�ڎl���ו��v���u�Z�ژZ���v�̌��ł��邱�Ƃ���������B
���̍���̌�����⽕��́u�l�v�Ɓu�Z�v�̎��`���ގ����Ă��邱�Ƃɋ��߂�̂��`���I���߁i�E�L�X�F�����j�ł���A�o�T�̕����̌Â����Î����Ă���B
�@���̔䗦�i�����ځ��`���ڂX���j�́A��y�̎剹�u�{�v�̎��g���ɑ������鉩�����ǁi���X���j���`���x�ʍt�̊�b�\�\�������ǂ��e�ρE�d�ʂ̊�\�\�ɂȂ��Ă��邱�ƂƂ̕������ӂ݂�ƁA�����[���B
�`���ڂ���������I�ł�����������A��y�����Ƃ̊W�ŗ����ł��邩��ł���B����ɉ��͈ȍ~�`���ڂ�����n�߂邱�ƂƂ�������������B
�@�`���ڂ��t�Z�����ÎҎ��ځA�����ځA�`���ڂ̎�����
�@�@�ÎҎ��ځ@17.3cm
�@�@�����ځ@�@21.0cm
�@�@�`���ځ@�@23.1cm
�ƂȂ�A�u���ڎ����Ƃ̘A�������������₷���B
62�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:51:15.09
���e�`�p �U�U
�p�F鰎u�ɐ�s����j���ł���鰗��ɂ����ẮA�s���L���͈ɓs���ŏI����Ă���I
�@�@�{���͈ɓs���܂ł̍s���̋L���ł������̂��I
�`�F鰗��͈핶�[�[���Ȃ͂��f�Ё[�[�Ƃ��Ă̂ݑ��݂��Ă��邽�߁A�u������Ă��邱�Ɓv�ł͂Ȃ��u������Ă��Ȃ����Ɓv�������ɂ��闘�p�@�͌����I�ɕs�ł���B
�@���Y�ӏ��͒��^���i���j�́w�ˉ��x���u�����E���� ���������v��贌��b�̕t�������ł���B�i�u���E�v�́u�E�v�ّ̈̎��ŁA���u���v�łȂ��u�g�v�j
�T���u�F�����������v��������邽�߂̈��p�ł���A���҂��s���L���Ƃ��Ĕ����������ł͂Ȃ��B�u�������F��������v�ň��p���I��鏊�Ȃł���B
�@�Ȃ��A�w�ˉ��x�͎ʖ{���e���ŒE���E�����A�s�K�Ȑߗ������A�����̂��Ӑ}�I�ȉ��ς��肪���X������݂̂Ȃ炸�A�o�T������L����L�邽�߁A�����ȗ��p���݂���j���ł���B
���e�`�p �U�V
�p�F��ḍ����Ďq�t�߂ɑz�肷��Έɓs���ւ̕��ʂ͓���ł悢�I
�@�@�Ȃ��Ȃ�A�n�C�ɓK�����ď�̓��̏o�͐^����肸���Ɩk�ł���I
�@�@�`�l�`�ɂ�����ʂɊԈႢ�͂Ȃ��̂��I
�`�F���̒��x�̏n���x�̐l�����L�ڂ����L�^�ł���A���ʂ⋗���ɐM����u�����ƂȂǂł��Ȃ��ł��낤�B�܂��āA��瓌���Y�����t�߂ɓn�q���Ă����ł��낤���ԑт��ӂ݂�A�ď�ɐ^����肸���Ɩk���̓��̓�������Ă���\���̕��������B
�@�����Y�����˒[�t�߂���͎����x�m�i��R�j���ڎ��ł��A�ɓs���̕��ʂ�����łȂ����Ƃ͏\���ɔF���ł���B
�@�E�����Y�����k�[�͖k��33.5�x�i��_�F�Ďq ���m���@�j
�@�E�ɓs���͖k��33.5�x�i��_�F�O�_ �אΐ_�Ёj
�@�E�z���͉��ɖk��33.5�x�i��_�F�t�� ���{��Ձj
�ł���A���ׂĘ`�l�`�̋L�ڂ�����ʂƈقȂ�B
�@���Ȃ݂ɔ��I�z��ł͂��邪�A�Ⴕ�w��鏎Z�o�x�ꐡ�痢�@�Ȃǂ��V���Z�p�Ƃ��Ď��p������Ă���A��L�R�n�_�������ɕ��Ԃ��Ƃ��������A�`�l�`�Ɍ������ʌ�F�͔������Ȃ��B
�Ñ�̊C�ݐ��ɉ����āu���엤�s�v���邱�Ƃ́A����ȏ��Y���ɎՂ��č���ł���B

�@���݂ɁA����̓����Y�����͖k���Y�����̖k���ɂ���B
�@�n�������ۂ̒n���ƒ������قȂ�B 63�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:51:39.04
���e�`�p �U8
�p�F�z�P�m�R�͕z�����ŁA�͔�̂��铺�V���o�Ă��邩��A3���I�����S���I���낤�I
�@�@�ޗnj��̎O�p���͂����ƐV�����I
�`�F�R���I�̌Õ��ƍl��������䒃�P�R�Õ���萳�n���N��������������Ă���B�����葁���ʒu�t�����鍕�˂��z���O�V���ŁA�R���I�㔼�ƍl������B
�@�z�P�m�R�͕掺�̖ؐ��V����������ĕ������Ă������߁A���̒Ǎ��J�╨�ƕ�ۓ��╨�̔��ʂɓ�������B�܂����^�ے�y��̕]���ɂ����_������A�A���N��ɂ��Ę_�����������B
�@�������k�����Ő[���Ƀp�b�N���ꂽ��ԂŔ��@���ꂽS���PA���ȂĊ���������Z���R�ޒ��t�i�����Q�j�Ƃ���i�L��2018�j���_���ŏI�I�Ƃ݂Ă悢�B
���j�Ӎ��J�ɋ����ꂽ�敶�ѐ_�b��B�i���j�̔N��ρi�H�_���ҔN�ɂ��B.C.230�`250������鰋��F���2008�j�Ƃ����v����B
�z���O�ɐ�s����i�K�ŎO�p�������Ȃ���́A���n��ŎO�p���̕������z���O�ɑk���Ɛ�������B
�@�͔�������V�͌Õ�����̂��̂Ƃ����C���[�W�Ō���邱�Ƃ��������A���ۂ͒A�O�E�ߍ]�Ȃǂ̒n��Ŗ퐶����`�I���̖퐶���u��Ŕ����Ⴊ�����Ă���A�z�P�m�R�̔N��Ɛ�����������B
���e�`�p �U9
�p�F����19�N�n�����V�R���͂����Ƃ��Č��u����鄴�A�����l�痢�v�ƌ����Ă���I�@�@
�@�@���̂Ƃ��Č������̂͗��z�������ł��邩��A�Z�����g���Ă����̂��I
�@�@鰗��H�u�����u�s��R���сA�u��R���R�B���F����B���R���~��v�Ƃ���
�@�@��R���R�ł��镣�̔C�n�͓s�ł���I
�`�F�Č������ɓԂ��Đ���������x�����ō��ӔC�҂ł��������Ƃ͏펯�ɑ�����B
�u�s��R�v�́u�s�v�́u�s�v�Ɠ����ŁA��s�̈ӂł͂Ȃ��B�u���R���~��v�ƕ��͂������Ă���A��R���R���s�ɒu���ꂽ���łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@��L�̑����u�������͖{���u�c�G�����R�O���A�F�吪���B���^�F��v�ɕt����Ă���B�u���^�F��v���u���R���~��v�Ƃ���Ƃ���A��R���R�͊O�������C�̊��ł���A������A�҂���ΔC���������B
�@�����s��R���R�ɔC����ꂽ�̂͌����u�\���N���c�T��鄴�A�ȕ��s��R���R�A���E�H�����A�Ԓ����A擊�j��R�����Y�A�~���O�A�����E���]�}������鄠�A�U�V�a���v�B
�s��R���R�Ƃ��Ē����ɒ��Ԃ��A�ȍ~��т��Ċ։E������B�ɂ����ĘA�킵�Ă���B�����N�U���͍s�s�쏫�R�A�������R���C���z���Ő펀�����B
�@�������鄴�܂ʼn��Ҏl�痢�́A鰂̐���ȗ��i1,800�ځj���p�����Ă���B
64�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:51:58.76
���e�`�p �V�O
�p�F����`�ɐ��n���u���ԉ��A�����z�O�S�]���B���R�U�ԁA�D�ݐ�r�A�L�}�s�������B
�@�@�T�\�o���V��A�K���R����B�A�A�_���B�C�q���m�ρv�Ƃ���I
�@�@���z�ߕӂ̉��r��鰂̑D�t�����Ԃ��Ă����̂ł���I�@���̎O�S�]���͒Z���ł���I
�`�F���z�̗��\�v��A�t�B�͎O���ɕ������ꂽ���A�։H���˂��冊��͌�ނ��A���������z�͑����ƑΛ�����鰂̏d�v���_�ł������B���쏫�R���ߓs�t�E�\���R���̉���́A���z�t�߂Ŋ����ƍ������鐴���i���́j�ɗՂޓ�z�S�V�쌧��Ɏ������ڂ��A�L���ɔ������B
�@鰑��a���N(227)�i�n�鉤�͈��ɓԂ��ēt�E�\��B���R����q�����B���̎��_�ŌS��͈��ł���B
�s���O���ɂ��u�����ԗz���A��鏮�t�B�s�A������B�����^����A�n�o����萒����R�����v�Ƃ���A���₪�㏑���ĐV��ɓk����ȑO�܂ł͈��邪���ł��������Ƃ����炩�ł���B
�@�K���ρE�D�J��̍l�܂��A���؏��ǂ͂��ߏ����Łu���ԉ��v�́u���Ԉ��v�ƍZ������Ă���̂�����ł���B
�@����i�́E���z�j����z�i�́E����j�܂œS������135km�B鰂̐���ȗ��i1,800�ځj���p�����Ă��邱�Ƃ͌���ւ��Ȃ��B
���e�`�p �V�P
�p�F�`������\���ɂ́u�n���C�k��\�܍��v�A����v�`�����ɂ́u���k��V���v�Ƃ���ł͂Ȃ����I�@�^�k�ɒ��N����������̂͋�B���I�@��B�`���Ȃ̂��I
�`�F���{�̂ǂ�����ł��A�C�k�ɓn��ɂ͑Δn���k�Ɍ����������암�ɒB����B
�@�����ł�鰎u�̐̂����v��̒n�����Ɏ���܂ŁA�`�l�̏Z�ޓ��X���A���N��������y������̑�p�t�߂܂ŐL�тĂ���Ƃ��������n���ς����z���Ă����B
�u�Í��؈��y�v�}�v �k�v���`��v�����i�\�I�O���j
�u���k�U�n���}�v ��v�i�\�O���I�j�@
�@鰎u�`�l�`�̍s���`�ʂ����r�����ʂ�����āA���֍s���ׂ��H�����ƌ�F���ċL�q�������ʂł��낤�B
�@���̓���v�`������
����\��N(777)�A����g�����J�i������j�C���g���B�i��_�����j�����v�B
�J���l�N(838)�����A���g�O������k�i������k�j�������v�B
�@���L�^���Ă��邱�Ƃ�����A�u���k��V���v���`���̈ʒu����B�Ɍ��肵���Ȃ����Ƃ͖��炩�ł���B 65�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:52:19.80
���e�`�p �V�Q
�p�F�`������\���ɂ́u�����ѐl�\�܍��A�����O�ΘZ�\�Z���v�Ƃ���I
�@�u�����v�́u���v�͎������������B�̖��͐̂����B�`���̉��̐b���Ȃ̂��I
�@�@�E���́u�����v�����ѐl���I
�`�F�u�ȗ͕��l�ҁA��S����v�i�Ўq�j
�@�@�u���v�͑������Ƃ��Ďg���B
�@�@�u�����O�v�̓����u���v������Ă���ړI��́u�O�v�ŁA�������ł���B
�@�u�����E�E�����E�E�v�͑�̍D��ŁA�E���𒆉��Ƃ������V���剤�̏����؎�`�̖G��ł���A�u���o���V�q�E�E���v���V�q�E�E�v�ƒv���������@�g��A�������u���ׁv�ɕ��ނ��������^�Ɍq�����čs�������v�z�̕����ł���B
���e�`�p �V�R
�p�F�����{�R�⑾�c��Ŕ��@���ꂽ���O�N���́u���v�̎��͌������I
�@�@����͖k鰂̍��̏��̂ł����āA鰋��Ȃǂł͂Ȃ��I
�`�F�u���v�͎ߓǂ̌��Łu�ށv�ł���B
�@�u���v���̝ӂ��u�ށv�Əȉ悷�邱�Ƃ͊��ォ��s���Ă���B
�@�w�D���ؒ����E�_�X���x�F���ؒ���A�i�㊿�i���N�i156�j�������j���ڂ́u龔�v���E�ӂ�����i�ށj/���ɍ��B��ʎ��F
�@�\�M�Ƃ̕M�������e��E�l�������ɖ͍�����Δ�Ƃ͈قȂ�A�E�l���w���Œ��ڔS�y�ɕ�����������������͎��悪�K�R�I�ɒ����I�ł���A�����Ȃǂ��˂ތ���l�̕Ό��͎����ł���B
���e�`�p �V�S
�p�F�������y��ɂ͏�����a�^�P�Ə����͓��^�P�̕ʂ�����I
�@�@��a�Ɖ͓��͌𗬂̂Ȃ��ʂ̍��������̂��I�@�E�����הn�䍑�ł͂��肦�Ȃ��I
�`�F�����P�́A�E����V�l���ɊO���̓��ʃP�Y���Z�@�Ɛ��`�Ԃ���荞��Ő��������B�n�搫�E��ꐫ�̍��������E����V�l���������n��Ƃ̐ڐG��ʂ��ĕϗe���n�߂��_���搧�̕ω��Ƃ��������Ă���i�Q�l�F���U�|�P�j�A�Õ�����ւ̐����E�Љ�I�ȕϊv�̎w�W�ł���B
�@��a���암�ł͔d����͓��̏����P��������������A���̖͕�܂��͂����̒n��̓y����H�l�̒�Z���z�肳���B�i�ēc1998�j�@�Z����Ղ̓��ِ������ꂠ��A������a�^�P���̂��Z���ɓ������ꂽ�d���̍H�l�ɂ���Đ��������\���i�ēc1992�j���ے�ł��Ȃ��B
�@�E����V�l�������Ŗ��ڂȌ𗬂��s���Ă����؍��ł���B 66�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:52:41.37
���e�`�p �V�T
�p�F�E�����͎הn�䍑���a����Ɠ��ꎋ���Ă���̂��낤�I
�@�@�E�����͍c���j�ς̓k�ł���I
�`�F���̂悤�ȒZ������N���Ȃ��悤�A�u���}�g�����v�u���}�g�����v���̌�b���p�����Ă���B�L�I�ɓo�ꂷ��u��a����v�Ƌ�ʂ��邽�߂ł���B
�@��`�I�`���̕��͂���A�E�a�̐����͂T���I�㔼��k��Ȃ��B�i�c��1995�j
�ƕ������͗��ߊ��ɂ����蒅�Ƃ��錩���������B�����ɂ��Ă��A�������ɉ��ē����Ǝ��q�̋�ʂ��Ȃ��������o�āA���n�̌����������m������̂͋Ԗ���k����ƍl������B
�@�����̌��Ђ���ƌn���n���瓝�����đ����������m�肵���V���r�J�L����ȂāA��a����̊J�n�Ƃ��đ�߂Ȃ��ł��낤�B
���e�`�p �V�U
�p�F�O����~���̕��z�ł͘`���͈̔͂Ȃǔ���Ȃ��I
�@�@�Ŗk�̑O����~���͊��̒_���̋߂������A�����������I
�@�@�W���I�ł�����̐��͔͈͂͋{�錧�܂ł��I
�@�@�Õ�����̊�茧�͂܂��ڈ̐��͔͈͂ł͂Ȃ����I
�`�F�Í����������鐭���I���̗͂̈�́A�s���Ȏ��R�������Ȃ���ΕK���ϓ�����B
���ƑO�ߑ�ɂ����Ă͖ʓI�łȂ��A��ʌo�H�ɉ����ċێ��I�ɓW�J���A�������r�������B
�@�Õ������ƑO����~���̑̐��͑O���Õ��̒i�K�ʼn�Òn��ɒB���Ĉ���I�ɒ蒅���A�X�ɎR�`���̍ŏ�여��A�{�錧�k�̖���E�]���여��ɓW�J����B
�k��여��ɂ��Õ��O���ɐ��c�k�삪�g�y���A�_����n�𒆐S�ɌÕ��O�����璆���ɂ����Õ������̏W�������W�������A���͂͗G�a�I�Ȍ�ꕶ�������ł���A�Ǘ��I��悵�Ă���B
�X�ɒ_��n��ɂ͍������ق�����A�T���I��R�l�����ɂ͉~�����ցE�l���E�����E�Z�b�E�k�b�E�ƌ`���ւȂ��O����~���̊p�˂��z�����B�U���I�ɓ���ƏW�����m�F����Ȃ��Ȃ邪�A�V���I�ɂ͌�������B
�@�퐶�`�Õ������̖k��ɑ��A�k�C���E���k�̑��ꕶ�����͌���ɓ�����k�厮�̒i�K�œ쉺���A�Õ������������߂�������������B�V���I�ɂ�����_��n��̒����͐Ė����̊����ȌR���s���Ƃ̊W�ő����邱�Ƃ��o���悤�B
�T�ς���Η��O�͑��ꕶ�����ƑΛ�����Õ��������̍őO���ł���A�����암�̒_��n��̓��}�g�����Ƒ��ꕶ�n�Z���̐e�a�I�ȊW��O��Ƃ�����ђn�ƍl���邱�Ƃ��o����B
���ߊ��ɋ߂Â������I�ȑΉ������߂��a����Ƒ��ꕶ�n�Z�����a瀂�w�i�ɂR�W�N�푈�Ɏ������{�Ə����̓W�J���l����A�ɖk�̑O����~������ɘ؎����̋��_�ƂȂ�n��ɑ��݂��邱�Ƃ͗����ɓ�Ȃ��B
67�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:53:02.05
���e�`�p �V�V
�p�F������w�̍��X�،���͘_���u�Õ��o���O��ɂ�����E���^�P�`�y��̐����g�U�Ɋւ��錤���v�ɉ��ċE���n�y��̊g�U�͂��A��������̍ݒn�Љ��a����Ɨ����āC�����I�ɋ@�\���Ă����ƌ��_���Ă���ł͂Ȃ����I
�@�O����~���̐��ȂǁA���z���I
�`�F�O����~���̐��𗥗߉��̓��ꍑ�ƂƓ�����悤�ȕT���́A���݂���E�����Ƃ͖����̂��̂ł���B
�@�G������Ƃ̖����n�ȓ����@�\�̉��ŁA�����p�y��̊g�U���x�����W�����m�̃l�b�g���[�N���O����~���⋟���y��ŏے������Ԃ̃l�b�g���[�N�Ƃ͕ʂɑ��݂����Ƃ��鍲�X�̌����́A����s���R�łȂ��B
�@���e���v���[�g���u�������̂����Ƀ��}�g�̉����_�Ƃ���G������Ƃ̕R�т��������ꂽ�v�ƌ������_����u�̖M���Ƃ̒a���͖����y����v�Ƃ��闧��ł���B���ʗ����̔��e���ł��낤�B
�@�z���[���n���[�הn�䍑�̊W���u�߉ϐ�n��[����여��[㕌��͍������ʂ̑哮�����x����g���C�J�v�Ƃ��ĔF������B
�O����~���̃l�b�g���[�N���u�n���I�W�c�Ԃ̑��̌����ɂ����鑊�ݏ��F�W����Ƃ����A�[���I�e�q�����͌Z��I�����͊w�W�v���u�d�w�I�Ɋe�n��ԗ����Ă���v�Ƃ��Ĕc������B
�����������{�e���v���[�g�̃X�^���X�́A���X�ؘ_���Ƃ������阨�����Ȃ��B
���e�`�p �V8
�p�F���n���܂ł́u���s��\���v���I
�@�@�����������ĂȂ��ł͂Ȃ����I
�@�@�܂蓊�n���́u�������Ȗk�v�ł͂Ȃ��I
�@�@���n���͓��B�ł悢�̂��I
�`�F�����ŕ\�L���ꂽ�����́u�����v�ɊY������̂ŁA���n���́u�ː������v�́u���ځv���ꂽ�u���������Ȗk�v�ɊY������B
�@�w��͎Z�p�x����Z�u�ϗA�v��
�@�u�~�ȓ������߁E�ː������A���o�V�v�Ƃ���B
������
�@�u�b���ꖜ�ˁA�s�������v�u�b����S��\�܁v
�Ƃ���̂ŁA�������߁E�ː���������Z�o���ꂽ�u���v��
�@�b���Ł@10,000 �� �W��125
�ł���A�u�s�������v���u�������߁v�ł��邱�Ƃ����炩�ł���B
�@�{���͑O���ォ��m��ꊎ��263�N�ɗ��J�������Ă�����̂ŁA�`�l�`�q�쓖���̏펯�I�p���@��\���Ă���B
68�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:53:21.52
���e�`�p �V�X
�p�F�Z���̑�^�����H
�@�@�����̑q�ɂ��낤�H
�`�F�q�ɌQ�͋ώ��Ȍ����������E���o�H�ɒ������ĕ��ԁB
�@�@�Z���̑�^�����Q�͏���ƕ��s�ɓ������𑵂��Č`��E�@�\�̈قȂ錚������������ł���A�q�ɌQ�ł͂Ȃ��B
�@����B�́A�����ɓˏo�������ʌ^���̓ˏo���ɑ����A��w���z�ł���Ή����ƕǖʂƂ������邽�߁A�]�O��̍��������z���ƍl������B
�@����C�́A��������L���Ė퐶�ȗ��̑q�Ɍ`�����Ƃ�A�ɁE�_��a���̗p�r���z�肳���B�����B��_�����̑c�`�i���c2013�j�Ƃ����������B
�@����D�́A�n���ォ��Z���`���ƌĂ�A������L���鍂���������Ƃ����B
�@�����K�i���������č\�z���ꂽ�����Q�ŁA�R���I�O����ɓZ����Ղ̒��S�I�Ȑl�����������و�ł������ƍl���ĂقڊԈႢ�Ȃ��i166���j�Ƃ����B
���e�`�p �W�O
�p�F�@���Ɂu��鰎u�����הn�i�Җ�v�Ƃ��邪�A鰎u�Ɏהn�i�Ƃ������̂ł͂Ȃ��I
�@�u���v�͐��Ԃł��������Ă���Ƃ����Ӗ��̓������I
�@�@鰎u�Ɏהn�i�Ə�����Ă����̂ł͂Ȃ��I�@
�@�@���������̕������������̂��I
�`�F�����I�Ȍ��ł���B
�@�q�������H�F�p�V���s�A�q�V�����B�@�[�E�q�������Ɍ������Č����Ă���B
�@�q���q�ˁF�N�q�Ǝ�l�I�@�[�E�q�͎q�˂̂��Ƃ�����Ă���B
�@�����u���v�̒��O�ɍs��̂��u�����B
�@�����u���v�͌�ʂ̓����ƌ������Ė�������\������B
�@����āu鰎u���L�ڂ��Ă���w�הn�i�x�v���Ӗ�����B
69�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:53:43.82
���e�`�p �W�P
�p�F�O�p���_�b���͌����̌n���ɑ����鍑�Y�����I
�@�@������הn�䍑�͋E���ł͂Ȃ��I
�`�F�_�b���͍L����冂Ŕ������A���]�̓�k�ɕ������`�d��������ł����āA���̖����Ɉʒu�t������O�p���_�b���͌����̌n���ɑ����Ȃ��B
�@�㊿���`�����̉�m�R�A�Ő��s�����^�C�v�̐_�b���́A�n���I�ɂ��ގ��I�ɂ��O�p���_�b���Ƃ͈قȂ�n�����}��ɂ��邱�Ƃ����m�ƂȂ��Ă���A������n���������t���O�p����Ő��Y�����Ƃ������͊��ɏI�������B
���݂͎O�p�������Y�ƒf�肵����_�������݂��Ă��Ȃ��B
�@�O�p���_�b����鰐W�������ł���Ύהn�䍑��B�����I�����邪�A���Y�n�̛x�ꂩ�Ɋւ炸�E�����͐�������̂ŁA�E�����Ƃ��Ă͌��_���}���K�v���Ȃ��B
����āA���I�����҂��O�p�������B�n���Q�A����n��łȂ��Δn�C���ȉ��Ƃ݂Ă���X���̋����̂ݎw�E����ɗ��߂�B
�@鰌i���N�ԂɔF�߂���ő����l�̕ϗe��R���I�㔼�ɓ����I�ȕ����ӏ��̓o��ȂǂƂ������v�f���A�O�p���_�b���ɂ����镶�l�̎j�I�ϑJ�̒��r�ɔ������Ă��邱�Ƃ�
�E�O�p���_�b����鰐W�̓��Ōp���I�ɐ��Y����Ă���[
�E���Y�҂�鰐W�̓����p���I�Ɉړ����ė��Ă���[
�Ƃ��������̛x�ꂩ��������K�v�����낤�B
�@�O�p���_�b���̎O�p�����̂��̂��̉͗��悩��y�Q�ɂ����ĕ��z���Ă���Ή��_�b������̔h���ł���A�O�p���_�b���ɕ��ނ���鏉�����Q�͎��ۂɂ͎Ή��_�b���ł���B
���e�`�p �W�Q
�p�F�Õ��ɕ������ꂽ�O�p���_�b���́A���O�ɒu�����ȂǁA������ɔ�גႢ�������Ă���ł͂Ȃ����I
�@�@���̂悤�ȕ��͈АM���ł͂Ȃ��������i�ł����蓾�Ȃ��I
�`�F�����ɁA������c���艺�������i�Ɋ܂܂��B
�@�u���������v�͂��̖��̂̂Ƃ���c�邪�b���ɉ�������ׂɐ��삳���함�ł���A�叫�R跌����I���ɓ�����u�����薩�v���ƂƂ��ɉ������ꂽ���ƂŒm���Ă���B�����ɋ���\��t��������̊함�ŁA��̂̓������A�Èł��Ƃ炷焎ׂ̑���ł���B
�@�O�p���_�b���̌��ʒu�Ɋւ��ẮA���Ɗ���ɕ����Ēu����Ă���A���|���؊��̊W���������łȂ����ߖ؊��ƍ��E�̐Ύ����ǂ̊Ԍ��Ɋ����������Ƃ��𖾂���Ă���B�i�L��2018�j
���������ɂ�����㐡���̌��\�F����ʖʋ��̌`��ƕ����A�O�p���_�b���́u���������v�̖������p����������i�ߓ�2004�j�ƍ����I�ɐ��F�ł���B
�@���˂ł́A�S�Ă̎O�p���_�b���������̑܂Ɏ��߂�ꂽ��ԂŁA���O�ɁA���ʂ�����ɂ��Ĉ�̏㔼�g���R���^�Ɉ�ㅂ��Ă���B��ۓ��ł̈ʒu�͕Ƃ��Ă̈����̌y�d�ł͂Ȃ��A���̊��҂����@�\�ɋ�����̂ƍl����̂��Ó��ł���B
�@���̂悤�ɎO�p���_�b���́A�����c�邪�`���ɉ������A�`�����A���Q���̏��N���ɍĉ�������함�Ƃ��āA�K�Ȑ��i��L���Ă���B
70�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:54:03.28
���e�`�p �W�R
�p�F�O�p���_�b���ɂ́u�p���A���C���v�Ƃ���������������ł͂Ȃ����I
�@�@���E�l�����{�ɂ��ċ��삵���Ɨ�����������Ă���̂��I
�`�F�J���C�̒��ɍ݂�`�l�ɉ������邽�߂ɓ��������Ƃ������̍����Ƃ����B
���O�p���l�_��b���@����17�F��㍑�����P�R
��얾���D�C���R�V���C[��]�l�C�C�p���C���C���B
���O�p��������ѐ_�b�Ԕn���@����15�F������R�Õ�
������r��H�C�Y���[��]�p���C�N�X�������C���C�ێq�X���B�i����l���Ȋw���ߓǁj
�@���R���͐�Áu���v�����̌���ł��邱�Ƃ��q�ׂ�B
�u�Y������v�͊��p��Łu����Y��A�������v�Ȃǂ̗p��ł�������Ƃ���Y��i�^�́j��p���Ő��������삳���`�ʂł���u�p���v�ɑ����B
�u�N�������v�u�ێq�����v�͋��̌��\���q�ׂĂ���A�S�ċ��̐����ł���B
�u���C���v�����̂����t���łȂ����Ƃ͖��炩�ł���B
�@�������P�R���́u���R�V���l�C�v�����p���
�u��L�_��l�s�m�V�C渴���ʐ�Q�H���C�����V���l�C�v�ȂǂƑ��p����Ă���B
�{���Łu���R�V���l�C�v����̂��_��ł��邱�Ƃ����炩�ł���B
�����u�p���C���C���v�R�E�R�����R���́u�Y������p���C�N���������C���v�S�E�R�E�S�E�R�̐ߗ��ł��邱�Ƃ͗����ɓ�Ȃ��B
�@�����Ƃ��A�i��������j���u���C���v�̋L�q���ł���B
�@���t�����n���싾�����Ƃ����L�q�ł͂Ȃ��B
71�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:54:25.30
���e�`�p �W�S
�p�F�ږ�Ă̕�́u�n�v�Ə�����Ă���ł͂Ȃ����I
�@�@�Õ��Ƃ͈Ⴄ�̂��I
�`�F�����ən���u������v�Ƃ���Ƃ���A���ˉ��i���U�y��FAQ 37�Q�Ɓj�����ȍ~�̖퐶���u��A�T�������Õ��̕`�ʂƂ��ēK�ł���B
�{�M�ł͏��Ȃ���ʌÕ����u�n�v�̓����ł���u�ˁv�ŏI�����j�I�ď̂�L���Ă���B
�����ł͎n�c��鋎R�˂��n�̎���i�w�j�L�x���тɁw�����x�������c�����H�H�u�ߎO��B�剤����`���\���A�H�Đ`�{���A�@�n�c��n�A�����������v�A���Ɂw���o���x���j�ł���B
�@�A����������Ɂu�n�v�ƌď̂������̂ł͂Ȃ��A����I�蒐�w鰏��ڕ�q�فx�ł͍��c���˕��тɌ������˂��u���v�ƌĂ�Ă���B�����͑�^�ŕ��`�̍c��˂ł���B
�@�F����P�˂��u�����R�s�N���v�i�F����I�j�Ƃ��邱�Ƃ�����A�召�ɍS�炸�l�H�̃}�E���h��z����́u���v�ɊY�����邱�Ƃ�����B
�������̑�������R�R�▽�Ɂu���R�ו��A�n���e���A�ʈȎ����A�s�{�함�v�Ƃ��邱�Ƃ��Ȃĕ����傫���n���������Ƃ�����߂�������J���ł��邱�Ƃ͌����܂ł��Ȃ��B
���R���ċN��������u���v�ɔB�s�N���̎w���͕����傫�����Ƃ��Ӗ����Ȃ��B
�펯�ō���ȁu�n�v�������ď��������Ƃ����C���ł���B�f���n�����������̂ł���u���e���v�ƈ▽����K�v�͂Ȃ������傫���˂�����������ł͂Ȃ��B
�@�ތ���d�����^���ӌ���C���I�ɑ�ւƕ�������C�����펯�I�Ȃ��̂ł���B�u�V���n�v�v�́u�V�n���v�v�ɓ������A�V�ƒn�̑�����q�ׂ����ł͂Ȃ��B
�u�����Ӕ��v�u�S�g���v�u�������ȋ`�Őg�v���R��ł���B���▽���u���v�Ɓu�n�v�̍��ق�\���ʂ��Ƃ͌���ւ��Ȃ��B
�@鰐W�̓x�ʍt�ɏƂ炵�A�����̓��{�Ōa�S�]���́u�n�v�ɊY������͔̂����R�Õ����B��ł���B
���e�`�p �W�T
�p�F�_���R�Õ��͏������̌Õ����I�@�ږ�Ă̕�̑���₾�I
�`�F�_���R�Õ��͓��@�ɂ�蔺�o�╨�F���̂��߁A���u�����P����K1�̔N��Ō����B
�@K1��́A���@����������70�N��ɂ͋�������敶�ѐ_�b���i�j���j�̔N��ς��琼��250�N�O��̎w�WKVf�i�����ҔN�j�ƍl����ꂽ�B�Ζ삪���O�������q���Ŕږ�ęn���̈����ɓ��ꂽ�̂��A���̂悤�ȔN��ςɊ�Â����̂Ǝv����B
�@�������s���ɉ�����ݗ��n�̗l���ω��ɂ��Č������i�ނɂ�A���c���ʑт��珯�����s���̓��������ɑr�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��w�E�i���c1982�j�����B
�����I�ɓ���ƁA�v�Z���z�����m���ȍ~�������p�ݒn��Ɏc������ݒn�n�P���Ƃ̏ƍ�����AIIc���i�z���P���E��i�K���s�j�ɕҔN�����B�i�v�Z2006�j
�S���I�����ƍl������B
72�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:54:47.81
���e�`�p 86
�p�F�ږ�ęn�́u�n�v�Ƃ���̂����獂���ł���̂��I
�@�@���{�̌Õ��͕��R�ŁA�����Ȃ��I
�@�@�ږ�Ă̙n�͌Õ��ł͂Ȃ��̂��I
�`�F�`�n�c�˂��n�ł��邱�Ƃ�FAQ84�ɏq�ׂ��Ƃ���ł���B
�@�@鋎R�˕��u�̑��ʌX�Ίp�́A�}�s���ɉ����ē��{�̌Õ��Ƒ卷�Ȃ��B

���e�`�p 87
�p�F鰍c��̐��قɁu�A�d�����D����v�Ƃ₠��I
�@�@�u�D���v�́u�悫���́v�ƌP����̂���
�@�@�������̍����ɂ͂Ȃ�Ȃ��I
�`�F�����S���͋{���ۊǂ̍ɂŘd���ɂ͉ߑ�Ȑ��ʂƎv���A�s������G���ȋ��ӂ��w��������`��̑������i���}篈ꊇ���Y����ق��������i�ɑ��������Ǝv����B
�@�S���������̉��Ό��u�t�f�ב���n���X��v�ɓf�ׂ̔n�C�����v�]�ɑ���Бt���u��鰏V�`���~�������當�B����P���s�ߍ�毗�Y���v�ƋL�^����Ă���B
�@���́u��毗�v�͊������z�`�ɋL�^���鉺���i�u������毗�v�i�t�Ò��u�ӑєV�b��v�j�ɑ������A���z���v�����������i�i���c1970�j�ł���B
�@���̂悤�ɁA���Ȃ��Ƃ�����ɉ���鰒�̓��������͘`�l���̗v�]�ɉ��������̂Ɨ�������Ă����B
�@�܂��A���r�R�̗�������I(FAQ45)���A�`�l�̓����ɒ��ؐ��E������������ł���B
�@�����S�����`�l���̗v�]�ɉ����ē������ꂽ�ƍl���鍪���ƂȂ낤�B
���e�`�p 88
�p�F��������đO�����̌a�������L�^����͕̂s�����I
�`�F�����R�Õ����z���ߒ��ʼn~�u�Ɗ�d���݂̂̑O�������琬���Ă������������邱�Ƃ�FAQ 23�Ɋ��q�ł���B
�@�����l�����ݓr��̔����R�Õ������i����ڎ������ꍇ�A�����������������R�ʏォ��ڎ������ꍇ�A���Ɏ�̕��̑����镭�u�{�͉̂~�`�ƔF�������ł��낤�B�a�S�]���Ƃ����K�͔F���ɕs���R���͖����B
�@�܂��A�����ɉ��Ă��ːQ���x���ł͉~�`���u�̈�p�ɕ��`�̐Q�a���t������B���Ղ���ΑO����~�`�̓y�n���p�ł���A�����l���O����~���̉~�u�݂̂n�ƔF�����邱�Ƃɕs���R�ȗv�f�͎旧�Ăđ����Ȃ��B
�@�]�ˎ���̊G��Ɍ��ꂽ�����R�Õ��͂T�i�i�z�̉~���Ƃ��ĕ`�ʂ���Ă���A��~���̒i�z�`�ʂ����m�ł���ɂ��S�炸�O�����������B
�@�Q�l�F��a�����}��i�����O�N�j�w���҉��~�x
�@
�܂��͑��G���͏��I�W���Ɂu���E�L���`�V�u�A���`�H����v�ƋL���B
�@���̂悤�ɁA��~���݂̂����n�ƔF������邱�Ƃ�s���R�Ƃ��鍪���͊ł���B 73�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:55:10.22
���e�`�p 89
�p�F�u�E���v�Ƃ����ď̂͑�a����̑��݂��O�I
�@�@�@�R���I�ɑ�a���삪���݂����A�Ƃ����ȁI
�`�F�u���E�v�Ƃ����p�ꂪ�����Ƃ���A�u�E���v�Ƃ����ď̂͏���x�z��̒������ɑ����鉤���̒��ړI�e���̈�Ɨ����ł���B�V�c���̑��ۂƂ͖��W�ɒ�`�ł��悤�B
�R���I�̑O�����璆�t�ɂ����A���{���̗L�ׂȔ͈͂ɑS���I�ƌĂׂ鉤�����a�������Ƃ����F���ɉ��āA���̒����̈���u�E���v�Ə̂��Ďx��Ȃ��B
�{�e���v���[�g�ł́AFAQ4�Łu�E���v���u�T�˂Q���I���t���_�̋ߋE��u�l�����z��v�ƒ�`�����B
�@���}�ɁA�퐶�Ζ_�������ƋߋE�������̕��z���������B
�E�L�������Ό����z��́A��̍L�`�������ɒ������Ă���B
���āA�����̖퐶�����ƍݗ��̓ꕶ�I���_�������Z�������퐶�Ζ_��������
�E���̒��j���ׂ����p�𒆐S�Ƃ����ߋE�n�悪�ߋE��������
�E���������˓������`������
�E���ӂ��O����������
�ɕ��Ă���B
�@���̋ߋE���������̍X�ɒ��j���ߋE��u�l�����z��ƂȂ�B
�@�v�X�A�ɓs���̎����ŕ����������`���A�הn�䍑�A���n���A��z���ɑz�肳���̈�Ƃ��ėL�]�ł���B

���e�`�p 90
�p�F�`�l�`�͒Z���ʼn��߂��邵���Ȃ��I
�@�@�Z���ł����ꂽ��鰐W�̒����������ʼn��߂������ߍ��낪�������̂��I
�`�F�������{�������ł��Ȃ��P�ʂ�p���ĕ����グ�钩�b�͂��Ȃ��B
�����Đ����̓x�ʍt��p���Ȃ��̂͒�͂̔ے�ł���A���t�ɗނ���s�ׂł��낤�B
�ȉ��̂Ƃ���A鰂̍c��{�l�����������l�܂ŊF�ȘZ�ڈ���E�O�S���ꗢ�̐���ȒP�ʂ��g�p���Ă��邱�Ƃ����炩�ł���B
�u���c�E�����ˎl�ʕS���A�s���g���k�q���́v�i鰏��ږ����q�فj
�u�������ˁ@�R���O�S��\�O步�C���Z��Z�ځB�i�Í�����j
�u�ݗՕ����V��C���]���A�C���싎雒�z�\�ܗ��B
�@���錰�ߗˁC�R���O�S步�A������v�i�鉤���I�j
�@���u�Í�����v�W���^��@���^�͐W�b�鎞�̑���
�@���u�鉤���I�v�W�c���(215�`282)�ҁi���В����Œm����c�ᐓ�̑\���j
�i�n�c��n�j�u�����\�]��A��珌ܗ��]�v�i�W�����c�T�j
�u���ƔV���A�����S���B�ߐ��z�ו���c�y���Ԕn�Օ^���ׁv�i�c�T�j
�@���u�c�T�v�i鰕�����j 74�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:55:32.48
���e�`�p 91
�p�F�u�쎊�הn�㚠�v�́u���s�\���A���s�ꌎ�v�͋N�_���ѕ��S�Ȃ̂��I
�@�@�@�P�O���ŋ�B�k�݂ɗ����̂��I�@���Ƃ͗��H�Ȃ̂ŋ�B�����I
�`�F�哯�]�͌��Ɉʒu�������Y��蓂�Â܂ŁA�C�ې��H�������\�Ɋ�Â���1,561km�𐔂���B�z�肳��铖���̑D���Ɠ��Ǝ��Ԃ����Ă���A�����I�ɕs�\�ȓ����ł���B
�@����ɑ����Č����A1719�N�ɗ����������N�ʐM�g��s�́A�\�ۊ˂̋L�^�ɂ��A���R�o�`����{���܂ł����ł��U�O���ȏ���₵�Ă���B���R�𗧂��앗�ɑj�܂��e���ɒ┑���Ă�����ɂR�P���ڂ̖锼�ɍ��{�ނɓ��`���Ă���B
���e�`�p 9�Q
�p�F�w��鏎Z�o�x�Ɉꐡ�痢�@����������Ă���I
�@�@���͑�ɒZ�������݂������Ƃ͋^�����Ȃ��������I
�`�F�w��鏎Z�o�x�̐����͌㊿�㏉���܂ők��Ȃ��B���W��̋U��Ƃ�����ɂ����̐M�ߐ�������A�Z�����ݐ��̍������蓾�Ȃ��B
�@�����N��s���́w��鏎Z�o�x��[���ƁA�ꐡ�痢�@�̏��o�͌㊿���̓A���ɂ��w����x���ł��邪�A���w�I�Z�o�ł��V���w�I�l�@�ł��Ȃ��A�×��m���Ă����Z�s�z��i�n���j�ɉ�����y�\���Ɖ��E�痢�v�z�̗Z���ɉ߂��Ȃ��B
�w��鏎Z�o�x�͊����|���u�ɋL�ڂȂ��A���p�҂����炸�A�����͌㊿�㏉���܂ők��Ȃ��Ƃ����B����ʼn~�����ɂR���g���Ðق�����㊿���܂ł͉���Ȃ��ƍl�����Ă����B
���������J��263�N���_�ňꐡ�痢�Ɍ��y�����ۂ��u���H�v�Ƃ��ēA��������p����݂̂Łw��鏎Z�o�x�ɂ͐G��Ă��Ȃ��B����ē����̐����N��͍X�ɉ���\��������B
�@�܂��w��鏎Z�o�x���L�ڂ��鐔�l����v���n�_�̖k�܂��t�Z����ƁA���ꐫ���Ȃ��B���̂��Ƃ͓������قȂ�o�T���癗�ނ��J��Ԃ������A�ˋ�̑��萔�l��p���������Đ������Ă��邱�Ƃ������B
��\�l�ߋC�̓������i���A�k�Ɏl���̓�k�A�Ȃ�тɓ�\���h���V��x�@�ɂ��Ă͉ˋm�肵�Ă���B
�@�܂����ڕ\�i�����z��ʼnĎ��ڌܐ��ł��邱�Ƃ͍ĎO��������Ă���A�Ď��i���ژZ���͟u�s���̕t�߂ł��邱�Ƃ���������Ă���B
�@����Ď���i���ژZ���́A���ځF�ژZ����80���F16�����T�F�P�Ƃ����P���Ȑ�����ɂ��邽�߂̝s���ł������\���������Ƃ����悤�B
�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`�`
75�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/13(��) 12:56:10.36
�ȏ�e���v��
��������������������������������������������
���Ӂ��O�X�����I�����Ă��珑������ł��������B
�Ȃ��A�������݂�
�@�הn�䍑�E�����ɊW���L����
�@�����̂�����e�����肢���܂��B
�@�E�����ȊO�̓Ǝ�����P�ƂŊJ���邱�Ƃ͂��������������B
�@�O�X���I���ȑO�̏������݂͍r�炵�s�ׂƊŘ��Ē����܂��B
��������������������������������������������
�y�lj��E�ύX�_�z �Ȃ�
76���{�������j����2019/02/13(��) 12:58:15.15
�`�����X��
77���{�������j����2019/02/13(��) 14:55:13.16
�ɓs�����}�y�S�����ɂ������E�E�A
�ȂǂƁA�_���c�@�L�̃p�N��������������܂�����Ȃ��Ȃ�B
���������_���c�@�L���A��a����̎v�f�����ẴX�e�}�Ȃ̂��B
78���{�������j����2019/02/13(��) 14:57:51.37
�������܂�1��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�E�E�E�~
�������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�E�E�E��
79���{�������j����2019/02/13(��) 15:14:38.83
>>78
���������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�E�E�E��
�嗤�j���ŁA�����Ɠ����̓�d�\�L�������Ⴊ��Ȃ�����A���̓ǂݕ��͖��m�ɊԈႢ
���������A���n���s���Ǝהn�䍑�s�����܂����������\���Ȃ���A
�ݓ�痢�����s10���A���s�ꌎ�Ƃ���ƁA���n���s���̋����̋L�ڂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂�
��B���̓ǂݕ��͏�ɃC���`�L�ǂ݂� 80���{�������j����2019/02/13(��) 15:55:43.60
�L�i�C�R�V�̉�ꂽ���R�[�h�v���[���[���Ȃ���̍r�炵���ɕ��ꂽ�B
�Ԉ�������߂������̂����ɘA�Ă��邾���ŁA�E�����ɂ��ĉ����ؖ��ł��Ă��Ȃ��B
81���{�������j����2019/02/13(��) 15:58:20.10
>>914
�k����B�̓y��Ȃǂ���a�ŏo�Ă��Ȃ�����A�������R�͖����B
���́A�ߋE�͐_�b������ŁA��B�̓��s�ԕ����ȂǂƂ͏����Ⴄ�B
�n�����Ȃ����Ȃ��`�B 82���{�������j����2019/02/13(��) 16:01:57.93
�S�g����B�k���܂ŗ��Ă����̂ɁA�����ƌ𗬂����������E���͎הn�䍑�ƊW���Ȃ��Ƃ������Ƃ��ˁB
83�E�����Ɏ���2019/02/13(��) 16:05:57.36
�Z���̌@���������͏@�_�̋��قƂ�����A
�����s�s��������H
84���{�������j����2019/02/13(��) 16:06:56.82
>>903
�E�}�V�}�W���i�������j�̈Ӗ��ɉ������̂́A8���I�B
���Ԃ�����������A5���I������B
�����̐�c����a�����̑O�̎x�z�҂������Ƃ����̂́A�����̎����_�b�B
��������a�Ɍ����̂́A5���I�B
����ȑO�ɑ�a�ɂ����A�Ƃ����؋����Ȃ��B 85���{�������j����2019/02/13(��) 16:10:25.14
>>84
��㋌���{�I�����łȂ��A�L�I�ł��`�������_������ɑ�a�ɂ������ƂɂȂ��Ă���B 86���{�������j����2019/02/13(��) 16:13:19.61
>>82
���H
�k����B�͋E�������Ɉ��ݍ��܂�Ă��܂���ł���w 87���{�������j����2019/02/13(��) 16:14:05.11
>>85
���ꂪ�����̑c�悾�Ƃ����̂��A�g�t�����Ă��Ƃł��� 88���{�������j����2019/02/13(��) 16:16:02.73
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
89���{�������j����2019/02/13(��) 16:19:42.55
>>910
�Y�Ԃ͔̕�t���t���́A�z�P�m�̖��t���̂��ƂɌ����`���낤�ȁB 90���{�������j����2019/02/13(��) 16:23:10.70
>>83
�l���Z���Ղ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����B 91���{�������j����2019/02/13(��) 16:26:47.32
>>90
���l���Z���Ղ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����B
���������ŁA�n�㕔���ǂ��g���Ă����̂��A�l���Z��ł����̂��ǂ�����
���ׂ���@�������Ă��� 92���{�������j����2019/02/13(��) 16:35:20.28
>>90
���l���Z���Ղ��Ȃ��A�Ƃ������Ƃ�����B
�u�Ƃ������Ƃ�����v���āA�N�������Ă�́H 93���{�������j����2019/02/13(��) 16:41:58.69
>>82
���S�g����B�k���܂ŗ��Ă����̂ɁA�����ƌ𗬂����������E���͎הn�䍑�ƊW���Ȃ��Ƃ������Ƃ��ˁB
�E���l���k����B�ɗ��Ă����؋��������猩���Ă�
�ق��Ė������đf�m��ʊ�̒m����
�����ăV�����ƌ����Ɣ���
����Ȃ��Ƃ�����
���ꂪ��B�� 94���{�������j����2019/02/13(��) 16:46:03.48
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ������i鰎u�j
�E�������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
95���{�������j����2019/02/13(��) 16:55:24.31
>>92
���C���\���グ���܂��i���ɂ��e�͂��肢�\���グ��i�ɂ��A���e�͂��肢���܂��B 96���{�������j����2019/02/13(��) 16:55:39.79
97���{�������j����2019/02/13(��) 16:56:44.20
>>91
�������̂��������炢�����Ă��邾�낤�B 98���{�������j����2019/02/13(��) 16:59:17.60
>>85
�L�I��8���I������Ȃ��B 99���{�������j����2019/02/13(��) 16:59:36.97
>>79���{�������j����2019/02/13(��) 15:14:38.83
���嗤�j���ŁA�����Ɠ����̓�d�\�L�������Ⴊ��Ȃ�����A���̓ǂݕ��͖��m�ɊԈႢ
�嗤�ŊC��n��Ȃ�ĂȂ��Ƃ́A������������킯�͂Ȃ��B
�`�l�`�͒�������d�\�L�̋L����������B
���������A���n���s���Ǝהn�䍑�s���͂܂����������\���Ȃ���A���L�̔@���Ł��B
���������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s20���ŏ����̓��n���E�E�E��
���������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�E�E�E�� 100���{�������j����2019/02/13(��) 17:01:04.98
>>91
���������Ȃ̂Ɂc
�Ƃ̂��Ƃł��邪�A�������Ȃ̂ɏZ��ł����Ƃ́A���ꂢ���ɁB 101���{�������j����2019/02/13(��) 17:07:49.46
>>97
���܂��̔]�͂�����Ɠ����ĂȂ��� 102��90�x��]����2019/02/13(��) 17:17:23.50
㕌��̗�̎O�A�ŕ��Ɉ͂܂ꂽ�������ږ�Ă̋��ق��Ȃ�āA�����N�ɂ�������Ȃ���B
�����A㕌���т̂ق�̈ꕔ���@���������ł���Ȃ̂��o�Ă�������A
���͓c��ڂƂ��Z��ɂȂ��Ă�����ӈ�т̓y�n�ɂ́A���R�����Ƃ��낢�떄�܂��ĂāA
�����͒������̓s�s�v��́w���n�I�Ȗ͕�x�ɂ�茚������Ă���̂��낤�Ƃ������Ƃ��A
�����̔��@�ς����Q���������Ă���B
�������̓s�s�v��ƁA�������̐��E�ρi�V�~�n���j�ɂ��O����~���B�����ē����̏��łƋ��̔Еz�B
������㕌��̂��̕ӂ肪�A�����̘`���̒��ɂ����Ē���������e�̃Z���^�[�ł��������Ƃ������Ă���B
����܂���w�e鰘`���x�̋���̍s������A���ʂɍl����ᓯ���Ƃ��ł��傤�ƁB
103���{�������j����2019/02/13(��) 17:19:58.93
>>170
�������������̂͌i�s�剤�ł��ˁB
�Ō�̃��C���f�B�b�V���𑧎q�Ɏ���Č��{���܂���������
�i�s�̏��I�`���ł́A�R�����̃T�o����o�����āA�}���t�߂ɊM�����Ă��܂�����A
�����炭�A�ނ́A��B�`�����̈��������̏��R�I�n�ʁB 104���{�������j����2019/02/13(��) 17:22:26.43
>>103
���i�s�̏��I�`���ł́A�R�����̃T�o����o�����āA�}���t�߂ɊM�����Ă��܂�����A
�؋��́H 105���{�������j����2019/02/13(��) 17:25:02.18
>>99
����S���������@�ݓ���P����͝Ӛ��A��z���̌�ɏ����Ă邩��
�]�������Ă��Ȃ� 106���{�������j����2019/02/13(��) 17:29:03.54
>>105
������S���������@�ݓ���P����͝Ӛ��A��z���̌�ɏ����Ă邩��
���]�������Ă��Ȃ�
������A�u�ݓ���P���v�͏������܂ł̒��������B�@�v�����ł͂Ȃ��Ƃ������Ɓ@�ƁA���x������w�@�@�����g 107���{�������j����2019/02/13(��) 17:29:26.85
>>171
����13km�Ȃ̂ŁA�o�R���O�\���Ƃ����\���͑Ó��B��
�C����756m��x�s����v�����A�Ƃ����_���C���`�L�B
�ܘ_�A�O�p���ʂ��o����̂�����A�u���v�́u�o�R���v�ł͂Ȃ��B 108���{�������j����2019/02/13(��) 17:32:22.20
>>103
��͂͂͂́B
�i�s�́A�}�����ʂ֊ό����s����܂��ɁA��a������Ƌ{��ʼn̉r���Ă邩��l�B
�}��ʉ߂́A�ږ�Ă̓s�A�R��̐�Ղ��ό����s���邽�߂̂��́B
���̂��ƁA�����͂����a�A���Ă���ł���B 109���{�������j����2019/02/13(��) 17:36:44.73
>>108
��͂͂͂́B
�i�s�́A�`���i���g�j����o�Ă��Ȃ���B�@�`���i���g�j�����̌�����ʂ֍s�K���������B�@�c�O�B�@�@�@�����g 110���{�������j����2019/02/13(��) 17:38:09.06
>>177
����鰑�ɂ͎g���Ă����̂��H�A�u�P�����P�ځv�ł͂Ȃ������̂��H�A
�����ł������̂ł���A��
������Ȗ��͂Ȃ�
�u�P�����P�ځv�ȂǂƎ�v���Ă�͖̂��m�ȑf�l����������l�����灃
鰎u�Ȃǂɏ����ꂽ�u���v�̋����L�^�̎j�����Ԃ���́A�A�[�I���_�B 111��90�x��]����2019/02/13(��) 17:39:17.40
鰎u�`�l�`�́A�����i�����j�ɂ��Ă͑債�����x�ȂȂ����āB
���ɋ�؍������́A1000���A500���A100���̂�����3�p�^�[���B
1000���F�܂��܂������B
500���F������Ɖ����B
100���F�����߂��B
���̒��x�̂���B�ׂ��������Z�����Z���āA�ǂ���������J�E���g���Ďc�艽���Ƃ��A����Ȍv�Z�ɂ͑S�R�Ӗ����Ȃ��̂�B
112���{�������j����2019/02/13(��) 17:41:27.69
>>105
�]�������Ă�̂́u���s20���v�Ɓu���s10�����s�ꌎ�v�̑O�ɏ�����Ă���s�����������B
1����痢�͂��̍s���̂������ƂɂȂ��������B 113���{�������j����2019/02/13(��) 17:42:17.19
>>111
�܂��A�����������Ƃ��B�@�@������A�u�ݓ���P���v�͏������܂ł̒��������B�@�@�@�@�����g 114���{�������j����2019/02/13(��) 17:47:59.87
�R��̓`���ł͌i�s�V�c�ɋ��͂����̂��F�×ǕP��
�K�ƉF�Òn�������邩��
���}�g�������R��i���}�g�j�n��������O�͉F�Â��낤
115���{�������j����2019/02/13(��) 17:48:00.44
>>180
���u���O�\���v�́u�o���O�\���v�̗��ƍl����̂��������ȁB��
�u���v���u�o��H�v���Ƌȉ����鎖���A�C���`�L�B
�܂��A�W���Q�O�O�O���ȏ�̓Ɨ����I���R�ł��邩��A
���Ȃ艓���̕W���̒Ⴂ�i�O�p���ʂ��o����j�n�͒T��������ł�����A
�u��x�s�v�Ƃ����悤�ȍ��n����̌v�������鎖���̂��C���`�L�B 116���{�������j����2019/02/13(��) 17:49:20.31
�A�z��B���̌��������Č��ǂ��蓾�Ȃ��s���̃o�J�ǂ݂ƁA���{���ɂ��郄�}�g�̒n������B�ɂ�����I������
���x���m����Ȃ�
117���{�������j����2019/02/13(��) 17:53:06.64
>>185
���������n�Ǝڐ��n�Ƃ̊��Z���߂ł���n�c��́u�P�����U�ځv���A
鰑�ɂ͎g���Ă����̂��H�A��
���g���Ă����� �����镶��������������Ă��遃
��ʊw�҂�̒��ɂ́A�g���Ă������m�������悤�����A
鰒���W���̖�l��́A�S���g���Ă��Ȃ������B 118���{�������j����2019/02/13(��) 17:55:37.27
>>87
�Ⴄ�X�^���X�ŏ����ꂽ�ʂ̎j�����������Ƃ��L�ڂ��Ă���B
��t�����Ƃ����Ȃ�A���̍����������Ȃ��ƁB 119���{�������j����2019/02/13(��) 17:56:33.54
>>91
���������̒��Ŏϐ����͊�{�I�ɂ��Ȃ��B
�䏊���g�C�����Ȃ������Ő����͂ł��Ȃ��B 120���{�������j����2019/02/13(��) 17:58:14.39
>>186
����鰒��̂P���́A�V�U�D�T���ʂ�����A
�P�T�O�O���ł��P�P�T�����ʂɂȂ��āA��B�̎��܂邪�A
����ȑO�ɁA�s�\�����ݓ��]�����قڏI����Ă��邩��A
�n�߂����B�Ɏ��܂��Ă��āA�����p���́~�B��
�����Ƃ���Ƃǂ����Ă� �v�Z���m�����̓��ɂȂ�Ȃ��Ȃ�@��B���͔j�]����ˁ�
��m�����V���́A�قڋ�B���t�߂ł��邩��A��B�ڂ͔j�]���Ȃ����A
��B�����j�]����A�Ǝ咣�����Ȃ�A
��a���͓����ɂ����Ɣj�]����B 121���{�������j����2019/02/13(��) 17:59:05.42
>>93
���E���l���k����B�ɗ��Ă����؋��������猩���Ă�
���s�ɏ����ɗ��Ă��������B
>>102
��������㕌��̂��̕ӂ肪�A�����̘`���̒��ɂ����Ē���������e�̃Z���^�[�ł��������Ƃ������Ă���B
��B�ɔ�ׂ�ƁA�嗤�����̍��Ղ��������R�����B
�S��������y����A�����͂��납�y�Q�ѕ��̍��Ղ���Ȃ��B 122���{�������j����2019/02/13(��) 17:59:30.33
�܂�ϐ����Ȃǂ𑼏��ł���Ď����Ă��鍂�M�Ȑl�Ԃ̏Z���ƌ���������
�`�l�`�̋L�q�ʂ肾��
123���{�������j����2019/02/13(��) 18:01:10.20
�Z���͍��J�Ƌ{��Ƃ��Ă̏ꏊ�������
�����̏Z�ޏZ���Ղł�
���d�������鐶�Y�n�ł�
�f�Ղ����邽�߂̎s��ł��Ȃ�
���J�ƍ��M�Ȑl�Ԃ̏Z���Ƃ��ē������ėނ��݂Ȃ��قNj��剻���Ă�����قȏꏊ�ƌ���������
124���{�������j����2019/02/13(��) 18:02:35.80
�t�ɋ�B�ɂ͋{����܂Ƃ��ȍ��J�Ղ��Ȃ�
����̂͏����̏Z���Ɛ��Y�̐�
�ނ��낱���ɘ`���Ȃ�Ă��Ȃ��̂��������
125���{�������j����2019/02/13(��) 18:05:28.06
��B�Ō�������J�ՂƂ��͒���{���Ă������̃`���P�ȕ��`���a�悾���������
�Ⴕ���͏������s�����K�͂Ȗ��ԍ��J
���J���Ƃ��Ă̐��i�����Ɩ��L����Ă�ږ�Ă̎p�Ɉ���Y�����Ȃ���
126���{�������j����2019/02/13(��) 18:06:42.13
>>107
��x�s�̊C����756m�Ƃ����̂́A�����B
��x�s�̊C����756m�łȂ��Ƃ����̂Ȃ�A�����[�g���Ȃ̂������o���ă`���B
���n�̗��z�s�̊C����151m�B
���z�̖k�ɂ����x�s��������ɖk�̑����s�̊C�����A814m�B
���̑����s�̂قƂ�ǂ͊C��1000m�ȏ�̋u�ˁB
�C���`�L�����āB
��͂͂͂́B
����̐������C���L�`���킢�B 127���{�������j����2019/02/13(��) 18:10:20.06
��B���̂ق����ږ�Ă̍��ՂȂ�ċ�B�ɂ́u�F���v�ƌ����Ă����̂��������
���ǂ��̍s�����悪�u�s���̂��蓾�Ȃ��o�J�ǂ݁v�u���{���ɂ��郄�}�g�̒n������B�ɂ�����v�Ƃ������]�݂��̑���Ȃ���\�l�^
����ᓪ�ǂ������Ă�z�������Ȃ���
128���{�������j����2019/02/13(��) 18:10:46.50
�g�샖���݂����Ȋ��W�����`�l�`�ɂ���ږ�Ă̋{��ɂ҂����肾�ƌ����Ă��܂��������
��B���̍��\�t�̎����\��Ă���
129���{�������j����2019/02/13(��) 18:13:18.39
>>123
���M�Ȃ��������理�т����A�Ƃ̂������B 130���{�������j����2019/02/13(��) 18:14:07.15
�L�`�K�C��B���̃T���x�肪���������Ɉ���
131���{�������j����2019/02/13(��) 18:16:47.43
>>128
�g�샖���ɂ́A�Փa�̋߂��ɒG�����Z����1�����邩��Ȃ��B
���Ȃ��Ƃ��A�g�샖���������������A���̖k���s�ɐl���Z��ł����Ƃ��鍪���͂���B 132���{�������j����2019/02/13(��) 18:20:22.83
�G�����Z���ɏZ��ł��`���l����
�`�l�`�̋L�q�Ɣ��o�����v���Ȃ���
���͋�B��
�K���ɍi��o�����������G���Z���ꌬ�Ɨ�������
133���{�������j����2019/02/13(��) 18:20:50.55
>>130
�A�z���Ⴄ�B
���C�̗��т�H�ׂ悤�Ǝv���A�d���l�̂��鐆���ꂩ��100m�ȓ��ɏZ�����Ȃ����Ȃ��B
�Z���̑�^�����̋߂��ɂ��̐����ꂪ�������̂��B
�����ɘd���l���Z��ł����̂��B
����́A�A�z���Ⴄ�B 134���{�������j����2019/02/13(��) 18:22:06.87
�����Ď����o���ꌬ�̒G���Z��
135���{�������j����2019/02/13(��) 18:23:26.30
�ق�I��`���l���G���Z���ɏZ��ł�I
�ꌬ����������������ԈႢ�Ȃ��I
�ō��߂��Ď��ɂ�����
136���{�������j����2019/02/13(��) 18:25:33.53
��i�n��Ǝ咣������ɂ͒G�����Z���D������Ȃ�
137���{�������j����2019/02/13(��) 18:25:43.70
>>102
�_���_���B
��^�����͂�����肵�������n�ɂ����āA���̎��͂͒J���n�B
����Ȕ����n����������ɕ����ɂ���A���̎��͂��J���n�B
�����L�����n�Ȃ�āA�Z���ɂ͂Ȃ��B
������A���̌�A���������]�T�̂��铌���֑�^�������ڂ����Ƒz�肵�Ă�̂���B 138���{�������j����2019/02/13(��) 18:25:46.04
����ς薜�t�W�̂��̉̂ɌÑ�j�͋Ïk����Ă���
�^�\�� �ƌ��� �y���z���T �y�_�z���B�� �y�V�Áz���y���z
�܂����A�Ƃ�ׂ������A���}�́A�_���B����A�V������
�Ƃ�͂��̌����A�����_���B���Ă���̂ł��傤���B����Ƃ��V�̖����B���Ă���̂ł��傤���B
�u�܂����v�́A�����h�ȋ��Ƃ����悤�ȈӖ��ł��B���̉̂ł́A��������(�܂��炱�Ƃ�)�Ƃ��Ďg���Ă��܂��B
139���{�������j����2019/02/13(��) 18:26:40.88
��͉�
������f�������_
�����̖h�q���_�A��
�։�`����`�b��`�ɉ�`�G��`�߉�i���g�j�`����i�]��j�`�p�� �i�d���j
�`���嗐�O�A��ň͂܂ꂽ��������Ă����\��������
�Ñ�ɂ����āA�ޏ��͕��c�ƃZ�b�g
�R���ɐ��s����ޏ��̈�R�̏��ւ��������Ă���
�܂����Ɏh�����ޏ��̏��ւ��������Ă���
�������[���̂́A�y��z�Ɓy���z�̊W��
�ɐ��ÕF�A���̖��́y���z�ʖ�
�ɐ��ÕF�͈ɉ�Ɂy�̏�z������Ă����Ƃ����`��������
�ɉ�ȊO�̉���y���ʁz�ƊW�����邩������Ȃ�
�����ʐ_�Ɖ����W������̂��낤���H
���ː_�A���H�ÕF�A���H�ÕP
�P�ˎl�_
�����̐_�X�Ƃ̊W���C�ɂȂ�
140���{�������j����2019/02/13(��) 18:28:22.78
4���I�̏H�È��
�ɐ��_�{�ƍ�肪���������Q
���ꉽ�̈�Ղ���
�������ň͂܂�Ă��銄�ɂ́A���n�I�ɖh�q�Ɍ����Ȃ��ꏊ����
�P�ɓZ���_�Ђ��߂��ɂ�����
��Ȃ��̂����Ɠ����ɁA��Ȃ��̂������Ȃ��悤�ɂ��Ă������Ɋ������
141���{�������j����2019/02/13(��) 18:28:27.11
>>99
�����������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s20���ŏ����̓��n���E�E�E��
�����������܂�1��2�痢�B������]�������ΐ��s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑�E�E�E��
�܂�A�ݓ�痢�͌��ǂǂ����w���Ă��Ȃ����Ă��Ƃ��Ȃ���
���ɗ����Ă⃓�̂� 142���{�������j����2019/02/13(��) 18:28:38.22
���J�ՁF����{���Ă������̕��B���͂ǂ������ԃ��x���̏W�����J
�{�a�ՁF�e���`������܂���
���͈̑�Ȃ���B�l��
�ږ�Ă̍��Ղ��炯����Ȃ���
���܂����Ȃ��E�E�E
143���{�������j����2019/02/13(��) 18:29:08.79
>>136
��a�݂����ȒG�����Z���������̂��낤���B
�@�����Ē������́A�������Ă����q�ɁB
�q�ɂɐl�Ԃ��Z�ނ���B
�l�����番���邾��B 144���{�������j����2019/02/13(��) 18:31:59.88
���A���x�͒G���Z���̋K�̝͂s���n�߂����H
�ŁH����ȋ���ȒG���Z�����ǂ��Ɍ��������́H
���[������
��B�������ӂ́u�������炢���ȁv���u�������I�v�ɂ���ւ��A����
���͔]�̕a�C�̋�B����
145���{�������j����2019/02/13(��) 18:32:20.87
>>119
�����������̒��Ŏϐ����͊�{�I�ɂ��Ȃ��B
���䏊���g�C�����Ȃ������Ő����͂ł��Ȃ��B
>>119�̂����u�����v���ĉ��H
�Q�c��������A�Վ���������A�Q���肷��̂͐�������Ȃ��́H 146���{�������j����2019/02/13(��) 18:33:19.15
>>132
�l�ԗl�̏Z�ޏZ�����G�����Ȃ̂ɁA������Ă����@�����Ē������ɂ��̐l�ԗl���Z�ނ킯�Ȃ����낪�B
�A�z���Ⴄ�B 147���{�������j����2019/02/13(��) 18:34:21.91
�{�a���x���̋���G���Z������
����Ȃ��̂��������琦����˂�
����Ȃ��̂�����������ɂ����˂�
��������Ȃ�����Ȃ���
148���{�������j����2019/02/13(��) 18:35:01.68
>>131�A>>132
�g�샖���̖k���u�悪�A�`�ʓy�������̕���Ă����\���͂ǂꂭ�炢���邩�ȁH 149���{�������j����2019/02/13(��) 18:38:42.86
>>144
�A�z���Ⴄ�B
���̐��E���ł��A�@�����Ē������ɏZ��ł�̂́A�^���̑�������A�W�A�̐��c�n�т����B
���Ƃ݂͂ȁA�n�ʂɉƌ��ĂďZ��ł�́B
���{�����C������̂ŁA���������n�ʂ���グ�Ă��邾���B
���ʂɁA���E�̐l���͒n�ʈʒu�ɏZ��ł���̂��B
�킴�킴���݂����ɍ����Ƃ���ɏZ�ނ���B
�ȂɁH�@����͌@�����Ē������ɉ��݂��ɏZ��ł�Ƃ����̂��B
��͂͂͂͂́B 150���{�������j����2019/02/13(��) 18:40:41.69
�G�����Z�����Č�����Ί펞�ォ��̏Z�����悗
151���{�������j����2019/02/13(��) 18:41:00.45
>>142
�����J�ՁF����{���Ă������̕��B���͂ǂ������ԃ��x���̏W�����J
�k���u��{�����̉�����ɁA�K���ƌĂ�鏬���Ȍ��������邩��A�����܂ō��J�Ղɂ��Ă�����
���́u���u��{������̑和�{���̉�����̏������v�̃Z�b�g��������Ղ�5����A1����Ō����邩��
�k����B�̕�����J�̒�^�Ȃ̂��Ǝv��
�O����~���ɂ͂܂������e����^���Ă��Ȃ�����ǂ� 152���{�������j����2019/02/13(��) 18:42:33.65
�ߋE�n���ł͕�������ɂ͂قƂ�ǂ����n�Z���ֈڍs�����Ƃ����
153���{�������j����2019/02/13(��) 18:42:41.44
�����炳
��B���l�̌���
�u����ȋ{�a�̂悤�ȒG���Z���v���ǂ��ɂ����ł����[�H
����{���Ă������̍��J�Ղ��ږ�Ă̏؋��Ȃ�ł����[�H
�ǂ��ɂȂɂ������ł����[�H
154���{�������j����2019/02/13(��) 18:45:06.94
�G���{�a��
155���{�������j����2019/02/13(��) 18:46:31.41
>>187
����鰒��̂P���́A�V�U�D�T���ʂ�����A��
�����ꂪ�E�\�Ȃ���ǂ����悤���Ȃ��� ��B���͒Z�������������Ȃ���
����A�ܘ_鰎u�̈ʒu�����������ł���j�]���Ȃ����A
���{�I�ɂ́A�ŏI�I�ȑ�����������������v�`���`�́A
�u���k�ڕS�Z�A���k��V���v�ɋ����āA
�`���̒��S�{�̂��k����B�ɂ���A
�Ƃ���Ă��鎖���A�ő�̍����B 156���{�������j����2019/02/13(��) 18:46:42.99
�ƌ�������B���̔]�����ƒ��̂��錚���͎ϐ������o���Ȃ��炵����
���Ⴀ�Ȃɂ��H
�]�ˎ���̐l�ԂƂ�������ѐH���ĂȂ�������
�ޗǎ���Ƃ��̓s�ɔт����ꏊ�����������v
�������o�J���o�J���v���Ă��������܂Ńo�J�������Ƃ�
157���{�������j����2019/02/13(��) 18:53:33.81
>>141
�Ȃ��Ȃ�����͂ɗD��Ă���悤���ȁB�ق�A�ڍ��߂��B
�`�l�`�̑S�̗����i�ѕ��S�`�������j�F 1��2000�]���i����̓�q�̉����Ƃ������p������p�j
�i���ۂ̓���j
�ѕ��S�`�i���s�j�`��؍��i7000�]���j
��؍��`�i�n�C���s�j�`��ḍ��i3000�]���j
��ḍ��`�i���s�j�`�������i2000�]���j
��ḍ��̍`�i���Áj�́A���Y��͌������4�q�k�サ�������̒ÁB
���엤�s500���œ���ɓs���́A�������莛�̂�i�Ɏ��j��\�B
���s100���Ŏ���s�\���́A����O���S�i�\���S�j�̋g��P����сB
���̋g�샖���̓���ɁA���n���i���s�s�s���j����A
�i�����A�����܂ł̍��ݓ������s��������v�Ē[�I�Ɍ��������j���s20���Ȃ�B
����������Ɏהn�䍑�����V���s�i1400���E���F�{�j����A
�i�����A�����܂ł̍��ݓ������s��������v�Ē[�I�ɉ]�������j���s10���Ɨ��s1���Ȃ�B 158���{�������j����2019/02/13(��) 18:54:20.71
>>131
���g�샖���ɂ́A�Փa�̋߂��ɒG�����Z����1�����邩��Ȃ��B
�����Ȃ��Ƃ��A�g�샖���������������A���̖k���s�ɐl���Z��ł����Ƃ��鍪���͂���B
�g�샖���̍Փa�߂��̒G���Z�����Ă���̂��ƁH

�����ɉ����Z��ł��āA�����Ŏϐ��������Ă����A�ƁH 159���{�������j����2019/02/13(��) 18:56:07.41
>>157
�ɓs���̎��_�Ńf�^����
���肵�đ����� 160���{�������j����2019/02/13(��) 18:56:40.92
�����������Ɏ������Ă��܂��ɂ͋g��P���Ƃ������o�����悗
�g��P���͒����̉��悪�W�c��n�����ɂȂ��Č��͎҂Ȃ�Ă��̂����ނ��Ă�l�q��������
��`���̋���Ƃ��킹��
161���{�������j����2019/02/13(��) 18:57:07.99
㕌��̔ږ�Ă͉���H���A�g�C���ɂ��s���Ȃ������킯���B
�����āA鰎u�`�l�`�ɂ���悤�ȘO�t���Ȃ���ΐ�l�̉����������������Ȃ��B
�E�����Ƃ͖{���Ƀ}�k�P���B
162���{�������j����2019/02/13(��) 18:58:10.33
>>194
�������������ɃY�{�����đ��삵�āA������㑱�̒�����ɋ����ăo����A
��Ȃ����灃
���؋�����H��
���݂́u�u�x�v�����ł̎n���B
������Ŏ��Y�ɂȂ����l�͒N�H��
�E���Ӗ���s�����x���ƔF�߂�ꂽ��A�~�i����ق��L�蓾�邪�A
���Ǝx�z���������悤�Ȕ��t�����F�߂���A�ɌY���L�蓾��B 163���{�������j����2019/02/13(��) 18:58:42.80
>>141
�Ȃ���O���ꂩ����F�{�ւȂ̂��A�lj��̐������B
�������A�`�n�ɂ͒����������g����قǂ̋��卑���������B
�����܂ł��Ȃ��A�����p�݂������n�ɂ����z���i�ߍ��j�ł������B
���̌�A�ѕ��S��206�`210�N����ɂȂ��Ă���ƊJ���ꂽ�̂ŁA
�`�n�i�o����ɂ́A�z���łȂ��ʂ̘`�������͂Ǝ�����ԕK�v���������B
�����Ŗڂ�t�����̂��A��O�E���̐��͂ŁA�`�l�`�ɉ]��������̈ɓs���ƁA���̎R���e�r����ɂ������הn�䍑�������̂ł��낤�B
���̂悤�ɍl����A
�Ȃ��A�����Гc�ɂ�������ḍ����Y�֏㗤���A���őO�s���l�������Ȃ��������������āA
�Ђ�����Ɠ���̍��ꕽ��֔����Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��������A���̗��R�������ł���ł��낤�B 164���{�������j����2019/02/13(��) 19:00:58.27
>>157
����ḍ��̍`�i���Áj�́A���Y��͌������4�q�k�サ�������̒ÁB
�����엤�s500���œ���ɓs���́A�������莛�̂�i�Ɏ��j��\�B
�����s100���Ŏ���s�\���́A����O���S�i�\���S�j�̋g��P����сB
�����̋g�샖���̓���ɁA���n���i���s�s�s���j����A
���i�����A�����܂ł̍��ݓ������s��������v�Ē[�I�Ɍ��������j���s20���Ȃ�B
�Ԃɗ��s�����܂�܂����Ă���̂ɁA�v��Ɛ��s20���ɂȂ�H
�f�^�����������܂ōs���ƁA�m�\�������K�v�Ȃ�Ȃ����H 165���{�������j����2019/02/13(��) 19:01:26.30
�g�샖�����הn�䍑�Ƃ��������Ă���̂͋E������������B
����͋�B�k���̓T�^�I�Ȋ��W���̃T���v���B
�����A�̂��錚���̂����ׂŎϐ��������ĐH��������邱�Ƃ͂ł���B
�ɐ��_�{�Ȃǂ̐_�����A�Ñ�̌��͎҂ւ̕�d�̗l�q������ɓ`���Ă���̂��낤�ˁB
166���{�������j����2019/02/13(��) 19:02:26.20
�ږ�Ă͔썑�̎R��̏o�g�ŁA��ɎR��͗L���C�Ɍ������Ċg�傷��}���Ɉ��ݍ��܂�Ē}��ƂȂ�B
����ɂ��썑�͔�O�Ɣ��ɕ���B
�ږ�Ă͂���܂ł̈ɓs���������p�����邽�߂ɓs�ł���ɓs�ɍs���A�`���S�̂������B
���ɓG�ΓI�������ɓs���k�̍��X�͈�呲��C�����ĊĎ������B
�ږ�Ă͎���ɓs�̕�����Ղɑ���ꂽ�B
�`���͒}���𒆐S�ɁA�썑�A�L���A�C��n��o�_�A�z�Ȃǂ���\�������A�����Ƃł���B
�Â��͏o�_�����̖���ł��������A������ȍ~�͒}��������ƂȂ����B
�܂��A�����Ƃ̌��Ղ͈�т��Ē}�����Ɛ肵�Ă����B
�}���̓��Ɍ��E����ӂ̐��͂́A�Δn�C���̌��v��Ɛ肵�ė͂����A�C�l�̍��A�V�Í��ƌĂ�A���̉����͓V�Ð_�Ƃ��ċ�B��{�B�̉����ł��鍑�Ð_�Ƌ�ʂ��ꂽ�B
167���{�������j����2019/02/13(��) 19:02:41.52
���ǃL�`�K�C�L���E�V���E�Z�c�̊����u��̘_���v�Ƃ��̓o�J�ۏo���̍s���̝s�������ƌ�����
168���{�������j����2019/02/13(��) 19:02:52.85
>>160
���g��P���͒����̉��悪�W�c��n�����ɂȂ��Č��͎҂Ȃ�Ă��̂����ނ��Ă�l�q��������
�����A���u���12���閄����̂̂����A�����̈���ʊi��������Ă��邩��A
���̒����̈�l�͂���Ȃ�̌��͎҂������Ǝv���� 169���{�������j����2019/02/13(��) 19:03:42.31
�y��z���z
��z�����̖��O�͔ږ�|�ĂƂ����A�ږ�ĂƉZ��ł���B
�ږ�ĂƂ͂��Ƃ��s�a�ł���Ƃ���B
�`���嗐�͘`���̉��ʂ��߂��鑈���̂��Ƃł���B
��B�ŏo�y���������i�̕��z�n�}
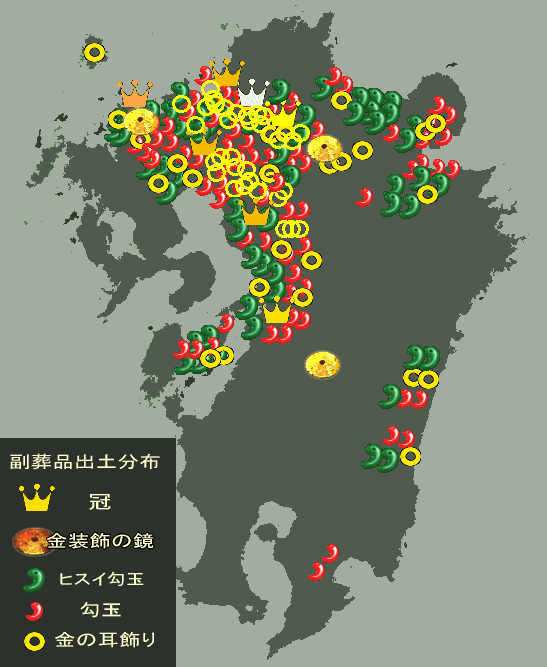
��z���i�F�{�j�����͔ږ�ĂƋ߂�����̓����������ł���A�ږ�ċ������߂����Ĕ����Ă��������ł���B
��L�̒n�}�͎הn�䍑�Ƌ�z��(�F�{)�����킹����B�k���̍��A�`���̒����������Ă���B
���̂��Ƃ���A��z���Ǝהn�䍑�͋߉��W�ł���Ɛ��@�����B
�ږ�ĖS����̑����́A��z�����}���ɍU�ߏ�������̂ł���ƍl�����邪�A���o�̋����ɂ�肱�ꂪ���܂����Ƃ������Ƃ́A��z�����[���̂����l���ł������Ƃ������Ƃ��B
��z���F�P�͎הn�䍑�̓�A�F�{�̐��͂ł��邪�A�����I�ɂ͔썑�̉��Ƃł���A��O�͏�̃��h�P�ł���ΌF�P�̕P�ł�����̂ŋ�z���̔[���̂����l���ł������B
�܂��A�ږ�Ă��}��R��̏o�g�ł���Ȃ�A�}����{���͔썑�̈ꕔ�ɒ}�����c�����Ē���o���������ł���̂ŁA�ږ�Ăƃ��h�P�������ł���B
���o���玌|�̔܂ł���u��̊C�_�̖��ł���L�ʕP�ɔ�肵�Ȃ��킯�́A�L�ʕP�ł͋�z���Ƃ̑��������߂闧��ɂȂ�Ȃ�����ł���B
�㐢�ɂ͔�O�̃��h�P�͖L�ʕP�ɏK������Ă��܂����A�{���͕ʐl�ł���B
�玌|�Ɛ_���c�@�͓V�Ð_�ł���}�����ƁA�ږ�ĂƔږ�|�Ăƚ��o�͔썑���ƁA�ȒÌ��_�ƖL�ʕP�͖L�����Ƃɑ����Ă���B
��������A�����Ƃł���`�����\�����钆�S�I�ȉ����ł���B 170���{�������j����2019/02/13(��) 19:05:42.77
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
171���{�������j����2019/02/13(��) 19:06:52.90
>>160
�g�샖���́A�`���嗐����̐퓬�p�̑��B
�v����ɗL���ɗ��Ă����������������B�ϐ�������ς������낤�B
�����̉��s�́A���̓��̖ڒB���i�ʓy���j�������̂���B���͎��q�����Ԓn�Ǝs�X�n�ɉ����Ă邯�ǂȁB
�����͋�����E�O���S�ŁA�`�l�`�̕s�\���������Ƃ���B 172���{�������j����2019/02/13(��) 19:08:45.95
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
173���{�������j����2019/02/13(��) 19:13:13.87
>>199
��������₷�������j�ɂ�������{�E�E�E�ƌ������������Ă���
�ŏ������B������B�����������͔��o�����ɂȂ�
�הn�䍑����a����ƌ����̂����� ��
���̒j�́A�����j�̗������������Ⓜ��v���A
���{���͘`���̕ʎ�̋������v�ł����āA�Ⴄ���ł������A
�Ƃ���������������B���Đ��Ԃ̐l�X���x�����A�Ƃ��Ă��鍼�\�t�ł��邩��A
�����ł���B 174���{�������j����2019/02/13(��) 19:16:39.98
>>164
>�Ԃɗ��s�����܂�܂����Ă���̂ɁA�v��Ɛ��s20���ɂȂ�H
�Ȃ��Ȃ��s���ł͂Ȃ����B
�Ԃɗ��s�����܂�܂����Ă���̂ŁA�ڂ�����������Ƃ�₱�����Ȃ邩�炱���A
���������Ă�킯���B
���n���̏ꍇ�́A���s10���ŏ��Y�E���Hḍ����A��������X�ɑD�ŋ�B���݂�����A
�F������������āA�{�萼�s�܂őD�Œ��s10���A���v20���������B
�ŁA��₱�����Ȃ邩��A���������Đ��s20���Ƃ����̂���B 175���{�������j����2019/02/13(��) 19:16:42.14
�����j��Ƃ��Ă���B������B�����������݂��Ȃ��̂��悭�������
��\��B���͂�������Ȃ��ϑz����銫���U�炷����
176���{�������j����2019/02/13(��) 19:24:51.70
>>206
�����菼�V��䗞@�͖w�Ǔ�����̐l�Ԃł���A
�菼�V�́A䗞@�́u�הn�i���v��u����v��m���Ă������ɂȂ�B��
���Ȃ邾�낤��
������u�����v�Ƃ����������t���g���Ă��璍�߂������Ȃ�����
���������ۂ͒��߂Ȃǖ��� �܂�`�l�`�ɂ́u�����v�ȂǂƂ͏�����Ă��Ȃ�����
�����������Ƃ��� ��
�Ȃ��ˁB
�菼�V�́A�㊿���́u��m����v�Ȃ�āA
�P�Ȃ�A�z�j�Ƃ́u���ȉ��߂ɋ��鏑�������v�����ł���A鰎u�̋L�ڂ̍l�̑Ώۂɂ��Ȃ�Ȃ���A
�Ƃ������f�������A
�Ƃ������Ȃ낤�ˁB 177���{�������j����2019/02/13(��) 19:27:37.20
>>209
��a���͕s�v�c
�u�쁨���v�Ȃǂ̂悤�Ɏj�������̔ے�ȉ��̃E�\�t���x�������A
�v�l�̉ߒ������� �ˑR���_����������
���̂����������_���o���̂� �N�ɂ��킩��Ȃ� 178���{�������j����2019/02/13(��) 19:29:39.71
>>175
>��\��B���͂�������Ȃ��ϑz����銫���U�炷����
�ϑz�Ǝv���l�����邾�낤���A
�Ȃ�قLjꗝ����Ǝ~�߂�l�����邾�낤�B
�܁A�₪�ẮA���������_���`�������B 179���{�������j����2019/02/13(��) 19:31:57.76
>>213
��a�����咣���Ă���l�����́A
�����Ȃ�w���E�Ƃ����A���ɏ����̊u�����ꂽ�W�c�ɑ����Ă��āA
�]���ɁA���̏�i�̌����Ȃ�ɂȂ��Ă����ƍl������
�����瑼�҂ɐ��m�ɓ`����R�~���j�P�[�V�����\�͂�K�v�Ƃ��Ȃ����� 180���{�������j����2019/02/13(��) 19:33:07.14
>>178
���܁A�₪�ẮA���������_���`�������B
�����A�Ƃ����Ɏ��Ԑꂾ��B�@�@�����g 181���{�������j����2019/02/13(��) 19:33:17.46
����ȋ{�a�G���Z���̖ϑz���F�߂���Ɨǂ��˂�
182���{�������j����2019/02/13(��) 19:34:08.35
>>148
�ʂ����^�Ɠǂ�ł���P�[�X������Ƃ����B
���̖ʂ����^�̓ǂ݂ł���Ȃ�A�ʓy�̓��^�c�`�Ɠǂ߂�B
���̃��^�͊C�̂��ƂƊ֘A������݂����Ȃ̂ŁA�g�샖���̂悤�ɓ������ʂɂ��鍑�����A���E����ʂ̍����ʓy���ł͂Ȃ����B
�Ȃ��A���^�c�`�́A�C�ØH�i�킽�E�E���j�Ȃ̂ł͂Ȃ����B 183���{�������j����2019/02/13(��) 19:35:08.98
>>181
���ꂪ�A�l�Î��������ȁB 184���{�������j����2019/02/13(��) 19:35:46.70
>>214
�����E�����͐@�o�y�f�[�^���o���ƈꔭ�ŏ�����ԁ�
���ł��o���Ȃ� �Ȃ̂ŁA�E�����͂��܂ł����G��
�ł���a���҂́A�u�쁨���v�Ȃǂ̉R���x���̂悤�ɁA
�s���̈����f�[�^�� �ے薕�E����R���x�������āA���Ԃ̐l�X���x�����Ƃ���B
�v�z�@���ɃN�������E�E�E�E�A�z�́A�����܂ł����G�B 185���{�������j����2019/02/13(��) 19:41:32.23
>>158
�g�샖���������̎咣�́A�Փa�ɍ��J�҂��Z��ŁA���̕t���l���G�����ɏZ��ł����Ƃ����l�����B 186���{�������j����2019/02/13(��) 19:48:16.63
�הn�䍑�_�����A
�Ñ���{�̔����i�o�̘I����h�~���Ă�
���Ă̂́A�������낢�ˁB
�Ȃ�ŁA�c���q��l���ɂ��Ă����{��
�S�ϕ����ׁ̈A�c���q��S�ύ����ɊC�R�t����
�������҂����H
��������Ȃ��Ă��A�A��ׂ����ɁA�A��H
187���{�������j����2019/02/13(��) 19:48:29.67
�{���ُ̈�҂��Ȃ�����
188���{�������j����2019/02/13(��) 19:49:30.37
>>145
�ǂ��Ŕѐ����āA�ǂ��ŐH�����̂��B 189���{�������j����2019/02/13(��) 19:51:47.76
�L�`�K�C��B���̔]�����ƒ��̂��錚���ł͎ϐ����ł��Ȃ��炵��
���̓L�`�K�C
�S�Ă̔��z����O���킵�Ă���
190���{�������j����2019/02/13(��) 19:51:57.89
���������g�샖���̍��������͓��ÁE����Ďq�s��g�p�c��Ղ̊G��y��A
���z���ނ��S�đ����̏o�y�╨����̑z���ŕ������Ă���̂�
�ᔻ���Ă���w�҂�����
191���{�������j����2019/02/13(��) 19:53:07.80
���ǂ̂Ƃ��됢�_�͋�B���ɗ���������Ȃ�
192���{�������j����2019/02/13(��) 19:54:02.81
>>144
���ꂩ�������Ă���悤�ɁA�G�����͓ꕶ���ォ�炠��`���Ɖ�����B
���ꂪ�A������@�����Ē��̑q�ɂŐQ���肵�āA�ѐH���悤�ɂȂ����̂���B
��a���҂́A���̂���������ؓI�ɐ������Ƃɂ͂ȁB
�A�z��������邾���ł́A���������ɂ����B 193���{�������j����2019/02/13(��) 19:59:36.02
���ƃL�`�K�C�̔]�����ƓZ���ɋ{�a��̏Z���ȊO�ɂȂɂ����݂��ĂȂ��Ǝv������ł�悤�����A
���ŋ�悳�ꂽ�{��̎�����@�����̌��������͂�ł����ԂɂȂ��Ă���
�G���Z�����ӂ������ɂ����Ă͖����s�s�̂悤�ȈЗe���ւ����s�s�������ƕ�����
�`���P�ȏ����̏����ȒG���Z�������Ȃ���B�̏W���Ƃ̓��x�����Ⴄ�̂��������
194���{�������j����2019/02/13(��) 20:00:55.86
�`�����@�����z�Z�p����
�J����������͎��C���Ȃ��Ȃ������Ȃ�����J�r�L��
195���{�������j����2019/02/13(��) 20:01:54.03
>>219
������ �O�\���~1��430m��12.9km�@���������B
���n�̍���鰎���ɂ́A9km��菭��������L�������̂��낤�B��
�����ȂNJW�Ȃ��B
�W���U�O�O���ȏ�̉�x�s����́u�o�R���̂�v�v�Z�����������A
�������̃C���`�L�B 196���{�������j����2019/02/13(��) 20:03:16.95
>>115
���z�͊C��151m�����A�������瑪�ʂ����̂��B
��R������̂��`�B 197���{�������j����2019/02/13(��) 20:03:58.22
>>220
�܂��a���ɂ͂����A
�u�쁨���v�Ȃǂ̎j�������̔ے�ȉ��̃E�\�t���x���́A
�S�~�t�B�N�V��������
�����킯�� 198���{�������j����2019/02/13(��) 20:09:44.30
�Z���͑�`���̏Z�ދ{�a�Əd�v�Ȑl���Ȃǂ��Z�ތ@�����̏Z����������͂ނ悤�ɗ�������ł���
�����ĐΒ˓��̌Õ��Ƌ{��n����q���悤�ɑ�a���@���Ă���
���J�Ƌ{�a�Ɠs�̗L�@�I�Ȑڍ����v��I�ɍs���Ă���̂�������
���̒����̒n����ŌẪ|�C���g�Ƃ��Ď��ӂɓs�s�悪�g�債�Ă��̊O���ɔ��悪�������
�Z������`���̋���Ɠs�Ƃ��Đ������Đ₦�邱�ƂȂ����W�g�債�Ă����l��������
���̎���ɂ͑��n��̏W���ȂNjy�т����Ȃ������I�ȓs�s�������̂�������
���̏W���Ȃǂ���������ׂ郌�x���ɂ��Ȃ�
199���{�������j����2019/02/13(��) 20:10:25.45
>>193
�����s�s�ł����B
����ƁA㕌��Ƃ����̂́A�����V�������������̂ł��˂��A�A�A�B 200���{�������j����2019/02/13(��) 20:12:59.96
>>224
�����y�Q�S�̍����́A���̍�(�̉��s)����ꖜ��痢�ł���B��
���{���ɂ��������ɂ��Ȃ�
���́i�̉��s�j�̕t���������A�C���`�L�̏ؖ��ł��薳���ǂ݂ł����Ȃ��؋�
�P�Ɂu���̍����`���v���A�ޕ��n�̉ʂāi�ݓ�痢�j�̉��������Ƃ����\��
�`�����̓���n�_���w������͂��Ă��Ȃ� ��
�{���ɂ��������ɂ��Ȃ�B
鰎g��̋L�^��A����A鰗���A�㊿�����A
�̓�q�ɂ������Ă��Ȃ������u����i�]�j���v�𑵂��ċL�ڂ��A
�`���܂Łu�ݓ��i�]�j���v�ƁA��v�����L�ڂ����鎖�Ȃǂ́A
�̓�q��S�����������P������A�Ƃ������͋N���蓾�Ȃ��B 201���{�������j����2019/02/13(��) 20:17:09.43
>>227
�����̓�q�̓��p�A�Ƃ����C���`�L�͂��Ȃ��B��
�����������������̓�q����̈��p ���݂��Ȃ��� �U���R�N�̏������݂͍������Ȃ�
�̓�q�F墬�`�P
�����쎊������C�������A�H���A�c�������A�u�������v�A�O�c���A���Җ��A�s�����A�������A���㖯�A泚[���A�wꏖ��A�O�����A�C�]���G
�����쎊���k���C�L��l���A�N�q���A�u��ꏖ��v�A���Җ��A�і��A�����G��
�ق�A
鰎u�́u���L�ˎݑ���A�l���O�l�ځA�������l���P���B
���L�����A��ꏚ����ݑ�����A�D�s��N���v������A
�̓�q�P���Ă��Ȃ��B 202���{�������j����2019/02/13(��) 20:19:20.01
>>228
����4�{����킸�A�V�T�����v���X�}�C�i�X�P�T�����ʂ̂����������A��
�����ꂪ�C���`�L
50�`200���[�g���̍����o�� ��
���ꂪ�A�ރX����́A�u���n�̌��ߕ��v�̃C���`�L�B 203���{�������j����2019/02/13(��) 20:21:16.32
>>195
���̃C���`�L���ؖ�����v�Z���o����B
�C���`�L�A�Ă�������ȁ`�B
�O�\�]���͐���������A�����v�Z�o����B
�v�Z�o����ƁA�C���L�`�A�Ă�������A�A�z���Ⴄ�Ƃ������Ƃ��ȁB
���������A�^��V���́A���O�\�]���͊ԈႢ�ŁA���\�]�����������Ə����Ƃ邾�낪�B
���㒆����1����500m�B
�\�]���͖�5000m�B
��R�̕W����2440m�B
��̑S�́A���㒆����1��76.5m���̗p���Ƃ�Ƃ����̂��B
����́A�C���L�`����B 204���{�������j����2019/02/13(��) 20:25:37.44
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
205���{�������j����2019/02/13(��) 20:26:30.34
>>239
����t�̐_��4��������m�J�c�M�̂���S�����o�Ă���Ƃ����B
�_��4����3���I�����`�㔼�Ƃ���Ă���B��
����Ȃ�A�������R��̕�Ǝv����z�P�m�̕����̕����̕�̉\�������邩��A
��͂�A�R���I���Ȍ�̕�̉\���������ˁB 206���{�������j����2019/02/13(��) 20:28:10.75
207���{�������j����2019/02/13(��) 20:33:06.62
>>174
�����n���̏ꍇ�́A���s10���ŏ��Y�E���Hḍ����A��������X�ɑD�ŋ�B���݂�����A
���F������������āA�{�萼�s�܂őD�Œ��s10���A���v20���������B
���ŁA��₱�����Ȃ邩��A���������Đ��s20���Ƃ����̂���B
�������j�]���܂��肾��
�v����ɁA���s���s�̓����L�q���A���s�����Ƃ����u�v�����̌�����v�͐��藧���Ȃ����Ƃ�
�����ł��������Ă���Ă��Ƃ� 208���{�������j����2019/02/13(��) 20:33:54.52
>>243
�u�ڂ�����m��Ȃ����炷���a�t���̘b��M����v
�u�t�����݂Ƃ߂Ȃ�������A�ڂ������F�߂Ȃ��v
�u�ڂ�����v���Ă��A��a���t���╶���Ȃ��ے肵����A�P��v
���ꂪ�����̘_���Ǝv���Ă�n���̏W�c
���ꂪ��a�� 209���{�������j����2019/02/13(��) 20:37:12.22
�菼�V��372�N�̐��܂�ŎO���u����429�N��58�̂Ƃ��v�����ɐi�サ����451�܂Ő�����
䗞@��398�N���܂�Ō㊿���������n�߂��͎̂��̎��s�ō��J���ꂽ432�N�ȍ~��445�N�ɖd���̌v��Ɋ������܂ꔽ�t�߂ō���
�����͎O���u�����㊿���̏����낤��
210���{�������j����2019/02/13(��) 20:37:49.65
�Z����ՂɁu�G���Z�����Ȃ��v�ƌ����_�������Ӗ��������炸�~�߂�
�l���Z��łȂ��I�����̑q�ɁI
�Ƃ��o�J�ۏo���̂��Ɗ����U�炵�Ă�̂��{���ɏ���
�Z���̎����Ȃ�Ĉ���ǂ��ƂȂ��낤��
�הn�䍑�̉�Ƃ��̐Q�����̂܂܂̎�����ł�̂����Ε�
�ނ���G���Z�������̓����̏W���ƃ��x���̈Ⴄ��i�s�s���ƌ����Ӗ��Ȃ̂�
����ł��ĕ��c�ɂ̃`���P�ȒG���Z�����炯�̃c�`�O���̍��Ɏהn�䍑�Ƃ��Q���ق����Ă邵
���͒�\��B����
211���{�������j����2019/02/13(��) 20:37:58.53
212���{�������j����2019/02/13(��) 20:38:35.17
>>244
�����̉�R�i�ȎR�j�̑�f�R�ɁA�I�����ɂ͓����̑嗅�{�������A200�N���̎O������ɂ͕����̎��@��������B
���̎��@�Ȃǂɓo���L���A��f�R������đ����Ă����Ƃ������Ƃ��낤�B
�����āA���݂͂��̉�L���Г�9km����Ƃ������Ƃ̂悤���B
���o�̍��ɂ́A���̉�R�̒f�R���@�Ȃǂ��L���ŁA�����֓o���L���O�\��������ƌ��`����Ă����A�Ƃ����킯���ȁB��
����A���Ӓf�R������A�i��x�s�̂悤�ȍ��n����ł͂Ȃ��āj�A
�܂��܂������̒�n���猩���A
�O�p���ʂŁu���O�\���v�̌v�����o���鎖�ɂȂ�B 213���{�������j����2019/02/13(��) 20:40:19.88
>>246
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R���x���̑�a���́A
�v�z�@���ɋ����āA
���o�̖ϑz�̃t�@���^�W�[���E�ɐ����Ƃ�̂� 214���{�������j����2019/02/13(��) 20:42:50.61
��`(�_�[�����a(���}�g)���Ƃ������o���|�������݂̋E������������w
�������A�������Ƃ��đ�`���Č����Ă��瑾�ɕ{�̂悤�ȋ@�ւ��������낤�Ƒz������̂�����҂��B
215���{�������j����2019/02/13(��) 20:45:29.24
ERROR: We hate Continuous...
�A���ł���
�₢���킹ID�F4a8707ab9a4eae4a
�z�X�g�Fp1650162-ipad020105kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
���O�F ���{�������j����
E-mail�F
���e�F
>>247
���_��3��������́A�M�����t���S�V���o�Ă��āA �����V�̓z�P�m�R���V�Ǝ��Ă��邻�����B
3������3���I�����Ƃ���遃
����Ȃ�A����ς�A�R���I���ȍ~���ɂȂ�B
�i����ł܂��A���_���e�����炭�X�g�b�v�������A
�Ԏ����x��ă����h�N�T�C���ɂȂ�j 216���{�������j����2019/02/13(��) 20:45:51.08
>>198
��`���̕\�L�������̂́A�㊿������ȁB
3���I�̔ږ�ď����́A��`���Ȃ�ĕ\�L�͂���ĂȂ����B 217���{�������j����2019/02/13(��) 20:58:38.39
>>215
�����V�̖��ł́A�͔킪�퐶����ɂ͊��ɂɌ���Ă��邱�Ƃ����炩�ɂȂ��Ă��āA�z�P�m�R�͔̕�t���P���t����3���I�����ɂ����Ă����������Ȃ��ƍl������B
�Y�Ԃ̖��t�����V�n�㕔�����P�ł͂Ȃ��Ȑ��I�Ȍ`�ƂȂ��Ă���̂́A���P���t�������C��R�Əd�����y�����邽�߂Ɏ�菜���ꂽ�ƍl������̂ŁA�z�P�m�R���V�̂��ƂɉY�Ԃ��V���o�ꂵ���ƍl����̂����R�B
�Y�Ԃ�3���I���Ƃ���A�z�P�m��3���I�����ł��������Ȃ��Ǝv���܂��ˁB 218���{�������j����2019/02/13(��) 21:03:20.96
>>214
��`����Ȃ��āA��`���ȁB
���̑�`�����牤���E�������̂��A��`�B
��ɕ{�̂悤�ȋ@�ւ̖������`�ɂȂ邱�Ƃ́A�Ȃ��B 219���{�������j����2019/02/13(��) 21:06:50.00
�j���̘b���������̂��H
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
220���{�������j����2019/02/13(��) 21:11:49.26
�V�Ƒ�_���ږ�Ă��y�������̂ł���Ȃ�A�V�Ƒ�_�Ɋւ���j�����琄������ƁA�ږ�Ă̌��т͉����̍��܂ō��ƂƂ��Ă̘g�g�݂̒��Ɏ�荞���Ƃ���
�`���嗐�O�̘`���͔ږ�Ă̎����肸���Ƌ����Ő}���������������
221���{�������j����2019/02/13(��) 21:19:04.98
>>218
���x�͑�`����a�����`���Ɉڍs�����̂��Hw
�ϑz�S�J�̒f�����Ēp���������Ȃ��̂��Hwww 222���{�������j����2019/02/13(��) 21:20:35.37
�e�X�g���e
223���{�������j����2019/02/13(��) 21:23:52.43
>>182
�����̖ʂ����^�̓ǂ݂ł���Ȃ�A�ʓy�̓��^�c�`�Ɠǂ߂�B
�嗤�j�����P�ǂ݂��Ă��Ӗ��Ȃ����낤�H 224���{�������j����2019/02/13(��) 21:25:30.39
>>185
���Փa�ɍ��J�҂��Z��ŁA
����H
�����̌����ɂ͐l�͏Z�܂Ȃ���Ȃ������́H���� 225���{�������j����2019/02/13(��) 21:26:50.85
�e�X�g���e
226���{�������j����2019/02/13(��) 21:37:31.77
>>280
����肪�Ƃ��������܂� ���ׂ܂������A
4������V�̌`�̏�Ȃ��������ǁA3����͒��P���t�����V���o�Ă���悤�ł���
�`���킩��摜���Ȃ��āA���Ă��邩�ǂ����͊m�F�ł��܂���ł���
��͂��Ă���̂ł��傤��
��̌��t����������Ȃ������̂ŁA��͂��Ă��Ȃ��^�C�v�ł́H�Ǝv���܂�����
��A�Y�Ԃ��V�͌^�����Ⴄ���ŁA�z�P�m�Ƃ͌n��������Ă��܂���
��r����Ӗ��͖��������ł��ˁc ��
�Ӂ[��B��t�ł́A�S�V�͏o�Ă��Ȃ�������ł����H�B 227���{�������j����2019/02/13(��) 21:46:09.72
>>290
����鰎g��́A�����Ă����B��
���ق�ȁA�܂��� ��B���͑S���؋����o���Ȃ� ��
���x���������B
�؋��́u�]�v����������Ȃ������肵�Ă��鎖�B
���炸�ɁA���p��`�e�I�Ȃ��̂ł́u�]�v��w�Ǖt���Ȃ����A
�u�]����������Ȃ�������v�����Ȃ����́B 228���{�������j����2019/02/13(��) 21:47:28.11
>>210
�A�z���Ⴄ�B
�l���Z��ł����̂Ȃ�A���̏؋����o�����������B
�N�_�O�_�����Ă�Ԃ�����Ȃ�A�؋�������B
�؋������Ȃ�A�ق��Ƃ�̂���V�B 229���{�������j����2019/02/13(��) 21:49:35.18
>>224
���C�́A�Փa�ɐl�Z�܂Ȃ��h�B
�g�샖�������������́A�Փa�ɐl�Z�ޔh�B
�����̂��ƁB 230���{�������j����2019/02/13(��) 21:55:30.60
�z�P�m�R�Õ��͌������ȁB
�Ȃ��Ȃ���o�Ă��܂������炾�B
�z�P�m�̞͉��R�̏|�z�Õ�Ɠ������̂ŁA
���R�̏|�z�Õ�͊y�Q����Ɠ������́i�����t���j�B
�y�Q�����鰎u�̕}�]�`�E�������`�E�ؓ`�Ȃǂ�
�u�ؗL��ǂ����Ȃ��v�Ƃ���ƋL���Ă�����̂�����ȁB
�c�O�����d���������A2000�N4���ɁA�E�����͏I�������B
231���{�������j����2019/02/13(��) 21:57:08.39
>>307
���הn�䍑���ƂȂ���Ղ̔N�オ�A���j�������Ƃ��������
2���I������3���I���߂��ƕ��������A�܂�הn�䍑�̔N��ŊԈႢ�Ȃ��Ƃ������Ɓ�
���j��AMS�ł̌v��������A�T�O�`�P�O�O�N�オ���ԂɂȂ邩��A
���j�̂����������R�̓y�B�́A
�R���I�㔼�`�S���I�ʂɂȂ�A�Ƃ������B 232���{�������j����2019/02/13(��) 22:02:09.32
>>230
���z�P�m�̞͉��R�̏|�z�Õ�Ɠ������̂�
���̏|�z�Õ��̐��������ʂ��`���i���g�j����̉����i�B�@�@�����g 233���{�������j����2019/02/13(��) 22:02:57.55
>>226
�_���5���A4���A3���Ƃ��A�F�S�V�ł��B
4�����͒�p���ƌĂ��`�ŁA���̓S�V�̊G�}���݂�ƁA�͔킪���Ă���悤�Ɍ����܂��ˁB 234���{�������j����2019/02/13(��) 22:07:41.61
�ȑO���珑���Ă��鎖�Ȃ��ǁA
�{���ɓ��̕a�@�ɍs�����ق����ǂ���Ȃ��́H
���������A
���������f�����́A�����������̂��A�킩��Ȃ�
���Ȃ݂ɉƂ́w���X�x�H
�����������O�̉ƁA�Z��ł���Ƃ���́E�E�E❓
235���{�������j����2019/02/13(��) 22:11:06.13
>>223
�������S�֏o�������v�\�����ɁA�u�`�ʓy���v�Ə����Ă������\���͂���B
���̐\������O���{�����ۊǂ��Ă����A�ƍl���邱�Ƃ��ꉞ�ł���B
�S�̖�l�́A���̐\�������āA������Ŗ�O���������Ɓc�B 236���{�������j����2019/02/13(��) 22:12:12.83
>>235
����
�O���{�����㊿�{���B 237���{�������j����2019/02/13(��) 22:13:37.38
�{���̘b
�Ƃ́A�ނ��[���ɒB�S�Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł������A
�̕����ŋ����`�D���ŁE�E�E�B
�w�ɒB�̓����Y�x
�Ȃǂ����ׂĂ݂�ƍ��v���Ă���H
238���{�������j����2019/02/13(��) 22:18:29.74
�݂�Ȃ������ȁH�@�@�O����~���ɓ��{�Y�u��v��u���ʁv����������Ă�����A���@�`���i���g�j�Ō���ƂȂ��H�@�@�������Ă�̂��ȁH�@�@�����g
239���{�������j����2019/02/13(��) 22:19:06.34
>>221
�g���`���J���B
�㊿���́i��`���j���牤���E�������̂���`�B 240���{�������j����2019/02/13(��) 22:24:14.72
�قƂ�ǘV�k�k�Ȃ��ǁA
�L����Ƃ����삪�����āE�E�E�Ƃ����b�����Ă����A
�w���L�����x�Ƃ����Ƃ���̘b�ł���
�����Z��ł����Ƃɂ́A
�{�⏑�Ȃ���R����ł����A����[���ƕ���ł����ƌ����Ă��Ă��肗
�{���ɓ����̐E�Ƃ͂킩��Ȃ�
241���{�������j����2019/02/13(��) 22:25:18.45
��\��B���͒��̂��錚���ł͎ϐ������o���Ȃ��Ǝv���Ă�炵��
�o�J�������܂ŋɂ܂�Ƃ����܂�����
242���{�������j����2019/02/13(��) 22:25:36.59
>>315
��AMS�@�ł́A�v���Y�}���������q���̎��ʂڌv���Ă���̂ł����āA
���蒆�Ƀx�[�^����悤�Ȏ��Ԃ͂�����Ȃ����H ��
�܂��ςȎ��������Ă�ȁH�B
�u�v���Y�}���������q�v�ł͂Ȃ��āA�u�v���Y�}���������q�j�v�����A
�v���Y�}���������u�ԂɌ��q�j�̕��ː���ς̑��i���n�܂��āA
����́A���q�j�̎��ʂ̌v�����������Ƒ��i�������Ă�����A
���������A
�i���q�ł͂Ȃ��j���q�j�̎��ʂ��A���o�����d�q�̎��ʕ��̔��ʂȍ��ق����ς��Ȃ��A��B 243���{�������j����2019/02/13(��) 22:26:41.37
244���{�������j����2019/02/13(��) 22:27:55.32
>>241
��͂�A�m�[�^�������ȁB 245���{�������j����2019/02/13(��) 22:28:56.67
>>235
���u�`�ʓy���v�Ə����Ă������\���͂���B
�Ȃ���
��{�I�ɘ`�l�͕�����m�炸�A��
�����o�Ă��邩�當�����������͂��Ƃ����ꍇ�ł��A���S�N���̂��ł��a��̕\�L��
���t�������������Ƃ��v���A�P�ǂݕ\�L��3���I�ɂ������Ƃ���͕̂s�\����
�܂Ƃ��ɍl��������ɕ����邾�낤��
�����̎v�����ʼn����l���Ă��Ȃ��̂��ە����肗 246���{�������j����2019/02/13(��) 22:33:53.11
>>242
���u�v���Y�}���������q�v�ł͂Ȃ��āA�u�v���Y�}���������q�j�v�����A
���q�̎��ʂƌ��q�j�̎��ʂ��ǂꂾ���Ⴂ�Ǝv���Ă�H����
AMS�@�ʼn������ꂽ���q������̒���ʂ鎞�Ԃɕ��Ă���A�n����Ɉ��茳�f�͂Ȃ��Ȃ�悗��
�U���R�N�͎���p�����炵�Ă����X�^�C������ 247���{�������j����2019/02/13(��) 22:37:16.04
>>242
���i���q�ł͂Ȃ��j���q�j�̎��ʂ��A���o�����d�q�̎��ʕ��̔��ʂȍ��ق����ς��Ȃ��A��B
AMS�@�Ōv���Ă���̂́A12C��13C��14C�̎��ʂ̈Ⴂ�ڌv���Ă����
���̒m�炸�͉��������Ă��g���`���J�������� 248���{�������j����2019/02/13(��) 22:38:19.89
>>317
���́A���̓����Ԃł͂Ȃ��A����e����Ԃ����\����
�����Ă��̊���e����Ԃ���闝�R�́A�Ǒ��������肷�邽�߂ŁA
���̂��߂ɂ͐l���o����ł���K�v������
�Ǒ��s�\�ȁA�Ǒ���z�肵�Ă��Ȃ����ߍ��݃^�C�v�̎�̕��͞ł͂Ȃ���
����́A������ƈႤ�悤�ȋC������ˁB
�́A����e���ɑ��鏬���ȕ��I�ȕ����̂悤�ȍ\�����Ƃ����Ӗ��ŁA
���̒��ɁA���̔����Ȃǂ��ォ������A�Ƃ����悤�ȁu�o����o���鎺�v���A
�n�߂���z�肵�Ă��Ȃ����́B 249���{�������j����2019/02/13(��) 22:38:22.27
>>212
��R�͕W��2440m�B
����1��76.5m�Ƃ����ꍇ�A�O�\����2295m�B
���ꂩ�炷��ƁA�O�\���Ɗϑ����ꂽ�n�_�̕W���́A2440m�|2295m��145m�ƂȂ�B
���z�͊C��151m�Ȃ̂ŁA���z�t�߂��瑪�ʂ����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B
���`�����A���z�����肩���R���]�߂邩�H
�������Ǝv����B 250���{�������j����2019/02/13(��) 22:39:14.66
㕌��̌�����
�F��V�c�̋��Z�قƎv��
���Q���ꁁ��^
251���{�������j����2019/02/13(��) 22:41:28.07
���̕��������Ɖ��̐���
�����a45�N�A
�E�E�E�ɉ����`�Ə����Ă���ł���H
�Ƃ́A���̓���(���a�S�T�N)�A�����ɂ͏Z��ł��Ȃ��������A
�e�ʂ������̉ƂȂ̂��ȁH
252���{�������j����2019/02/13(��) 22:42:11.87
�Z���̌@���������͏@�_�̋���
253���{�������j����2019/02/13(��) 22:43:44.04
�Z���̌@���������͏@�_�̋���
254���{�������j����2019/02/13(��) 22:44:43.47
�Z���̌@���������͏@�_�̋���
255���{�������j����2019/02/13(��) 22:44:57.52
�Z���̌@���������͏@�_�̋���
256���{�������j����2019/02/13(��) 22:47:18.53
�푈�����Ă���Ƃ��̘b�i�w�V�k�k�x�j�A
�ɒB�S�Ƃ����Ƃ���ɏZ��ł���A
�e�ʂ̉Ƃɑa�J��������ƌ����Ă��邵�B
���̂Ƃ����ŋ��������`�Ƃ��A
�R�̏�̂ق��ɏZ��ł��āE�E�E�B
257���{�������j����2019/02/13(��) 22:48:08.72
��ꂿ�����
258���{�������j����2019/02/13(��) 22:50:00.55
>>191
�ϑz�Ŏ������Ԃ߂邵���Ȃ���B���͉��z 259���{�������j����2019/02/13(��) 22:50:35.12
>>318
���O�p���_�b���́A�ȊO�ɂ͑S���̂悤�ɑ��݂����A����T�O�O���ȏ�o�y�����A��
���ŏ����̔��ڋ��͎Ή��_�b���ŁA�Ή��_�b���͓��{��500�����o�y���Ă��Ȃ���
�ȊO�ł����ʂɏo�y���Ă��遃
�Ή����_�b��������A���t�ߌn�����ł���A���z����o�y�����A
鰒��̍H�[�̑I���ɂ͓��炸�A
����̉������ɑI������Ȃ��A�Ƃ������ł́A���Ɠ����B 260���{�������j����2019/02/13(��) 22:52:53.31
�����������ʂ̊��o�̐l�ԂȂ�
���ŋE�����X���ɋ�B�����R�قǏ�������ł�Ƌ^��Ɏv�����낤
�����Ă��������������������ɍr�炵�Ă�Ǝ@����
261���{�������j����2019/02/13(��) 22:54:43.07
�\������B���̓o�J������Z����Ղ̌@�����������{��̈�����Ȃ��Ǝv���Ă�
������o�J�ۏo���̂��Ɗ�����낤�Ȃ���
262���{�������j����2019/02/13(��) 22:55:28.82
>>220
�`���嗐�O�A�`�Ƃ͑Δn�C���Ƃ��̗��݂����B
��B�̒��ł͔����p���݂̒}�O�����B
�ږ�Ă̎��ɒ}����O���g�ݍ��܂�A���F�{�ƑΗ������B
���o�̎��ɔ����`�ɍ��������B 263���{�������j����2019/02/13(��) 22:55:43.58
�����_�b���Ƃ�������Ȃ�鰂ł��o�Ă邩��
���n�]�X�͂����ʗp���Ȃ����
264���{�������j����2019/02/13(��) 22:56:53.52
>>323
���E�������Ƙ`�̗̈�͂��Ȃ�傫������H
���p�͉��s�Ɍ����Ă���Ɍ��܂��Ă���B
�n�����܂߂�����p�͂����悤�ɂ��Ȃ��Ă��܂��B��
�����B���ԋ����v�Z�̒n�_�ȂǂƂ͏��������
�A��͂�قڒ��S���̕��� �قڂȂ�ł��傤�ˁB 265���{�������j����2019/02/13(��) 22:58:08.43
>>248
���R�̏|�z�Õ�͊y�Q����Ɠ������́i�����t���j
�Ƃ������_���o�Ă��܂��Ă���B
�y�Q�����鰎u�̕}�]�`�E�������`�E�ؓ`�Ȃǂ�
�u�ؗL��ǂ����Ȃ��v�Ƃ���ƋL���Ă�����̂�����A
�z�P�m��|�z�̞�鰎u�Ō����łP�O�O���ԈႢ�Ȃ��B 266���{�������j����2019/02/13(��) 22:58:11.69
>>198
���Z���͑�`���̏Z�ދ{�a�Əd�v�Ȑl���Ȃǂ��Z�ތ@�����̏Z����������͂ނ悤�ɗ�������ł���
�d�v�Ȑl���@���ď����ɏZ�ނ̂��H
鰎u�`�l�`�ɏ����ꂽ�A�O�t���A��l�̉����͂ǂ��֍s�����H
����Ȗ����s�s�͑S�R�הn�䍑�ł͂Ȃ���B 267���{�������j����2019/02/13(��) 22:58:36.63
�|�z�̞͒�����銮�S�Ȕ��`
�z�P�m�̞͒���Ȃ��A���𗧂Ăđ��ň͂��A����Ό�����
����̊w�҂������̓s���œ������̂ŌĂ�ł邾���ŁA�\���͑S���Ⴄ
268���{�������j����2019/02/13(��) 23:00:52.24
�ł������l��������ƌĂԂ��낤�ˁB
���߂�B
�E���̗l�q��鰎u�`�l�`�ƐH���Ⴂ������B
����I�Ȗ����s�s�H
����Ȃ��̂�鰎u�`�l�`�ɓo�ꂷ��הn�䍑�ł͂Ȃ���B
269���{�������j����2019/02/13(��) 23:01:28.30
wiki�w�����Y�x��ǂ�ł݂�
�w�Z�q�P�x
���̂悤�Șb������Ə����Ă���ł���H
�Ƃ̎ʐ^���L���E���̂悤�ȗt���ʂ��Ă���
270���{�������j����2019/02/13(��) 23:01:33.94
>>324
�����Ȃ�
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a���́A
�j�������⑊��̔����̒�����A
�����̎v�z�@���ɓs�����悢��������A�Ă�����A
�j�������k�̋A�[�I���_����������߂��̂̂��邾���ŁA
�؋��͏o���C���F�������A�ؖ�����C�����炳�疳���킯�� 271���{�������j����2019/02/13(��) 23:01:39.07
�܂������Ⴄ�āA���������Ă邾������B
272���{�������j����2019/02/13(��) 23:03:26.71
�����̞͏|�z�Ɠ������`
�����̑嗤�l���z�P�m�����Ă����Ƃ͎v��Ȃ�
���m�Ȃ̂ɒm�������Ԃ�̂͒p�����炷����
273���{�������j����2019/02/13(��) 23:03:54.74
�E�������āA�u���{�̞͒����Ō����△�����͑吳����Ɍ��_���o�����I�v���ĉR���Ă���ȁH
�ǂ����Ă��������������C�ł��邩�ȁH�H
274���{�������j����2019/02/13(��) 23:04:36.93
>>268
�|�z�ƃz�P�m�̞̈Ⴂ��m��Ȃ������̂��ۂ킩�肗 275���{�������j����2019/02/13(��) 23:04:36.85
276���{�������j����2019/02/13(��) 23:05:59.78
�ŁH
��B���l�̂������̋���ȋ{��̂悤�ȒG���Z���͂ǂ��ɂ���́H
�ږ�Ă��`���P�ȋ�B�̒G���Z���ŕ�炵�Ă�́H
277���{�������j����2019/02/13(��) 23:06:30.08
����Ɍ��߂���̂͋�B�]���L
278���{�������j����2019/02/13(��) 23:08:03.38
279���{�������j����2019/02/13(��) 23:10:18.18
���_��ɂ��肫�ŋt�Z���Ă��܂�����
��B���͒����Ȑ����ɂȂ��Ă��܂������
280���{�������j����2019/02/13(��) 23:12:30.20
>>230
�y�Q���l�Ƃ̌𗬂��������̂���
������L�����أ�͘`�l�̈�ʓI���K 281���{�������j����2019/02/13(��) 23:14:16.24
�^�e�c�L�����`�������l���[���̞�
�z�P�m����Ȃ��ړ��s�\�ȑ�����������l�͞Ƃ͎v��Ȃ�
282���{�������j����2019/02/13(��) 23:15:49.33
���̎ʐ^�Ɏʂ��Ă���A���E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�A
�m���Ɂw�E���ȁx�̐A���A�Ȃ��ڂ����낤�H
�ƂȂ�ł���
283���{�������j����2019/02/13(��) 23:17:19.09
���������R���I����
�Ȃz�P�m�R���R���I���t�ƉȊw����ƍl�È╨���猋�_�Â��Ă邩��
284���{�������j����2019/02/13(��) 23:18:12.57
>>267
>>272
>>274
>>277
>>278
>>279
>>281
http://makimukugaku.jp/info/iseki.html
�Έ͂��؞Ƃ����\�����̂��̂͋g����]��E���g�E�d���n��ŎU���������̂ł���A�z�P�m�R�Õ��̒z���ɓ������˓��n�悪�傫�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ��z�肳��܂��B
�K�L�݂ā[�ɂ܂�ˁ[���X���Ăˁ[�ŁA
�L���L�[�̃A�z�ǂ��͂���ے肵�Ă��Ă�B
�z�[���y�[�W�����������Ă���咣���Ă������������ł��ȁB
�o�J�Ȗ�Y�����܂������B
������L���L�[�̓L���L�[�Ȃ悗����
�l�Ԑ��̖��ł��B 285���{�������j����2019/02/13(��) 23:19:26.53
��B���͞�����ƂR���I�㔼�Ƃ����ҔN��啝�Ɍ������Ȃ��Ƃ����Ȃ��悤����
�����Ȋw�I�����Ɠy��ҔN�����ɔ����Ă���̂�����
286���{�������j����2019/02/13(��) 23:20:38.71
>>325
����70�����āA�Z������4.9�L�����炢����H �m���V�c�˂��P���R�L��
�j���ɂ��L�^�����悤�ȎR���A����Ȃɏ����ȋu���x�̏��R�̂͂����Ȃ����낤���I ��
�܂��A���V�O���ō��R�O���Ƃ������́A���Ȃ�́u�Ƃ�R�v���A�Ƃ��������ȁB
�d���ɐ�R�͑�R���邪�A���ł��P�H�̕W���X�O�Om�ʂ̐�F�R���L�����B
�����猩����A��R�̌X�͂U�O�x�ʂɊ������ȁB
��R�����Ȃ�̊�R�炵�����A
�Z���ŁA���V�O���ō��R�O�����Ď��́A�\���ɂ��蓾��ȁB 287���{�������j����2019/02/13(��) 23:21:29.61
>>250
��㕌��̌�����
���F��V�c�̋��Z�قƎv��
�����Q���ꁁ��^
�F��V�c�̋{�͍��c�I�ˋ{�ŁA�ޗnj����S�c���{�����c�ɂ́A
���ː_�Ёi�I�ː_�ЁA�F��_�Ёj������
���Ì���Ղ���2�L�����炢�̏ꏊ
�K���Ȏv�����������Ă��_������ 288���{�������j����2019/02/13(��) 23:21:47.83
�|�z�����J�S���퐶����̕��u��
�̗L���Ŏ���͔��ʂł��Ȃ�
���Ȃ݂ɖk����B�ł��퐶����ɞ����悪�������Ǝw�E���錤���҂�����
289���{�������j����2019/02/13(��) 23:24:20.47
>>284
�܂��_�j���ꂽ��B�����������Ă���� 290���{�������j����2019/02/13(��) 23:25:35.20
�悸�L���L�[�͋g���̏|�z�̞͊y�Q����̞Ɠ����ƔF�߂��������B
���ꂪ�����Ӗ����邩�A�o�J�����痝�����Ă��Ȃ��悤���Ȃ�����
�`�����̂��̂ɞȂ���鰎u�`�l�`�Ƀn�b�L�����L���Ă���̂ɁA
鰂̎g�҂͋g�����щz���đ�a�ɗ����������������
�o�[�J������
291���{�������j����2019/02/13(��) 23:26:50.93
�Ñ�ɐ������ЂƂтƂ̔F����
����w�p�p��̎w���������̂�
�K��������v����킯�ł͂Ȃ�
�Ƃ������Ƃ𗝉��ł��Ȃ��m�\�ł�
���j�w�Ɏ�������ނ�������
292���{�������j����2019/02/13(��) 23:27:09.30
>>266
���d�v�Ȑl���@���ď����ɏZ�ނ̂��H
��B���́A�@���Ē������ƁA�@���ď����̋�ʂ��t���Ȃ����Ă����̂́A�s�s�`�����Ǝv���Ă�
�ł��A�{���ɋ�ʂ�������Ȃ��Ȃ���
����ł悭�Ñ�j�̃X���ɏ����������Ǝv�����Ȃ��A���S�����
���̌��疳�p�������ɂ��� 293���{�������j����2019/02/13(��) 23:27:21.45
�_�j������
�o�J������L���L�[�ɂȂ����Ⴄ���āA
�܂����Ă��ؖ�����������Ȃ�����
�o�J�����큨�E����������
294���{�������j����2019/02/13(��) 23:29:16.66
>>290
�|�z�ƃz�P�m�̞̍\�����Ⴄ���Ƃ͗����ł����悤���� 295���{�������j����2019/02/13(��) 23:31:03.67
���|�z�ƃz�P�m�̞̍\�����Ⴄ���Ƃ͗����ł����悤����
�z�P�m���Ǝv���Ă���킯���Ȃ�
296���{�������j����2019/02/13(��) 23:31:41.32
�A����Ǔ_�A�ʃL�����ł�����ς蔭��
297���{�������j����2019/02/13(��) 23:32:06.18
>>294
http://makimukugaku.jp/info/iseki.html
�Έ͂��؞Ƃ����\�����̂��̂͋g����]��E���g�E�d���n��ŎU���������̂ł���A�z�P�m�R�Õ��̒z���ɓ������˓��n�悪�傫�ȉe����^���Ă��邱�Ƃ��z�肳��܂��B
�K�L�݂ā[�ɂ܂�ˁ[���X���Ăˁ[�ŁA
�L���L�[�̃A�z�ǂ��͂���ے肵�Ă��Ă�B 298���{�������j����2019/02/13(��) 23:33:17.44
>>329
���������� ��B�͘`���̈ꕔ
���̈ʒu�W�́A�ړ����z�肳��Ă��邩�甼������`���ɓn������������Ă��邾����
����A���̏ꏊ�������������鎞�́A��̒n���I���S�������s�̂�������B
�������A���ԋ�����������鎞�́A�n���I�ŒZ��Ԃ��A���S���Ԃ̍ŒZ��ԁB 299���{�������j����2019/02/13(��) 23:33:48.72
>>293
�o�J�͋E�����X���ɂ킴�킴�_�j����ɗ����B������ 300���{�������j����2019/02/13(��) 23:35:34.08
>>330
���ږ�Ă������Ă���̂͑�a�̎R�ԕ��u���V���i�䏊�s���V�j�v���B��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 301���{�������j����2019/02/13(��) 23:36:13.15
>>290
���`�����̂��̂ɞȂ���鰎u�`�l�`�Ƀn�b�L�����L���Ă���
�����ĂȂ� 302���{�������j����2019/02/13(��) 23:36:59.86
>>294
>>299
�|�z�ƃz�P�m�̞̍\�����Ⴄ�̂͂����킸������
�ǂ�����Ȃ̂��Ƃ������Ƃ͗����ł��܂��� 303���{�������j����2019/02/13(��) 23:37:45.59
>>301
鰎u�`�l�`�ے肗����
�����Ă��ȃL���L�[�͂����� 304���{�������j����2019/02/13(��) 23:38:53.48
>>245
�܂Ƃ��ɍl������������邱�Ƃ����A���v�\���ɍs���̂ɁA�S�ɘ`�ꂪ�b����҂����Ȃ���A�����炩��ʖ���čs���K�v������B
���̒ʖ����������邱�Ƃ́A���R���B
�ʖ�͕����������āA�������b���A�`���������钆���l���������낤�B
�����āA�����̍��̘`��̈Ӗ���[���Ӗ�ł���ʖ�Ƃ����A�`�����܂�̓��l������B
���̌��ʁA�ʁ����^�A�y���c�`�i�C�ØH�j���Ƃ����킯�ł��邪�A�S���͖ʓy�̓����h�Ƃ����ǂ߂Ȃ����A�����h���Ȃ�ĕ��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�s�R�Ɏv����O�����ɂ����B
���������^�����낤�B
�������A�ʂ����^�Ɠǂނɂ͗��R������B
�������܂̑c��_�̓��^�c�~�ł���A���̃��^�c�~�̌�������ǂƂ����B
��ǂ́A��ɉ��y���т����蒣��t���Ă���A���̖ʑ�����ǂ��ے�����B
�܂�A���^�c�~�͉��y���т����蒣��t�����ʁi��j�����Ă���̂��B
�Ȃ̂ŁA���^���ʂȂ̂ł���B
���̈��܂̃��^�c�~���ʐ_�ɒʂ����҂������ŁA�����̍���ʓy�i���^�c�`���C�ØH�j�Ə̂����̂́A�����炭���ܑ��̖T�n�̎҂���������ł͂Ȃ����B
�����̍������Øp�̉��R��ł͂Ȃ����Ƃ���l������̂ŁA���邢�͂��������m��Ȃ��B
�܂��A���������z�肾�B 305���{�������j����2019/02/13(��) 23:39:28.26
�����Ă�����̂�����
�����ĂȂ����̂��L��
���i�����jvs���i�����̂��j
306���{�������j����2019/02/13(��) 23:39:35.42
���x�����B����ϗ��I��������Ȃ��I�ɂ��������Ă�낤
����Ƃ킩��Ȃ��o�L�ڂ��������背�X�̒��ɕ��ꂳ��
�C�Â��ĂȂ��̂̒��ł�����
���ꂪ�I�Ɍ������낤
307���{�������j����2019/02/13(��) 23:39:38.59
>>335
��鰎u�`�l�`�̋L�ڂƎ��ۂ̔��n����A���v�w�I�Ɍ�����ꗢ�̒���
�C�㋗���͑���ł��Ȃ��̂ŁE�E�E��
���̕���������A�����C���`�L�B
�n�C�������v�����o������B 308���{�������j����2019/02/13(��) 23:40:25.15
�؉]�X�Ƃ����̂͘`�l�̖��̕��K�ɂ��Ă̌��������
�����疳�Ӗ��ȋc�_�A�킴�Ƃ��m���
�؊��ɓy���ʼn������Ȃ�
309���{�������j����2019/02/13(��) 23:41:35.77
310���{�������j����2019/02/13(��) 23:42:12.12
>>302
����Ǟ������Ă��R���I���t
�R���I���t�̕�����z�P�m�R������ƌ����Ȃ�� 311���{�������j����2019/02/13(��) 23:43:03.97
�R���I���t�ɞ�����Ȃ�הn�䍑�ł͂Ȃ��؋��ɂȂ�
312���{�������j����2019/02/13(��) 23:43:21.77
�Z�q�P�`�E�E�E�V���f�����`�Ƃ����{���o�Ă���ł���
�V�k�̌����Ă����A
��e����������(�f���ɉ���)���Ƃ����b�H
�K�̉̎ʂ��Ă���ق��A�֎q�ɍ����Ă���l���ƌ����Ă���
���̎ʐ^�Ȃ낤
313���{�������j����2019/02/13(��) 23:43:31.30
>>303
�L���L�[�L���L�[�Ƃ܂�ʼn��̂悤�ɋ����Ă����B�� 314���{�������j����2019/02/13(��) 23:43:33.01
>>303
��`�n���g�@�~�ĐH���@�F�k��@�L�����@����Z��卧���ٙ|�@
�Ȏ�O�h���g铁@�@�����p����@�H���p籩���@��H
�����L�����@���y��n�@�n����r�\�P���@�c���s�H���@�r��L���@
���l�A�̕������@�ߑ��@���ƌw�����U���@�Ȕ@�����
����͈�ʓI���K
�`�����̂��̂ɞȂ��Ƃ͏����ĂȂ�
�������Ȃ��œǂق������� 315���{�������j����2019/02/13(��) 23:45:02.99
>>336
�����R��t���ȁA�ރX����B �u���S���������ݓ���P���v�́A�������܂ł̗������B��
����������
�����ď������Ƃ����͍̂L���͈͂ŁA���̒��̓���̏ꏊ���w�����̂ł͂Ȃ��� �E�E�E��
���R�A�����̂���Ƃ���𒆐S�Ƃ����n����w���B 316���{�������j����2019/02/13(��) 23:46:49.08
>>304
�`�ʓy�͘`�����̓]�L�~�X�炵����
��ԌÂ��L�q�ł͘`���������ƂȂ��Ă��� 317���{�������j����2019/02/13(��) 23:47:15.56
>>308
�c�O�ł����`
鰎u�̕}�]�`�E�������`�E�ؓ`�ȂǂɁu�ؗL��ǂ����Ȃ��v�ƃn�b�L�����L����Ă��܂��B
�y�Q����͉��R���̏|�z�Õ�Ɠ������̂ł����炗���� 318���{�������j����2019/02/13(��) 23:49:06.78
>>315
���̏������͉�m����(��)�̓��ʼn�����p�̕ӂ� 319���{�������j����2019/02/13(��) 23:49:36.78
�`�l�`�����ł͂Ȃ����̖����ɂ��Ă����Ɗ��ɂ��ď����Ă�B
�l�X�Ȍ`���������ʕ��K�ł�����������L�^����K�v�������킯�ŁA
����i�w���҂̏o���j�̌`���ł��邱�Ƃ͖��炩�B
320���{�������j����2019/02/13(��) 23:50:42.14
>>314
���Ȃ��͉��R���̏|�z�Õ�Ɠ����y�Q������A
鰂̎g�҂��u�ؗL��ǂ����Ȃ��v�ƃn�b�L�����L���������A
���̒��Ƀr�V�b�ƍ��ݕt���Ă����Ă��������B 321���{�������j����2019/02/13(��) 23:52:57.72
>>337
���܂����v�ǂ�����������悤�ȏ��ʂ���ւ�ȁ�
�S���珗���V���s�����ł̗����L�ڂ����ł��P�O�ʂ̗���������A
�ȒP�ȓ��v�Ȃ�A�\���\���B
�������A�ރX����́A�u�쁂���v�̏ꍇ�Ɠ������A
�s���̈����f�[�^�̔ے薕�E���Ă����Ƃ����s���������v�Z�����Ă��邩��A
�E�E�E�E���\�t�Ȃ̂��B 322���{�������j����2019/02/13(��) 23:53:04.18
>>317
�`���̈�ʓI�ȑ��V�K��������
�הn�䍑�s���|�C���g����Ȃ���
������E���ɞؗL���Ċ�������Õ��������Ă��������Ȃ�
�����������L���ĞȂ��������Ǝv������ 323���{�������j����2019/02/13(��) 23:53:26.02
>>320
鰂̎g�҂��|�z�Õ�@���������������́H
���ƁA�ؓ`�͢�L�����أ 324���{�������j����2019/02/13(��) 23:58:56.01
>>311
��������������R���I���t����Ȃ��Ƃ����l�ÓI�Ș_�����Ȃ� 325���{�������j����2019/02/14(��) 00:01:33.62
�����͊y�Q�S����Ȃ����B
326���{�������j����2019/02/14(��) 00:03:48.10
>>309
���͂S���I�ȍ~�n�������Ă��Ă���
�z�P�m�R�͊����╨��AMS�@�łR���I���t�ƌ��_�Â��Ă���
����Ɍ����Ȃ�z�P�m�̖x����R���I���t�ɑ�������y����o�Ă��� 327���{�������j����2019/02/14(��) 00:04:19.46
�Ζʂ̊p�x60�x�̉~�����Ƃ����
����30���Ȃ��̒��a34.64���Ŏ���114�����炢�ł���
��70���ɂȂ�ē���Ȃ�Ȃ����
328���{�������j����2019/02/14(��) 00:04:55.23
鰎u�̂ǂ��Ɋy�Q�̕搧�̋L�q������H
329���{�������j����2019/02/14(��) 00:05:12.79
>>286
�Ȃ��Ȃ��B
��70���Ƃ́A�R�̘[�̂������͂�70���قǂƂ����Ӗ��B
����ɑ����č��O�\���Ƃ���̂�����A�[�̒n�ʂ���O�\���̈Ӗ��B
1��76.5m�ŎO�\�����v�Z�����2295m�B
��R�̘[�ɋ߂���x�s�ŊC��756m�Ȃ̂ŁA���̉�x�s�Ōv�������Ƃ���A�O�\����2951m�ɂȂ�B
����A���ۂ̉�R�̊C�����W����2440m������A��x�s�ł��̎R�̍����𑪂��1684m���x�̍��������Ȃ��B
��R�O�\��2951m��1684m�ł́A�������S�R�قȂ�B
�����������Ƃ���A�O�\������R�̎R�̍������Ӗ����Ă��Ȃ����Ƃ́A�������B
�O�\���� 330���{�������j����2019/02/14(��) 00:05:39.21
�y�Q����
�����̑O������O������ɂ킽��C���N�k�����̊y�Q�C�ѕ����S�̒n����ɉc�܂ꂽ����B
1�� 10�`30m�O��̕���`�̕��u�������C�����ɖ؞� ?�̖����{�݂�����B
�؞͑O������㊿�ɂ����āC?�͌㊿����O������ɂ����Đ��s�����B
��\�I�Ȃ��̂Ƃ��āC�O��������㊿�����̐Ό���9�����C�� 194�����C�㊿�̉�����C
������C��⸒� (�������傤�Â�) �Ȃǂ�����B
��{�I�Ȓm�������Ă������ȁB
331���{�������j����2019/02/14(��) 00:08:26.35
�O�q�q��B���͂܂����̏o�L�ڂɋC�Â��ĂȂ��̂�
�o�J����������
332���{�������j����2019/02/14(��) 00:09:59.64
�`�H���H
333���{�������j����2019/02/14(��) 00:10:20.26
>>330
�ŁA鰎u�̂ǂ��Ɋy�Q�̕搧�ɂ��Ă̋L��������́H 334���{�������j����2019/02/14(��) 00:11:48.22
�Z����Ղ̋�����ӂɂ͑����̑召���܂��܂Ȓ����Ղ��������Ă���
5m�l�����x�̏����Ȍ������������݂��Ă���
�M�l�Ƃ���Ɋւ��Ɛl�Ȃǂ����͂ɏZ��ł��邱�Ƃ��z�肳���
�G�����Z���ł͂Ȃ��s�ł���Z���ł͐�i�I�Ȓ������������z�����L�����Ă���
�ޗǂ╽�����ł��s���ɒG�����Z���͖������l�̃X�^�C���̐�s�I�ȓy�n�������ƌ�����
���̏W���Ƃ͎����̈Ⴄ��i�I�ȓs�s���ƕ�����
335���{�������j����2019/02/14(��) 00:11:50.31
���_�ł������ł�����
��B���͂����Ռ`������܂���Ȃ�
336���{�������j����2019/02/14(��) 00:12:51.96
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
337���{�������j����2019/02/14(��) 00:16:18.72
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
338���{�������j����2019/02/14(��) 00:16:45.28
���Ȃ݂ɔn�͕ʖ��A�P���Õ��Љ�ƌĂ�Ă���B
���R�ؖ������L��悾�B
鰂̎g�҂͂�����ƕ�̖������@�ɂ��ă`�F�b�N���Ă��������ؖ����Ă���B
339���{�������j����2019/02/14(��) 00:17:00.77
㕌����ēy��̕�ܑw���߂��Ⴍ����L�͈͂Ɋg�����Ă����
�ǂ��y����������A���ē˂����݂����Ȃ邭�炢�ɂ�
340���{�������j����2019/02/14(��) 00:18:58.71
341���{�������j����2019/02/14(��) 00:19:03.93
>>283
3���I���낤���Ȃ낤���A�ږ�Ă������הn�䍑�Ƃ͕ʂ̍����E���ɂ������Ƃ������Ƃ���B 342���{�������j����2019/02/14(��) 00:20:57.21
>>291
�������瓖���̗p��Řb����B
����̎j�w�͏����`�̝s���p��Ŗ�����ꂽ�ϑz�w��Ȃ̂���B 343���{�������j����2019/02/14(��) 00:22:55.66
>>342
�����̔F��������l�����S�ɔc���ł���Ƃł��H 344���{�������j����2019/02/14(��) 00:24:28.98
2���I���ȗ��̒��������ł������ږ�đ̐������ł��邱�Ƃɂ��E���ɂ������̃`�����X���K�ꂽ���A�ق�̏\���N�̔N��̌�F�ɂ��A���������E�����ږ�Ă̂��ƂŔ��W�������̂悤�Ɍ����Ă��܂��B
�����������܂ł�3���I�̋E���͒}���̑����ɂ��y�Ȃ����W�r��n��ł���A�܂��Ĕږ�Ă��������ꂽ2���I���ɂ́A�E�����������o����قǂ̔��W���܂Ƃ܂�����o���Ȃ��B
345���{�������j����2019/02/14(��) 00:24:57.75
�Z���_���Ȃ�ē����̔F��������ŗ����ł��ĂȂ�����̍ł�����̂��Ȃ�
346���{�������j����2019/02/14(��) 00:25:32.45
�ږ�ēo��܂ł̉���͒}�O�ɂ̂ݑ��݂���B
�}��͋_���R�Õ����M���M��3���I�㔼����4���I�O���B
����5���I�ɂȂ��Ă���B
��O�L�O�Ȃǂ͒}�O�ɋ߂����邪���߂ɑ�������q�����ƂȂ�A
�x�z�҂͒}�O�ɍݏZ���Ă����̂��낤�B
�l�Êw�I�ɂ́A�e�n�ɉ����������āA����ɓ������ꂽ�̂ł͂Ȃ��A
�}�O�ɉ����o�����A�}�O����e�n�����Ďx�z����z���Ă��������Ƃ����炩�ł���B
��B���҂��悭�w�E����
�u�����{���Ȓj�q���@�Z�����\�N�v
�͔��ɏd�v�ȏ��ł���B
�הn�䍑�̔��n�́A�ږ�ēo��ɔ����ēˑR����Ȃljh����ꏊ�ł͂Ȃ��A
�ږ�ĈȑO����j�������݂������Ƃ̒n�Ȃ̂ł���B
���̏��������ꏊ�́A
�O�_�쏬�H���䌴���a�̒j���悩��A
����������ւƘA������ɓs�݂̂ł���B
�ږ�Ă������ł������`���Ƃ́A�ɓs����s�Ƃ���k����B�`�Δn�C�����Ƃł��������Ƃ�
�l�Êw�I�ɂ������w�I�ɂ��^���]�n���S�������B
347���{�������j����2019/02/14(��) 00:26:52.05
�����Ē��N�Ŋy�Q�S�ɋA�����邱�ƂƂȂ����̂������ȁB
�̗l�q���ڂ���������Ă���B
348���{�������j����2019/02/14(��) 00:28:37.37
>>341
����������؋����Ȃ�
�l�È╨����E������ԊW�R�������� 349���{�������j����2019/02/14(��) 00:29:51.27
>>316
�ˉ��ɂ́u�㊿���ɞH���A����̉i�����N�A�`�ʏ㍑����������v�Ə����Ă���炵���B
�㊿���ʖ{����������A�`�ʏ㍑�Ə����Ă���ʖ{���������̂��낤�B
���̂ق��ɁA�ʓT���`�ʓy���A���ޔ����`���y�n�A���{���I�[�`���`�ʍ��Ȃǂ����邻�����B
���݂���ꂪ�ڂɂ���㊿���������`�����Ƃ��Ă�����́B
�ʓy���Ȃǂ͌�L���A�Ƃ͌�������Ȃ��B
���݂̌㊿���̘`������L��������Ȃ��B 350���{�������j����2019/02/14(��) 00:31:52.26
351���{�������j����2019/02/14(��) 00:31:53.00
�l�È╨����B���̍����ɂ��悤�Ƃ��Ă�
�l�Êw�҂͂قڋE����������
352���{�������j����2019/02/14(��) 00:31:58.13
���̗l�ɂ��āA鰎u�ł́A�ؗL�芻�����A���L��ؖ����Ƃ��������̌`���ŁA
�L�b�`���Ɨ����E�y�Q�̋�ʂ��t���悤�ɂȂ��Ă���B
353���{�������j����2019/02/14(��) 00:33:33.30
>>346
�|�z�����J��㕌��Β˂������ł��� 354���{�������j����2019/02/14(��) 00:33:52.02
�o�J���ǂ�Ȗϑz�������U�炻���������j�͔��o����B������B�������l���ĂȂ�
��B�͑����ō��J�Ղ��Ȃ���{����Ȃ�
�`���P�ȒG���Z�������Ȃ��c�`�O���̏W��
���������Ȃ���B���̂܂�
355���{�������j����2019/02/14(��) 00:37:09.64
>>348
�`�l�`�́A�������̓���]���̍��B 356���{�������j����2019/02/14(��) 00:40:07.15
�`�l�`�̋�B
�E�P��2�痢�����Ɩ��L����鏗�����͈̔͊O�̕����n��
�E��呲�����Ԃ��ĊĎ����ꋯ���Ă���
�E�������ɓ������Ă��鑮��
�E�Ӌ���������z�u����Ă�ƒn
�����đ��������j�����S�đ�a�̒��S���̘A�����L�ڂ��A��B�͂��̑�a�����呲�𑗂荞�܂�鑮�����Ǝ����Ă���
�ǂ��ɂ��o�J�̖ϑz����悤�ȗv�f�͈���Ȃ�
357���{�������j����2019/02/14(��) 00:43:06.97
358���{�������j����2019/02/14(��) 00:45:28.05
>>334
�ޗǂ́A8���I���낤�B
3���I�̘b���Ă�̂ɁB 359���{�������j����2019/02/14(��) 00:49:44.90
>>338
�����Ȃ݂ɔn�͕ʖ��A�P���Õ��Љ�ƌĂ�Ă���B
���k��B�Ŗv�������͔̂n�ؐl�Ȃ낤 360���{�������j����2019/02/14(��) 00:56:30.93
�͂��I
>>319��
������i�w���҂̏o���j�̌`���ł��邱�Ƃ͖��炩�B
�����m��I 361���{�������j����2019/02/14(��) 00:56:40.67
�הn�䍑�����A
�_��E�̂ق��������悤�Ȋ������������
362���{�������j����2019/02/14(��) 00:58:16.40
�Z�E�W�����E���[�g�H
363���{�������j����2019/02/14(��) 01:00:47.86
�w���X�x�`�w郁x
�V��郁E�E�E�y�K�T�X�H�Z�C���g�Z�C���̋ȁH
364���{�������j����2019/02/14(��) 01:05:26.85
���悪�ǂ������H�H
365���{�������j����2019/02/14(��) 01:08:08.64
>>348
�l�È╨����E���͊��S�ے肳���B 366���{�������j����2019/02/14(��) 01:14:45.90
�̏o�y
�`���嗐�������l�È╨����
�S��̏o�y�p�x�̏��Ȃ�
�S���I�n�߂̓y�w����g���Â��ꂽ�n��̏o�y
�S�]���̏}���������l�È╨����
�E�����͍l�È╨���犮�S�ے肳���B
367���{�������j����2019/02/14(��) 01:16:01.24
>>348
���l�È╨����E������ԊW�R��������
���}�g�����Ǝהn�䍑���������Ă��邾������B 368���{�������j����2019/02/14(��) 01:18:00.36
�y�הn�䍑�͂ǂ�ȍ��H�z
�u鰎u�`�l�`�v�|�u�`�l�͕���ɖ���p����v
�\�����ł���S���ł���A
�������ʂɏo�y���Ă���͖̂k��B�A�ޗnj��͏o�y�����B
�u鰎u�`�l�`�v�|鰂ւ̎��Q���A鰂��珗���ւ̑��蕨�ɑ����́u���D���v
�|�הn�䍑�̂������퐶�������܂ł́u���v�́A���ׂċ�B����̏o�y�B
�u鰎u�`�l�`�v�|�u�`�l�͓S���V��p����v
�S�͈��|�I�ɋ�B�ɂ���B
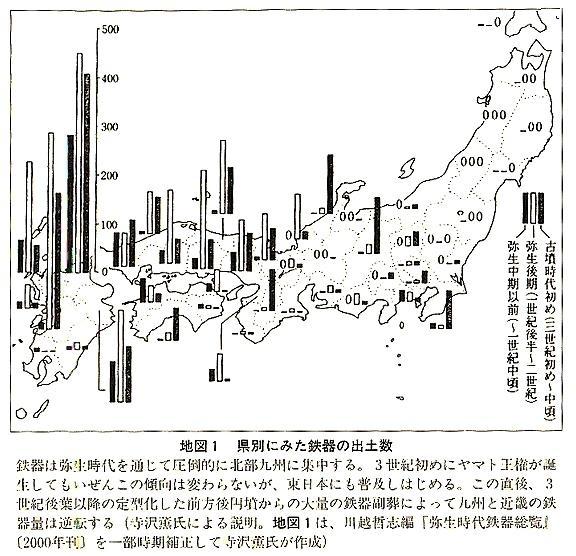
�u鰎u�`�l�`�v�|�u鰂͔ږ�ĂɌړ������^�����v
�|�퐶����̓S���A�S���͕���������X�Q��o�y�A�ޗnj�����͂P��݂̂̏o�y�B
�O�p���_�b����鰂̋��ɔA�ږ�Ă̎���́u���i�K��l�_���A���s�ԕ����v
�הn�䍑����A�Õ������ʂ��āA����������R�V�ʁA�ޗnj�����́A�킸���Q�ʁB
���̎R�ɒO����
�퐶����̓ޗǂł́A��O�͓�ӏ��� �����g�p����Ă��Ȃ��B
�������ł�41�ӏ��̈�ՂŎg�p����Ă���B 369���{�������j����2019/02/14(��) 01:37:01.25
�{���ɋC�Â��Ă���C�Â��Ă��鎖�Ȃ��ǁA
�l�̉ƂɊ��Ă���l����������ł���H
���������Ƃ����Ȃ�A���̂悤�Ȑl�B�͉��Ȃ낤
���Ɓw�`�H���x��wiki���ǂ�ł݂āA
�x�[�X�{�[���������`�Ƃ�
�^�}�C�N�E�I�[(�Ȃ������̒a�����Ɠ����A�T���P�T�����܂�)�H
��MV
370���{�������j����2019/02/14(��) 01:37:47.03
>>364
�ȒP�Ș_������
�������������ł��Ȃ�
�@��
������������̓��e���m�F�ł��Ȃ�
�@��
鰎u�ɋL�����Ɨ����̕搧�Ƃ͑Δ�ł��Ȃ�
�@���@
鰎u�ɋL�����搧������̓��e�ł���Ƃ͂����Ȃ�
�@��
���R�`�̋L�q�ɑ��Ă����l
�@��
�|�z�ɖ؞��A�z�P�m�Ɂu�؞v�����݂��Ă�������Ȃ� 371���{�������j����2019/02/14(��) 01:39:48.21
�w�͓��̎O���x�`�w�Q�Q�Q�x�H
���ƕ�˂̏��D��wiki���ǂ�ł݂�
�����W�̐l���A�V�Á`�H
372���{�������j����2019/02/14(��) 01:45:04.57
>>356
���̒����j���̌�F�����j��Ȃ���a���k�B 373���{�������j����2019/02/14(��) 01:45:57.97
�R�P�P�Ȃ��l�H�n�k�����ƌ����Ă�l��������A
�Ȃ����Ǝv��
374���{�������j����2019/02/14(��) 01:52:18.62
�w���X�x�`�w�s�x�Ƃ������O�ł���A���̖��O�B
�ނ��[���Z��ł����Ƃ����Ƃ�����A�ɒB�S�Ƃ����Ƃ��낾���ȁE�E�E�B
�X�g�[�J�[������̂��ȁH
375���{�������j����2019/02/14(��) 01:55:21.46
���������c�̋�B���]
376���{�������j����2019/02/14(��) 01:59:39.98
�{���ɁA���̎ʐ^����E�E�E�A
�w���X�x�̉Ƃ́E�E�E�q���̍����������ȁ`�ƌ����Ă�����A
�������S,�T���炢�Ƃ��A�����̐����̂悤�Ȃ��̂𒅂Ă���
377���{�������j����2019/02/14(��) 02:10:15.34
�Z���̌@���������͏@�_�̋���
378���{�������j����2019/02/14(��) 02:17:08.58
�{���ɓ����̐E�ƕs���A
�����̉Ƃ������̂��ȁH
379���{�������j����2019/02/14(��) 02:24:42.65
mike oldfield�wlet there be light�x
���̋Ȃ̓�����ςĂ݂āE�E�E�A
�w���X�x�`�Ȃ����w�T�C�o�[�p���Nspecial�x�Ƃ����R�~�b�N�E�E�E���̑��H
380���{�������j����2019/02/14(��) 02:32:43.37
�ŋ߁A��10��V�c��拍���ǂ߂Ȃ��Č�ϊ��������Ă����{�l�������
381���{�������j����2019/02/14(��) 02:51:56.77
�w�_��E�x
382���{�������j����2019/02/14(��) 03:00:47.46
���������@�̘b�����Ă�����A
���ƓD�_�̂悤�Ȃ��̂ɓ���ꂽ�Ƃ����b�Ƃ��A
�ǂ����������Ǝv��
383���{�������j����2019/02/14(��) 03:19:01.56
�h���S���{�[���H
�Ȃ����A�قƂ�Ǔ����悤�ȃR���Z�v�g
384���{�������j����2019/02/14(��) 03:36:47.17
�Ƃ���A�j���̐ݒ�Ȃ��ǁA
�S�L�u��(��)���������Ə����Ă���͂�
�Z��E�E�E���Ɩ�������
385���{�������j����2019/02/14(��) 04:32:22.55
>>276
��������Ȃ��́B
鰎g�������ږ�Ă̋{���Ƃ����͍̂Փa�̂��ƂŁA�]�l���݂���ɗ�������Ȃ��悤�Ɏ�q�������Ƃ������Ƃ��낤�B
鰎g�́A�ږ�ĂƉ�����̂͂��̍Փa�������̂ŁA�ږ�Ă͂����ɏZ��ł���Ǝv�����Ƃ������Ƃ��B
�������A���ۂ́A�Փa�ɔږ�Ă͏Z��ł����A�ʂ̂Ƃ���̒G�����Z���ɐ��b�l�̛ޏ������ƈꏏ�ɏZ��ł����̂��낤�B
鰎g�́A�����m��Ȃ����������Ƃ������ƂɂȂ�B
�܂�A�`���̓`���I�Z���́A�G�����Z���������͎̂����B
���������A�Z����Ղ̑�^�����Q�̒��̍ł��傫�������c�́A����19.2m�A�c��12.4m�B
���̋K�͂̌������g����h�Ə̂��Ă���킯������A3���I�̈�ʓI�Ȍ����̂���悤�͉����Ēm��ׂ��ł���B
�����c�́A�����Ƃ��Ă͑匚�z�������킯���B
�Ƃ���A�ږ�Ă����h�ȒG�����Z���ɏZ��ł����Ƃ��Ă��A�������Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B 386���{�������j����2019/02/14(��) 04:38:49.32
424>>346
�����傪�����Ă���u���o���v�̕����i�R���ȕ�����2006�j�ł́A�u���n�̍��O�\���͊ԈႢ���Ƃ��āA��R�́w���\�]���x���v�Ə����Ă���B
���㒆����1����500m�Ȃ̂ŁA10�]����5000m�A5km�قǁB ��R�̊C����2440m�B
������A���̕��ł���10�]���́A��R�̕W����10�]����5000m�]��Ƃ����Ӗ��ł͂Ȃ��B
�܂��A���̋L�q��2018�N8��14���t�̐V�������R�����̋L���Ȃ̂ŁA��R�̕W����10�]���Ə����͂����Ȃ��B
�R��ɂ͕_������ƌ����Ă���̂ŁA�R��܂ł̓o��������5km���ƌ����Ă�����́B��
�Ӂ[��H�A�R���ȕ�����2006���A�V�������R�������A
���{�̒J�{�v�Z���܂��m�炸�A�u���ł��ԈႢ�_�v�ɂȂ��Ă���A�z�ł������̂��B 387���{�������j����2019/02/14(��) 04:42:40.52
424>>347
���ɓs���i�����j�͕��ʂ��Ⴄ����A�m���Ȃ��͂O��
�܂��u����͏o�������v�ƕ�����Ȃ���a���A�z���\�t���A�o�Ă����B 388���{�������j����2019/02/14(��) 04:47:21.86
�z�����m�͋C�Â��Ă��邵�m���Ă����
�������_(��)�ɂȂ肽���Ƃ��A����(�_)���Ǝv���Ă���E�E�E��
���������̂���
�S�L�u���ȉ�
389���{�������j����2019/02/14(��) 04:49:17.89
414>>350
�������Ș`�����������s��A��ਓ��{�B���]�u���{�p�����A�ە��`���V�n�v
�Ƃ͂�����A�u�Ⴄ���ł������v�Ə����Ă���B��
���������� �u���Ș`�����������s��A��ਓ��{�v �o�I�`�Œ������Ă邼
���ꂾ�����B���� �_�����Ȃ� ��
���������A���{�`�̎n�߂Ɂu���{���ҁA�`���V�ʎ��v�Ƃ��āA
�ʂ̍��ł���Ə����Ă��鎖���A�܂���������B���̂��H�A
���ꂾ�����a���́A�_�����\�t���Ȃ��B 390���{�������j����2019/02/14(��) 04:50:20.25
414>>351
���������R��
���C�̕����ŏ�����
��a���̂ЂƂ̐_�o����
�z���g����ɂɂ������Ǝv���� 391���{�������j����2019/02/14(��) 04:53:27.37
����Ȃ��Ƃ����w���҂ɂ��Ȃ�Ȃ��@���O�����x����
�Ȃ��E�E�E����(����)�̏������݂Ȃǂ��E�E�Ɠ����ȂƎv���H
392���{�������j����2019/02/14(��) 04:55:34.21
424>>354
�����i��a�j���{���ҁA�`���V�ʎ��A������A�~�B��
���U���R�N���Ȃ�ƌ�������
����v�A�������A�V�����́u�`���`�v�ɏ����Ă��鍑���S���A�E����a�̑�a����Ȃ��炗��
�`������a����A���{������a����
�ʎ���ǂ��f�^�������߂����Ƃ���ŁA����̘`������a����Ȃ̂͊m�肗��
�ق�A�܂��A���́E�E�E�E���\�t�̑�a���A�z�́A
�u�V�����ɘ`���`������v�Ƃ����R�f���x���������Ă���B 393���{�������j����2019/02/14(��) 05:00:51.78
����������i�Ȃǂ��A
����(��)���`�`�`(���낢��)�`�`�`�Ɛ�����������O�̍�i�ł���H
�n�������A��̓��Ƃ�
394���{�������j����2019/02/14(��) 05:02:51.26
424>>362
�����t��a���w�҂͍ߐ[���� 395���{�������j����2019/02/14(��) 05:06:14.78
424>>363
���C�_�ł��A��a���̉��C�w�҂́A�Óc����ɘ_�j����Ă���B
�܂��a�����̉��C�w�҂�
�Óc����Ɋ��ݕt���ꂩ��Ă���Ƃ������Ƃ�
������w��̕���ő�a���͌Ǘ����Ă�
�S���ʕ�͖Ԃ��o���Ă�݂������� 396���{�������j����2019/02/14(��) 05:19:50.74
424>>371
���}��R��́A3���I�ɂ̓��}�h�B ���݂̐�t���̐_��́A�S�E�h�̔����B
���������������̎R���̓��}�h�m�B ����h�ƓǂރP�[�X�́A������ł�����B��
�Ñ�ѐl�Љ�ɂ����ẮA�n�������̐V�K�̎x�z�҂́A
�u�_�v�Ƃ��u�J���C�v�Ƃ��Ă�A
���̋��E�́u�����v���u����g�A�ˁv�ƌĂꂽ�̂����m��܂���ˁB
�܂�u�_��v�̐_�́A��B�`���́u�����ѐl�\�܍��v�̕�����B 397���{�������j����2019/02/14(��) 05:29:54.80
424>>381
���u��7�́@��Ղ���̏،��v�̐_��4���̒�p���S�V�i22�ԁj�́A
���P���t�������A�l����s�̊剮��Ձi�퐶�����`����j����t���t�����V�ɋ߂���
�Ӂ[��A�l���̓��V�Z�\���A��t�ɓS�V�ɕς���ē`������A�Ƃ������́E�E�E�B 398���{�������j����2019/02/14(��) 05:36:19.92
424>>389
���Óc���A�n�}��ŋ��ϓ�����Δn�܂ł�km���v���āA�����痢�Ŋ������̂��u75m�ɋ߂��l�v�B
����ɁA�����@���\�E������̒n�}���km�����痢�Ŋ����āA
���킹��1��75m�`90m���炢�Ƃ����B��
�Óc����́A����Ȏ�����ꂽ�����Ȃ�����A
������E�E�E�E��a�����\�t�̝s���ł����グ�B 399���{�������j����2019/02/14(��) 05:51:58.93
>>377
�e���v���ǂނƁA���������ӌ��������ėǂ��Ǝv��
�����ɔږ�ĂɌ��ѕt����͕̂����� 400���{�������j����2019/02/14(��) 05:59:38.37
���N�O�̉A�d�X��
���`�`�`�`�`�A�l�́��ɂȂ������ǁA��悳��Ă��肾�A
�Ƃ����������݂����Ă���l�������ł���
����A�A�j���A�Q�[���E�E�E���̑�(�|�\�Ȃǂ��܂�)�̘b�A
�Ȃ��m���Ă���l������Ǝv��
401���{�������j����2019/02/14(��) 06:31:09.99
㕌��̌@���������͒n�������̊قł����������
�������͋L�I�o��̐l���̊قł�����
�ږ�Ăƌ��ߑłɂ͍ޗ��s��
402���{�������j����2019/02/14(��) 06:33:22.92
424>>396
���w��90�x��]�x���w�I�b�J���̒䓁�x�Ƃ��ēǂ݉����A�E�E�E
������ɂ��Ă��A�{�������Ƃł͂��邪�{�B�������v���ɔ���Ԃ��Ă���`�܂ŁA
�s���L������肭�ʂ�����Ă��邱�Ƃ�������B��
�u�쁂���v�Ȃǂɂ���āA�~�B 403���{�������j����2019/02/14(��) 06:34:31.67
ERROR: We hate Continuous....
�A���ł���
�₢���킹ID�F4a8a1cc36bfe6e9f
�z�X�g�F219.115.235.241
���O�F ���{�������j����
E-mail�F
���e�F
424>>391
���퐶����̐l�����z�����Ă݂�A

�s���L�����ŁA
1�Ԗڂɏo�������l�����F�z���i2���]�ˁj�͖k��B�̔����p���݁A
2�Ԗڂɏo�������l�����F���n���i5���]�ˁj�͏o�_�i�R�A�A�R�z�܂ށj�A
3�Ԗڂɏo�������l�����F�הn�䍑�i7���]�ˁj�͓ޗǁi�ޗǖ~�n�y�щ͓�������܂ށj�A
�����Ďהn�䍑�ƍR�������z���́A�����炭�͓��C�n��������̐��͂��낤�B��
�z���̔�肪�����������A
�u�쁨���v�̉R�f���x�����V���[�V���[�Ƃ��Ă���Ă��邩��A
���̃T�C�g�̎���A�E�E�E�E��a�����\�t�ł���A�~�B 404���{�������j����2019/02/14(��) 06:38:30.96
�ږ�ĂƂ����̂��A�}�e���X�A�X�T�m�I�E�E�E�H���ƌ��������́H
�r���Ȃ�Ȃ��̂��H
405���{�������j����2019/02/14(��) 06:51:38.90
424>>400
��������ɂ��悱�̐l�����z�����Ă݂�A

�z���A���n���A�הn�䍑�A��z���A���̑��̏����Q��S�ċ�B�ɖ�����l�ߍ���ŁA
�{�B�ɂ��Ắw���������@�n�C���P���@���L���F�`��@���L�ˎݑ���@�l���O�l�ځx
�̂�����28�����ŋL�q����Ȃ�Ă̂́A�ǂ�قǕs���R�Ńo�J�������ƂȂ̂��������낤�B
���ۂɋI��200�N���̐l���ł́A��B����10���l�A�{�B�{�l���Ŗ�50���l�B
�����̋�B�ɐl���ʂɂ����邻�̂悤�ȃL���p�V�e�B�͑��݂��Ȃ��B
�i�o���j�FWikipedea �u�ߑ�ȑO�̓��{�̐l�����v�v
�u�ꕶ�E�퐶����̓��{�̒n��ʈ�Ր��Ɛ���l��(���R�C�O, 1978,1984�N)�v��
������ɂ���A���R�́A
�`�l�`�́u��v���u���v���ƉR�f���x����������ŁA�X�ɁA
鰎u�L�ڂ́u�P�T���ˁv�̓��̂T���˂̓��n���Ƃ̂V���˂̎הn�㚠����B����O���A
�c��́u�ܖ��ˁv���u1�ˁ�2�l�ȉ��H�v�Ƃ��āu��B����10���l�v�Ƃ��Ă��鎖���A
�ۂ킩��B
���R���A�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���́E�E�E�E�A�z�̑�a�����\�t�B 406���{�������j����2019/02/14(��) 06:53:37.02
424>>401
���̓��e�����_�ς݂ł���A�~�B 407���{�������j����2019/02/14(��) 06:53:52.19
>>355
��������鰎u�`�l�`�ɉ�m����(��)�̓��ʼn���Ƒ�p�ƋL����Ă���
���ꂩ�猩��Ǝ��ۂɓ��ɍ��Ȃ�ĂȂ��� 408���{�������j����2019/02/14(��) 06:56:05.15
>>365
���������ƍl�È╨�ƉȊw���茋�ʂ��犮�S�ے肳���̂͋�B�� 409���{�������j����2019/02/14(��) 06:57:52.93
>>407
���{()�̂��Ƃł͂Ȃ��Ƃ����Ӗ��ł��� 410���{�������j����2019/02/14(��) 07:01:53.92
424>>404
���E�E�E���ꂩ��l���Ă��ږ�Ă���B�̕Гc�ɂ̏��U���ł���͂����Ȃ��A
�����̓��{�S�̂��\���闧��̏����ł��������Ƃ͎������낤�B��
鰎u�ɂ́A��B���t�߂̘`�l�炾���ŁA15���˂��Ə����Ă������A
�P�ˁ��T�l�Ƃ���A���ꂾ���łV�T���l�ɂȂ��Ă��܂��B 411���{�������j����2019/02/14(��) 07:05:53.10
���ʂ⋗���ɂȂ�̃A�v���[�`������
�ԈႢ���Ƌ��ԋE�����͂��C����̂���
412���{�������j����2019/02/14(��) 07:11:10.02
424>407
�����{���ɂ��郄�}�g�̒n������B�ɂ�����I
�����A�Ă��Ă邾���̃L�`�K�C��B���ɖ����킹�Ă�����Ă邗������
�͎R���肾����A
��B�`���̎הn������A���̐b���́i���������́j��嗦��A�������R��ɐ�������āA
���̋��E�n�̓�������A�u���}�h�A���}�g�v�Ɩ��t����ꂽ�B
413���{�������j����2019/02/14(��) 07:15:12.13
�{���ɁA���܁[�ɃS�L�u�����N���Ă��邯�ǁA���Ȃ낤
414���{�������j����2019/02/14(��) 07:16:25.04
424>>408
�����_�����B
���V�Ɍ������̂͘`���`�ł��邩��A�`���g�ł���A
���{���g�Ƃ��ď����ꂽ���c�^�l���A�Ƃ͏�����Ă��Ȃ��B��
�����̘`���`�ő��V���ɓ��{���ւ̉�����\���o���A�����R�N�̌����g��
�����{�I�ő�a���삩��h�����ꂽ���c�^�l���Ɗm�F�ł����E�E�E��
����_�����B
�`���`�ɂ� ���c�^�l���Ȃ�āA�S��������Ă��Ȃ��B
�ȉ��������B 415���{�������j����2019/02/14(��) 07:17:48.43
���O�ɑ��S�L�u�����ƌ����Ă����
�ƃ��X(��������)�����Ă���̂�
���̃X����T���ēǂ�ł݂āA
�ǂ̃X������������
416���{�������j����2019/02/14(��) 07:18:07.72
���ꂾ�ȁ@�펯�I�Ȍ�������
----------------------------------------------------------------------------
�O�X��
>>916���{�������j����2019/02/13(��) 07:54:32.33
>>907
��>>739
�����l�Êw�҂̐X�_��(1928-2013)�搶�́A
���u�Z����Ղ̌������o���Ƃ��A���_�̋{�ł͂Ȃ����A���m�̋{�ł͂Ȃ����A
���i�s�̋{�ł͂Ȃ����Ƃ������Ƃ́A�ǂ����ďo�Ă��Ȃ��āA�����Ȃ�ږ�Ă�����̂ł����B�v
���Ƌꌾ��悵�Ă���B
��☝
���^���A�ˑR�̔ږ�Ă͗E�ݑ����Ǝv���B�܂� ���_�̋{�H���m�̋{�H �i�s�̋{�H�ƍl����̂��Ó�
���ӁB
���̋E������鰎u�`�l�`�ǂ��납�����̎j���������������āA�Ǝ��̖ϑz�ɑ���߂��Ă��� 417���{�������j����2019/02/14(��) 07:20:14.74
424>>409
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x�������A
�����Ȃ�w���E���i�̋���ɗ�]���A
�����甽�_���Ă��V�����炵�ē������ƌ�����������
���_�ɂ͔��_�͂��Ȃ�
�����������A�ŏ��̎咣��A�Ă���
�u�����������������v��
���ꂪ��B���K�L�̐����� 418���{�������j����2019/02/14(��) 07:24:18.77
424>>410
��鰎u�`�l�`���ł�̂��H
�`�̂�܂Ƃ̂��ƂȂ�A�הn�䂾��B��
�הn��Ȃ�đ��݂����Ȃ��R���x���̑��ꕶ�������A
�u��܂Ɓv���́A�u�쁂���v�Ȃǂɂ���āA�~�B 419���{�������j����2019/02/14(��) 07:25:25.78
�K�L�Ƃ������A�K�L�̐��_�N��ɂȂ������������V�l�̐l���E�E�E
���f�Ȑ���������Ȃ�
420���{�������j����2019/02/14(��) 07:33:45.11
�X �_��́A���{�̍l�Êw�ҁB���u�Б�w�����_�����B
421���{�������j����2019/02/14(��) 07:33:59.56
424>>418
������v����͖��炩�ɁA���V���@�̎���ɘ`�������{���Ɖ�����\���o���Ɠǂ߂�̂ŁA
��B�g���f�����̐��藧�]�n�͂Ȃ� ��
�ǂ߂Ȃ��B
�������Ɠ���v�́A���{���`�̖`���ŁA
�u���{���ҁA�`���V�ʎ��v�ƒf�肵�Ă���B
��a�g���f�����̐��藧�]�n���Ȃ��B 422���{�������j����2019/02/14(��) 07:37:22.78
�w���_�ȁ@�{�݁x�����ɍs����
423���{�������j����2019/02/14(��) 07:40:16.34
�ǂ��̍��̐_�b�Ȃ낤
��ÁA���̐_�Ƃ����̂�����ł���A
�������הn�䍑�H�̘b�ł͂Ȃ���
424���{�������j����2019/02/14(��) 07:44:53.00
�w��Á@�_�x
425���{�������j����2019/02/14(��) 07:45:20.00
424>>423
���u�Í��؈��y�v�}�v �k�v���`��v�����i�\�I�O���j �u���k�U�n���}�v ��v�i�\�O���I�j�v
����v���u���k��V���v�Ə��������� ���{�̐��k�ɐV��������Ƃ����̂͏펯�݂�����
��B������˂�ł�����
�����A�����a���҂⒆���̌Ñ�j�Ƃɂ́A
�u���ȉ��߂ɋ�����j��n���̏��������③��v���������A�z��
������ł������낤�B
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a���A�c�O�ł����B 426���{�������j����2019/02/14(��) 07:47:58.84
�_�E���̘b�H���̂̂��P�H
427���{�������j����2019/02/14(��) 07:56:18.14
�w�q�h���̎s�x�H
428���{�������j����2019/02/14(��) 08:04:39.70
>>316
���`�ʓy�͘`�����̓]�L�~�X�炵����
����ԌÂ��L�q�ł͘`���������ƂȂ��Ă���
���̐V���̂Ȃ獑���ʂ͂��肻���Ɍ����邯��ǁA���Ƃ��ƍ��͚��Ƃ������������̂�����
�����ʂ͂܂����蓾�Ȃ��Ƃ��Ă������낤
�ʓy���ʏ�ɂȂ��Ă�Ƃ����]�L�~�X�Ƃ����̂ƁA�ǂ����Řb���������Ă��Ȃ����� 429���{�������j����2019/02/14(��) 08:10:07.88
>>385
�����������A�Z����Ղ̑�^�����Q�̒��̍ł��傫�������c�́A����19.2m�A�c��12.4m�B
�����̋K�͂̌������g����h�Ə̂��Ă���킯������A3���I�̈�ʓI�Ȍ����̂���悤�͉����Ēm��ׂ��ł���B
�N���̂��Ă����B
鰎u�`�l�`�ɂ���Ȃ��Ə����ĂȂ�����B 430���{�������j����2019/02/14(��) 08:11:29.98
�w���\�t�ƈꏏ�ɂ����̂����Ȃ̂Łx�H
431���{�������j����2019/02/14(��) 08:17:32.03
�w�T�C�o�[�p���NSPECIAL�x
���g�����Ƃ����̃L�������o�Ă����i�A
�Ȃ�������̓암�̂ق�??�E�E�E�Ƃ����b�ł���A
���Ȃ낤
432���{�������j����2019/02/14(��) 08:19:59.37
�w�T�C�o�[�p���NSPECIAL�x
���g�����Ƃ����̃L�������o�Ă����i�A
�Ȃ�������̓암�̂ق�??�E�E�E�̘b�ł���A
���Ȃ낤
433���{�������j����2019/02/14(��) 08:23:23.17
�E���͑卑����������`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����̂�
�E�����E��a���̍���ɂ���悤���B
�������A����͂����炩�Ȍ��B
鰉����Ɛe���������`�̍��X�݂̂��A鰎u�`�l�`�̎�l���Ƃ��Ď��^���ꂽ�̂���B
434���{�������j����2019/02/14(��) 08:37:46.01
����הn�䍑�ɔ�肷��ɂӂ��킵��������B�ɖ�������E���ɋ��߂Ă邾��
435���{�������j����2019/02/14(��) 08:44:21.03
��������w�L�_�₨��낸�x
�单�V�̉����`�Ƃ����L����������ł���A
�Ȃ��w���܂������I�x�́E�E�E�Ɠ����ȂƎv���H
�w���X�x
�|�̊Ƃ������H
�Ƃ́A�����������O�̉ƂȂ���
436���{�������j����2019/02/14(��) 08:48:22.91
>>433
�G���������珑���Ȃ����Γ`�Ȃ�Ă�����̂�
��B���̓E�X���n���������Ȃ��̂��� 437���{�������j����2019/02/14(��) 08:50:11.76
�u���t�}�[�H
�V�k�������ɂ͈ɒB�S�Ƃ����Ƃ��낪�����ā`
�Ƃ����b�����Ă�����B
�w�T�C�o�[�p���NSPECIAL�x�ɂ������悤�ȃL�������o�Ă���H
�E�ڂ̖����E�E�E�ɒB�S�H
438���{�������j����2019/02/14(��) 08:50:23.29
>>434
������הn�䍑�ɔ�肷��ɂӂ��킵��������B�ɖ�������E���ɋ��߂Ă邾��
�E���̂ǂ��H�@�@���܂�ɂ���G�c�B�@�@�u�E���v�œ�������C�J������B�@�@�����g 439���{�������j����2019/02/14(��) 08:51:22.92
>>399
�������ɔږ�ĂɌ��ѕt����͕̂�����
���Ⴀ������ĐÂ��ɂ��Ă����
���ʂɑ����� 440���{�������j����2019/02/14(��) 08:54:28.65
>>434
������הn�䍑�ɔ�肷��ɂӂ��킵��������B�ɖ�������E���ɋ��߂Ă邾��
�퐶�l�ɂƂ��āA�u���g�v�͂܂��ɗ��z�̓y�n�B
���g�ȋC��E�����̑�͂̌b�݁E��͗���̓y�n�̌b�݁E����������C�̌b�݁E�R�[���X�т̌b�݁E����ނ̊z���̌b��
���k���i�הn�䍑�j�ɂ́A���A�D���Њ�A�ΐF�Њ�A�Ő��A�֖��A�g�@��
���암�i��z���j�ɂ́A�C�����̂��B
���g�ɐl���W�܂�A�Ǝ����������ˁE�S���W�J�����̂́A���R�Ƃ����Γ��R�B�@�@�@�����g 441���{�������j����2019/02/14(��) 08:55:38.51
�单�V�̉����`�Ƃ����L�����������H
�w���܂������I�x�u�Ƃ��݁v�H
����������̓암�̂ق��ŁE�E�E�A
�T�����܂�E�E�E�A
442���{�������j����2019/02/14(��) 08:57:25.00
424>>433
���E�E�E�A�z���^�ے�ق������̖퐶����̖���Ղł݂���Ƃ������Ƃł���E�E�E�A�z���A
�͔�t���t�����V���퐶����͓̉��̈�Ղŏo�Ă���Ƃ������ƂȂ̂ŁA��
���́u�퐶����v�Ƃ����N����ł́A��ΔN��ɂ͂Ȃ�Ȃ�����A
���Ȃ�B
�����̓�̗v�f�ł��z�P�m��3���I�����z���͂n�j�Ȃ̂ł͂Ȃ����B��
�z�P�m�́A�ږ�Ă̙n�ł͂Ȃ��O����~�������A�L�����ł͂Ȃ��A
�Ƃ�����ΔN�ォ��̐��������A
�ږ�Ă̕�ɂ́A�u�쁂���v�Ȃǂ̐�������邩��A�u�R���I�����z���v�́A�~�B 443���{�������j����2019/02/14(��) 09:00:01.61
>>439
�s���j�ς�吺�ŋ���ł���̂͂������B 444���{�������j����2019/02/14(��) 09:04:35.07
���E�̐_�X�H
���[�Ƃ����_(���z�_)�E�E�E�w�f�X���[�x�̂��Ƃł���
445���{�������j����2019/02/14(��) 09:07:05.58
424>>440
�܂��A�ǂ�ȃE�\�����Ăł�
�z�P�m�R�̔N���3���I�����ɂ��Ȃ��Ƒ�a���̎��S�͊m�肾�����
���������邳 446���{�������j����2019/02/14(��) 09:07:06.38
����쉺���W���Q�ł́A�퐶�I�����ɂ͌y�ʔ��^�̓y�킪���ݏo�����B
���E�������˓�������p�ݒn��A����n��E�R��n��ɔ��o���ꂽ���g���\����y��ł���A�����g�^�y��ƌĂ�ł���B
��搫�������A��Ǔ��ʂɃw���P�Y���Ǝw���������c������Z�@�ɓ���������B�y�퐻���ƏW�c�ɂ����̂��낤�B
�ގ��Z�@�ɂ��y��͎]��E�g���Ɋg����A���^�y��̓�k�����`�����Ă���B�@�@�����g
447���{�������j����2019/02/14(��) 09:10:13.42
424>>445
�������� ��a���̒������́A
�����n�_�A�o���n�_�� ���ӓI�ɐݒ肷�邱�Ƃ� ��������Ă���̂Ƃ�
���炩�ɂȂ�̂ł����� 448���{�������j����2019/02/14(��) 09:12:01.19
�قƂ�Ǔn���n(�R��)�̘b�ł���A
���{�N���A���˂̐_�Ȃ�Ă��܂����
�݂����Ȏ��������Ă�l��������A�ǂ̃X������������
449���{�������j����2019/02/14(��) 09:12:02.00
424>>446
��a���҂��A�u�쁨���v�Ȃǂ̉R���x����A�l�|�ȊO�A
�Ȃɂ������Ă��Ȃ����ɂ��� 450���{�������j����2019/02/14(��) 09:12:15.94
�u�����Ձv
�퐶����I�����̏W�����
���R�̓쐼�̘[�A������̎��R��h��ɉc�܂ꂽ�W����ՁB1983�N�i���a58�N�j�ȍ~�����ɂ킽�锭�@�����ɂ��A�퐶����̏I�����̒G���Z���Ղ�ޗǎ���̌@���������ՂȂǂ��������Ă���B
�G���Z���Ղ���͓y���Ί�ȂǑ����̈╨���o�y���Ă���A���ł������g�^�y�킪�����܂܂��_�͈�Ղ̑傫�ȓ����ł���B
���̂ق����ڂ��ׂ��́A�Ԃ��痿�ł���邪�t�������y�킪�����o�y���Ă��邱�Ƃł���B�����̓y��̕��z�͈͍͂L���A�l�X�̌𗬂������ł������l�q���킩��B
�����Ղ̏W�����ɂ́A���L�����ՂɊւ�����l�X����炵�Ă����̂ł��낤�B�@�@�����g
�u�����Ձv�@�@ http://awakouko.info/modules/xpwiki/?%C6%C1%C5%E7%BB%D4%2F%C8%F5%B8%FD%B0%E4%C0%D7 451���{�������j����2019/02/14(��) 09:22:37.25
���Ձi�������O�D�S���݂悵����j�́A�퐶�������̋ʍ��ՂƂ��đ�\�I�ł���B
�Ĉꐫ�̋������^���ʂ̈�Q�����g�n��𒆐S�Ɂ@�]��n��E�g���n��Ɛ����E�ɗ\�n��E�L�O�A�}�O�A��O�n�� �ɓ_�݂��Ă���A
�ށE�F���E�`�����̏ꏊ�ō��ꂽ�ƍl������B
�֖��̐����Ձ@���݂悵�����ՁE�����s����ՁE��������o�ˈ��
���ΎY�o�n�@�������g�����ΒJ�쐅�n�֖��
�������Ō��ʂ��o�y���ꂽ��ՁF���ՁA����ՁA���J��S����ՁA��o���ՂȂǁB
�����Ձi�������O�D�s��쒬�����j�i�퐶�������I���`�Õ�����O�������̏W���j�o�y���Ő������ʂ́A
�V����������ŎY�o�����Ő����g�p���k�����ӂʼn��H���ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩���Ă���B
�o�y�����╨�́A�g��쉺����A�]��A�g�����̔����y�킪�܂܂�Ă���A
�����̌��Ղ͈̔͂�m���ŋM�d�Ȕ����ƂȂ��Ă���B�@�@�����g
�u���Ձv�@http://www.awakouko.info/modules/xpwiki/138.html 452���{�������j����2019/02/14(��) 09:26:38.32
>>450
�鋫�����ɁA�����̂悤�ɏ����Ȉ�Ղ��Ȃ� 453���{�������j����2019/02/14(��) 09:31:46.77
>>452
�����̂悤�ɏ����ȗ������Ȃ� �@�@�����g 454���{�������j����2019/02/14(��) 09:45:55.52
>>458
�u�쁂���v�Ȃǂ̉R���x�������ł͂Ȃ��A�l�ނ̏펯�ɔ����āA
������ǖʂł܂������؋��̏o���Ȃ���a����
�؋��́H�A�����́H�Ɩ����e�ɋ��ԈȊO��
�ł肪�Ȃ� 455���{�������j����2019/02/14(��) 09:53:59.78
>>451
�d���Ő���ɋʂ́u�N�q���́@�ʕs���g�v��ܓ������Ȃǂƌ���ꂽ����
�Ƃ��֖��̓A�X�x�X�g�𑽂��܂ނ�����H������Z���ɂȂ����Ⴄ����� 456���{�������j����2019/02/14(��) 09:55:10.63
>>464
�����������̓��{���̌��g�́A�O������k�ɓ��s�������{�����g�ł������낤�A
�Ƃ������ɂȂ邾�����B��
�����A�����Ԍ������Ƃ���ނ����Ȃ�
�O���O������k�́A�������b��k����Ȃ����Č����Ă��̂ɂ�����
Yahoo�œV�n���A���̎w�E�ŁA
�u���Ђ̏��I�v�ŃE�\�������Ă��������o���ď�����������������A
�����A�u�������b��k�v���Ȃ�āA���������Ȃ���B
���ł��A�`���̌��g�������͂��ꂩ����{���ōs���܂��ƌ���������
�`��=���{���Ȃ͓̂������悤���Ȃ���Ȃ�
���V���A�����u�����ߓ����o�A���j���{���B�v�W�������s�뎧���V�B��
����͑��V�̎��̖��ł���A
���V�Ȍ�́A
����v�̘`���`�́A������Ƙ`���g�߂��L�^���Ă���B 457���{�������j����2019/02/14(��) 10:04:19.03
>>456
�ǂ��������̓A���^���E�\���Ēp�����������Ȃ낤�� 458���{�������j����2019/02/14(��) 10:12:33.86
�ꕶ���̌뎚������������ʐl�@���Ƃ��ʍ����@�Ƃ�
�t���^�[�������p�^��w
459���{�������j����2019/02/14(��) 10:25:46.30
>>469
���`�l�`�̍s���ɋL���ꂽ�ː��́A
��B�����ꂠ����܂ł̋��哇�Ɛݒ肵�ď��߂đÓ��Ȑ����ɂȂ���́B��
����Ȃ�Ă��蓾�Ȃ��B
�`�l���瓾��ꂽ�`���ƁA鰎g��̎��������n��̌ː�����́A�T���T�Z���B
��B���t�߂̒��ł��A���P�Ӛ����z���Ȃǂ̌ː��͋L�ڂ���Ă��Ȃ��B
�����ۂɁA�}��R����ӂɉ���35���l���Z��ł����Ƃ�����A
����͐H�������炩�ɑ���낤��B��
�הn�㚠�̎����˂��P�ˁ��T�l�Ƃ����낤���A
������A鰂́u�ˁv�́A�i�Ƒ��S�����ł͂Ȃ��j�[�ŕ��𐔂̐������ł��邩��A
�P�˕��ςP�`�R�l�ʁA�Ƃ������́A�\���ɂ��蓾��B
���Ƃ������Ƃ́A�s���̌ː����܂Ƃ��Ɉ����K�v�Ȃ���
�Ƃ������́A���̑�a���j��̘b�́A�܂Ƃ��Ɉ����K�v�Ȃ��B 460���{�������j����2019/02/14(��) 10:36:08.15
>>456
������͑��V�̎��̖��ł���A
�����V�Ȍ�́A
������v�̘`���`�́A������Ƙ`���g�߂��L�^���Ă���B
���A�N�������ƋL�^���Ă�H
��B���܂��^���ԂȃE�\���ȁH 461���{�������j����2019/02/14(��) 10:40:21.66
>>459
��������A鰂́u�ˁv�́A�i�Ƒ��S�����ł͂Ȃ��j�[�ŕ��𐔂̐������ł��邩��A
���P�˕��ςP�`�R�l�ʁA�Ƃ������́A�\���ɂ��蓾��B
���̎咣�͂��������ǂ�ȕ����I������������
�ǂ�Ȍv�Z���āu�P�˕��ςP�`�R�l�ʁv�ɂȂ�H
��B���͂܂��ϑz�f�}���H 462���{�������j����2019/02/14(��) 10:40:53.50
>>474
���_��4������V�̓z�P�m�ƌ^�����Ⴂ�A��̌`������Ă���݂��������֘A�͂���̂��낤���H
�_��4����̎��ɐ_��3���悪�����Ă��āA
����3����ɂ̓z�P�m�Ɠ������P���t�����o�Ă���݂���������A������̎����Ǝv����
�����V�ɂ���͂���̂��낤���H
�z�P�m�� ��t���P���t�����V�ŔN�オ��莋����Ă��遃
�z�P�m�́A�S�V�����|�I�ɑ����A���炩�ɂŁA
�S�V�̍��̋�B�`������u�����ѐl�\�ܚ��v�Ŕh�����ꂽ���R�I�n�ʂ̐l�Ԃ̕�ł������\���������A
�����̓��V�́A�����r���ʼn�������ѐl�n�⓺���n�̓��V�����������̂ł������낤�˂��B
���ꂪ�A�_��ł������鎖�Ȃ̂ł́H�B 463���{�������j����2019/02/14(��) 10:44:13.76
>>317
��鰎u�̕}�]�`�E�������`�E�ؓ`�ȂǂɁu�ؗL��ǂ����Ȃ��v��
����ƁA�|�z���u��̖����{�݂��������Ƃ����ۏ͂ǂ��ɂ��Ȃ���
�������Ǝv������ł���悤������ǂ���
�|�z���u��ɂ��Ĉ������T�C�g�ł͂����Ƃ��炵�����ۂ��\���̐}���ڂ��Ă��邯���
����A�����܂Ő���}�������
�������ǂ��ł��������͕�����Ȃ�
�z�P�m�R�Õ��ɂ��ẮA�Έ͂��؞ƌĂ�Ă��邯��ǁA���̎��͂ɒ���������A
����ɒ��������ɂ������������v�킹�钌��������A���̏�ɏ����Ȗؑ������������
�����Έ͂��ŕ������悤�ɂ�������
������ɂ��Ă��A�z�P�m�R�Õ��͞���Ȃ��悗�� 464���{�������j����2019/02/14(��) 10:44:29.33
>>455
���Ƃ��֖��̓A�X�x�X�g�𑽂��܂ނ�����H������Z���ɂȂ����Ⴄ�����
�u�����͂�v �ɂ́A���̐���邪���邩����v����B�@�A�n�n�n�@�@�@�����g�@�@ 465���{�������j����2019/02/14(��) 10:51:32.21
>>462
���A���̔N���莋�Ƃ���
�����I������b������ 466���{�������j����2019/02/14(��) 10:53:33.20
>>463
��������ɂ��Ă��A�z�P�m�R�Õ��͞���Ȃ��悗��
������ɂ��Ă��A�z�P�m�R�Õ��́u�����͂�v �̂��悾�悗���@�@�����g 467���{�������j����2019/02/14(��) 10:54:19.45
���g�͊����̕�������
468���{�������j����2019/02/14(��) 10:55:33.21
�ŋ߂̂����|�C���g�����_�͌Óc�h���͌����ǂ����ŏE�����������Ñ�̈╨�Ɏd���ďグ�Ēp�������ꌏ����
���x�}�W�����
469���{�������j����2019/02/14(��) 10:57:42.25
>>341
��3���I���낤���Ȃ낤���A�ږ�Ă������הn�䍑�Ƃ͕ʂ̍����E���ɂ������Ƃ������Ƃ���B
�E���ɂ����������ږ�Ă̍��ł́u�Ȃ��v�Ƃ���ϋɓI�ȗ��R�͉���Ȃ�
�t�ɁA�؋��͂قڂ��ׂāA�E���̍����הn�䍑�����}�g���ł��邱�Ƃ������Ă���
�ږ�Ă̍�����Ȃ��Ǝv���������Ă���̂́A�����̋�B���̐l�������� 470���{�������j����2019/02/14(��) 10:59:39.50
�]�L�~�X�ɂ��Ă͞����ƍs���̎��̗̂������������Ȃ���_�����낤��
471���{�������j����2019/02/14(��) 11:17:12.22
�E�����E��a���̍���ɂ́A
�E���͑卑����������`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂�����悤���B
�������A����͂����炩�ɖ��M�B
鰉����̑����Ɛe����������B�E�`�n�̍��X�݂̂��A鰎u�`�l�`�̎�l���Ƃ��Ď��^����A
�a���������ߋE�E�a�̒n���́A�����̘`��Ƃ��ĕЂÂ���ꂽ�̂���B
472���{�������j����2019/02/14(��) 11:20:51.57
�����������
��B���̑މ����~�܂�Ȃ�
473���{�������j����2019/02/14(��) 11:21:29.90
�ǂ��̒�]�Ȃ�
474���{�������j����2019/02/14(��) 11:22:54.88
>>469
���ږ�Ă̍�����Ȃ��Ǝv���������Ă���̂́A�����̋�B���̐l��������
�������ɓx�ɓ��̈����A�� 475���{�������j����2019/02/14(��) 11:24:57.63
������Ȃǂ�����ł���A���Ɖ͔��H���{�ł͉͓��E�E�E�A
���̂悤�Ȑl�X�̂ق����ゾ�낤
���������b������Ƃ������Ƃ́A���{�ɓn���Ă��Ă���́H
�ƌ����Ă��E�E�E�����A���{�Ƃ��������̖�����������
476���{�������j����2019/02/14(��) 11:26:23.42
>>467
�����g�͊����̕�������
���g�͊����ꑰ�i�`�l�j�̑��{�R����B�@������V�c�Ƃ̌̋��B�@�@�����獡���V�c�Ƃƈ��g�͋b��ʂ��Ă���ł���B�@�@�����g 477���{�������j����2019/02/14(��) 11:26:40.11
�הn�䍑�E�������A���S�ɔj�]�������Ƃ��A�������Ă���ȁB�B�B
478���{�������j����2019/02/14(��) 11:30:44.41
�E�����E��a���̍���ɂ́A
�E���͑卑����������`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂�����悤���B
�������A����͂����炩�ɖ��M�A�Ўv���A�A�A
鰉����̑����Ɛe����������B�E�`�n�̍��X�݂̂��A鰎u�`�l�`�̎�l���Ƃ��Ď��^����A
�������������ߋE�E�a�̒n���́A�����̘`��Ƃ��ĕЂÂ���ꂽ�̂���B
479���{�������j����2019/02/14(��) 11:38:37.04
����ƁA�Ȃ������Ȃ̂��H�Ƃ��E�E�E
��������t����ꂽ�H
480���{�������j����2019/02/14(��) 11:40:15.55
>>344
�������������܂ł�3���I�̋E���͒}���̑����ɂ��y�Ȃ����W�r��n��ł���
���ꂪ�A��B���̂��s����`�v�����݂̍ł������
�r��]����ՁA�T���ՁA���q����ՂɕC�G����W����Ղ͋�B�ɂ͂قƂ�ǂȂ���
�i�܂������Ȃ��Ƃ͌���Ȃ��j 481���{�������j����2019/02/14(��) 11:40:53.41
�`���̃`�����s�I���A���̒��̉��A�A���X�H��
�����ƌ����Ă�l��������
482���{�������j����2019/02/14(��) 11:42:07.72
>>346
���}��͋_���R�Õ����M���M��3���I�㔼����4���I�O���B
��B���͋_���R�Õ��������グ�����邪�A�K�͂��炢���Ă������i���炢���Ă�
����ӂꂽ�������ɂ������A����ƌ���͖̂����Ȃ��̂ł����Ȃ� 483���{�������j����2019/02/14(��) 11:43:53.99
>>489
���������琅�s20+10���A���s1���̉��n�Ɏהn�䍑�͂��遃
�Ȃ��B
�הn�䍑�Ȃ�đ��݂����Ȃ��R���x�������ł��邵�A
�s�\�����ݓ��]�����قڏI����Ă��鎖�ƁA
�u���s�\�����s�ꌎ�v�́u�������V���s�v�̐����ł��邩��S����̏��v�����ɂȂ鎖��A
�u�쁂���v�Ő��˓��ȓ��́~�ɂȂ鎖�B 484���{�������j����2019/02/14(��) 11:46:36.96
�u�ł������A�u�����A�����E�E�E�Ƃ��A
���̂܂܉��Ƃ������O�̐l����������A
�����̂ق��������Ƃ����Ӗ��Ȃ�Ȃ���
485���{�������j����2019/02/14(��) 11:47:31.37
>>482
�����ĂȂ�ɂ����������B 486���{�������j����2019/02/14(��) 11:47:46.84
>>492
���}�y�S���ɓs�����A�����̓s���Ŕے肷��l�����������Ă������̓[������
�u�쁂���v���A�����̓s���Ŕے肷��l���A
���������Ă������̓[���� 487���{�������j����2019/02/14(��) 11:51:59.51
>>486
����ȑO�ɖ����E�\���U���R�N���ȂɌ����Ă������̓[�������� 488���{�������j����2019/02/14(��) 11:53:56.27
>>361
���הn�䍑�����A
���_��E�̂ق��������悤�Ȋ������������
�Ƃ������A���ؐ��E�̓��̊C�ɓ������̖H���R�����邱�ƂɂȂ��Ă��āA
�������H����ڎw����
�̓�q�ł��A�������E�ɂ͑�l����N�q�������邱�ƂɂȂ��Ă���
�̓�q�F墬�`�P
�����쎊���k���C�L��l���A�N�q���A��ꏖ��A���Җ��A�і��A�����G
�`���́A�����̑�l����N�q���̃C���[�W��������Ă���Ƃ����̂�
鰎u�`�l�`�̋L�q��ǂނƂ��Ɉӎ�����K�v������
�嗤���̏���ȗ��z���E�̏ꏊ�Ȃ�ˁA�����C��̐�l���Ƃ����Ƃ���� 489���{�������j����2019/02/14(��) 11:55:38.26
>>367
�����}�g�����Ǝהn�䍑���������Ă��邾������B
���}�g����=�הn�䍑�ł���W�R������ԍ�����
�����ے肷��ϋɓI�ȗ��R�͂Ȃ�
�Ⴄ�Ƃ����̂͒P�ɋ�B���̊�]�Ȃ��� 490���{�������j����2019/02/14(��) 12:06:20.55
�߂ɏ�艽���`�H�@�D��W�̘b�ł���B
�����Z��ł����ߏ���
�H�����Ƃ����Ƃ��낪�������ƌ����Ă��邵
�w�V�k�k�x
�Ȃ��w�H���x���̂悤�Ȗ��O�����Ă���̂��H
�ނ��[���E�E�E�E�n���ė����l�E�E�E�E���Z��ł�������Ȃ낤
491���{�������j����2019/02/14(��) 12:09:49.60
��(�w���X�x)�H�́A
�ނ��[���A���̋ߏ��ɏZ��ł�����Ƃ������Ă���
�H����A�_���H���������b����������
492���{�������j����2019/02/14(��) 12:13:43.90
�Ȃ����A���܂̕������̂ق��̘b�A�і쒬�H
�삪����Ă��āA�����Ƀ_������������E�E�E�E�A
�d�C�A���d�������`�Ƃ�
�w�V�k�k�x
493���{�������j����2019/02/14(��) 12:16:12.88
>>377
���Z���̌@���������͏@�_�̋���
���ꉽ���낤�Ǝv���Ă���A
>>380
���ŋ߁A��10��V�c��拍���ǂ߂Ȃ��Č�ϊ��������Ă����{�l�������
���Ă��Ƃ��I
�@�Ƃ̎��_�̂��Ƃ��Ǝv���Ă����� 494���{�������j����2019/02/14(��) 12:19:19.23
>>385
���Ƃ���A�ږ�Ă����h�ȒG�����Z���ɏZ��ł����Ƃ��Ă��A�������Ƃł͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B
���̗��h�ȒG�����Z���́A�ǂ��ɂ���H���� 495���{�������j����2019/02/14(��) 12:23:18.02
�{���ɁE�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�A
��̌f����������ǁA�Ƃ̘b�����Ă����Ȃ��́H
�ɒB�S�̐얓���A�і�Ƃ����Ƃ���̘b�A�{�\�A�@�D��E�E�E�A
���ƍ���Ƃ����Ƃ��������Ƃ�
496���{�������j����2019/02/14(��) 12:26:23.33
>>392
���u�V�����ɘ`���`������v�Ƃ����R�f���x���������Ă���B
�V����
�ɓ�S��\ ��B���S�l�\�� ����
�`�C���{
���{�C�Ø`�z��B�����t�ݎl�痢�C���V������C�݊C���C�������C�����܌��s�C��k�O���s�B
������缁C����C�ȑ���B���E�����\�P�C�F�������C���b���V�B�u�{����l�C���@�����B
�����������j�C�L�����C�����j�@�B�����\�L�B��������每���C���������j�V�䒆��C��彥�q�C
�}�O�\�C�F�ȁu���v��j�C���z����B彥�q�q�_�����C�X�ȁu�V�c�v��j�C�o����a�B�B
���H�V���C�����J�C�������C���F���C���V���C���F�ˁC���F���C���J���C
�����_�C�����m�C���i�s�C�������C�������B�������C�ȊJ���\�����_��ਉ��B
����_�C���m���C�������C�������C���C�����N�C���Y���C�����J�C�����@�C
���m���C������C���铁C������C���鉻�C���Ԗ��B�Ԗ��V�\��N�C�����������N�B
���C�B�B���p���C���H�ڑ����v��ǁC���@�J�c���C�n�o�����ʁB�����s�B���s���C�Ԗ��V�����Y�×��B
�������C���c�ɁB������韁C������C��ȍs�C���Е���C�M�Җ`�сG�w�l�ߏ��F��C�����@�C��雉���B
������C�������ѐ����C���ȋ��ʁC���zਈ߁C���E��蘤�������C�ȑ������M�ˁB
���@���V�ܔN�C���g�ғ����B���������C�ٗL�i�x�S歲�v�B���V�B�h�j���m�\���@�C�o����X�s���C
�s�m��V�q�����ҁB�v�V�C�X���V���g�ҏ㏑�B
�i�J���C�����F�����ʁC�����H��賁C�ٌ�鮑�@�l�C��硇�����B
���V�����A�S�Z���\�C���@�������C�ߏo�����V���B����F�����C���q�V沍����B
���C�q�V�q���B���N�C�g���o��蛦�l�B��蛦�����C�����C���g�Ґ{���l�ڋ��C
��������C�ߐl���@���ɏ\步�C�˖��s���B�V�q���C�q�V�����B���C�q�`�����B
�������N�C���g�ꕽ����B���c�K�ĉ��C���`���C�X�j���{�B
�g�Ҏ����C���ߓ����o�C��ਖ��B 497���{�������j����2019/02/14(��) 12:29:12.10
>>421
���u���{���ҁA�`���V�ʎ��v�ƒf�肵�Ă���B
������A�u�ʎ�v�Ƃ����̂͂��Ƃ��Ɓu�������̂̕ʂ̌Ăѕ��v���Ƌ����Ă��邾�낤���� 498���{�������j����2019/02/14(��) 12:30:00.38
�H���_���̗��j
��1936�N�i���a11�N�j�`
�ł��Ƃ͐���(�_�ސ쌧)�ɏZ��ł����ƌ����Ă��邵�A���Ȃ낤
499���{�������j����2019/02/14(��) 12:32:26.40
>>438
���E���̂ǂ��H�@�@���܂�ɂ���G�c�B�@�@�u�E���v�œ�������C�J������B
�T���ՁA�r��]����ՁA���q����Ղ��̑���������̑�W����ՌQ���A
�E����u�l���y��̒i�K�i�퐶����j�ň�̐��͂Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă��邩��A
���͈̔͂��הn�䍑�����˂͈̔͂Ɖ��x�������Ă��邾�낤�� 500���{�������j����2019/02/14(��) 12:37:21.28
>>456
�����V�Ȍ�́A
������v�̘`���`�́A������Ƙ`���g�߂��L�^���Ă���B
���̑��V�ȍ~�̘`���`�ɏo�Ă���
�J���l�N�����B���g�L������k���Ғ��v�B
���A��a����̓������b��k�Ȃ���A�`��=��a����Ȃ̂����m����H���� 501���{�������j����2019/02/14(��) 12:49:55.51
�E�����E��a���̍���ɂ́A
�E���͑卑����������`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂�����悤���B
�������A����͖��M�A�Ўv���A�A�A
鰉����̑����Ɛe����������B�E�`�̍��X�݂̂��A鰎u�`�l�`�̎�l���Ƃ��Ď��^����A
�������������ߋE�E�a�̒n���́A�����̘`�̈��Ƃ��ĕЂÂ���ꂽ�̂���B
502���{�������j����2019/02/14(��) 12:52:22.67
>>499
���T���ՁA�r��]����ՁA���q����Ղ��̑���������̑�W����ՌQ���A
�����̃o���o���̂ǂ����퐶����̑�W���Q�ȂˁH�@���ŏW������Ȃ��́H�@�@�p���������ɂ���������B
���E����u�l���y��̒i�K�i�퐶����j�ň�̐��͂Ƃ��Ă܂Ƃ܂��Ă��邩��A
�퐶�y������������Ɍ����Ă�www �y�ʔ��^�y�킾��A�ږ�Ă̎���́B�@���e���B�@�@�����g
�����͈̔͂��הn�䍑�����˂͈̔͂Ɖ��x�������Ă��邾�낤�� 503���{�������j����2019/02/14(��) 12:55:54.73
>>499
�����͈̔͂��הn�䍑�����˂͈̔͂Ɖ��x�������Ă��邾�낤��
�������x�������Ă���̂́A�N���ˁH�@�@�R�\�R�\�����B�ꂵ�Ă���C�J������B�@�@�����g 504���{�������j����2019/02/14(��) 12:59:11.28
wiki�w�H���� (�����s)�x�ɂ��Ē��ׂĂ݂��Ƃ���A
�H萊�n��A�������Ƃ����Ƃ��낪����ł���
�w���{�̘b�@�W�����x�H
505���{�������j����2019/02/14(��) 13:02:31.89
�l�V�������ĐF�X�䂪������
�F�X�ȓ`�����c���Ă���
���^��ł������������̊����ƂƂ��ɐΐ_�ɕς�����Ƃ����`��������A���������J���Ă���
�����ɂȂ�Ƃ������`�[�t�͂�����x���L����Ă����̂���
�吨�͂������̂�������Ȃ�
506���{�������j����2019/02/14(��) 13:04:21.96
>>471
���E���͑卑����������`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂�����悤���B
���ӂ̔؈̂̍��̉��F��ɁA�嗤�����͌��\�C���g���Ă���
���̖�����푰�ň�Ԃ̐��͂̃g�b�v�ɉ������o���̂łȂ���A
�������o�����c��̌��Ђɏ��������ƂɂȂ�
������A�u���v�����ƔF�߂�v�ł͂Ȃ��A�����g�E����g���킴�킴�h�����āA
���̍�����m�F���Ă���
���̌��ʁA���n���ܖ��˂�A�z���˂��`�����̑卑�Ƃ��ċL�^����Ă����
��B�Ɩ{�B�̋����ŁA�ʂ̍��������ꂽ��͂��Ȃ�������Ă��Ȃ�
�܂��A�����`���Ƃ��A���̌�̎������{�̊����f�Ղł͑喼�����{������
������Ă����Ƃ����̂�Ƃ��ďグ��l�����邯��ǁA���{�����{��
�ő吨�͂Ȃ̂͊ԈႢ�Ȃ����A�א���������{�̑�\�i��G�̂��Ă���
�ꍇ�����邪�j�Ƃ��Ėf�Ղ��s���Ă��� 507���{�������j����2019/02/14(��) 13:05:55.56
�і쒬 (�����s)�ł���H
�{���ɁA�ǂ������b�Ȃ낤�A
wiki�ŗǂ�����A���̂ق������Ă݂�
�u�����s�̒��E���v�Ƃ����Ƃ���
508���{�������j����2019/02/14(��) 13:09:53.23
��Ȓn��Ƃ����Ƃ���ɁA���{�Ƃ������H
�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H�H❔
509���{�������j����2019/02/14(��) 13:12:53.97
>>506
���ӂ��ǂ��킩��ʂ��A�A�A
���̖�����푰�ň�Ԃ̐��͂̃g�b�v�ɉ������o���Ƃ����̂͂��̂Ƃ���B
���ꂪ�A�ѕ��S�̎x�������S�̋�B�הn�䍑�������ƁA�I���͂��������킯���B
�i�܁A�����A�א�A����͌㐢�̎���Ƃ��Ă͗ǂ����A�O���I�̎Q�l�ɂ͂Ȃ�ʂ�ȁE�E�A�j 510���{�������j����2019/02/14(��) 13:18:15.74
>>509
�����ꂪ�A�ѕ��S�̎x�������S�̋�B�הn�䍑�������ƁA�I���͂��������킯���B
�u�S�̋�B�הn�䍑�v�́A�Ȃ��B�@�@�@�S���f�R�A�`���i���g�j�B�@�@�c�O�ł����B�@�@�@�����g 511���{�������j����2019/02/14(��) 13:18:21.19
���{�E�E�E�H�w�T�C�o�[�p���NSPECIAL�x�H
���g�����Ƃ����L�������Z��ł���Ƃ���̋ߏ��ł���A
����̓암�̂ق�
512���{�������j����2019/02/14(��) 13:20:36.06
>>509
�����ꂪ�A�ѕ��S�̎x�������S�̋�B�הn�䍑�������ƁA�I���͂��������킯���B
�u���������v�ł͂Ȃ��A������Ɓu��̓I�ɍ����������āv�_���ĂˁI��
�ꕶ�ȗ��A���ݍq�s�Œ��������Ղ��s���Ă��Ă��āA���݂̌𗬂��\���ɂ������`������
�퐶�I�����ɂ͊e�n�ŋ��啭�u�����鎞��ɓ����Ă���̂ɁA�߂ڂ���������Ȃ��k����B��
�ő吨�͂��Ƃ����̂́A�܂Ƃ��Ș_���I�v�l�͂̂�����{�l�ɂ͖������� 513���{�������j����2019/02/14(��) 13:24:48.73
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
514���{�������j����2019/02/14(��) 13:33:32.48
>>512
���g���Ȃ��ċ�̓I�Ȃ��Ƃ������Ȃ�����ݒɂ���Ȃ��̂���B���� 515���{�������j����2019/02/14(��) 13:34:38.14
>>513
�A����Ǔ_���A�{���Ɋ؍�����D������Ȃ���
���Ă�A�u�הn�䍑�͋�B�A�c���͔����o�g�v���Č����������Ă���̂��A
�����n�����Ă̂̓o���o���Ȃ̂ɂ� 516���{�������j����2019/02/14(��) 13:40:47.18
�הn�䍑�E�������`����؍����{�Ɍٗp���ꂽ�؍��l���A�הn�䍑�E�������j�]�������Ƃ�F�߂āA�V������`�̍��q���f�����̂ł͂Ȃ��̂��ȁB�B�B
515���{�������j����2019/02/14(��) 13:34:38.14
>>513
�A����Ǔ_���A�{���Ɋ؍�����D������Ȃ���
���Ă�A�u�הn�䍑�͋�B�A�c���͔����o�g�v���Č����������Ă���̂��A
�����n�����Ă̂̓o���o���Ȃ̂ɂ� 517���{�������j����2019/02/14(��) 13:45:51.34
>>516
���̃X���b�h�ŁA���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���A�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A
�`�l�Ƃ����������A���X�́A��B�𒆐S�Ɏl���ɔɉh���Ă������{�����̌ŗL�̑c��Ƃ������Ƃ��A�B�����߂ɁA�V�����v�z���`���悤�Ƃ��Ă���̂ł́A�Ȃ��̂��ȁB�B�B 518���{�������j����2019/02/14(��) 13:48:00.35
>>517
515�Ԃ̓��e�\�����A�הn�䍑�E�����̐�`�W���́A�؍��l���k���N�l�̂ǂ��炩�ł́A�Ȃ��̂��ȁB�B�B 519���{�������j����2019/02/14(��) 13:48:21.20
�������킢�z
520���{�������j����2019/02/14(��) 13:51:40.61
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
�؍��l��k���N�l�̐�`�W�����ł��Ă���ȁB�B�B
521���{�������j����2019/02/14(��) 13:51:54.81
�W�����ɏo�Ă���ւ�����ł���A
�{���́E�E�E�Ƃ������{���́H
���̎�(�{���̂ق��͗��H)�𓁂⌕�Ŏa��E������A
�ގ��������Ƃ����b�E�E�E�H
522���{�������j����2019/02/14(��) 13:55:21.38
�ǂ�ǂx��(�X�P�[��)���������Ă��Ă���́H
�ǂ������R���Z�v�g�Ȃ낤
����Ƃ��w�X�̐��E�x�Ƃ����ȁH
523���{�������j����2019/02/14(��) 14:21:09.32
�P0 ���_�V�c
11 ���m�V�c
12 �i�s�V�c
㕌��̌@����������萌W���肻���ȓV�c
�ږ�Ă̂ł開�͖���
524���{�������j����2019/02/14(��) 14:46:31.49
>>523
��㕌��̌@����������萌W���肻���ȓV�c
���ň�Ղ����Ԃ肷���B�@�@�����g 525���{�������j����2019/02/14(��) 14:46:44.24
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
526���{�������j����2019/02/14(��) 15:08:40.47
>>512
>�퐶�I�����ɂ͊e�n�ŋ��啭�u�����鎞��ɓ����Ă���̂ɁA�߂ڂ���������Ȃ��k����B��
>�ő吨�͂��Ƃ����̂́A�܂Ƃ��Ș_���I�v�l�͂̂�����{�l�ɂ͖�������
�u���啭�u�����鎞��E�E�v�Ƃ����̂��}�`�K�C�̍����B
�ȂA�ږ�Ă̕�́u�ˁv�������̂�����ȁB������Ƃ�����C�����Ă̓C�J���B 527���{�������j����2019/02/14(��) 15:16:57.53
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
�؍��l��k���N�l�̐�`�W�����ł��Ă���ȁB�B�B
528���{�������j����2019/02/14(��) 15:35:27.81
>>512
>�퐶�I�����ɂ͊e�n�ŋ��啭�u�����鎞��ɓ����Ă���̂ɁE�E
���啭�u��āA�Ȃ�̂�������H
��̗��������B�A 529���{�������j����2019/02/14(��) 15:39:24.64
>>526
���ȂA�ږ�Ă̕�́u�ˁv�������̂�����ȁB������Ƃ�����C�����Ă̓C�J���B
�قƂ�ǂ̌Õ��͗��j�I��
�˂ƌĂ�ė������� 530���{�������j����2019/02/14(��) 15:47:22.44
>>85
�L�I�̐_�b�͂����Ȃ��Ă��邪�A�Ώ�ɕ�������������葽���̍H�[�����悤�ɂȂ�͍̂l�Êw�I��5���I�Ƃ���Ă���B
����ȑO�̕������̎p�͕s���ł͂Ȃ����B
�k�͓��ɂ͂����̂�������Ȃ����B
�k�͓��������̐�c�̐_�b���j�M�n���q�ł͂Ȃ����B
�_���́A�n��̉\�������邵�B 531���{�������j����2019/02/14(��) 15:52:17.89
>>87
�������������������邩���ȁ`�B 532���{�������j����2019/02/14(��) 15:58:41.43
>>109
�F�P�́A�����l���������̂��B 533���{�������j����2019/02/14(��) 16:01:05.93
>>529
���قƂ�ǂ̌Õ��́A�i���{�́j���j�I��
���˂ƌĂ�ė�������
���{�̗��j�ł͂ǂ����������m��ʂ��A�b��̘`�l�`�͒����̗��j�����B
�����ɂ����Ēˁi���傤�j�ƕ��i�ӂ�j�͂ǂ������ʒu�Â��������̂��Ŕ��f���Ȃ��Ă͂Ȃ�ʂ��낤�B 534���{�������j����2019/02/14(��) 16:07:13.88
>>115
��R�́A��x�s����20km���炢�̈ʒu�����B
�C���L�`�Ƃ����܂��ɁA�O�\���̌v�Z���o����B
�ǂ��ő��ʂ����Ƃ����B
���̈ʒu�������Ə�����ȁ`�B
�C���L�`�͂��傶���B
��͂͂͂͂́B 535���{�������j����2019/02/14(��) 16:17:56.95
�n�F������B�i說�������j
536���{�������j����2019/02/14(��) 16:24:20.27
>>533
�O����~�����n�łȂ�
�Ƃ����䗬�����ɂ�
�Ȃɂ��������Ȃ�
�܂������Ȃɂ� 537���{�������j����2019/02/14(��) 16:29:22.23
>>122
�Z����Ղ̊O�Řd�����āA��^�����܂Ŏ����Ă����ɂ�1�������邶���B
�т�`�́A��߂Ă��܂��āA�܂����B 538���{�������j����2019/02/14(��) 16:35:21.50
>>115
���܂��A�W���Q�O�O�O���ȏ�̓Ɨ����I���R�ł��邩��A
�����Ȃ艓���̕W���̒Ⴂ�i�O�p���ʂ��o����j�n�͒T��������ł�����A
���A�O�p���ʂŕW�����o����C�ł���`�G�I�N��������� 539���{�������j����2019/02/14(��) 16:41:49.00
>>145
�A�z���Ⴄ�B
�Z�ނƂ����̂́A�ߐH�Z���ƒ��w�Z�ŏK�������낪�B
���̐H�̍��Ղ��Ȃ��ƌ����Ƃ��B
�S�c��Վ�����̂��Z�ނƂ����B
�H�킸�ɐQ�邾���Ȃ�A�����~�C���ɂȂ邵�ȁB
�Ƃɂ����A���̌@�����Ē��ŐH���ďZ�Ƃ����̂�����A����͐H�������Վ�����ƂȂ��B
������L�����L�����i�����A���i��������B
��͂͂͂́B 540���{�������j����2019/02/14(��) 16:50:26.52
>>153
����̓A�z�݂����ɋ��ԑO�ɁA�Z���̑�^�����c�ɐl���Z���Ƃ��ؖ����B
����A�W�A�̐��c�n�т̌@�����Ē��Z���ł́A�ϐ����͒n�ʂł��Ă邼�B
��^�����c�̋ߕӂɂ���ȐՂ�����B
�Ȃ��Ƃ����̂������̌��ʂ����B
����A�A�z���Ⴄ�B 541���{�������j����2019/02/14(��) 16:55:50.77
>>156
�A�z���Ⴄ�B
�G�����̒����ƁA�@�����Ē��̌��͑o���قȂ�̒m���̂��B 542���{�������j����2019/02/14(��) 16:59:59.06
>>160
�A�z���Ⴄ�B
�N���A�g�샖�����ږ�Ă̎הn�䍑��Ƃ����Ă�́B 543���{�������j����2019/02/14(��) 17:04:31.19
424>>503
���הn�䍑�Ƃ����̂̓��}�g�ɂ����������Ȃ���
���}�g�����ȊO�̂Ȃ�ł�����܂� ��
�הn�䍑�Ȃ�đ��݂����Ȃ��R���x�������ł��邵�A
�הn�㚠�̎��Ȃ�A�u�쁂���v�ɋ����āA�~���B 544���{�������j����2019/02/14(��) 17:08:28.94
>>539
�����̐H�̍��Ղ��Ȃ��ƌ����Ƃ��B 545���{�������j����2019/02/14(��) 17:09:47.56
�ŁH
�N���A�H�̍��Ղ��Ȃ��ƌ����Ƃ��H
546���{�������j����2019/02/14(��) 17:10:13.87
>>181
�ږ�Ă����݂����ɓZ���̌@�����Ē��q�ɂɏZ��ł����Ƃ�������̖��z�́A�A�z�̏ؖ����ȁB 547���{�������j����2019/02/14(��) 17:12:05.80
548���{�������j����2019/02/14(��) 17:12:24.62
>>540
���Ȃ��Ƃ����̂������̌��ʂ����B
������A�A�z���Ⴄ�B
�͂��A���̒����̌��ʂ������Ă� 549���{�������j����2019/02/14(��) 17:13:10.38
>>545
�ϐ������ďZ���Ղ���B 550���{�������j����2019/02/14(��) 17:14:12.39
>>548
�A�z���Ⴄ�B
�Ȃ����ׂ��B 551���{�������j����2019/02/14(��) 17:14:21.87
>>547
������s�̋��{�P�F�B
�������Ƃ����؋��́H 552���{�������j����2019/02/14(��) 17:16:23.83
>>550
�܂�A�܂���B����
��؏؋��Ȃ��ɉ䗬���������������Ă����
�����������Ƃł��ȁH 553���{�������j����2019/02/14(��) 17:18:00.81
424>>504
�������������{���`�́u�J���l�N�A����g���v�v�ƁA
����v�`���`�́A�u�J���l�N�����A���g�O������k���Ғ��v�v�́A
�����N���ł��邵��
������Ⴛ���� �������̓�����s������
��P�X���g�@���a5�N�i838�N�j ��g�F������k�@���g�F����� �~�m�炪������
�`���`�Ɠ��{���`�ɏ���������ꂽ�A�Ƃ����������Ԃł���A
�`���̎g�߂𖼏�����̂́A�O������k���A�Ƃ��������B
�܂�A�`���Ɠ��{���̗������猭�g�������A�������ɂȂ�B
�� 554���{�������j����2019/02/14(��) 17:18:15.43
>>549
���ϐ������ďZ���Ղ���B
�����
�X�X�̕t�������їp�y�킪�R�ق� 555���{�������j����2019/02/14(��) 17:20:42.56
>>553
���`���`�Ɠ��{���`�ɏ���������ꂽ�A�Ƃ����������Ԃł���A
����͂��Ȃ��́u���߁v�ł���
�����Ă��ꂪ�u���ԂȂ̂��v�Ƃ�����`�咣
�������A�؋��͖��� 556���{�������j����2019/02/14(��) 17:27:01.37
>>368
�הn�i�����z�����ɓs�����݂�Ș`
3���I�O���̖k��B�͏������A���̈ꕔ
�ȏ� 557���{�������j����2019/02/14(��) 17:27:58.52
>>550
���A�z���Ⴄ�B
���Ȃ����ׂ��B
�������邾����������
���������؋��͏o���Ȃ�
���ꂪ��B���Ƃ��������� 558���{�������j����2019/02/14(��) 17:28:12.72
>>554
�����A���n�l��O���l���Z���̓y�؍H���̂Ƃ��ɒ��тɎϐ��������P�����B
�@�����Ē������c�̋߂��ɁA�����ɂ킽���Ďϐ��������y��⏬���Ղ�����B 559���{�������j����2019/02/14(��) 17:30:23.08
>>558
�������A���n�l��O���l���Z���̓y�؍H���̂Ƃ��ɒ��тɎϐ��������P�����B
㕌��́A�Õ����c�O����n������ˁB�@�@�����g 560���{�������j����2019/02/14(��) 17:30:57.07
>>557
�l�ɗ���ȁA����w�͂����B
���ꂪ�`�A�����́`�A�ƂƂȂ�`�B
�������A����ɂᖳ�����`�B 561���{�������j����2019/02/14(��) 17:31:27.49
424>>511
��㕌����הn�䍑�̓s�̒��S���J��ŁA���ꂪ���}�g�����̐��_�A���m�A�i�s�O��̋{���Ȃ�
�̂��̃��}�g�����ł͂Ȃ��A���̂܂܃��}�g�������̂��̂��恃
�הn�䍑�Ƃ������݂����Ȃ��R���x���������g���āA
�Z�����הn�㚠�����V���s�ł��邩�̂悤�Ȍ�����������A
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 562���{�������j����2019/02/14(��) 17:34:01.43
>>559
�Z���́A���J�{�݂ƕ��̏ꏊ�B
�l���Z��ŕ�炵���ꏊ�ł͂Ȃ��ȁ`�B 563���{�������j����2019/02/14(��) 17:35:52.36
>>560
�܂�A�܂��E�\�����̂ˋ�B��
ww 564���{�������j����2019/02/14(��) 17:37:54.44
>>551
�Ȃ����ׂ��B
�A�z���Ⴄ�B 565���{�������j����2019/02/14(��) 17:39:24.85
>>523���{�������j����2019/02/14(��) 14:21:09.32
���P0 ���_�V�c
11 ���m�V�c
12 �i�s�V�c
㕌��̌@����������萌W���肻���ȓV�c ��
☝
�˕�䂦�����Ɍ��E�����邪�m���I�ɂ͉\���͍����Ǝv�� 566���{�������j����2019/02/14(��) 17:39:38.93
>>562
���l���Z��ŕ�炵���ꏊ�ł͂Ȃ��ȁ`�B
�Õ����c�Ɍg������l�͗Վ��I�ɂ͏Z��ł��B�@�@�����g 567���{�������j����2019/02/14(��) 17:40:43.76
>>558
�������A���n�l��O���l���Z���̓y�؍H���̂Ƃ��ɒ��тɎϐ��������P�����B
��y�؍H���͒��N�������ˁH
�܂�A�ϐ��������ꏊ���m�F�ł��Ȃ��Ɛl���������Ă��Ȃ��A�Ƃ����咣�����藧���Ȃ����Ƃ͏ؖ����ꂽ 568���{�������j����2019/02/14(��) 17:41:07.89
424>>512
�����n���̋L�q�Ǝהn�䍑�̋L�q�͍\�������ꁃ
�ʂɓ���ł��Ȃ����A�הn�䍑�Ȃ�đ��݂����Ȃ��R���x�������B
�܂��A���n���́A�����T�����Ƃ��Ă̐����B
�����āA�הn�㚠�́A�����V���s�Ƃ��Ă̐����B 569���{�������j����2019/02/14(��) 17:41:33.96
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
570���{�������j����2019/02/14(��) 17:41:56.89
>>565
���˕�䂦�����Ɍ��E�����邪�m���I�ɂ͉\���͍����Ǝv��
�܂������A�����B�@�V�c�̗˕�ł��A�����@�@�����g 571���{�������j����2019/02/14(��) 17:42:36.90
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
572���{�������j����2019/02/14(��) 17:42:46.97
>>564
���Ȃ����ׂ��B
���A�z���Ⴄ�B
�咣�͖��������ɂ���
�؋��͐�Ώo���Ȃ�
��B���Ƃ������C�y�Ȑ�����
�w���Ƃ��Ď��ʂ͓̂�����O�ł��� 573���{�������j����2019/02/14(��) 17:44:23.09
���J���̌������g���فh�����āB
�v�v�v�B
574���{�������j����2019/02/14(��) 17:45:39.84
>>568
�ق��
��B���͏؋����o���Ȃ�
�}�C���_���������邾�� 575���{�������j����2019/02/14(��) 17:48:18.92
���}�g�͔ږ�Ă�הn�䍑�Ɩ��W�̘`�n���낤��
576���{�������j����2019/02/14(��) 17:48:47.86
>>523
��㕌��̌@����������萌W���肻���ȓV�c
���ږ�Ă̂ł開�͖���
��B���͍l��������Ȃ�����v������Ȃ��悤������ǁA�q���q�R����
�q�������ږ�āA��^�ŁA�q�R�������_�A���m�A�i�s�ƍl����܂����������������Ȃ� 577���{�������j����2019/02/14(��) 17:50:23.17
>>572
����A��^�����c�ɔږ�Ă��Z�؋������ă`���B
�咣�͖��������B
�؋��F���B
����́�@�A�z�̑�a��`�ҁ�
���z�̉ʂĂɖ쐂�ꎀ�Ɂ�
�[�͒��̉a�ƂȂ��
��[�́A�Z����Ղɑ����Ă�邩��A���S���Ă��̐��֗������ȁB 578���{�������j����2019/02/14(��) 17:50:35.89
>>574
�A�z��
���n���̗l�q�͘`�l�`�ɋL�q����Ăˁ[�� 579���{�������j����2019/02/14(��) 17:51:16.07
��B���̂悤��
���R���Ȃ��f�����
���Ă�l�����̐���
���Ԃ���Y����Ă����̂�
���R�̂��Ƃ�
������
�������l�͗��R���킩��Ȃ�����
�킯�̂킩��Ȃ����Ƃ��茾������l��
���܂ł������X����킯�Ȃ����
580���{�������j����2019/02/14(��) 17:51:28.52
>>526
���u���啭�u�����鎞��E�E�v�Ƃ����̂��}�`�K�C�̍����B
���ȂA�ږ�Ă̕�́u�ˁv�������̂�����ȁB������Ƃ�����C�����Ă̓C�J���B
�Õ��̂悤�ȕ��u���u���ˁv�Ƃ����̂���
�ږ�Ă̕悪�u�ˁi�n�j�v�Ȃ̂����炻�̂��̂��낤����
��B���̓U���R�N���͂��߂Ƃ��āA�����̏�����߂𐳂����Ɗ��Ⴂ���Ă��邩��ɁX������ 581���{�������j����2019/02/14(��) 17:52:26.06
582���{�������j����2019/02/14(��) 17:52:29.03
583���{�������j����2019/02/14(��) 17:54:56.97
>>577
������A��^�����c�ɔږ�Ă��Z�؋������ă`���B
���咣�͖��������B
���؋��F���B
������́�@�A�z�̑�a��`�ҁ�
�|�̂Ȃ��I�E���Ԃ���
���
�u��^�����c�ɔږ�Ă��Z�v
�ƒN�����������؋������Ă� 584���{�������j����2019/02/14(��) 17:55:39.77
>>528
�����啭�u��āA�Ȃ�̂�������H
����̗��������B�A
�ق���
�g���̏|�z���u��͓�̕��`�ˏo�������ĕ��u��72���[�g��
�o�_�̐��J9����͎l���ˏo��ł��̓ˏo���܂œ����Ƃ��悻60�~50���[�g��
�O�g�̐ԍ⍡�䕭�u��͓���36m�A��k39m�A����3.5m�̕��u���ɉ����l����5〜9m�̕��R��
�ĂȃT�C�Y������
�E���Z����Ղł͂����Ƒ傫��
㕌��ΒˌÕ��őS��96���[�g���A
���c��ˌÕ��ŕ��u��120���[�g������
�k����B�ł��A�ږ�Ă����O�̎���ɂ�
�O�_�쏬�H��Ղ̕��u�T�C�Y������̎��a��30���[�g���l�����炢
�{�艪�{���D�n�_���u��������x�̃T�C�Y
�g�샖����Ղ̖k���u��ł���k��40m�A������27m�̒����`�ɋ߂��`�ԁA�Ƃ����傫��������
�����P����@12�~8���[�g��
�_���R�Õ��@25���[�g���̕����@�Ƃ����̂́A����肷��Ȃ�Ă���Ȃ�����H
����1����̖ʐς́A�g�샖����Ֆk���u���10����1�ȉ��� 585���{�������j����2019/02/14(��) 17:56:18.81
586���{�������j����2019/02/14(��) 17:57:34.72
�T���ȉ��̋�B���Ɖ�b���Ă����ʂ�
����܂Ƃ��Ȏ��m��Ȃ������
�����j�ɋ�B�Ȃ�đS������ɂ�����ĂȂ��̂Ƀo�J�ۏo���̖ϑz�ł������
587���{�������j����2019/02/14(��) 17:57:35.91
588���{�������j����2019/02/14(��) 17:58:30.73
��z���Ɛ푈��Ԃɂ���̂�
���}�g�ŕ�Y���Ă��͎̂הn�䍑�Ŗ����؋�����ˁ[��
589���{�������j����2019/02/14(��) 17:59:12.44
>>579
�E�\���A�Ă��Ă���l���͐M����A�ƌ������̂̓q�g���[�̎q���Q�b�y���X�B
��a��`�҂��A�ȂA���ĂȂ����B 590���{�������j����2019/02/14(��) 18:00:02.93
�`���P�ȒG���Z�������Ȃ��i�j
����{���Ă������̑�Վi��Ձi�j
���̏Z����B�̌���
�ǂ��ɋ{�a�������ł����[�H
�ǂ��ɍ��J��Ղ������ł����[�H
�Ȃ�ɂ��ˁ[��Ȃ������������c�`�O���̏Z�ރh�c��
���ꂪ��B
591���{�������j����2019/02/14(��) 18:00:15.86
��̓I�Șb�̂ł��Ȃ���B��
����ĂȂ�����
�ł���킯�Ȃ����
�]���̌��_��߂��ȊO���邱�ƂȂ�
592���{�������j����2019/02/14(��) 18:00:37.22
�g�샖���̂�14�l��
�����P���͋g�샖���ɂ͏����Ă���
593���{�������j����2019/02/14(��) 18:01:33.83
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
��B������畷�����Ȃ��U�肵�Ă����ꂪ����
594���{�������j����2019/02/14(��) 18:02:11.40
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
�\������B�L�`�K�C���ǂ�Ȃɓ�����낤�����ꂪ����
595���{�������j����2019/02/14(��) 18:02:40.91
>>585
�����オ�Ⴄ���ǂ�
�������A�Z���̌Õ����c�͌Õ�����B�@�@�����g 596���{�������j����2019/02/14(��) 18:03:06.07
>>590
���ꂪ�ˁA㕌����N��̌Â��g��P���̕���
�s�s�Ƃ��ĕ������x�������̂���� 597���{�������j����2019/02/14(��) 18:03:24.32
>>533
�����{�̗��j�ł͂ǂ����������m��ʂ��A�b��̘`�l�`�͒����̗��j�����B
�������ɂ����Ēˁi���傤�j�ƕ��i�ӂ�j�͂ǂ������ʒu�Â��������̂��Ŕ��f���Ȃ��Ă͂Ȃ�ʂ��낤�B
�n�@
��������
������B����豖�߁B�m譐� ���\�܁@�d�O
����������
������B�y���H�B���ҁA���B��V���ҞH�n�B���X�n�l������V�n����B
���R�]�B�R���H�n�B�A���n�l�]�B�n�A���yu���B�ۙn��ਔV�B���n����說��B
���șn����V��偁�B���s�p����說�B���L�V�}����H�n�B�R�y�\���V��B�B
�R���H�n�B�T�ؙn偁���B���e�H�B�n�A���B���q�H�n�q�B���ɞH�n�ɁB�����B��景�`�B
豖�߁B�m譐B�㕔�B��豖�ߖ{�ݎO���B��������B�É��n�K��椔@����B
���˂����Ŗ��Ȃ����A���{�ŌÕ��ƌĂ�Ă�����̂͊ԈႢ�Ȃ��u�n�v����
http://www.zdic.net/z/15/sw/51A2.htm 598���{�������j����2019/02/14(��) 18:03:36.97
>>588
����z���Ɛ푈��Ԃɂ���̂�
�����}�g�ŕ�Y���Ă��͎̂הn�䍑�Ŗ����؋�����ˁ[��
�푈���ɂ���Ƃ����؋��́H
���Ȑ\�������ł���H
�j���ɂ͐푈�̖ڌ����̓[���ŁA�a100�]���̕�����H�������Ă��Ɩ��L����Ă邪�H 599���{�������j����2019/02/14(��) 18:05:09.34
>>537
���Z����Ղ̊O�Řd�����āA��^�����܂Ŏ����Ă����ɂ�1�������邶���B
�Z����Ղ���������Ղł��A�����܂ő傫���͂Ȃ��悗��
1�L���������ΓZ����Ղ̊O�����^�����܂ōs������
15�����炢���Ȃ� 600���{�������j����2019/02/14(��) 18:06:09.88
>>583
�Ƃ��Ƃ��A�����ȁB
�o�J���m�B
������A�ږ�Ă������c�ɏZ�Ǝv���ĂȂ��A�Ƃ������Ƃ��ȁB
�悵�A�悵�B
�������́A�q�ɂ����J���ɉ��C�����{�݂łn�j�ƁB
��͂͂͂͂́B 601���{�������j����2019/02/14(��) 18:07:40.21
>>539
�x���ŗ�ɂȂ��Ă��Ă邼����
���Z�ނƂ����̂́A�ߐH�Z���ƒ��w�Z�ŏK�������낪�B
�u�Z�ށv�Ƃ����̂́A�ߐH�Z�́u�Z�v��������H����
�����̐H�̍��Ղ��Ȃ��ƌ����Ƃ��B
���S�c��Վ�����̂��Z�ނƂ����B
�������́A�u�Z�ށv�ł͂Ȃ��u�����v�ƌ����Ă�����H
�Љ���Ƃ��A������ԂƂ��������t������
�ږ�Ă̐����̏ꂪ�A���������ʼn�����肪���邩�H 602���{�������j����2019/02/14(��) 18:07:47.73
�R���̐S��
�u�����������炢���ȁv
��
�u�����ɈႢ�Ȃ��v
��
�u�ŏ����炱���������v
��B�T�������̂܂܂̃T���x��x���Ă��ő唚��
603���{�������j����2019/02/14(��) 18:07:59.11
>>598
���a100�]���̕�����H�������Ă��Ɩ��L����Ă邪�H
����A�`���i���g�j�ł̘b����B�@�@�����g 604���{�������j����2019/02/14(��) 18:10:29.47
>>599
15�����x���ӓ������ăI�J���`�^�ׂA�т�`�͂��Ȃ��߂�ȁB
�ږ�ẮA���ѐH�ׂĂ����Ƃ������Ƃ��B
���ꂶ��A�������ł����B 605���{�������j����2019/02/14(��) 18:11:26.95
>>596
�����ꂪ�ˁA㕌����N��̌Â��g��P���̕���
���s�s�Ƃ��ĕ������x�������̂����
�ق��
��B���͈�؏؋��Ȃ��Ɍ��_��߂����� 606���{�������j����2019/02/14(��) 18:12:34.21
>>588
����z���Ɛ푈��Ԃɂ���̂�
�����}�g�ŕ�Y���Ă��͎̂הn�䍑�Ŗ����؋�����ˁ[��
���ہA鰎u�`�l�`�ɁA�ږ�Ă̎��ɍۂ��āu���n�A�l�S�P步�v���ď�����Ă邾��H
�푈���ł���s�Ő퓬������킯����Ȃ����A�����˂̑卑�Ȃ���l�͂�����ł�����
�傫�ȕ悪���Ȃ��Ƃ���ɘ`���͂��Ȃ��� 607���{�������j����2019/02/14(��) 18:14:31.23
>>595
�ӂ邢��
�g���f������
�w��I�ɂ����ے肳���
���j�̃N�Y�J�S�ɓ������ߋ�����
�ӂ�܂킷���� 608���{�������j����2019/02/14(��) 18:16:53.73
�����ɋ����ċg��P�����הn�䍑�Ƃ������o�����T���̃o�J�x���������������
609���{�������j����2019/02/14(��) 18:17:39.42
>>604
�؋��[���̃��m�x�����̂�
��B���̐����铹��
ww 610���{�������j����2019/02/14(��) 18:18:35.63
>>601
�A�z���Ⴄ�B
����c�����c�����ŋc�_����̂�����ƌ����̂��B
����́A��������B
�m�[�^�������قǂقǂɂ����B
�������A�N���ɐH�ׂ��ՂȂ�����Ɠ˂����܂�āA���ꂱ��E�\�d�˂āA���܂��ɂ͌������ƂȂ��Ȃ��āA���ɔ]���X�j�]�B
������ɂ��Ă��A�הn�䍑��a���́A�����A�����B 611���{�������j����2019/02/14(��) 18:25:02.53
>>584
�������n���������Ⴄ�Ȃ�A���̔�r�ɂ��Ȃ��
������ŁA�����������̔�r�Řb���Ă���邩�H
�����n��╶�����Ⴄ�Ȃ�A�Љ����v�z���l�X 612���{�������j����2019/02/14(��) 18:27:04.23
>>595
�������A�ӌ��������B
���V�́A�Β˂Ȃǂ��Õ��Ƃ��Ă��邪�A���̊w�҂ɂ͖퐶���u��ł����ČÕ��ł͂Ȃ��Ƃ���҂�����B 613���{�������j����2019/02/14(��) 18:31:54.95
>>600
���o�J���m�B
��������A�ږ�Ă������c�ɏZ�Ǝv���ĂȂ��A�Ƃ������Ƃ��ȁB
���ނ̎ア��B����3��
�����������
�C�^�R�|������
���� 614���{�������j����2019/02/14(��) 18:33:08.28
>>592
���g�샖���̂�14�l��
�������P���͋g�샖���ɂ͏����Ă���
����܂��A�Ђǂ��k�ق������o���Ă����Ȃ�
�ł��A�O�g�̐ԍ⍡���A�g���̏|�z���u��A�o�_�̐��J9����A�Z���Õ��Q�ɂ�
����1����͈��|�I�Ɍ���I�ɕ����Ă���Ă��Ƃł����˂� 615���{�������j����2019/02/14(��) 18:33:55.08
>>590
������{���Ă������̑�Վi��Ձi�j
�O�ɂ�����������ǁA�g�샖���̖k���u��͍��J�̂��߂̎{�݂����Ȃ�[�����Ă��邩��A
�����͓˂����݂ǂ���ł͂Ȃ��Ǝv��
���u�悪�����āA���̒����̎����ɍ��킹�ė��������Ă��Ă��āA���̉�������K��������
����ɁA���̒�����̏W���̔��̒[�ɁA���ē앭�u��ƌĂꂽ�Ւd������A
���̃��C����ɖk���s������
�k���u��[�����[�K��

�g�샖����Ղ̕��ʃv����

616���{�������j����2019/02/14(��) 18:35:47.56
>>611
��������Ď������瓦�����������ʂ�
��B���̂��܂̎S��Ȃ��� 617���{�������j����2019/02/14(��) 18:36:13.51
>>604
��15�����x���ӓ������ăI�J���`�^�ׂA�т�`�͂��Ȃ��߂�ȁB
�N���O����H�ו����������Ƃ����Ă�H����
�Z����Ւn������A��������̔ѐ����P���o�Ă���̂͒m���Ă��邾�낤���H
���������āA�m��Ȃ������́H���� 618���{�������j����2019/02/14(��) 18:40:26.28
>>607
���g���f������
���w��I�ɂ����ے肳���
�ȑO�͓Z���Õ��Q�́A����ȑO�̂��͓̂Z���Βˁu�Õ��v�ȂǂƌĂ�Ă��Ă��A
�Õ�����ȑO������퐶���u��ƍl����ׂ����Ƃ���ӌ�������������ǁA
�ŋ߂͓Z���^�O����~���̎��ォ��Õ�����Ƃ���悤�ɂȂ����A�܂�
�Õ�����̎n�܂肪�O�|������l�������ʐ��ɂȂ��Ă��Ă���
������>>595�́u�������A�Z���̌Õ����c�͌Õ�����v�͈������āA���������ƂɂȂ��Ă��
���́A�Z����ՂŌÕ����c���Ă����Õ�����́A�ږ�Ă̎���Ƃ�����d�Ȃ���ǂ� 619���{�������j����2019/02/14(��) 18:41:28.66
>>610
������c�����c�����ŋc�_����̂�����ƌ����̂��B
������������
���{�ꂪ�s���R�ȂȁA>>610�͂��� 620���{�������j����2019/02/14(��) 18:41:36.76
424>>518
���s����v�t�ł́A���V���ɓ��{���։������Ă邩�炢����B��
����Ȃ�A����v�́A
�u�J���l�N�̌��g�v����{���`�ɏ����悢���ł���̂ɁA�����Ă��炸�A
�`���`�̕��ɂ��������Ă���B
���s�p�����t�́A���V�ȍ~�̂ݓ��{���̍��ɏ����ҏW���j���Ƃ��������B��
������A�ԈႢ�Ȃ��A�J���l�N�Ɂu���{���g�v�𖼏�������g�������A�Ƃ��������B
���Ⴄ�����������ĕ]�����ׂ��ł͂Ȃ��B��
����A�m�蓾�����A�o���邾�������̎j���ɓ�����ׂ����B 621���{�������j����2019/02/14(��) 18:43:50.13
>>598
�הn�䍑���A��z���ƌ�킵�Ă���ƌS�֒��i���A�S�̖�l���o�����Ă�������ɓs������ɑ��~�߂���Ĕږ�Ăɉ���A������đ������Ƃ����̂�����A�퓬�������Ă����Ɖ��߂���̂��Ó��B 622���{�������j����2019/02/14(��) 18:45:04.66
>>611
���������n���������Ⴄ�Ȃ�A���̔�r�ɂ��Ȃ��
��������ŁA�����������̔�r�Řb���Ă���邩�H
�`���Ƃ��������n��ŁA2���I�㔼����3���I�͂��߂Ƃ�����������Ȃ��H
�ׂ������ق͂����Ă��A�����`�l�̓�����������
�������n��╶�����Ⴄ�Ȃ�A�Љ����v�z���l�X
�Љ��������ŁA�`��������̎��Ԏ��E�Ŕږ�Ă���������Ƃ����Љ������L���Ă���
�k����B�̓z���ł��Z���^�O����~���̓߉ϔ����Õ�������Ă邾��H
��B�����ʕ������Ă��Ƃ͂Ȃ���
�k�قɂ��Ȃ�Ȃ������̌�����ɂ��Ȃ�Ȃ����� 623���{�������j����2019/02/14(��) 18:46:20.98
>>612
�����V�́A�Β˂Ȃǂ��Õ��Ƃ��Ă��邪�A���̊w�҂ɂ͖퐶���u��ł����ČÕ��ł͂Ȃ��Ƃ���҂�����B
������ɂ���A�ږ�Ă̕�́A�����Q�������O����B�@
�����Q�������Õ��Ƃ��邩�A�퐶���u��Ƃ��邩�́A�ǂ��ł��悢�B�@�ږ�Ă̕�͉~���B�@�@�����g 624���{�������j����2019/02/14(��) 18:48:00.34
��B���̖�͔т̐S�z���肵�Ă���
625���{�������j����2019/02/14(��) 18:48:50.77
>>621
���הn�䍑���A��z���ƌ�킵�Ă���ƌS�֒��i���A�S�̖�l���o�����Ă�������ɓs������ɑ��~�߂���Ĕږ�Ăɉ���A
��������đ������Ƃ����̂�����A�퓬�������Ă����Ɖ��߂���̂��Ó��B
FAQ19���>>17
�u�`�����ږ�Ă͓�S�̑Ίؐ���ɋ��͂����`�Ղ��Ȃ��A���̌�����ɋ�z���̋��Ђ��������ꂽ�\��������B�v
���ۂɁu���n�A�l�S�P步�v�Ə����Ă������A�푈�����낤�ƂȂ��낤�ƁA
�a�S���̙n������Ă�����A�傫�ȕ悪�Ȃ��Ƃ���͌��n�ɂȂ�Ȃ��� 626���{�������j����2019/02/14(��) 18:49:36.44
�L���C���ӂ͕ʕ�������
627���{�������j����2019/02/14(��) 18:49:58.73
424>>519
���̓��e�́A���_�ς݁B
���̒j�́A�u�쁂���v��u�v�`�������k��V���v��u���{���ҁA�`���V�ʎ��v�A
�Ȃǂ̖�����������B�����R���x�������Ă��邩��A�~�l�ԁB 628���{�������j����2019/02/14(��) 18:51:21.24
>>618
�����́A�Z����ՂŌÕ����c���Ă����Õ�����́A�ږ�Ă̎���Ƃ�����d�Ȃ���ǂ�
����́A�Ȃ��B�@�@�����g 629���{�������j����2019/02/14(��) 18:53:44.74
>>624
����B���̖�͔т̐S�z���肵�Ă���
����1���Ƃ��z��0���Ƃ������A�y�t��̗l���ҔN�́A
�Z����Ղő�ʂɏo�y�����ѐ����P�̌`�������̐��ʂȂ��ǂ˂�
�����āA���̔ѐ����P�ɕt�������Y�f��14�b�N�㑪��ɃN���[����t����l����������
�A���ɒY�f�Œ肳�ꂽ���N�����ł��邱�Ƃ��m���ȓ��j��14�b�N�オ���߂đ��肳���
2���I���ɂ͓Z����Ղ����݊J�n���Ă��邱�Ƃ��m���ɂȂ��Ă�
�ѐ����P�ŁA�������Ă������čl���Ă���낤�ˁA��B���̐l�͂��� 630���{�������j����2019/02/14(��) 18:54:54.44
>>610
���������A�N���ɐH�ׂ��ՂȂ�����Ɠ˂����܂�āA���ꂱ��E�\�d�˂āA���܂��ɂ͌������ƂȂ��Ȃ��āA���ɔ]���X�j�]�B
�����������b���邱�Ƃ�
�ЂƂ͔]���X�j�]�ƌĂԂ�
���̂��Ƃ� 631���{�������j����2019/02/14(��) 18:56:57.49
>>629
416�F ��t���l:2015/02/22(��) 13:20:34.54 ID:.net
�y��̂��ƂɊS������悤�Ȃ̂Ő��Ƃ̌����������������݂܂�
�����g���y��Ƃ́A�����Q�`�R�~���ƁA���n��̓y��Ɣ�ɒ[�ɔ����ޗ��̔S�y�ɂ�
�ׂ�������ׂ��ꂽ���g�̐i�����Њ�j���܂܂�Ă���
����s���������Z���^�[���u���}�g�����͂����ɂ��Ďn�܂������v�i�����P�X�N�҂́j�̒���
�u�Z���ł́A�ߔN���g�n�̓y�킪�������i�ނɂꑝ�����Ă��肻�̌X���������҂̊Ԃ�
�r���𗁂тĂ���v�Ƃ���Ă���
���{�������Z���^�[�Z�t�̕��������ꂽ�u���{�o�y�̎]��E���g�E�d���n�y��v�ł�
�u����Ȗk�ےÓ����̂U��Ղň��g�n���P�V�A�ےÒ����P�P��Ղň��g�n�P�U�A����a��
���Ӊ��ϕ���̂S�P��Ղň��g�n�Q�O�W�A�a��s�P�P��Ղň��g�n�P�X�Ȃǁv
���g�n�y�킪���|�I�ɑ������Ƃ���������Ă��� 632���{�������j����2019/02/14(��) 18:59:26.94
>>628
�ق��
�g���f�����͗��R�������Ȃ�����H
�悢���ʕ��@�� 633���{�������j����2019/02/14(��) 19:02:48.07
>>621
> �הn�䍑���A��z���ƌ�킵�Ă���ƌS�֒��i���A�S�̖�l���o�����Ă�������ɓs������ɑ��~�߂���Ĕږ�Ăɉ���A������đ������Ƃ����̂�����A�퓬�������Ă����Ɖ��߂���̂��Ó��B
���A�����I�n�i�V����ĂȂ����H
���ꂾ�����B���� 634���{�������j����2019/02/14(��) 19:03:25.69
424>>521
�����u���E�A��E������C�C���E�A�k�E�L��R��C�R�O���ѐl�V���B �v
�����̓��e���Ƌ�B���܂܂�Ă���ˁB��
�������̘`���`�́A�@�`���ҌØ`�z����Ƃ��āA
���̎x�z�n���u�����܌��s�A��k�O���s�v�Ƃ��Ă��邪�A
���������{���`�́A�Ƃ��ςȂɁu���{���ҁA�`���V�ʎ��v�Ƃ��āA���{���͘`������ʂꂽ�ʎ킾�A�Ƃ��Ă���B 635���{�������j����2019/02/14(��) 19:05:53.83
>>627
�����̒j�́A�u�쁂���v��u�v�`�������k��V���v��u���{���ҁA�`���V�ʎ��v�A
���Ȃǂ̖�����������B�����R���x�������Ă��邩��A�~�l�ԁB
�e���v���Ɍf�ڂ���Ă�悤�Șb��
�u��������B�����v
�Ƃ����R�ƃE�\�����B����
������������������ 636��90�x��]����2019/02/14(��) 19:07:00.52
>>576
�S�����ӂ��܂��B
�L�I�ŁA�_���ȗ��A�j�n���Y��Ɉꑱ���ɂȂ��Ă���̂́A����͋L�I�̕Ҏ[���ɂ����������ɏ�������������B
���̎���̓����̃f�t�H�́A�j���y�A�̃q���q�R���A�Z��܂��͌Z���̃y�A�B
���Ƀ��}�g�����̓G�Ύ҂┽�t�҂̂قƂ�ǂ͂����������ɕ`����Ă���B
���̒��Ń��}�g�������������I���̌㐢����肵���悤�Ȓj�n�ł������Ƃ͂ƂĂ��l�����Ȃ��B
���_�Ɛ��m���A�e�q�łȂ����͌Z��ł������Ƃ��Ă��A�S���s�v�c�ł͂Ȃ��Ǝv���܂��B 637���{�������j����2019/02/14(��) 19:07:30.60
>>618
�����́A�Z����ՂŌÕ����c���Ă����Õ�����́A�ږ�Ă̎���Ƃ�����d�Ȃ���ǂ�
�ق��
�g���f�����͗��R�������Ȃ�����H
�悢���ʕ��@���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����g 638���{�������j����2019/02/14(��) 19:10:16.07
>>634
�����������{���`�́A�Ƃ��ςȂɁu���{���ҁA�`���V�ʎ��v�Ƃ��āA���{���͘`������ʂꂽ�ʎ킾�A�Ƃ��Ă���B
�����o���̃E�\���U���R�N������
�u����ʂꂽ�v���Č����ɂȂ��̕t�������Ă�
��s�ŏ���������ė�R����
�˂����B���C���Ȃ����Ă� 639���{�������j����2019/02/14(��) 19:14:49.99
>>637
����A�悭�킩��Ȃ�����
�Ȃ����Ԃ������ς���Ȃ̂��H 640���{�������j����2019/02/14(��) 19:15:00.28
>>637
�e���v���ɂ�������Ă邵
���Z�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă邩��
�������ƂȂ�ǂ��J��Ԃ��Ȃ���������
�����H 641���{�������j����2019/02/14(��) 19:19:58.89
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
��B������畷�����Ȃ��U�肵�Ă����ꂪ����
642���{�������j����2019/02/14(��) 19:20:39.19
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
�\������B�L�`�K�C���ǂ�Ȃɓ�����낤�����ꂪ����
643���{�������j����2019/02/14(��) 19:21:10.16
>>640
���e���v���ɂ�������Ă邵
�e���v���H�@�@�l�ϑz�̃e���v�����ǂ��������́H�H�H
�����Z�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă邩��
�E�\�̓C�J������B�@�@�����g 644���{�������j����2019/02/14(��) 19:23:29.95
���啭��͉ߏ�ȘJ���͂̌��ʂ��
�ɂݍ����Ă���ԕ��m�͂��邱�ƂȂ������
�ɂقǓł͂Ȃ������
���ƌÍ��������̐������͏d�v�Ȗ��
�ږ�ĂɎg��������1000�l�́A���̖��Ɩ��̋�����S���Ă�����Ȃ�����
645���{�������j����2019/02/14(��) 19:25:46.24
�S�V���������畺�����Ȃ��B
�������Ȃ����琫�������K�v�Ȃ��B
������Z���������B
646���{�������j����2019/02/14(��) 19:28:49.81
>>613
�ږ�Ă������c�ɏZ�A�Ƃ͌����ĂȂ��̂���B
�Z��łȂ���ȁB
��͂͂͂͂́B 647���{�������j����2019/02/14(��) 19:29:55.11
>>643
�g���f������͔��_���ł��Ȃ�����ɂ͒����ł���������܂� 648���{�������j����2019/02/14(��) 19:30:48.42
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
649���{�������j����2019/02/14(��) 19:33:24.62
>>647
�����Z�̋��ȏ��ɂ��ڂ��Ă邩��
�E�\�̓C�J������B�@�@�����g 650���{�������j����2019/02/14(��) 19:34:35.28
>>646
���������Ȃ���
�����ĂȂ��Ƃ������Ƃ�
�Z�Ƃ��Z��łȂ��Ƃ������ĂȂ��Ƃ������� 651���{�������j����2019/02/14(��) 19:38:52.88
>>428
�`���������̋L�q�̕ϑJ
�㊿��(�Ō�)�@�`��������
�ˉ��@�@�@�@�@�`�ʏ㍑���t��
���{���I�@�@�@�`�ʏ㍑���t��
�ߓ��{�I�@�@�@�`�ʍ����g��
�ʓT�@�@�@�@�@�`�ʓy�����t��
�@�@�@�@�@�@�@�`�ʓy�n���t��
���ޔ��@�@�@�@�`�ʓy�n���t��
�ُ̓��{�`�@�@�`�ʓy�n���t��
�ԈႢ���`���Q�[���݂����ɓ`�����
�`�������ŏI�I�ɂ͘`�ʓy�n���ƕs���Y���ɂȂ��Ă��܂�
�`�ʏ㍑���ɂȂ��Ă���̂͏o�W���łƏ��ʂ��d�˂��㊿���n��
�`�ʓy�n���ɂȂ��Ă���̂͒ʓT�n�� 652���{�������j����2019/02/14(��) 19:41:04.15
>>605
���͍l�Êw���i����
�g��P����Ղ�����������ǂ��ł�
���͋g�샖���͉��s�Ƃ͎v���Ă��܂���
�������x��㕌���茻�������ʂƂ��ċg��P���̂ق����Ñ�ł͓s�s�����Ă�Ǝv���܂���B 653���{�������j����2019/02/14(��) 19:41:38.43
��B���͉��̂��������ɏ؋����o���Ȃ��̂��H
�����ƒm���ĂČ����Ă邩�炳
654���{�������j����2019/02/14(��) 19:42:25.83
��a�ł�

655���{�������j����2019/02/14(��) 19:43:37.98
>>605
���_������Έ╨�Ŏ����Ă�������
�g�샖��VS�Z���@�̓s�s�@�\ 656���{�������j����2019/02/14(��) 19:44:51.51
>>652
�ق�A��B���͂܂����R������Ȃ�
������O����ꂽ 657���{�������j����2019/02/14(��) 19:44:57.08
>>653
�Ⴆ��̂͒N�ł��ł���
�_����ׂ� 658���{�������j����2019/02/14(��) 19:45:44.86
��424>>533
���`�z���͋�B�����ŁA�הn�䍑�͒}��R��ɂ����Ė��傪�ς���Ă���A
�����5���I�ɂ͑�a�̉������傪�ɂȂ��Ă��āA���ꂼ�ꍑ�����ƂȂ��Ă���B��
�Ȃ��Ă��Ȃ��B�����]�̌�̂V�O�P�N�܂ł́A��B�`��������ł������B
�������́A�����̍�����̈�т������ł���ƍ������Ă���B��
�������Ă��Ȃ��B�����́A��B�`���Ƒ�a�}�K�������������Ă���B 659���{�������j����2019/02/14(��) 19:46:55.63
>>613
�C�~�t
�������������̂��� 660���{�������j����2019/02/14(��) 19:48:28.90
>>649
���E�\�̓C�J������B�@�@�����g
����B���Ă͈̂��g�قł�����̂��H
���n�����m�ق̃C���[�W�����B 661���{�������j����2019/02/14(��) 19:48:43.59
>>656
���̍l�����q�ׂȂ��Ƃ����Ȃ��� 662���{�������j����2019/02/14(��) 19:49:48.21
>>624
�ږ�Ă��т��H���Ε�������
����펯 663���{�������j����2019/02/14(��) 19:51:17.88
>>624
�ޏ���l�������т�H���� 664���{�������j����2019/02/14(��) 19:51:52.60
>>631
�����g���y��ɂ��Ă̋L�����݂�ƁA���ꂪ��a�Ȃǂɔg�y����̂́A�O���Õ��̎����Ƃ��Ă���悤�ɂ݂���B
���g���͂��E���ɈڏZ���A�u�E�������Õ��̒z���ɐ[���ւ�����v�Ƃ̕\�����Ȃ���Ă���B�i�T�C�g:�u��ʎВc�@�l�@���������������@�����Ƃ́v�j
�Ƃ���ƁA���̎����Ƃ́A3���I�㔼�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
�z�P�m�̂��ƂɂȂ�B 665���{�������j����2019/02/14(��) 19:53:56.60
�����g�H
�����A�����Ȃ�A3���I�O���ɓޗnjʼnj���ł���B
���̖ڂŌ�������ԈႢ�Ȃ��B
666���{�������j����2019/02/14(��) 19:54:32.15
424>>540
�������͓��{���̎�����Ǝ��L�^���琸�����ăA���m�^���V�q�R�i�p���V�c�j�ƒf�肵�Ă遃
�V�����́A���p�����H�u�ڑ����v��ǁv������A�A���m�^���V�q�R�́~�B
�����{�̉B�����A�M�p�ł��Ȃ����t�Ƃ����W�Ȃ�
�������g�����f�����L�^���n�b�L���L�ڂ���Ă���
���x�������Ƃ����������ڂ�����a��鰎u�̎הn�䍑 ��
�u�쁂���v�ȂǂŁA�~�B
��a������a����������͈�؍l���Ă��Ȃ��B 667���{�������j����2019/02/14(��) 19:56:58.63
�����E�����̃X���Ȃ�
��B���͋����
�ږ�Ă͓V���s�����s�ɋ����̂���
����s�͍֏ꂾ��@��n
668���{�������j����2019/02/14(��) 19:57:16.24
>>622
��̕��������ׂ�������H�ɂ͎����͌����Ȃ���
�����̍�����ˁH
200�N�O��A�M���Ŕږ�Ăɓ͂����ǂ����̕�
3���I�O���ł݂�Ƃ�������
�悪���ꂳ��Ă��邩�ǂ����H���d�v�����A
�O����~���̓߉ϔ����Ǝ����Ⓜ�Òn��̕��`���a��͖��炩��"����"�ł͂Ȃ�
�����P���ɑ傫���ł̔�r���l����̂͂ǂ����Ǝv����
���ɖk����B�̓o������������`���u�悾������~�`���u�悾������A��̗l���͗l�X
�n������ŕ�ɑ���v�z���Ⴄ�A�Ƃ������Ƃ��낤 669���{�������j����2019/02/14(��) 19:57:26.35
�A���m�^���V�q�R�i�p���V�c�j���E���ɂ��������͋L�I����H
���Ⴀ�A�_���������F�߂Ȃ��ƂˁB
670���{�������j����2019/02/14(��) 19:58:41.31
�E������舢�g���̂ق������������
���g�͋E�����̖ڂ̏�̂����
671���{�������j����2019/02/14(��) 20:00:47.30
424>>541
���o�J��B���̖ϑz����������̂Ȃ�
�A���m�^���V�q�R�i�p���V�c�j�̋L���́u���{���ɂ���͂��v
�Ƃ��낪���̋L�^�́u�������ɂ����Ȃ��v��
�ߓ��{�I�Љ�̉���u�L�ɁA���얅�q���@����Ɂu���{���v�𖼏�����b���ڂ��Ă���B
���܂�A�������Ǝ��̋L�^����f�肵�����̂�������
�����͑�a�̐������הn�䍑����A�����ē��{�̒��S�������ƍl���Ă���̂�������
�����́A��a���{���́A�`������ʂꂽ�ʎ�̋������ł���A�ƍl���Ă������������B 672���{�������j����2019/02/14(��) 20:01:21.55
>>1
�ŋ߂̋E�����̓��[�v���Ăˁ[��
�E�����̐V�������𗬂��Ă� 673���{�������j����2019/02/14(��) 20:02:47.94
424>>542
��a�̂悤�ȓc�ɂ̒[�����ȂɁA
�הn�㚠�����V���s�͂Ȃ� 674���{�������j����2019/02/14(��) 20:03:02.09
>>658
�㊿���̑�`���́A���炩�ɑ�a�E�͓������̑剤�B
�S�z�������ɂ���Ƃ��Ă��邱�Ƃł��A�הn�䍑�͑�a�ł��邱�Ƃ�������B
���̏��́A�`���]�̎g�ߒc���瓾�����̂��낤�B
��a�̓�ɋ������Ȃ����ƁA���ɂȂ炠��Ƃ��������Ƃ������Ƃ��B
���̏������ƂɁA�`�l�`�̓�𓌂ɏ����������B
����5���I�̑�a�̉����ƁA3���I�̖k����B�̔ږ�Ẳ������A�����Ă���Ƃ݂Ȃ����ŏ��̎j�����㊿���ŁA����ȍ~�A�����j���͂���P���Ă���B
鰎u�`�l�`�ł́A�k����B�̔ږ�Ẳ����ƁA���̓���]���ɂ��鏔�������͕ʂł���Ə����Ă���B
�㊿������A���̓�̉����̘A�����A�������n�܂�B 675���{�������j����2019/02/14(��) 20:04:46.10
424>>543
���Ȃ�قǂł��ˁB
�������A�הn�䍑���ޗǖ~�n���ƌ����͍̂ő��������悤���Ȃ��ƍl���Ă��܂�����
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 676���{�������j����2019/02/14(��) 20:05:04.79
㕌��̌@���������̎���ɗ˕悪�����ς�����̂�
�ږ�Ẳ��{�ƌ��߂���w�҂̓����^����
677���{�������j����2019/02/14(��) 20:07:41.65
�z�P�m���H����
������╨�I�ɂ܂�����ˁ[
678���{�������j����2019/02/14(��) 20:07:48.61
�����g�H
�����A�����Ȃ�A�E���ѐl��S���`���֑��肱���{�l������ȁB
�����āA�N���A���Ȃ��A�Ȃ����B�B�B
���̖ڂŌ�������ԈႢ�Ȃ��B
679���{�������j����2019/02/14(��) 20:10:07.76
424>>550
�����ꂪ�u�p���V�c���A���m�^���V�q�R�v�̋L�� �A
���p���A���H�u�ڑ����v��ǁv
�ł����āA�u�A���m�^���V�q�R�v�ł͂Ȃ�����A�~�B 680���{�������j����2019/02/14(��) 20:11:05.90
�הn�䍑�͍���s�̑�������
������Ȃ��狦�͂��Ă������ƍl�����
���ו��̎����̂��撣���ĐԎ������点�Ηǂ�
681���{�������j����2019/02/14(��) 20:13:08.93
424>>552
���E��a���הn�䍑����
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 682���{�������j����2019/02/14(��) 20:16:19.16
424>>555
���הn�䍑����B�ł���ڂȂNJ��ɑS���Ȃ��̂�����A
��B���̊�łȃA�}�`���A�V�l�̑���͂قǂقǂɂ��Ă����āA
�E�������m�ŋc�_���������L�v���Ǝv���̂ł���B��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 683���{�������j����2019/02/14(��) 20:16:21.05
㕌��̊ό��p�g�C���͖w�ǒn���̐l�����p
���p�͎q�ǂ��������݂���������
�����V�����x���𐳂��ɂ͗ǂ�����g�C��
684���{�������j����2019/02/14(��) 20:20:00.89
�����̐ŋ��ŁH
685���{�������j����2019/02/14(��) 20:20:57.13
424>>561
�����ꂽ���̏z�_�@���� ������3���I�̓��Ɂu�Z�����g���l����l�����Ȃ��v
�����������Ɛ������Ă���A�Z����������Ď咣���Ă��������Ȃ���������
�����́A鰎u�̋L�ڂł���A
�j����������̋A�[�I���_�ł��邩��A�u���_��ɂ��肫�v�ł͂Ȃ��A
������z�_�@�ł͂Ȃ��B 686���{�������j����2019/02/14(��) 20:32:03.03
4424>>567
���A���^���V�q�R��拍��ł͂Ȃ��A�A�������A�^���V�q�R���P������閼�Ղ�
�嗤�������f���Ă������A���{�̋L�^��拍��ƈ�v���Ȃ��ƌ����Ă����ꂱ���Ӗ����Ȃ���
�������̋L�^�́A
�u俀���������A�������v�k�ǁv�Ɓu���p���A���H�ڑ����v��ǁv�ł���A
��������u �A���^���V�q�R�v�ł͂Ȃ�����A�~�B
��������ɂ��Ă��A����v�A�������A�V�����̘`���`�̘`�����E����a����Ȃ͓̂����Ȃ�
���ʂȂ��������Ȃ���
�V���I�ȑO�ɂ́A�E������a������Ȃ���������A�~�B 687���{�������j����2019/02/14(��) 20:34:26.43
292 �p�q �����ꑰ�A�}�����z���A�הn�䍑�𓌐�����ƕ�������
294 �b�� �הn�䍑���E�����F�A�����F�ƐےÂɐ키���A�����ꑰ�s��đނ��A��C���ɕ�����
298 ���� �Ăѓ����������A�������̕F�ܐ����͘a��ɓ�����A��Ȃ�F�j�і��͓�g�ɓ�����A
�@�@�@�@�@�@��O�c�q�Ȃ���я����͍s���s���Ƒ�����
299 �ߖ� ��l�c�q�Ȃ���я����͓����ꑰ�����A����ɓ�C���A�ؕ��A�W�H���̕����킹��
�@�@�@�@�@�@�הn�䍑���U�߂�ɁA�����F�͏d�������ē����ɑނ��A�����F���܂��z�ɑނ��A
�@�@�@�@�@�@���B��Âɂč��R���A����ɉ��B�������Ɉڂ���Z���A�����ɍr�f���̑c�ƂȂ��
315 ���� �r�f�܉��ꋓ���Č̒n�E�הn�䍑���U�߁A���������n�ł��A�V�c����ʂȂ炵�߂�����A
�@�@�@�@�@�@�r�f���̎茤���s�ꂽ��ɂ��ĉ��B�ɑނ�
�@�@�@�@�@�@�r�f���̑�a�ւ̉����͎����A���̒�ʂɕK����U�h���J��Ԃ�
�@�@�@�@�@�@����݈̍ʎ����A�r�f���܉��R�͑勓���Ďהn�䍑���U�߂�ɂ�薒�A�V�c����ʂƑ��ׂ�
�@�@�@�@�@�@�̂��������Ƙa����
688���{�������j����2019/02/14(��) 20:38:18.25
�n�����E�̌㊿�����������O�ɁA�㊿���͂��邩��Ȃ��B
689���{�������j����2019/02/14(��) 20:44:57.03
424>>569
���Ⴆ�����\�q�����ږ�Ă̍��Ղ��Ƃ���A
���_�i�݂܂�����т����ɂ��̂��߂�݂��Ɓj�́A��n�l�x�B
���m�i�����߂���т��������̂��߂�݂��Ɓj�́A�Ɏx�n�B
�ƁA���܂�ɂ��s���ǂ�������̐l�����������߂��Ă��遃
�Ɏx�n����n�l�x���A�ǂ�����הn�㚠�̊����ł���A
�܂��A���������ږ�Ắu��v�v�ł͂Ȃ��A
�Ƃ������́A
��a�̐��_�␂�m�́A��B�`���̒��̎הn�㚠�̊��ł������A�Ƃ������ɂȂ�A
�u�����ѐc�\�ܚ��v�̏��R�⊯�̒n�ʂ��炢�ł����Ȃ��������ɂȂ�A
������A��a��������ł������A�Ƃ������̔ے�ɂȂ�B 690���{�������j����2019/02/14(��) 20:47:16.16
>>664
�����g���͂��E���ɈڏZ���A�u�E�������Õ��̒z���ɐ[���ւ�����v�Ƃ̕\�����Ȃ���Ă���B�i�T�C�g:�u��ʎВc�@�l�@���������������@�����Ƃ́v�j
���Ƃ���ƁA���̎����Ƃ́A3���I�㔼�Ƃ������Ƃł͂Ȃ����B
�Ȃɂ��E���Ɍ���Ȃ����A���g���͂��E���ɈڏZ�����̂́A�u�����g�^�y��v�ȑO����B�@
�ꕶ���������琼���{�e�n�Ζ_��Ε���W�J���Ă���B�@�@�����g
���z�P�m�̂��ƂɂȂ�B
���̃z�P�m�͔����Q�����̂��ƁB 691���{�������j����2019/02/14(��) 20:49:45.71
424>>571
���������B
�����u�쁨���v�Ȃǂ̉R���x���̑�a���ғ��m�ŁA
�����������o�̖ϑz�̃T�M�b��������������ŏ��i��B 692���{�������j����2019/02/14(��) 20:50:41.87
�L�E�X���\����
693���{�������j����2019/02/14(��) 20:51:11.14
>>685
鰎u�̋����L�ڂ͎��ۂf���ĂȂ���
鰂Ŏg���Ă����P����S�R�O���ƍ���Ȃ����肩
�ЂƋ�ԂɂS�{�������������肷��
�䂦��鰎u�`�l�`�̋����L�ڂ͕s�m���Ȃ��̂�
�t�ɋ�B�����̔����ɋg���������ォ��w�E���Ă�����
���������Ƌ�B���͖���������މ����Ă��܂��Ă���悤���� 694���{�������j����2019/02/14(��) 20:53:24.52
>>655
���O�����g�샖�����s�s���Ƃ����������ƍl���Ă�╨�������Ă݂�悗 695���{�������j����2019/02/14(��) 20:56:22.17
424>>573
������͐W�̍��c�i�n��̌����������̌��т������グ�邽�߂ɁA
�`���̌��g��n�̉ʂĂ���̒��v�Ƃ��邽�߂ɋ������֒�����Đ����Ă��邩��A�Ƃ���
�N���g���l�̂��Ȃ��Z����s��������A������₷���P���Ȑ��������łɂ��邾�낤��
�����A�u�i�n��̌����������̌��т������グ���v�Ƃ������̏؋����Ȃ�����A
������A�ރX����̕��o�́E�E�E�E�̖ϑz�B 696���{�������j����2019/02/14(��) 20:58:15.47
>>630
�������������b���邱�Ƃ�
���ЂƂ͔]���X�j�]�ƌĂԂ�
�����̂��Ƃ�
�O�_�O�_�����Ă邯��ǁA�v�͓Z����Ղ��W����Ղ��ǂ������Ă��ƂŁA
�������͍����������ł͔т��H���Ȃ�����Z��łȂ��Ƃ������Q���������o����
�j�]������������
�Z����Ղł͔ѐ����P���R�قǏo�Ă�
�ѐ����P�ʼn��������Ǝv���Ă�H���Ă���
�т𐆂��͔̂т�H�ׂ�l�����邩�炾��H
����ȒP���Ȃ��Ƃ����Ă邩��A�o�J�Ă�肳���� 697���{�������j����2019/02/14(��) 21:06:37.14
>>637
���g���f�����͗��R�������Ȃ�����H
���悢���ʕ��@���@�@�@�@
�Z���Õ��Q�̓Z���^�O����~���́A���@���ɏo�y�����y��ҔN�ő��ΔN�オ
������Ă���A���̓y��ҔN�̑��ΕҔN�ɂ͉ݐ�Ȃǐ�ΔN��̕�������̂Ƃ̑Δ��
��ΔN��Ƃ̕R�t�����s���Ă���
����ɂ́A���j��14�b�N�㑪��@��2���I�㔼����3���I�͂��߂Ƃ����N��������Ă���
�ŏ����̓Z���ΒˌÕ��̒z���N���2���I������3���I���߂Ɛ��肳��Ă���
�Ƃ������Ƃ́A���̌�ݑ�I�ɓZ���Õ��Q�̑��c�͑������A�Z����Ղ��̂��̂�
4���I�܂ő������Ă��邱�Ƃ���A�Z���Õ��Q������Ă�������́A�ږ�Ă̎����
�۔�肷�邱�Ƃ͊m����
���R�����߂ď��������A�e���v���Ɋ��ɏ����Ă����
�A�ƈ���āA������Ɨ��R�͏������
���R�̏����Ȃ��A�A�̏������݂́A�g���f����������ǂ� 698���{�������j����2019/02/14(��) 21:10:27.73
>>668
�������̍�����ˁH
��200�N�O��A�M���Ŕږ�Ăɓ͂����ǂ����̕�
�O������������ǁA�ږ�Ă����ʉ��\�N���O�ɒN��������ꂽ���
�ږ�Ă̕�ƌ�������̂͂�߁[�ₗ��
���ꂾ���ŁA�o�J�ɂ��������Ȃ������� 699���{�������j����2019/02/14(��) 21:11:03.25
>>696
���ѐ����P�ʼn��������Ǝv���Ă�H���Ă���
�Õ����c�l�v���ѐ����P�Ŕя�т𐆂��Ă������Ă��ƁB�@�@�����g 700���{�������j����2019/02/14(��) 21:11:29.93
424>>577
���߂�ǂ������o�J���Ȃ���
�������ł�����v�ł��A�`���`�̋L����o��l�������ׂċE����a����Ȃ���A
���̕ӂ������ɂ������͘`�����E����a�ŏI���Ȃ悗�� ��
�߂�ǂ������o�J���Ȃ���
�������ł�����v�ł��A
�`���`�Ɠ��{���`�̗������ꏊ���Ⴆ�ď��������Ă��邵�A
���̓��e���S���Ⴄ���A
���̊W���A
�u���{���ҁA�`���V�ʎ��B�ȑ����ݓ�粁A�̈ȓ��{ਖ��B
���H�A�`�����������s��A��ਓ��{�B���]���{�p�����A���`���V�n�v
�Ƃ͂�����������Ă������A
�`�������{���ŏI���Ȃ�B 701���{�������j����2019/02/14(��) 21:14:34.52
>>668
���悪���ꂳ��Ă��邩�ǂ����H���d�v�����A
�ԍ⍡�䕭�u���J����Q�A�|�z���u��́A�e�n�̎��e�𑈂���
���͌֎��̂��߂ɋ��啭�u�������Ă��鎞�ゾ��
���ꂪ�ږ�Ă̋����ɂ���āA�O����~���Ɏ����̕�����J�����ꂳ���
���̌��͌֎��̋��啭�u�悪����鎞��ɁA�k����B�ł͋��啭�u���
�܂��������Ă��Ȃ���
�܂�A���͂̏W���̂Ȃ��G���̌Q�ꂾ������
���ł��ő�̓z���͂��������E���Ƌ����W�ɓ����Ă���
����ŋ�B�`���ɘ`�l���E�̉��������Ƃ������̂��A�܂������̋Y�������ĕ����邾��H 702���{�������j����2019/02/14(��) 21:16:30.61
>>677
���z�P�m���H����
��������╨�I�ɂ܂�����ˁ[
����̈╨���ĉ��̂��肾�H
����͕��u��ŏE��ꂽ�����䂭�炢�����A���ڂ̈╨�͂Ȃ��� 703���{�������j����2019/02/14(��) 21:29:19.56
>>657
����_���ĂȂ��̂���B���Ȃ�ŁA�E�������_���Ă邱�Ƃ�ǂ�ł� 704���{�������j����2019/02/14(��) 21:30:07.20
�S�킪�n����h�W���E
705���{�������j����2019/02/14(��) 21:30:15.89
424>>579
���s���|�C���g�Ŋm��͂��Ȃ����A���݂̕W���ҔN�͑����̏��̐�������ǂ���
�������ꂽ���̂�����傫���͓����Ȃ��恃
�I�N���Ε���A����̂悤�ȕ����Ƃ̏ƍ����o������̂łȂ���A
���ΔN��ł́A�S�̂����������ŁA��ΔN��͌��܂�Ȃ��B
�����ƁA�����ΔN�Ȃ�W���Ƃ���14�b�r���Ȑ������p�ł���悤�ɂȂ������i���x���オ��
����̕ҔN����B���ɂ͓s������������A�������ł��ے肵�����낤���ǁA
���łɂ��������i�K�ł͂Ȃ���
AMS�́A�v���Y�}���Ƃ������{�I�Ȍ��ׂ����邵�A
�N�ւ�N�Ȃ�_�f���A��ɁA
���̂ƕW���ޗ��Ƃ�����C��⎩�R�����ł������̂��H�A
�Ƃ������̕ۏ��Ȃ����߂ɁA��ΐ����Ȃ��B 706���{�������j����2019/02/14(��) 21:32:43.09
>>584
���g���̏|�z���u��͓�̕��`�ˏo�������ĕ��u��72���[�g��
���o�_�̐��J9����͎l���ˏo��ł��̓ˏo���܂œ����Ƃ��悻60�~50���[�g��
���O�g�̐ԍ⍡�䕭�u��͓���36m�A��k39m�A����3.5m�̕��u���ɉ����l����5〜9m�̕��R��
����̐��j�����u��@��ӂ�60m�ȏ�@������Ă� 707���{�������j����2019/02/14(��) 21:32:57.73
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
��B������畷�����Ȃ��U�肵�Ă����ꂪ����
708���{�������j����2019/02/14(��) 21:33:28.55
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
�\������B�L�`�K�C���ǂ�Ȃɓ�����낤�����ꂪ����
709���{�������j����2019/02/14(��) 21:33:56.49
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
710���{�������j����2019/02/14(��) 21:34:12.81
���@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA
�Z�_������
�~�_�����J
711���{�������j����2019/02/14(��) 21:34:30.12
>>702
��B���͖��m�Ȃ���d���Ȃ� 712��90�x��]����2019/02/14(��) 21:36:11.76
>>654
�ۑ����܂����B
�Ȃ�قǂł��ˁB
�܂��A��������˂��B�����펯�I�ɍl����ˁB
�B��Ɂw�s���x�ƌ����A���n���̍��Ղ��c���Ă�̂͒m��܂���ł����B
�B��͏o�_����C�^�V����ڎw�����[�g�́A���ɒ��p�_�B
���̑��̌S�����̂����������˓��C���ɔ�肳���̂��A
���{�C���[�g����⋭���܂��ˁB
�e���v���Ƃ͈Ⴄ���ǂ��A����͂����A���{�C���[�g���Ǝv���܂���B 713���{�������j����2019/02/14(��) 21:38:11.99
>>705
���I�N���Ε���A����̂悤�ȕ����Ƃ̏ƍ����o������̂łȂ���A
�����ΔN��ł́A�S�̂����������ŁA��ΔN��͌��܂�Ȃ��B
�Ƃ����Đ����̕������E���Ă��Ė퐶����̂��̂ƌ��������B�� 714���{�������j����2019/02/14(��) 21:43:22.54
>>701
������A�v�z�╶�����Ⴄ�����ł���
�����{�S�������o���ꏏ�Ƃ����͎̂v�����݂ɂ����Ȃ� 715���{�������j����2019/02/14(��) 21:45:36.08
424>>582
�������A3���I�̓��ΐ��E�ɂ͒Z����m���Ă���l���g�����R�̂���l���N��l���Ȃ��A��
���_�������Ȃ�ǂ����I������
��鏎Z�o��̓�q�̈ꐡ�痢�́A���R�m���l�͒m���Ă��邵�A
鰂̖�l�́A�g���Čv���������A
���� ��洂��@�~�����n���ЍN���g�����B 716���{�������j����2019/02/14(��) 21:45:47.59
>>714
��������A�v�z�╶�����Ⴄ�����ł���
�Ȃ�A�R�ЂƂz���������Ŏv�z�╶���̈Ⴄ�k����B�Ɏהn�䍑���������Ȃ�Ė�������
��B���܂��I�E���S�[���Ŏ��� 717���{�������j����2019/02/14(��) 21:47:18.60
>>698
�킽���͔ږ�Ăƒf�肵�ĂȂ���H
�N��̓M���œ͂��\���̂����Ȃ͎̂�������
���\�N���O�ƂȂ��f�肵�Ă�́H 718���{�������j����2019/02/14(��) 21:49:18.40
>>717
���N��̓M���œ͂��\���̂����Ȃ͎̂�������
���������ď؋��́H
��B���͂܂��t�J�V�H 719���{�������j����2019/02/14(��) 21:51:07.14
>>716
����A�E�����̂����ʂ�Ȃ�ɂ��A���ł����������Ȃ���
�𗬂͖��ɂ���̂��� 720���{�������j����2019/02/14(��) 21:52:24.40
424>>589
���הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���
�Ɨ������Ă���̂����m��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 721���{�������j����2019/02/14(��) 21:52:38.65
>>715
�؋����Ȃ��ƃ_��
�������邾���ł͔��_�ɂȂ�Ȃ� 722��90�x��]����2019/02/14(��) 21:56:59.03
鰎g�ɁA���s�������Ȃ���{�C���[�g��ʂ点���͉̂��łȂ낤�Ȃ��c�B
�Δn�C�����s���̃��[�g�Ő����瓌�ɑD������ɓ������Ă����Ƃ����̂�������ǁA
����ς�o�_�ɑ��āA鰎g�������т炩�����������̂��Ȃ��c�B
723���{�������j����2019/02/14(��) 21:58:40.92
>>719
�c�O�Ȃ��炻��͖k����B�ȊO
�k����B�͒N������݂�悤��
�e���͂����ꂽ�`�Ղ��Ȃ��ƃ_���Ȃ�
����ȗ͂��ł����̂͋E�����͂��� 724���{�������j����2019/02/14(��) 22:08:43.96
>>706
������̐��j�����u��@��ӂ�60m�ȏ�@������Ă�
���j�����u��͂��Ȃ�r��ĂĂ܂Ƃ��Ȕ��@���ł��Ă��Ȃ����A�O����̕�����������Ȃ�����
�]����������
�܂��A�o�_�i�l���ˏo��̍��j�̉���͐��J����Q�ł�����Ȃ����� 725���{�������j����2019/02/14(��) 22:09:54.52
>>697
���ŏ����̓Z���ΒˌÕ��̒z���N���2���I������3���I���߂Ɛ��肳��Ă���
����Ȃ��Ƃ��A���́u㕌��ΒˌÕ��v��h�̌{�`�ؐ��i�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u㕌����R�Õ��v��h�̔̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u���ˌÕ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u���厛�R�Õ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u���䒃�P�R�Õ��v��u���r�R�Õ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u��a�V�_�R�Õ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u���{��ˌÕ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
�u�z�P�m�R�Õ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ���a�������������u�ᐙ�R�Y�v����B
���łɁA���̓�����a���������������Č�ŐH�ׂ�������A�����ƁB�@�@���͂͂́B�@�@�����g 726���{�������j����2019/02/14(��) 22:12:28.64
>>550
��>>548
���A�z���Ⴄ�B
���Ȃ����ׂ��B
�܂�A�܂��E������
��؏؋��Ȃ��ɉ䗬���������������Ă����
�����������Ƃł��ȁH 727���{�������j����2019/02/14(��) 22:13:19.47
>>725
����Ȃɔږ�ċ�����������ł��������Ⴄ�� 728���{�������j����2019/02/14(��) 22:13:31.56
>>576
����B���͍l��������Ȃ�����v������Ȃ��悤������ǁA�q���q�R����
���q�������ږ�āA��^�ŁA�q�R�������_�A���m�A�i�s�ƍl����܂����������������Ȃ�
����Ȑ��x�Ȃ�A鰎u�`�l�`�ɂ���������邾��B 729���{�������j����2019/02/14(��) 22:17:20.96
>>727
������Ȃɔږ�ċ�����������ł��������Ⴄ��
�ږ�ď����l�͎��n�тŕГc�ɂ̓ޗǖ~�n�Ȃ͌��������Ă��B�@�@�����g 730���{�������j����2019/02/14(��) 22:18:20.12
>>636
�V�Ð_�͒j�n�ŁA���Ð_�����n�B
���Ð_�̕P�̂Ƃ���ɓV�Ð_�̒j���Ȗ⍥����̂��`���̊�{�B
�Ƃ��낪�A�ږ�Ăɂ͕v�����Ȃ��Ɩ��L����āA���o�����n�̎q���ł͂Ȃ��悤������A�q�����Ȃ��B
��������O�ꂽ�Ǎ��ȑ��݂��ږ�Ă��B
���肫����̕P�F�Ȃ�A���̂悤��鰎u�`�l�`�ɏ����ꂽ�͂��B 731���{�������j����2019/02/14(��) 22:19:04.44
>>726
���H
�����]����ł�́H
��B�����ςȎ咣���āA�Ȃ̂ɏ؋���o�͒f����
�Ƃ����ُ�ȏ�ԂȂ���
��B���͓����������Č������ł��Ȃ��́H 732���{�������j����2019/02/14(��) 22:20:27.34
>>669
�p���V�c��拍��̓^�`�o�i�g���q����B
�^���V�q�R�͌i�s�V�c�⒇���V�c��拍��Ɋ܂܂�Ă���B 733���{�������j����2019/02/14(��) 22:21:41.65
>>717
���킽���͔ږ�Ăƒf�肵�ĂȂ���H
���N��̓M���œ͂��\���̂����Ȃ͎̂�������
�܂����������Ȃ��Ƃ�����
�����ł�200�N�����ď����Ă�����Ȃ�����
�ږ�Ă̎���248�N�i���j
����̐���N�オ260�`280�N������A����̕����߂���
����͔N�オ����Ȃ��Ƃ��A���O�͂�����x�ƌ����Ȃ悗��
�����\�N���O�ƂȂ��f�肵�Ă�́H
200�N����248�N���Ŗ�50�N�Ⴄ����H
�ȒP�Ȉ����Z���� 734���{�������j����2019/02/14(��) 22:21:53.11
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
��B������畷�����Ȃ��U�肵�Ă����ꂪ����
735���{�������j����2019/02/14(��) 22:22:10.58
�y�הn�䍑�̎��ӂ̍��z
1�ԁ@�z�n���͎u���i���j�S�i�����������s�j
2�ԁ@�ȕS�x���͈ɖ����i���ꌧ�ɖ����s�j
3�ԁ@�Ɏ��͕��˓��i���茧���ˎs�j�܂��͈ɍ������i���茧�|���s�j
4�ԁ@�s�x���͑���i���茧�����ێs����j
5�ԁ@�\�z���͒��茧����s�i�܂��͒��茧���ދn�S�j�܂��͗�i���ꌧ�݂₫���O���j
6�ԁ@�D�Ós���͍����S�i���茧�_��s�j
7�ԁ@�s�č��͐{�Ái���ꌧ�n���S���Β��j
8�ԁ@���z���͑]���i���ꌧ�_��s�_�钬�{�x�]�������j
9�ԁ@���h���͒����i���ꌧ�����s�M�䒬�j�̈��i�c���
10�ԁ@�h�z���́H
11�ԁ@�ėW���͍��ꌧ����s
12�ԁ@�ؓz�h�z���͍��ꌧ�_��s�̋g��P�����
13�ԁ@�S���́H
14�ԁ@ፑ�͈ɌÁi���茧�_��s���䒬�ɌÈ�Ձj
15�ԁ@�S�z���͏��S�i���������S�s�j
16�ԁ@�הn���͔����i�����������s�j�̍L�삩���Ǒ�A�����E�T�m�b���
17�ԁ@�Z�b���͋��i�啪�����S��쒬�j
18�ԁ@�b�����͔f�i���������q�s�j�܂��͐j���i�������}����s�j���j
19�ԁ@�x�ҍ��͊������i���ꌧ�O�{��S��R���j
20�ԁ@�G�z���͑�����i����������s�j
21�ԁ@�z���͓߂��p�i�����������s�j�̍Čf
�הn�䍑�i�`���j�͈̔͂͂����ނ˒}���Ɣ썑�������z�����������͈͂ł���A�����v���Ɏ���5000���ł���i�Δn�C����3000���j�B
鰎u�`�l�`�ɂ́A���ɊC���킽�����Ƃ���ɂ��`�l������ƋL�ڂ���A�{�B�Ǝl���̂��Ƃƍl������B
��؍��@���N�������
�ΊC���@���茧�Δn�s�A��卑�@���茧���s
���I���i��������j
�ɓs���@�����s�i���}�y�S�j�A�z���@�����s�i�߂̒Áj�����킹�Ďהn�䍑�i�����̓s�j
�s�\���@�����s����i���ŋ{�j
���n���@�{�茧���s���s�i�s���_�Ёj

736���{�������j����2019/02/14(��) 22:22:23.78
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
�\������B�L�`�K�C���ǂ�Ȃɓ�����낤�����ꂪ����
737���{�������j����2019/02/14(��) 22:22:52.12
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
738���{�������j����2019/02/14(��) 22:23:34.36
�הn�䍑�E�������A�j�]���Ă��܂����̂��ˁA�A�A
739���{�������j����2019/02/14(��) 22:24:08.51
�E���́u�����͂�v �̂��悾�炯�B
�E���n��̌Õ��̐ޒ������i�ނɂ�āA�`���i���g�j�̌����Њ��Ύ��╘�ɗp�����O���Õ��̎��Ⴊ�������Ă����B
���{�́u���{�R�Õ��v�A�u���R�R�Õ��v�A�u��ˌÕ��v�A�u�q��ԒˌÕ��v�A�_�ˎs�́u�������ˌÕ��v�Ȃǂ��T�^�Ⴞ�B
�����āA�������������Њ���g�����Ⴊ�A�E���k���̗��여�悩�琣�˓��k�݂ɂ����Ă̈�тɑ����X������薾�ĂɂȂ��Ă����B�@�@�����g
http://www.let.osaka-u.ac.jp/kouko/061018awaitano.htm 740���{�������j����2019/02/14(��) 22:24:56.95
��B�L�`�K�C���ǂ�ȂɌ����Ȃ��U�肵�ăo�J�ۏo���̊Ԕ����ȓ�����������������悤�������͌���
741���{�������j����2019/02/14(��) 22:25:24.09
�w���g�̐i�ΐF�����Њ�j�̐Ξؐޔ��o�x
�E�������ˌÕ��i���Ɂj�E�ܐF�ˌÕ��i���Ɂj�E�����R�Õ��i���j�E��؏��R�R�Õ��i���j
�E�ٓV�R�b�P�����i���j�E���R�Õ��i�͓��j�E���ĎR�Õ��i�͓��j�E���x�R�Õ��i�ޗǁj�E���P�ˌÕ��i�ޗǁj
�E�ʎ�R�V�E�X�����i�ޗǁj�E�L���R�Õ��i�ޗǁj�E�z�P�m�R�Õ��i�ޗǁj
�@�@�@�@�k���F���u�]��^�O����~���̒v�i�P�X�X�X����w�l�Êw�������@�L�O�_�W�j���
742���{�������j����2019/02/14(��) 22:27:02.01
�E���̌Õ��́A�`���i���g�j�̗L�͎x�z�҂����ɂ���āA�`���i���g�j�̋Z�p�i�ϐH�@�j�A
��v���ށi�E����铙�j�A�����i�i�S��ށE���ʁE�y�퓙�j���g���Ēz�����ꂽ���̂ł���B�@�@�����g
743���{�������j����2019/02/14(��) 22:28:08.81
�l�Êw�͎c���ł���B�@�@�����g
744���{�������j����2019/02/14(��) 22:28:09.20
�הn�䍑�E�����́A�j�]���Ă��܂����̂�����A���̃X���b�h�͕�����Ηǂ���
�A�A�A
745���{�������j����2019/02/14(��) 22:28:25.63
>>722
������ς�o�_�ɑ��āA鰎g�������т炩�����������̂��Ȃ��c�B
鰎g�͘`���̏���������d��������A�`�����������т炩�����������Ƃ������A
鰎g���o�_�����悤�ɋ��߂��Ǝv�� 746���{�������j����2019/02/14(��) 22:28:42.86
424>>590
���E�������u�܂Łv�ꖜ��痢�A�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�הn�䍑
�E�P����痢�����̋�B�����̓^�����Ƃ������s�������������犫�������u�������ł������Ȃ������v���Ɩ��L�����
�E�������ł͈�呲�Ƃ͑����ɔh�������Ď������Ɩ��L����A��B�������ł��邱�Ƃ́y�m�肷��z
���ꂪ�^����
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 747���{�������j����2019/02/14(��) 22:29:29.68
�����j�͑�a�̐��͂��הn�䍑���畽������ɂ܂Ōp�����Ă��邱�Ƃ�����
��B�͎הn�䍑�̍����瑮���ł��邱�Ƃ��������Ă���
�l�Êw�ł͋�B�ɂ̓��N�ȕ����Ȃ��Õ�����ɂȂ�܂ŋ�������������Ȃ�
���ꂪ�o�J����������ڂ����炵������葱�����B�̌���
748���{�������j����2019/02/14(��) 22:29:50.40
>>744
���l�̗��R�ŁA��B�����ˁB�@�@�����g 749���{�������j����2019/02/14(��) 22:31:18.64
�הn�䍑�E�������A���S�ɔj�]�������Ƃ��A�������Ă���ȁB�B�B
750���{�������j����2019/02/14(��) 22:32:44.58
424>>590
���E�A���m�^���V�q�R�̓s�͑�a�ł��鎖�A�����Ďהn�䍑�Ɠ����ł��鎖��
�הn�䍑�Ȃ�đ��݂��Ȃ����ƁA
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 751���{�������j����2019/02/14(��) 22:33:17.46
>>749
���������Ă���ȁB�B�B
����A�ǂ��ǂ߂����̂��ˁH�@�@�����g 752���{�������j����2019/02/14(��) 22:35:13.76
�o�J��B���������Ă������͕ς��Ȃ�
753���{�������j����2019/02/14(��) 22:35:19.69
>>728
������Ȑ��x�Ȃ�A鰎u�`�l�`�ɂ���������邾��B
�����Ă��邾��H
�ږ�Ă����ŁA�������̒j�킪�������
鰎u�`�l�`�̂��̋L�q���A�q���q�R���̑傫�ȍ����ɂȂ��Ă��
�嗤�ɂ͒j���̋����������Ă̂��Ȃ�����A���͔ږ�Ĉ�l�Ə�����Ă��邯�ǂ�
�v�g���}�C�I�X���G�W�v�g���`���̂��Ƃ��j���ɋL�^���Ă�����A�j��������Ə����ꂽ���낤�� 754���{�������j����2019/02/14(��) 22:36:31.10
424>>593
�������ɁA�Ⴆ�Έ�c���ɂ����Ȃ������\�q����ږ�Ăɔ�肷��]�n���o�ė����
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 755���{�������j����2019/02/14(��) 22:37:10.28
>>752
���o�J��B���������Ă������͕ς��Ȃ�
�o�J��B�������A����ɏo���Ȃ�����A�h�����Ȃ����B�@�@�����g 756���{�������j����2019/02/14(��) 22:40:37.03
424>>594
�������邩�ȁH�\������B�L�`�K�C �A���m�^���V�q�R�����ɗp���V�c�ƈႤ�l�������Ƃ��Ă����ɂ��ς��Ȃ���
�A�z����
�A���m�^���V�q�R�Ȃ�Ă��Ȃ�����A�~�B
�����邩�ȁH�A�\������a�L�`�K�C�̃A�z���B 757���{�������j����2019/02/14(��) 22:40:50.15
��\��B���Ɖ�b����K�v�ȂǂȂ�
������������������
��B�L�`�K�C���ڂ����炻�������ꂪ����������������
758���{�������j����2019/02/14(��) 22:42:34.60
��B�̃A�z���������Ēm��Ȃ��U�肷��Ό������ς��킯���Ȃ�
�����{���̎������������邾���ŗǂ�
759���{�������j����2019/02/14(��) 22:43:58.12
�E��������ꂽ���R�[�h�̂悤�ɂ���ڂ������邾���ɂȂ��Ă��܂����B
760���{�������j����2019/02/14(��) 22:45:16.90
�ŏ��̉��s�Ƃ��ĕ�������ɋg�����؈�Ձi�I���O2���I�j�A�z���ƍl�����Ă���{�艪�{��Ձi�I���O2�`1���I�j������A
��ɍ��c�R���͂������̎�������Ɉړ����Ĉɓs���Ƃ����O�_�쏬�H��Ձi�I���O1���I�̉��E���ܕ�j�A�䌴���a��Ձi�I��1�`2���I�̉���j�A������Ձi�I��2�`3���I�̏�����j������B
�O�_�쏬�H��Ղ��P���悩�甭�����ꂽ���s�ԕ����ɂ́u�����V���V���喾�v�Ƃ�������������A���z�����ۂ������ł��邱�Ƃ��킩��B���s�ԕ����͒����ʼn���ɉ�������Ă����`���ł���A�`�����������̍����̌��ł̍Ր���v�������Ƃ��Ă������Ƃ��킩��B
���a40�N(1965�N)�ɕ�����Ղ���o�y�����ő�̓��s�ԕ����͍��Y�ƍl�����Ă���B���̉~���������8�@�i���a1�ڂ̉~�̉~����4�@�j�ɑ������邱�Ƃ���A�L�I�Ȃǂɂ����ăA�}�e���X���j�j�M�ɗ^�����Ƃ���锪�@�̋��ł���ƍl�����Ă���B
���Ă͔��@�͒P�ɑ傫�����Ƃ��Ӗ����邾�����Ƃ����������������A���̋��̏o�y�ɂ����ۂɉ~�������傤�ǔ��@�ł��鋾�����݂������Ƃ��m�F���ꂽ�B
�����̉����͍��c�R�̓����̕�������̓z���ɐ������A��ɐ����̎�������̈ɓs���Ɉړ����Ă��邪�A�o�y�i��搧�������ł��邱�Ƃ����{�I�ɂ͈�A�̉����ł���ƍl������B
�O��̐_��͌��݂̓V�c�Ƃɂ����Ă��ے��Ƃ���Ă���A�`�������̋N���͈��`���̒n�ł����邱��甎���p�E���E����ӂɂ��������ƂɂȂ�B
���ꂪ�ږ�Ă������ƂȂ����`���̎p�ł���B
761���{�������j����2019/02/14(��) 22:45:45.59
>>759
���E��������ꂽ���R�[�h�̂悤�ɂ���ڂ������邾���ɂȂ��Ă��܂����B
��B�����������������B�@�@�����g 762���{�������j����2019/02/14(��) 22:46:12.86
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
��B������畷�����Ȃ��U�肵�Ă����ꂪ����
763���{�������j����2019/02/14(��) 22:46:55.15
424>>599
������߂��Ȃ���u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x�������āA
�A�[�A�[�L�R�G�i�C�����Ă��a�o�J�̎p���A
�������ō��ɏ��� 764���{�������j����2019/02/14(��) 22:48:21.56
�E�������܂łP��2�痢�B�������琅�s10���A���s�ꌎ�ŏ����̓s�̎הn�䍑�i鰎u�j
�E�P��2�痢�����̋�B�͏������ł������Ȃ��i鰎u�j
�E��B�͏������ɓ������闧��Ɩ��L�i鰎u�j
�E��呲�͑����ɔh�������Ď����i鰎u�A�������A�V�����j�ł��ꂪ�풓���Ă����B�͎הn�䍑�̎��ォ�瑮��
�E�q�i�����͕ƒn������B�e�n�Ɏc��ڈ�F�P�A�嗤�Ƃ̋��ɕ��z����n���A�_�Ж��i�a�����j�ł��ꂪ�z��������B���ƒn�ł��邱�Ƃ�������
��B�͒����j��ʂ��đ�a�ɑ�����ƒn�ł���Ə����Ă���̂�������
��B�������B���Ȃǂƌ����Q���͂��������ǂ��ɂ����݂��ĂȂ�
�C���`�L�P�ʂ�������s�����悤���A�o���_��������떂����������B�͏������ɂ�������Ȃ�����
�\������B�L�`�K�C���ǂ�Ȃɓ�����낤�����ꂪ����
765���{�������j����2019/02/14(��) 22:49:01.80
�y�}���𒆐S�Ƃ���`���̌��H�z
���Ƃ��Ɠ��{�C���[�g���`���̌��Ղ̎�͂������B4���I�̒����V�c�̂Ƃ��Ɋ֖�C�����J�킳��A5���I�̗Y���V�c�̂Ƃ��ɕ��҂��`���Y�W����������A���˓����[�g���������ꂽ�B�Ȃ��A�����m���[�g�͎����㑶�݂��Ȃ������͗l�B㕌��͓��{�C���[�g�̖����̕Ӌ��B
�}���������o�_���O��E�ዷ���\�o�E�z���z�K���b��E����
���@�@�@�@�@�@�@�@�@��
���@�@�@�@�@ �@�@�@�ߍ]���������Z��
��
�F�������|�E�ɗ\�����g�E�g�����W�H�����ےÁE�͓�
�y��B�k�����͂ɂ��`���̊g��z
�I���O�ɁA�z�̃q�X�C���ʂ��܂ގO��̐_�킪�o��
�����{�C���݂̓y�킪�����p�֗���
1���I�ɓ����Ȃǂ��g�U
2���I�ɍ��n���W�������˓��C�𓌐�
�����˓��l���̓y�킪�����p�֗���
2���I���ɓ��������p�㗤
��3���I���ɋE�����珯�����y�킪�����p�֗���
3���I���ɑ�^���s�ԕ������E���N��
���E������z�����y�킪�����p�֗���
�x�z�͐����瓌�֊g�債�A�y��Ȃǂ̎Y���͉��s�ł���}����
766���{�������j����2019/02/14(��) 22:51:36.26
424>>600
�܂��u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a�����́A
�����Ŏ����o���Ă��鎑�����S�Ď��ł��Ă�ӂ�A�z�����Ėʔ���
������������v���S����a���Ȃ�Ă���܂���
��B�͎הn�㚠�����V���s�̒n�ŁA��a�͐̂��瑮���ł����I
���Ă̂����X�������炢�n�b�L���Ɩ��L����Ă�킯������Ȃ� 767���{�������j����2019/02/14(��) 22:51:53.00
������������������
�Ȃ�ɂ��Ȃ��ޗnjȂ̂���
768���{�������j����2019/02/14(��) 22:52:12.65
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
769���{�������j����2019/02/14(��) 22:53:02.69
>>765
��2���I���ɓ��������p�㗤
����3���I���ɋE�����珯�����y�킪�����p�֗���
��3���I���ɑ�^���s�ԕ������E���N��
�����E������z�����y�킪�����p�֗���
�������������āA�Z���[���� 770���{�������j����2019/02/14(��) 22:53:26.90
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
771���{�������j����2019/02/14(��) 22:54:28.35
424>>601
���הn�䍑�͑�a ��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 772���{�������j����2019/02/14(��) 22:55:46.10
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
773���{�������j����2019/02/14(��) 22:57:19.00
�U���R�N�����A�_�j���Ă��܂����B�B�B
771���{�������j����2019/02/14(��) 22:54:28.35
424>>601
���הn�䍑�͑�a ��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 774���{�������j����2019/02/14(��) 22:58:19.65
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
775���{�������j����2019/02/14(��) 22:58:56.25
424>>694
�u�ڂ�����m��Ȃ��v �u�ڂ�����F�߂Ȃ��v �u�ڂ���������v�����v
���ꂪ�_���Ǝv���Ă�̂��u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̔\�����̑�a��
�ڂ�����F�߂Ȃ��I�Ƌ�����߂��Ă�̂����_�ɂȂ�Ǝv������ł�̂�����
���낻��ރX���傩�X�O�x�ӂ肪�N���āA
�X�����������낤�Ȃ� 776���{�������j����2019/02/14(��) 23:00:30.01
>>773
���ꂪ�ō��ɏ����肵��
��B���]������ 777���{�������j����2019/02/14(��) 23:02:27.30
424>>605
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a���o�J�́A
���������u���������������s�����I�v�Ƃ��o�J�ۏo���̖ϑz�������
�ڂ������̔]���̃z�����������A
�Ƃ��̂���������Ă�̂ɂȂ�
1����10�܂Ŗϑz�����Ȃ���a�����Ȃɂ��ق����̂�� 778���{�������j����2019/02/14(��) 23:03:13.85
����̘J���́A������ς������̂ŁA�C���^�[�l�b�g�Ŏהn�䍑�E�������`����؍��l�𝈝������Ηǂ��ȁB�B�B
779���{�������j����2019/02/14(��) 23:03:37.98
>>776
�����A���O�I
�����L����
�ޗnjŎ����Ă��� 780���{�������j����2019/02/14(��) 23:04:03.07
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
781���{�������j����2019/02/14(��) 23:04:39.01
�K���Ɍ����Ȃ��L�R�G�i�C���J��Ԃ���������B���̎p�ɕ�����|
782���{�������j����2019/02/14(��) 23:06:13.54
��̒��ɓS��O��
��̊O�ł͂Ȃ�Ɩ؊���g�p
�ȁ[�[�[�H��
783���{�������j����2019/02/14(��) 23:06:32.09
�܂�A�הn�䍑�E�����́A���S�ɔj�]�����̂��ˁA�A�A
784���{�������j����2019/02/14(��) 23:06:53.98
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
785���{�������j����2019/02/14(��) 23:08:32.82
�הn�䍑�E�������A���S�ɔj�]�������Ƃ��A�������Ă���ȁB�B�B
786���{�������j����2019/02/14(��) 23:09:55.26
�הn�䍑�E�����́A�j�]���Ă��܂����̂�����A���̃X���b�h�͕�����Ηǂ��ȁA�A�A
787���{�������j����2019/02/14(��) 23:11:58.50
�A����Ǔ_�͊��S�ɉ�ꂽ���Ƃ����Ԃ���}���Ă��
788���{�������j����2019/02/14(��) 23:11:58.37
�l����ǁ@�l����ǁ@�P�@�킪���n�ɒ�������
�����ƒn�}������
�L�i�C�R�V�@�w�ޗnj̍��x
789���{�������j����2019/02/14(��) 23:13:20.99
��B�̃A�z���K�������Č�������ڂ����炵�ăz���𐁂��Ȃ���̂��������p���ō��̌�����
790���{�������j����2019/02/14(��) 23:13:56.86
�A����Ǔ_���ϑz�ޗnj��L�i�C�R�V�A��
791���{�������j����2019/02/14(��) 23:15:11.58
��������S��͑S�����V�̂��̂��Ⴀ�I
���܂���͖؊킶��؊���g���Ă������Ⴀ�I
792���{�������j����2019/02/14(��) 23:17:07.91
�הn�䍑�̍��̋�B�̌���
�E���͌Â��j���⋾�ЁA���^?��������Ŋ��`����V�������Ȃ��V�����⊮�`�����o�Ă���̂�4�`5���I�̌Õ��o�y����
�E�������Â����𒒂Ԃ���?�������炯�ňꕔ�̋����Â����A������������Ō�ɋ�B���狾���܂Ƃ��ɏo�y������ꏊ���Ȃ��Ȃ�
�E���͒�����13��Ղ��猃����1��ՂŖ��z�����e�G�Ȏ��������ꂩ����o��̂�
�E�{�a�Ȃlje���Ȃ�
�E���J��Ղ�������{���Ă������̕������Ȃ�
�E���̓������@����Ă����O�R�ȂǂȂ�
�E������g��P�����܂߂ĂقڑS�悪�E���̓y��ɓh��ׂ���Ǝ��̐����l����r��
���ꂪ�o�J���ڂ����炷�u���{�̒��S�̍Ő�[�n��v�Ƃق�����B�̌���
793���{�������j����2019/02/14(��) 23:19:39.01
>>784
���[��˂�
�P�Ȃ铺�ł͂Ȃ��S���ł�������ő���������
�U��߂�ꂽ�{���̉������̎������A�����Ė퐶���㐻
���̋��͑啪�ŏo�y���܂���
�����̒������F�߂��`���͋�B�ɋ�����ł��� 794���{�������j����2019/02/14(��) 23:19:55.79
��B���������悤�Ƃ��Ă������Ɍ����ɉ�荞�܂��
795���{�������j����2019/02/14(��) 23:20:53.66
�L�i�C�R�V�������悤�Ƃ��Ă������ɓޗnjɑj�܂��
796���{�������j����2019/02/14(��) 23:25:11.98
�啕R���̓��s�ԕ��������ʂɏW������o�y���Ă����ȁB
�X����͂�͂薲�ł����Ă���̂ł͂Ȃ��̂��ȁH�B�B�B
����Ƃ��ςȃN�X���H�B�B�B
797���{�������j����2019/02/14(��) 23:25:15.34
>>733
���H�f�肵�����R�����̈ӌ��H
���͕�̔N��͕��������čl���Ă���̂���
����͔n��l�b�N�ŁA����ȏ�Â��ł��Ȃ�������300�N�O��̉\�������邾�낤��
�����͋��̌^����2����Ǝ��a�̋��L�ɂ��2���I�����Â��Ȃ��̂͊m��
����ƁA�����̔N��Ɋւ��Ă͂����܂Ŗ��c����d���āA�ʐ����q�ׂ������ŁA�l�I�ɂ͋��̋Z�p�͂�����̊Njʂ̒��N�����̏o�y�ɂ���ẮA�N��I�ɂ͔ږ�Ă̕�̉\��������悾�Ǝv���Ă��� 798���{�������j����2019/02/14(��) 23:26:20.55
�����j�̓��{
�E��^�̌�ɒj�����������W�A�v�A�āA���A�@�ƌp�����Ďg�߂𑗂��Ă��Ă���i��ď��A�����A�k�j�A�@���j
�E�p���V�c���@���̃A���m�^���V�q�R�ƒf�肵�_�ォ�犺���V�c�Ɏ���n���ɓ���Ă���i�V�����A�v�j�j
�E�v�j�ɂ����ē��{�̉����������ƌp�����Ă鎖���̎^�i�v�j�j
�@�A���m�^���V�q�R�E�p���V�c�̓s�͐_����̑�a�Ȃ̂ŁA��a��鰎u�̎הn�䍑�ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�V�����j
�A�}����]�X�͐_���O�̎��Ȃ̂ŋ�B�͎הn�䍑�ł͂Ȃ��̂��m��i�@���A�V�����j
�B��呲�͑����ɔh������A������Ď������E�ŋ�B�������ł��邱�Ƃ��m�肷��i鰎u�A�������A�V�����j
�C��L����`������{�ւ̉��̂͐p�\�̗��ł��邱�Ƃ��m��i�@���A�������A�V�����A�v�j�j
�������͓��{�W�Ȃ��Ǝ��̋L�^����L�ڂ��Ă���̂ŁA�����������{�̈Ӑ}�ȂNJW�Ȃ����������ċL�q���Ă���̂��킩��
�����ɃA���m�^���V�q�R���p���V�c�ł��낤���Ȃ��낤���@���A���B���C�������ς��Ȃ�
�����͎הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m
�ŏ������B�����A��B�����������͈�؍l���Ă����Ȃ��̂�������
799���{�������j����2019/02/14(��) 23:26:59.73
���A���V�I�H�H
�ԁA���킪�Ⴂ�܂��I
���̕���͎����͌��Ă��܂���I
800���{�������j����2019/02/14(��) 23:29:15.90
�E�����̊NjʂƓ��ނ̂��̂́A���{����͏o�y�����A
�؍��̍]�������C�s�������ꍆ�Z���Ղ�c���쓹���C�S�Ǔ����O�l���؞��悩��
���ʂɏo�y���Ă��āA�����́A�������Ă���y���S�킩��O���I�O������
�l���I�ƍl�����Ă���
�E��璫���W��i265 – 316�N�j�O��ɓ����I�ȓ���Ȍ`��̂��̂ŁA
��������Z�������ɑ���ꂽ�Ɛ�������韴�]�ȍY�B�V�a�R�����悩��
�o�y�������̂Ɠ��^�ł���B
801���{�������j����2019/02/14(��) 23:29:26.99
��B�̃S�~�N�Y���K���߂��Ċy����
802���{�������j����2019/02/14(��) 23:30:10.69
������Ղ̔N�オ�`���嗐���k�邱�Ƃ͂Ȃ�����������A�Y�����鏗���͔ږ�Ă������Ȃ��B
�ȒP�Ȃ��Ƃ���B
803���{�������j����2019/02/14(��) 23:34:19.64
�������������������邾���Ŗウ�ꂵ��ł̂���������B���v���̎p������̂��ō��̌�y
804���{�������j����2019/02/14(��) 23:46:55.42
805���{�������j����2019/02/14(��) 23:56:38.98
�ɓs�N�Y�̓C���[�W�ł������Ȃ�
�e�_�������o�����Ƃ����g���Y��
�قƂڂ肪���߂�Ƃ܂��ϑz�������͂��߂�
806���{�������j����2019/02/15(��) 00:03:35.37
���̕a�@�ɍs���ƌ����Ă����A
�ǂ߂Ȃ��̂��H
807���{�������j����2019/02/15(��) 00:05:44.28
�퐶�n�H�ނ��[���̒����l������ł���A
�Ȃ����{�̐�Z���ɂȂ��
808���{�������j����2019/02/15(��) 00:07:20.65
�A�}�e���X�A�X�T�m�I�`�H�Ƃ��A
��n�O�Ɠ����悤�Șb�����Ă���̂�������
809���{�������j����2019/02/15(��) 00:10:51.75
���̃X���ɂ������Ă��鎖�Ȃ���
����ς܂��A�x��H�܂������́H
���������̂̏W�c�Ȃ낤
810���{�������j����2019/02/15(��) 00:11:47.51
811���{�������j����2019/02/15(��) 00:14:35.19
���y�n���_�b(����)�Ƃ����̂�����ł���H
�ŏ��A�n�܂�̏ꏊ�͂ǂ��Ȃ�
812��90�x��]����2019/02/15(��) 00:16:50.09
>>689
�L�I�͔N�㒲����n�}�˂��̂��߂ɉˋ�̓V�c��}�������肷�����A
����ɔ�ׂ�Ώ����̗L�͐b������t���Œj�q��n�̓V�c�ƌ������Ƃɂ��A
��������c���Ɋi���������肵�Ă��A�ʂɕs���R�ł��Ȃ�Ƃ��Ȃ��B
�܂��A������ɂ��Ă��ږ�Ă������ɁA
�Q���߂��l�X���������悤�Ȑ����ł��ĂȂ��K�͂̋���ȗ˕���������A
�i���l�ҁA����l��A���_��j�i�ڜ\�ĈȎ��@���n�j�ƁA
�ޗǖ~�n�̒[����[�i�����ɂ��ď\���L���j�܂ŁA1���l��2���l�̐l�Ԃ��Y�����ƕ���ŁA
���R�i���R�j���產��Õ��܂Ő���n���ʼn^�ƌ����̂́A
�l�S�N��̐l�Ԃɂ��`��鋭��ŖY�ꂪ�����G�s�\�[�h�������̂��낤�B
�����Ă��̕K�����́A鰎g�ɂ�������^�����̂��낤�B
�i���l�ҁA����l��A���_��j�i�ڜ\�ĈȎ��@���n�j
����2�̕��͂́A���S�ɃV���N�����Ă�Ǝv���B 813���{�������j����2019/02/15(��) 00:20:20.89
���{�̐_�b�H
���Ƃŗǂ�����A��ė����ƌ����Ă����A
814���{�������j����2019/02/15(��) 00:21:38.96
�����R�i���R�j���產��Õ��܂Ő���n���ʼn^�ƌ����̂́A
���l�S�N��̐l�Ԃɂ��`��鋭��ŖY�ꂪ�����G�s�\�[�h�������̂��낤�B
����ŖY�ꂪ�����G�s�\�[�h
����ŖY�ꂪ�����G�s�\�[�h
����ŖY�ꂪ�����G�s�\�[�h������
815���{�������j����2019/02/15(��) 00:23:02.13
>>797
�����͕�̔N��͕��������čl���Ă���̂���
�N�㕝�́u50�N�v���Ȃ�����
�������͋��̌^����2����Ǝ��a�̋��L�ɂ��2���I�����Â��Ȃ��̂͊m��
����2����̎�������o���y��Ђ�2���I���������Ă���H
�P������������܂��Ă�����ꂽ�y�B��̈╨�����2���I�����Ó�
���l�I�ɂ͋��̋Z�p�͂�����̊Njʂ̒��N�����̏o�y�ɂ���ẮA
���N��I�ɂ͔ږ�Ă̕�̉\��������悾�Ǝv���Ă���
���ǁA�u�ʐ��͐M���Ȃ��|�v���悗
�T�^�I�ȋ�B�����Ȃ�
���ł�
������͔n��l�b�N�ŁA
����͔��悪����Ă��玞�Ԃ��o���Ă�������ɓ��������̂ŁA
����̒z���������������̂ł͂Ȃ�
�����̃}�k�P���� 816���{�������j����2019/02/15(��) 00:28:53.18
>>802
���Y�����鏗���͔ږ�Ă������Ȃ�
���������������ǁA�����P����̔푒�҂͏����L�͎҂ł����āu��������Ȃ��v
�{���Ƀ}�k�P����
�����́u�v�����݁v���]���Łu�����v�ɕϊ�����Ă邾��
���ڂ̗̒n�̎הn�䍑�����Ŏ����˂̑卑�Ȃ̂ɁA���l�j�q��10�l�������
1�T�Ԃō���悤�ȏ����ȕ��`���a�悪�`���̕悾�Ǝ咣�ł���ӂ肪
��B���̂��Ԕ�������@���Ɏ����Ă���ˁI 817���{�������j����2019/02/15(��) 00:38:45.08
���ĎR�`�A���{�Ō����Ɖ͓��Ȃǂ��o�Ă���b�H
�Ƃ͖{���Ȃ̂ŁA
�����������̂��e�[�}�ɂ�����i�Ȃǂ͊ς���ǂ肵�Ȃ�����A
�悭�킩��Ȃ�
818���{�������j����2019/02/15(��) 00:41:00.78
>>811
�����y�n���_�b(����)�Ƃ����̂�����ł���H
���ŏ��A�n�܂�̏ꏊ�͂ǂ��Ȃ�
�悭������̂́A�����ݐ_�b�͂��Ƃ��Ƃ͒W�H�����ӂ̐_�b���낤���Ă���
���ƁA�������낢�ȂƎv�����̂��A�ŏ��ɓV�V��������H�藎���Ăł���磤�f������
�͓��̒��̓��������Ƃ�������
���ł͗��n�ɂȂ��Ă��邩��A������T���Ă����͌�����Ȃ� 819���{�������j����2019/02/15(��) 00:42:00.91
�L���E���̂悤�ȗt(�J�b�p�H)�Ȃǂ��ʂ��Ă���ʐ^������ł���H
����(�ނ��[���H)�H���`�Ƃ����Ƃ���̋ߏ��ɏZ��ł����ƌ����Ă��邵�A
�\�������A�@�D�����Ă�����E�E�E�E���Ǝ��@���`�Ƃ�
820���{�������j����2019/02/15(��) 00:47:45.00
�ŋ��Ȃǂ������H
���҂̂悤�Ȑl�X������ł���H
���������l�X������ɂ���Ă��邾����
821���{�������j����2019/02/15(��) 00:52:17.07
���҂Ȃǂɕ����Ă݂�Ƃ킩��
���Ȃ��̉ƂƂ����̂́A
�����Ă�����Ɠ����Ȃ̂ł����H
�Ⴆ�Ύ��@�Ɂ`(�m�H)�A�\�A�@�D������Ă���E�E�E�����H�ׂȂ�
822���{�������j����2019/02/15(��) 01:01:38.27
�����̏��_�H���V�L�H
�Ƃ̘V�k�ɂ��ƁA
���̎ʐ^�̉Ƃ́`�`�`�`�`�`�`�`
�w�T�U�G����x�̂悤�Ȏ��������Ă�����A
����(�f���ɉ���)�Ł`�Ƃ����Ƃ��낾��
823���{�������j����2019/02/15(��) 01:04:36.73
�����̂܂܂Ŕ�яo���ā`�Ƃ����Ȃ������ł���H
�Ƃ̘b�ł���
824���{�������j����2019/02/15(��) 01:07:09.83
�K�A�K�̉��ʂ��Ă��āE�E�E�A
�Ƃ͌����Ă��K�_�ƂƂ����Ƃł��Ȃ����A���@���H
825���{�������j����2019/02/15(��) 01:17:20.78
���x�����Ă������A�{���̘b(�w�V�k�k�x)
�����Z��ł����ƂƂ����̂����������ǁA
����[���ƕ���ł����{�⏑�Ȃ��A�N���ɂ������̂��ȁ`
�E�E�E�E����Ƃ��E�E�Ƃ�
826���{�������j����2019/02/15(��) 01:17:40.89
�����Ƃ��C�Ƃ����@����Ăˁ[���낤�ȁH�H
827���{�������j����2019/02/15(��) 01:20:09.21
�Ȃ��A�悭�킩��Ȃ��{����ƌ����Ă���(�V�k�k)
�{�\�A�@���W�̖{�Ȃ̂��ȁH
828���{�������j����2019/02/15(��) 01:23:43.99
�w�����s�[�X�@����x
���̘b�������Ȃ�Ȃ��́H
829���{�������j����2019/02/15(��) 01:25:20.82
�w�f�X���`�x�H
830���{�������j����2019/02/15(��) 01:39:49.43
�����y�����B�̂��̂͂قƂ�ǖ����݂������ȁB
�����l������ȋE�����́B
831���{�������j����2019/02/15(��) 01:42:57.38
�w���X�x�H
�����������O�̉ƂȂ��ǁA���Ȃ낤
832���{�������j����2019/02/15(��) 01:46:05.56
>>818
�ُ�҂Ƀ��X����Ȃ�
�v���U��Ƀ��X�Ⴆ���������������n�b�X����������Ă邶��ˁ[�� 833���{�������j����2019/02/15(��) 01:53:49.85
834���{�������j����2019/02/15(��) 01:57:15.79
������
�������ŃS�U����
�������������Y�̌������𐿋�����ŃS�U��
835���{�������j����2019/02/15(��) 01:58:11.65
�w�h���t�^�[�Y�x�Ƃ�����i�̘b�Ȃ̂��ȁH
836���{�������j����2019/02/15(��) 02:01:13.61
�Ƃ͌R�l�ł͂Ȃ��H�݂����Ȏ��������Ă������ȁE�E�E�A
�푈�Ȃɂ��s���Ă��Ȃ���Ƃ��A���Ȃ낤
837���{�������j����2019/02/15(��) 02:26:47.27
�w�ɒB�̓����Y�x
�{���ɂǂ��������ƂȂ낤�A
��̖��O�̓ǂݕ��`�`�`�`�݂����Ȏ��������Ă�����
838���{�������j����2019/02/15(��) 05:35:12.30
>>1
�����{�C���[�g�̖��_���w�E���ׂ����ᖳ������ 839���{�������j����2019/02/15(��) 05:39:20.62
>>792
����l�ɖ�肪���邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��́H 840���{�������j����2019/02/15(��) 05:45:58.39
�w�h���t�^�[�Y�x�E�E�E�����s�[�X�H
�w���҂ɂ��Ȃ�Ȃ��@���O�����x
�قƂ�Ǔ����R���Z�v�g�A�b�ł���H
841���{�������j����2019/02/15(��) 05:46:59.28
424>>619
�����������ѕ��S�Ə������̂��������s���悭1����痢�ł������킯�͂Ȃ��B
�܂��ŏ��ɗ��Ԃ��A�����Ƃ������p��́u1����痢�v�ƒ�߁A
���ꂩ��A���������������̂��B
�i�Z���Ōv���Đςݏグ�����̂ł͂Ȃ��B�Z���̓t���^�̖\���j ��
鰂̖�l������ȃC���`�L�ł����グ�����āA
������㑱�̒����Ƀo���Ȃ������Ȃ��A�c���Ƀo���Ď�Ȃ����́B
���ꂪ�l�ނ̏펯�ł���A
��a���҂́A�l�ނ̏펯��������Ȃ��A���o�̖ϑz�́E�E�E�E�B 842���{�������j����2019/02/15(��) 05:47:04.11
>>816
�킩���
���͋�B�������A�ږ�Ă̕�͖��������ł��Ă��Ȃ�������ł��Ȃ��h
����ɂ����_�͑�������̂ŋE����������͂ł��Ă��Ȃ�
�L�͌�₮�炢���낤�@�z�P�m�̕��������Ƃ��v�����הn�䍑�͋E������Ȃ�����✖ 843���{�������j����2019/02/15(��) 05:52:04.15
424>>621
���{���ɒ�\����
�u�֒�����Ă���v�Ƃ����̂́A�u�Z���ȂǂȂ��v
�u���n�Ƃ͊W�Ȃ������������Ă���v���Ƃ������Ă����������
�ރX����́A�l�ނ̏펯�m�炸�́E�E�E�E��\�ł���A
���o�̉R�f���x���̖ϑz�ŁA�E�\���o���āA��Ȃ��B 844���{�������j����2019/02/15(��) 05:53:30.95
���x�����Ă��{���̘b�A
�L���E���̂悤�ȗt�A�K�̉��ʂ��Ă��Ă�ʐ^������ł���A
�֎q�ɍ����Ă���A���̏��̐l���łȂ�A
�Ȃ�ň�l�����A�f��(����)�ɉ��ʂȂ낤�A
�������\�������Ă��āA�@�D��Ȃ����Ă����ƂȂ�
�Ƃ������Ă����w�V�k�k�x
845���{�������j����2019/02/15(��) 05:57:21.09
846���{�������j����2019/02/15(��) 05:58:51.96
424>>623
�������āA�הn�䍑�ւ͂������炳��ɐ��s30���A���s�ꌎ�̔ޕ��Ȗ���
��B�ł͐��s�H����Ȃ��� ��
�s�\�����ݓ��]�����قڏI����Ă��邩��A
�u����ɐ��s30���A���s�ꌎ�v�́A�~�B
�u���s�\�����s�ꌎ�v�́A�ړI�n�ł���u�����V���s�v�̐���������A�S����̓����B
��a�́A�u�쁂���v�ɋ����Ă��A���S�Ɂ~�B 847���{�������j����2019/02/15(��) 06:04:02.08
424>>624
���S�̂��֒����Ă���̂ŁA�p���c�̃S���Ђ��̂悤�ȊW���B
�ǂ����Ƃ��Ă������悤�ȐL�т����݂̗��ł��邱�Ƃɂ��헢�͂Ȃ��B
�����ے肷��̂��A���\���E�E�E�B ��
��a���҂̐����́A�S�̂o�̖ϑz�̉R�f���x���Ōł߂Ă���̂ŁA
�p���c�̃S���Ђ��̂悤�ȊW���B
�ǂ����Ƃ��Ă������悤�ȉR�f���x���ŐL�т����݂ł����Ă���A
�S�̂��~�ł���킯���B
������m�肷��ރX�������A���E�E�E�E�A�z�̖\���E�E�E�B 848���{�������j����2019/02/15(��) 06:05:12.70
�V�k(�吳�ꌅ)�����܂�Ă��Ȃ����̎ʐ^���ƌ����Ă��邵�E�E�E�E�A
�ŋ��Ƃ��A���������̂���ςĕ�炵�Ă����H
849���{�������j����2019/02/15(��) 06:09:04.19
�钆�ɐV�X�����Ă����̂͂킩�邯��
��肷������ˁ[��
850���{�������j����2019/02/15(��) 06:16:17.33
424>>632
���ے�́A�������Ƃ̑Δ�Ƃ����K�`�؋�����̘_���I�ے肾��
��؍��i�v�T���j�[�Δn���@�@�@�@�@100km/1000����100m/1��
�Δn���[��卑�i���j�@�@�@�@�@�@�@70km/1000����70m/1��
��卑�i���j�[���I��(���Áj�@�@�@ 50km/1000����50m/�P��
���I��(���Áj�[�ɓs���i�����j�@�@�@ 25km/500����50m/1��
�ɓs���i�����j�[�z���i�����s�j�@�@�@20km/100����200m/1��
�Z���͖ϑz���� ��
�ق�A���Ԃ̊F���܁A�悭�������������ˁB
���ꂪ�ރX����̃C���`�L�̌���B
�����L�ڂ̏o���_�ⓞ���_���A鰎u�̋L�ڂƍI���ɂ��炵���R�f���x�������Ă���A
�������A���̑S�Ă��A
�u�����v�̂P�����S�R�S���ʂƉ��{���Ⴄ�悤�ȃA�z�����ɂȂ��Ă���A
���E�I�Ŏ��Ȕj�]�̕��o�̖ϑz�̂悤�ȋ��ɂȂ��Ă���I�B 851���{�������j����2019/02/15(��) 06:27:25.79
414>>638
���S�̂��֒����Ă���̂ŁA�p���c�̃S���R���L�т��N�ɂȂ��Ă�A
m�^1�������Ƃ������Ƃ́A���̔��n���̂��Ԉ���Ă��邱�Ƃ̉����̏؋���
���̗ރX����̋��ؑS�̂��A
�����́u�P�����S�R�S���v�̂U�{�{�ʂ̍��قɂȂ��Ă��邩��A
�������̔ے�̎��E�I���ɂȂ�������A�Ƃ����E�E�E�E�A�z���������B 852���{�������j����2019/02/15(��) 06:38:35.76
424>>641
���^�����A�^�����Ƒ��������ɂ́A�t���^����̔��n�̓g���f���E�I�\�}�c�N�������킯���B
�����A���̃t���^�̃g���f�����n�⎅�N�Y�S���t�N���u�������ƂɁA
鰎u�`�l�`�̗��͊Ԉ���Ă���]�[�A�Ƌ���ʼn��̂��A����܂���\���A�A�A�A�B
���������̑�O���u�����Ȃ��Ă̓C�J���B ��
�ރX���厩�g���A�����́u�P�����S�R�S���v�ʐ����A
�U�{�ʂ��Ⴄ���������āA
�ے肵�Ă��܂������A���Ă��ꂽ�B 853���{�������j����2019/02/15(��) 06:49:07.58
>>804
����a�̉����ւ̏�[�ȁB
�E���́u�����͂�v �����̕�ꂾ�����B�@�@�����g 854���{�������j����2019/02/15(��) 06:52:59.09
>>818
���悭������̂́A�����ݐ_�b�͂��Ƃ��Ƃ͒W�H�����ӂ̐_�b���낤���Ă���
�W�H���͘`���i���g�j�@���ƁA���x������w�@�@�E���͏o�開����Ȃ����Ă��ƁB�@�@�����g 855���{�������j����2019/02/15(��) 06:54:09.20
424>>644
������̌`�͓����I �ǂ�����̕����Ȃ̂��H��
���l����̂͏��肾���A�N������������闝�R�ɂȂ�� ��
���V�ƓS�V�Ƃł́A���̎E���З͓͂S�V�̕������|�I�ɋ����A
���V�������S�V��m��A�S�V���̗p����̂ł���A
���ꂾ���ł��A�S�V�̕����N�オ�V�����B
������A���V�́A�����ꂽ�o�_�n�������J�����̗̍p����ł����āA
�S�V�́A�k����B�����ʂɏo�邩��A鰎g�炪�L�^�o���A
��B�`���́u�����ѐl�\�܍��v�̕���ł���A
��a�Ȃǂ̓S�V����ʂɏo���́A�������R�₻�̕����̕�ł������낤�A
�Ƃ������ɂȂ�B 856���{�������j����2019/02/15(��) 06:56:22.78
>>854
���g�͂�
�������}�g�������הn�䍑�̏o��@�ւȂ̂��� 857���{�������j����2019/02/15(��) 06:56:23.66
>>833
�u�߉ϔ����Õ��v��u�ÌÐ��|�Õ��v�̐����́A�܂��ԈႢ�Ȃ��}���������������u�ᐙ�R�Y�v����B�@�@�@�����g�@ 858���{�������j����2019/02/15(��) 07:00:20.85
��K�̎E���͂̔�r�����������̂ɓK���ɏ����Ă��
�E���͂̓_�Ō��������ł��\���ɂ������̂Ŗ퐶�ȍ~�������g�p����Ă�
859���{�������j����2019/02/15(��) 07:02:22.93
424>>647
����B���̒�����A�ǂ�����Ԑl�C�Ȃ̂���
�k����ɓs�����הn�䍑���A���������A��ɕ{�����A�F�������A�F�������A��ゾ���A�{���
�܂�����H �ߔ������������́H��
�������́A�������W���ł���A�i��z���ȊO�́j�قڋ�B���t�ߑS��B
�����āA�`���ƂȂ�ƁA��z�����܂܂��B 860���{�������j����2019/02/15(��) 07:05:06.73
>>856
���̏o��@�ւ̕����A�ޗǖ~�n���y���ɂ��Δ����Đ�i�����������Ă���Ƃ������e���b�B�@�@�����g�@�@ 861���{�������j����2019/02/15(��) 07:09:35.93
����͕�e�ł���A
����Ǝq���Ȃ�Ȃ������H
�q�����s���s���ɂȂ����Ƃ����b�Ȃ́H
862���{�������j����2019/02/15(��) 07:11:57.26
���̃X������Ȃ�������
�W�U�P�́w�W�����x�̘b
863���{�������j����2019/02/15(��) 07:11:59.84
424>>651
���u��v�֍s�����H ����Ȃ��Ǝj���ɏ����ĂȂ����� ���s���c�Ȃ͂������ ��
鰎u�Ɂu�s�\�������v���Ƃ͂����菑����Ă��邵�A
�@���ł��A������|�z���ɏ㗤���ē��̐`�����ɍs���A
���̓��́u�F�v���f���ł���Ƃ��Ă��邩��A�s������ے肵�Ă���A
�k�͊C�ł��邩��A�����@�ŁA�u��v�ɍs�����ɂȂ�B 864���{�������j����2019/02/15(��) 07:16:53.86
424>>660
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̂悤�ɁA
�j��������j�����Ԃɑ���s���Ɏ����s�����ȁA
��a�� 865���{�������j����2019/02/15(��) 07:17:17.45
>>569
�z���z���͗��ɑ�
�E���Ȃ̂͊m�������A���C�͂ǂ��̒N���S���������ē����Ă�̂�w 866���{�������j����2019/02/15(��) 07:19:56.01
>>860
���g�̓`���P�ȕ悵������ 867���{�������j����2019/02/15(��) 07:28:55.43
>>866
�u�����͂�v �����̂��悪����ȂɎ������ˁH�@����J����B�@�@�����g 868���{�������j����2019/02/15(��) 07:30:48.36
>>839
������l�ɖ�肪���邱�ƂɋC�Â��Ă��Ȃ��́H
�t����
��B���̕����A��������n����������āA�ږ�Ă̎�����100�N�P�ʂŌÂ����̂������āA
��B�͂������|���Č����Ă邾���A�Ƃ����̂��w�E���Ă��
��B��
�E3���I�̂���
�E�ɓs���Ɠz��������
�̓�̏�����t����ƁA�����Ȃ����Ƃ������� 869���{�������j����2019/02/15(��) 07:36:39.37
>>866
�����牜�n�̓ޗǖ~�n���撣���Č��������Ă��A�{���`���i���g�j�ɂ͓��ꂩ�Ȃ�Ȃ���B�@���ƂȂ������Ă��Ȃ����B�@�@�����g�@ 870���{�������j����2019/02/15(��) 07:40:38.80
�A�́A���̎l���ɂ��H����̔��\�������̗�ꂪ����悤�ɁA
�����ȂƂ���Ō����������������̂������̂Ƃ���ɂ���肽�����Ă���
���W�Ȃɒʂ��鐫�Ȃ������Ȃ����ȁH��
�^�̂Ȃ��ĂȂ��C�k���T���_�����W�߂�̂Ɠ����H
871���{�������j����2019/02/15(��) 07:45:17.86
>>870
�`���i���g�j��A�܂����Ǝv���C�����͗����ł����B�@�@�����g 872���{�������j����2019/02/15(��) 08:10:45.09
���̘`���Ƃ����͉̂��Ȃ́H
�A�}�e���X�Ƃ����̂��Z��ł���́H�o�g�n�H
�f�^�����H
873���{�������j����2019/02/15(��) 08:14:35.60
�_�b�ł����ł��ǂ��A
���Ȃǂ����̍������������̂��Ə����Ă���ł���
���{�̐_�b�ł����_�Ƃ����̂��A
����(���̍�)�ɏZ��ł�����Ȃ���
874���{�������j����2019/02/15(��) 08:17:44.78
���̐_�Ƃ����̂�����ł���H
��Ɂ`�`�`�`���{�ɓn���ė����Ƃ����b�H
875���{�������j����2019/02/15(��) 08:31:19.24
424>>664
���������āE�E�E�u���|�z���ȓ��A�F���f��俀�v�́u�F�v������A
�����ɂ́u俀�̓s�v���Ȃ��B��
����B���̐l�͂������{�̂�����������
�]�˂��猩��Δ����̊ւ����O���u�F�v�֓�����
��a���̐l��́A�S�������A�]�����������ȁB
�u�F�v�Ƃ́A�u��O�Ȃ��S�����v�Ƃ����Ӗ����B 876���{�������j����2019/02/15(��) 08:35:36.85
�w���_�@���̉����x
�Ƃ̘V�k��(�V�̐�)�A
���̍�i�Ɠ����悤�Șb�����Ă�����
�\�������Ă��āA�@�D�`�A
���������Ƃ̐l�ƌ��������Ƃ�
�w���X�x�H
877���{�������j����2019/02/15(��) 08:41:40.31
�����̂��Ƃ߁i�S�ς��痈�����̐��̘b�B��ɐ��̍��j
���̐��E�E�E�H�ǂ������Ӗ��Ȃ낤�A�d���H
878���{�������j����2019/02/15(��) 08:44:21.12
�w���@�d���x�H
�ނ薼�l�̂悤�Șb���o�Ă�����A
�Ñ�̒����̐l���̘b�Ƃ�
879���{�������j����2019/02/15(��) 08:53:17.68
�E�����E��a�_�҂̑����́A�u�`�l�`�͈핶�v�Ɩ��ӎ��Ɏv������ł���悤���B
�܂�Ñ��a�Ɂi�`�l�`�j�Ƃ����Õ���������A�O���I�ɂ���Ă���鰎g������������A���āA
�O���u�E鰎u�`�Ɉ핶�Ƃ��Ď��^���ꂽ�E�E�A�Ƃ������ӎ��̈ӎ����B
�����āA���łɓ����̋E���͑卑����������A�E����鰎u�`�l�`�ɓo�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂��B
�������A����͂����炩�ɖ��ρA�Ўv���A���ȉߑ�]���A�A
�����́A鰉����̑����Ə����̂�������B�E�`�̍��X�݂̂��A鰎u�`�l�`�̎�l���Ƃ��Ď��^����A
�����������ߋE�E�i���n���́A�����̘`��i���Ƃ��ĕЂÂ���ꂽ�̂���B�B�B
880���{�������j����2019/02/15(��) 08:54:49.24
�͓��Õ��Q�i�R���L���j�Ƃ����A��B���͂ǂ��������Ă��H
881���{�������j����2019/02/15(��) 08:56:17.54
424>>672
�����퐶�����100���߂��}�����F�߂������ċ_���R�Õ������Ȃ�����H ��
�����̕�B���A�_���R�Õ������Ƃ��̒n�R���`�ŏ㕔3���̈ꂭ�炢
���ꂿ����Ă�̂������
�}���҂𑒂��Ă���A���̕��j�ă��C���̕��u���������
���肦�Ȃ����Ƃ��炢���{�l�Ȃ画�f�ł����ȁH �����������������������������邱�ƂɂȂ遃
�Ȃ��B
����Ă����̂́A���Ђ⌕�����Ă����P���P���̐��l�����B
�ޏ��́A�����炭�z�X�̃g�b�v�̃��[�_�[�I���݂ŁA�ږ�Ă̐M���������A
�ږ�Ă̎��ɔ߂���ŁA�ӔC�������āA�}�����A
������A�ږ�Ă̎������̌����ɂȂ�悤�Ȍ��̈ʒu�ŁA��ɏ}������A
������A�ږ�Ă̙n����鎞�ɁA�o���肪�o����悤�ɁA�P���̏������A
��������āA������A�ޏ��ɏ]�����z�X�̓��̕S�l�ʂ��Ǐ}�����A
���ꂪ�A���ʂ���O�ʂɏ}�����ꂽ���́B 882���{�������j����2019/02/15(��) 09:04:33.94
���͂Ȃ�����B��
����͗��j����Ȃ�
883���{�������j����2019/02/15(��) 09:06:02.78
>>879
�������B���C�^�R�|�Ƃ����� 884���{�������j����2019/02/15(��) 09:07:16.20
�C�Â��Ă���l�͋C�Â��Ă����A�Ƃ̘b
�w���X�x�H�Z��A���Ɩ��������ł���
885���{�������j����2019/02/15(��) 09:19:15.71
>>875
���u�F�v�Ƃ́A�u��O�Ȃ��S�����v�Ƃ����Ӗ����B
��B��蓌�͐��E�̉ʂĂ܂Ř`���̎x�z���H
�܂�����
���������Ӗ�����Ȃ�
���֓��i��Ř`���̊C�݂֒����ď㗤����Ƃ��U��Ԃ��āA�}�����܂ߋ�B���炱���܂Łu��O�Ȃ��S���v�`�����}�g�̑������Ƒ��������� 886���{�������j����2019/02/15(��) 09:22:34.93
��B���͗��Ƃ��b�������A�E�����̓j�Z��b�������B
887���{�������j����2019/02/15(��) 09:26:11.68
�E�����E��a�_�҂̑����́A�u�`�l�`�͈핶�v�Ɩ��ӎ��Ɏv������ł���悤���B
�܂�Ñ��a�Ɂi�`�l�`�j�Ƃ����Õ���������A������O���I�ɂ���Ă���鰎g�������A���āA
�O���u�E鰎u�`�Ɉ핶�Ƃ��Ď��^���ꂽ�E�E�A�Ƃ������ӎ��̈ӎ����B
�����āA���łɓ����̋E���͑卑����������A鰎u�`�l�`�i�핶�j�ɋE�����o�ꂵ�Ȃ��͂��͂Ȃ��A�Ƃ����v�����݂��ȁA�A�A�B
888���{�������j����2019/02/15(��) 09:29:58.61
�U�����`�Ƃ�����i������ł���H
���Ɗς����ƂȂ����ǁA
������������A�A�j�������������H
889���{�������j����2019/02/15(��) 09:31:52.28
424>>684
�����̎��_�ŁA�܂Ƃ��ȓ��{�l�͉��~���ɂ��ꂽ��Ɖ��~���ɂ�����̊Ԃɂ�
�W���Ȃ��Ɣ��f������H��
�P�����c���Ă������Ƃ������́A���R�A�n����l��͒m���Ă��đ����������ɂȂ�A
�P���̒��̋��Ђ�S�������������l�������N�ł������̂��H�A
���m���Ă�������c�������ɂȂ�B
�����@���ł��A�}����}�w�Ƃ͔��f����Ă��Ȃ� ��
���@�҂́A���R�w�ǁA
�u�쁨���v�Ȃǂ̃E�\�t���x���́u��a���Ƃ������_��ɂ��肫�v�̐l��ł��邩��A
��a���ɂƂ��Ă͕s���ɂȂ�A�Ǝv���A�S�ĞB���ɂ��Ė��E���鎖�ɂ�����́B 890���{�������j����2019/02/15(��) 09:43:02.63
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
891���{�������j����2019/02/15(��) 09:43:26.17
424>>684
�����͂Ŋm�F���ꂽ��B��62������͂� ��
�P���́A�����炭�u��l�����v�ł��낤���A
�ΊW�y��32�┠���Ί��V��G�����Ύ�13�Ȃǂ́A
������^��ł̕�����������������������Ă������ł���A
����炪�S�ĕ��������ł�������A���ꂾ����100�l�ȏ�ɂȂ�A
������A�W�c��n�̔ے�ł������B 892���{�������j����2019/02/15(��) 09:46:31.71
�؍����{�Ɍٗp���ꂽ�j�]�����E�����̐�`�W���̊؍��l�̃L�i�C�R�V���A�S�L�u�����@���ׂ����悤�ɂ��āA���S�ɘ_�j���ꂽ�ȁB�B�B
893���{�������j����2019/02/15(��) 09:47:46.83
>>891
��������A�W�c��n�̔ے�ł������B
�W�c��n�Ȃ��Ƃ�ے肵�Ă�̂͌Óc��h�����ł��� 894���{�������j����2019/02/15(��) 10:01:01.80
�{�b�킪�o�y�����O���I�̕悗��
895���{�������j����2019/02/15(��) 10:03:14.74
424>>696
���_���R�̏}���̓����ɁA�����̈�̂������Ƃ������̂�����B
��ʂ��������낤�ƍl������Ί��悩��A
�����̛ޏ��ƍl������ّ̂��o�y���Ă���B
���ꂩ��l���Ă��A��ŕ��q��j���̋�ʂ͂Ȃ��Ƃ����A
�הn�䍑�̋L�q�f�����Ƃ����悤�B��
�Ӂ[��A�����B
���A�L��������܂��B 896���{�������j����2019/02/15(��) 10:04:58.37
�w�d���@���x
�O�O��ƁA�L�^���[�̉摜���o�Ă����肷�邵
�w�͓��̎O���x
�Ƃ̎ʐ^�ƁE�E�E�E�ł���H
897���{�������j����2019/02/15(��) 10:06:44.43
�{�b�킪�o�y�����O���I�̎הn�䍑�̏��悗����
898���{�������j����2019/02/15(��) 10:07:39.15
���{�ł͉͓��`�͔��H
�Ƃ́w���X�x�H
�����������O�̉ƂȂ��ǁA�ǂ������b�Ȃ낤
899���{�������j����2019/02/15(��) 10:29:05.47
>>870
�c�O�Ȃ���O�@��t�䂩��̎l�����\���ӏ��̂��������̈�ӏ���
���ꋳ��n�`�}�`���S���_���X�����ɂȂ��Ă��� 900���{�������j����2019/02/15(��) 11:06:55.77
901���{�������j����2019/02/15(��) 11:12:46.01
�k���N�Ɏx�z���ꑀ���Ă���؍����{���A���S�ɔj�]�����הn�䍑�E�����������܂���`���Ă���ړI���A鰎u�`�l�`����܂ł͘`�l�Ƃ�����������B�≫�ꂾ���ł͂Ȃ��A���̊؍��̗̓y�̑啔�������X�̗̒n�ɂ��Ă����Ƃ����^�����B�����Ƃ��Ɣ��������̂ŁA
���̃X���b�h�œ��_����b����A鰎u�`�l�`����ɘ`�l���{�B��l���́A�ǂ͈̔͂܂ŁA�̒n���L���Ă����̂���A鰎u�`�l�`����ɓޗǂɏZ��ł����ҒB�����҂������̂���A��B�̂ǂ��ɘ`���̓s���������̂��̘b��ɁA�ϊ�����Ηǂ��ȁB�B�B
902���{�������j����2019/02/15(��) 11:44:12.74
>>386
���܂ŁA��R���ǂ�ȎR���������܂�Œm�炸�ɁA1��76.5m�̏؋����Ƃ��āu��R���O�\���v���R�̍������Ƌ������Ă����̂ɁB
�v�v�v�B 903���{�������j����2019/02/15(��) 11:59:02.34
424>>703
���Z����Ղ͓��{�̓s�s�̏����Ƃ���������邩��A�Z����Ղ�
���{�ŏ��̉��s�ł���Ƃ������Ƃł����ȁH���� ��
�Z���́A�u�s�s�v�̏�ԂɂȂ��Ă��Ȃ�����A�~�B 904���{�������j����2019/02/15(��) 11:59:18.74
>>398
1����75m�`90m�B
���̂�����75m�ɋ߂��B
�Óc�́A�ǂ������킯�ŁA���̒l��m�����̂��B
1��76.5m���҂́A�Óc�����̒l���ǂ��Œm�����̂��A�m���Ă��ˁB
����������ƁA����������Ă݂Ă���B 905���{�������j����2019/02/15(��) 12:01:22.16
������̕���in�퐶��������邯�ǂ�
906���{�������j����2019/02/15(��) 12:03:09.76
>>903
�u�s�s�v�̏�ԂɂȂ��Ă��Ȃ��Ƙ`�����ږ�Ă��s�������Ă͂����Ȃ�
�Ƃ������R�́H 907���{�������j����2019/02/15(��) 12:07:07.29
>>412
�Ȃ�ŁA���}�h�A���}�g�Ɣ������Ⴄ�̂���B 908���{�������j����2019/02/15(��) 12:10:33.31
��B���̐S���������̂�
909���{�������j����2019/02/15(��) 12:15:25.05
>>440
���ʁA������Ă���O�ւ͍s���ȁB
�O�֏o�čs���̂́A���ŐH����B 910���{�������j����2019/02/15(��) 12:16:39.60
424>>707
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R���x���̑�a���҂�
����ׂ����ׂ����
���p�I�Ȑl�Ԑ��ƁA�����x���̓��{��̍I�����������Ȃ� 911���{�������j����2019/02/15(��) 12:19:52.45
>>909
���O�֏o�čs���̂́A���ŐH����B
�܂��ɂ��̒ʂ肾��B�@�`���i���g�j�C�l���̍q�C�p�������āA�O�֑�B�ɏo�Ă������̂��B�@�@�����g 912���{�������j����2019/02/15(��) 12:26:04.15
>>442
1���I�`3���I���퐶����B
���N��Ȃ��B
�z�P�m�́A�ږ�Ă̙n�ł͂Ȃ��O����~�������A�L�����ł͂Ȃ��A�Ƃ�����ΔN�ォ��̐��������c�āA��������Ȃ��珑�����̂��B
�ږ�ẮA�}��R��B
�z�P�m�́A�Z���A���̑�\���J�҂̕�B
�ږ�ẮA�}��R�傿���l�B 913���{�������j����2019/02/15(��) 12:31:38.89
>>386
�����l���J�{�v�Z��m��������
�Q�O�O�O�N�ȏ�O�̎�鏎Z�o�ɏ����Ă��鎖��^�ɎČv�Z���ďo����������
��̉��̈Ӗ�������̂Ƃ������������ 914���{�������j����2019/02/15(��) 12:38:34.25
>>912
���z�P�m�́A�Z���A���̑�\���J�҂̕�B
��B���Ƃ��āA���ꂵ���������ˁB�@�@��B���ł́A�E���̌Õ��m�ɐ����ł��Ȃ��B�@�@�����g 915���{�������j����2019/02/15(��) 12:42:16.58
>>908
�������ȁB
��B�́A�����Ƒ���������������B
���������A�R��샄�}�h�m�Ƃ����Ƒ���������������B
��t�̐_��A�S�E�h���A�����Ƒ���������������B
�����h������̂́A���Ńg�Ɣ�������̂ƈႤ�̂���B 916���{�������j����2019/02/15(��) 12:46:21.59
>>914
�ȂɌ���������āB
�Z���̕�́A�����̑O������^����x�[�X�ɁA���̌�����ɋg���̉~����u���������V���̂��́B
��B�̔ږ�Ă̕�́A�_���R�B 917�P ��UiepmfCeDJqf 2019/02/15(��) 12:48:10.94
�V�X�����Ă܂����B
http://2chb.net/r/history/1550200332/
��������������������������������������������
���Ӂ��{�X�����I�����Ă��珑������ł��������B
�Ȃ��A�������݂�
�@�הn�䍑�E�����ɊW���L����
�@�����̂�����e�����肢���܂��B
�@�E�����ȊO�̓Ǝ�����P�ƂŊJ���邱�Ƃ͂��������������B
�@�{�X���I���ȑO�̏������݂͍r�炵�s�ׂƊŘ��Ē����܂��B
�������������������������������������������� 918���{�������j����2019/02/15(��) 12:52:29.36
>>916
���Z���̕�́A�����̑O������^����x�[�X�ɁA
����A�u�����̑O������^��v�̃x�[�X�́H�@�@�@�����g 919���{�������j����2019/02/15(��) 12:54:09.28
�R��͊C��2�`4�������Ȃ�
�n���ɂ��c���Ă�悤�ɕ���
920���{�������j����2019/02/15(��) 13:02:35.77
>>916
�O����~����O��������̃x�[�X���`���i���g�j�B�@�@�@�����g 921���{�������j����2019/02/15(��) 13:09:42.57
424>>710
����������k1��͕z���h���E���������
���Ƃ��Ƙb�ɂȂ�Ȃ��ˁH ��
�_�����B
�_���R���u�y�t��̌Â����v���o�Ă���A�Ƃ�����������A�������B 922���{�������j����2019/02/15(��) 13:22:19.62
424>>714
���_���R�Õ������l�ɍl����悢
�퐶����̓y�B��A�P����̂�����ɁA���̑��݂����Ēn�R���`�̊�Ց�����
�s���A���������ꂽ�u�����v�� ��
�_�����B
�_���R����P�O�O���ʂ̋߂��Ɂu�_���R�Õ��Q�v�Ƃ����W�c��n�����݂��Ă���A
�_���R�͖��炩�ɁA�_���R�Õ��Q�Ƃ͕ʂɓƗ��I�ɒn�R�`���܂ł��č������ł���A
�P���P���̂悤�ȁA���Ђ�S����t�������l�������A
�ǓƂɖ��������悤�Ȏ����Ȃ��ꏊ���B 923���{�������j����2019/02/15(��) 13:26:51.16
�u�y�t��̌Â����v�����ׂď����̂��Ƃ��ƌ��߂���
���m�ȑf�l��������
�_������B����
924���{�������j����2019/02/15(��) 13:29:30.27
424>>727
�u�쁨���v�Ȃǂ̃E�\���x���̑�a���́A
��̓I�Ȏj��������j�����Ԃ̎�����������A
�I��肾����� 925���{�������j����2019/02/15(��) 13:33:43.11
>>922
���ǓƂɖ��������悤�Ȏ����Ȃ��ꏊ���B
�Ȃ狤����n�����
�_��������� 926���{�������j����2019/02/15(��) 13:37:47.36
>>919
���v�B
�퐶����̊C�ݐ��̐}���݂�ƁA�݂�s������͗��n�B 927���{�������j����2019/02/15(��) 13:39:11.24
424>>729
���_���R�Õ����i�z�A���������Õ�����̕����Ȃ��ǁH
�����ƑO����~���Ŏ��オ�قȂ�Ȃ�Ă������Ƃ͂Ȃ����H ����
�_���R�́A�����Ƃ͈���āA
�u�l���~�ʂ̒i�z���������̑�v�I�ȌÕ��ł���A
�O����~�����́A���炩�ɌÌ^���B 928���{�������j����2019/02/15(��) 13:39:15.69
>>918
�����̑O������^��̃x�[�X�́A�����̕��`���a��B 929���{�������j����2019/02/15(��) 13:45:09.40
>>815
������2����̎�������o���y��Ђ�2���I���������Ă���H
�y��̔N����͂����܂ł����ΓI�Ȃ��́B
������Ղ��ږ�Ă̕�Ȃ�A��������y��ҔN�̐�ΔN������߂邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ�B
��������2���I���Ȃ炷�łɘ`���嗐����ł���A�ږ�Ă̎����ł���B
������Ղ̎�͔ږ�ĈȊO�ɂȂ��Ƃ������ƂɂȂ�B 930���{�������j����2019/02/15(��) 13:49:38.59
424>>731
���a�S���ɑS�R����Ȃ����ږ�Ă̕�ɂ��悤�Ƃ��Ă��ŏ����疳�������Ă�
�Z���Ŋ�ՓI�ȑ�̏�̕s��`�̐��̑��̂���ł���A
���̑䕔�����a�S�]���łقڃs�b�^�����B
����������B���́A�u�a�v������~���Ɍ��܂��Ă邩��O����~������Ȃ�����
���������ɋ_���R�Õ��͕������� ��
�u�a�v�́A�Y��ȕ����ȊO�́A�s��`��~�`�̑傫�������\�����@�ł���A
�_���R�ɂ͂قڃs�b�^���ȕ\�������B 931���{�������j����2019/02/15(��) 13:51:06.08
�}�y�����E�ɓs�����́A�_���c�@�L�̃p�N��
932���{�������j����2019/02/15(��) 13:51:29.46
>>929
�́H
�`���嗐����ɂ�
�ږ�ĈȊO�͒N�����ȂȂ��̂��H
�A�i�^���]�̘_����H������łȂ����H 933���{�������j����2019/02/15(��) 13:55:22.89
>>930
���Z���Ŋ�ՓI�ȑ�̏�̕s��`�̐��̑��̂���ł���A
���X�Ǝj���ɂȂ��V�����P�ʂ�s�������B�� 934���{�������j����2019/02/15(��) 14:00:40.02
>>920
�������u������R3�������~���B 935���{�������j����2019/02/15(��) 14:01:01.22
>>928
�����̕��`���a��̃x�[�X�́H�@�@������������B�@�@�����g 936���{�������j����2019/02/15(��) 14:10:00.28
>>934
���R3�����͖퐶�̕��u��@�הn�䍑���̓���������^����
4���I�㔼�`5���I�i�Õ�����j�̑O��������Ƃ���Ă����C�z����]�̎��R3������3���I�����i�퐶����I�����j�̕��u��Ƃ݂��邱�Ƃ��A�������������Z���^�[�̐����N�v�ꖱ�����̒����ŕ��������B
�הn�䍑�̎���ɁA���암�ɑ傫�ȕ��z���鐨�͂��������Ƃ݂���B
���R3�������܂ގ��R�Õ��Q�́A1977�N�ɂُꐮ���v�悪�����オ��A79�N�̔��@������ɐ��c�̋q�y�Ƃ��č�����ď��ł����B
�����ꖱ�����͓����̎ʐ^��}�ʁA�o�y�i����ɁA��s�喃���̔������u��ɑ�\�����퐶�������`�I�����̌������u��Ɣ�r�����B
���̌��ʁA���R3�����i���a��12���[�g���j�͋K�͂͏��������̂́A�������u��i��20���[�g���j�Ɠ����~�u�Ł�����ɐ���ׂĎl�����͂����ꏊ�����遤���u�̕\�ʂ�ϐŕ����Ă���
�������s�̈���여��̏W���ő���ꂽ�u�����y��v���o�y�����|�Ȃǎ��̋��ʓ_���m�F�B�u�퐶���u��Ɨ������ׂ��ł��낤�v�ƌ��_�t�����B
�j�Ђ��o�y�����������u���s�ԕ����v�̗����o�H�ɂ��Ă��l�@�B�u���s�ԕ����v�͔������u�悩����o�y���Ă���A�u���g���v�n�悩������炳�ꂽ�\���������v�Ƃ��A���k���̐��͂Ƃ̂Ȃ��肪�[�������Ƃ݂Ă���B
���Ɍ����l�Ô����فi�����d�����j�̐Ζ씎�M���_�ْ��i81�j���ޗnj������s���́u�הn�䍑�̎���ɁA���u���邾���̐��͂��������암�ɂ������Ƃ͋������B
�ߋE�Ǝl�������ԊC�H�̋��_�Ƃ��Ă̖�����S���Ă����̂�������Ȃ��v�Ƙb���Ă���B�@�@�����g 937���{�������j����2019/02/15(��) 14:14:53.36
>>919
�퐶�I�������́A�Õ���������O�̒ቷ���ŁA�C�ʂ͌��݂��2�`3m�Ⴉ�����Ƃ����B 938���{�������j����2019/02/15(��) 14:20:20.37
>>926
���������A�Ƃ���ǂ��땂���̏����Ȉ�Ղ��� 939���{�������j����2019/02/15(��) 14:25:46.98
940���{�������j����2019/02/15(��) 14:26:49.91
>>938
���̖퐶�̊C�ݐ��̎����́A���H 941���{�������j����2019/02/15(��) 14:30:20.33
942���{�������j����2019/02/15(��) 14:35:25.68
>>937
�~�n�͊C���ʂɊW�Ȃ��B
���������r�ԃW���W���������n���ޗǖ~�n�B 943���{�������j����2019/02/15(��) 14:38:08.68
>>930
���Z���Ŋ�ՓI�ȑ�̏�̕s��`�̐��̑��̂���ł���A
�����̑䕔�����a�S�]���łقڃs�b�^�����B
�u�Z���v���Ă͉̂��Z���`��
���̎j���I�����ƎZ�o��͉���
�_���R�̂ǂ����ǂ������
�u�a�S�]���v�ɂȂ�̂��ˁH 944���{�������j����2019/02/15(��) 14:38:49.23
945���{�������j����2019/02/15(��) 14:44:00.51
>>938
200�N�̊C�ݐ��͖���s�t�߁B
�퐶�����܂ł͍����ŊC�ݐ��͉��Ɍ�ނ��Ă������A����㔼����͒ቷ�����i��ŊC�ݐ�����։���A200�N���ɂ͖��삠����ɊC�ݐ����������B
�R��́A�\�����n�B 946���{�������j����2019/02/15(��) 14:46:01.44
>>945
�C��������̓D�n���ᗤ�n�ł����c�S���E�����H�ׂ��Ȃ� 947���{�������j����2019/02/15(��) 14:47:45.94
>>944
���؋��́H
���R�����A�~�n�`���̏؋��ł́H�@�@�����g 948���{�������j����2019/02/15(��) 14:47:51.36
>>945
�R��̌��ƂȂ��K�͈�Ղ������������̘b 949���{�������j����2019/02/15(��) 15:02:19.14
�ޗǖ~�n�̂������͍X�V�������i��87�`50���N�O�j�ɂقڌ��݂̂������ƂȂ���
�E�����X�����I�����銮�V���i��1���N�O�ȍ~�j�ȍ~�A�~�n���ɂ͌Õ�����܂�
���n�E���n�͑����c���Ă���
�L������ܕS�H���䍑�����{���y�̔���
http://www-im.dwc.doshisha.ac.jp/~nihei/nara/index.php?%C6%E0%CE%C9%CB%DF%C3%CF%A4%CE%B7%C1%C0%AE%B2%E1%C4%F8 950���{�������j����2019/02/15(��) 15:09:56.57
424>>743
���������đO����~�������鎞�_�ŁA����͂����Q�U�U�N�ȍ~�̍\�����ł���A��
������Ȕ�Ȋw�I�Ȃ��ƌ����Ă邩�� ��B���͎��恃
�u�쁨���v�Ȃǂ̂悤�ȁA
����ȁu�l�ނ̏펯�O��̔�w��I��Ȋw�I�v�Ȏ�����������A
��a���͂V���̍�������̎x���������Ȃ�����B 951���{�������j����2019/02/15(��) 15:16:44.15
424>>756
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a���҂̐S�����ăX�S�����
�m������Ȃ��œK���ȑz���𐂂ꗬ��
�����W��Nj������ƁA
�����܂łȂ� �u�E���o���ŊԈႦ��������e�w�v�ōς̂�
�S�}�J�V�̂��ߕېg�̂��ߊ��S�ɃE�\�����n�߂��Ⴄ�̂�
�l���̓]�����G�ɕ`�����悤�� 952���{�������j����2019/02/15(��) 15:24:18.32
424>>770
�u�쁨���v�Ȃǂ̉R�f���x���̑�a����
�ǂ����Ă���Ȃ�
�؋������̂������Ȃ낤�� 953���{�������j����2019/02/15(��) 15:25:30.11
���������Ԃ�������
�E�\���������𑱂���j
���������f�@�������E
���̖����U���R�N�����V�l
954���{�������j����2019/02/15(��) 15:34:07.92
㕌��̌@���������͒n�������̊قł����������
�������͋L�I�o��̐l���̊قł�����
�ږ�Ăƌ��ߑłɂ͍ޗ��s��
955���{�������j����2019/02/15(��) 15:34:29.86
㕌��̌@���������͒n�������̊قł����������
�������͋L�I�o��̐l���̊قł�����
�ږ�Ăƌ��ߑłɂ͍ޗ��s��
956���{�������j����2019/02/15(��) 15:35:45.53
���[�[�[��
>>1�����
���{�C���[�g�ւ̔��_�Ȃ��Ȃ�
�e���v������������ 957���{�������j����2019/02/15(��) 15:42:20.88
424>>784
���E�����ɕs�s���Ȃ̂ł͂Ȃ��A�Z��������ƍl���闝�R���܂������Ȃ�����A
�Ԉ�������Ƃ������̂͂�߂Ȃƌ����Ă��邾�� ��
�E���Ȃ�đ��݂����Ȃ��R���x�������ł��邵�A
�������鰂̖�l��ɋ�����n�̌����v���̂̋L�^�́A
�q�ϐ���M������m�������ɍ����A
�Z�����������A�ƍl������Ȃ��B 958���{�������j����2019/02/15(��) 16:04:47.76
�E�������݂��Ȃ��Ƃ��A�ȂɐQ�������Ă��
�����ܕςȂ́H
959���{�������j����2019/02/15(��) 16:06:57.11
424>>798
���Ȃ���
����͕z���O
�_���R�͕z���P���`�����
�Ȃ���
����͕z��
�_���R�́u�y�t��̌Â����v�ł��邩��A�����B
��������A�P����u�n�v�ł��邩��ł��A3���I�����B 960���{�������j����2019/02/15(��) 16:08:18.59
>>955
�ޗ��s���ƌ��߂��闝�R�́H 961���{�������j����2019/02/15(��) 16:13:09.23
>>959
�ЂƂ����R�̂Ȃ��Ƃ������̃c�{ 962���{�������j����2019/02/15(��) 16:20:53.77
>>955
��㕌��̌@���������͒n�������̊قł����������
���������͋L�I�o��̐l���̊قł�����
�`�����ł��������B 963���{�������j����2019/02/15(��) 16:22:06.67
>>960
���߂���Ȃ�A���̍ޗ���������B
�ؖ�����ӔC�́A�E�����������Ă��鑤�ɂ���B
�ؖ��ł��Ȃ��Ȃ�A�E�����͂����̖ϑz���t�@���^�W�[���B 964���{�������j����2019/02/15(��) 16:25:00.52
>>959
���_���R�́u�y�t��̌Â����v�ł��邩��A�����B
���́A�_���R���u�y�t��̌Â����v�ł���
�Ƃ����̂��炵��
�U���R�N�̂˂�������b�ɂȂ���
�����������B���Ă�̂�
�R�����ĂȂɂ��̏؋���
��܂����Ƃ��낪�����Ȃ�
�ǂ��������R�ŋ_���R�́u�y�t��̌Â����v�Ȃ̂�
�ƈ��тꂸ�Ɍ����͂��� 965���{�������j����2019/02/15(��) 16:26:17.42
>>963
�N���ޗ��s���ƌ��߂����H
���O����
�����痝�R������ 966���{�������j����2019/02/15(��) 16:27:29.82
�_���Ƃ����̂́A�����̐��n�̂��Ƃł��B
���łɎO���I�ɂ́A�}��ɕ����������Ă��܂����B
�ږ�Ă̋S���̐��̂́A�����̂��Ƃ������̂ł��B�얳�얳�I
967���{�������j����2019/02/15(��) 16:38:34.64
��B���͗��R�������̂��匙��
�؋��o���̂��匙��
������ł�
968���{�������j����2019/02/15(��) 16:48:02.29
�E�������ޗ��s�����Ƃ���
���R�������̂��C���Ȃ������
�E�������ޗ����o�����Ɍ��ߕt����
�Ƃ����؋����o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ���
�����ȋ�B��
�Ȃ����邽�тɏ������J���Ă���
�����ȋ�B��
969���{�������j����2019/02/15(��) 16:55:09.36
�U���R�N���_���R���u�y�t��̌Â����v�Ƃ��A�Ă����Ⴂ�܂�����
��������ȏ�\�[�X�o�����Ƀg�{�������Ă��
�R���U���R�N�̖��͂܂��܂����܂�܂��Ȃ�
970���{�������j����2019/02/15(��) 17:00:46.67
�_���Ƃ����̂́A�����̐��n�̂��Ƃł��B
���łɎO���I�ɂ́A�}��ɕ����������Ă��܂����B�_���R�͕����k�̍�����ł��B
971���{�������j����2019/02/15(��) 17:16:02.18
>>969
���̋_���R�Õ��́u�����v��u���ʁv�u�����v�u�����Ί��v������A�܂��ԈႢ�Ȃ��}�������̂��悾��B�@�@�����g 972���{�������j����2019/02/15(��) 17:16:21.30
����Ȃ��B�͔ږ�Ă̎��߂��הn�䍑���Ⴀ�Ȃ���
�ږ�Ă͕�������Ȃ��S���ɂ���č������߂�����
�����}�オ�������Ȃ�הn�䍑���炷���Έً���
973���{�������j����2019/02/15(��) 17:19:18.15
>>971
����������A�h�䎁�n�́u�����͂�v ���낤�B�@�@�����g 974���{�������j����2019/02/15(��) 17:21:29.75
>>968
�����͋E�����̃X���Ȃ���A�E�������ؖ�����؋��������Ƃ����̂ɁA�C���C�������ď؋��������Ȃ��̂��˂����܂�Ă���킯�ŁB
�؋��������Ă��Ȃ��؋����ĉ�����B
�`������������t�M�����H 975���{�������j����2019/02/15(��) 17:22:34.56
>>972
�����A�L�i�C�R�V�B
�������������쎩���͂�߂��B
���ꂾ����E�����͐M�p����Ȃ��B 976���{�������j����2019/02/15(��) 17:27:23.70
>>975
���ꂱ��A�Ȃ��悭���܂��Ȃ����B�@�@�i���̗ǂ��l�葊��Ȃ���B�@�@�����g 977���{�������j����2019/02/15(��) 18:06:28.09
424>>839
�����ɓ���S��l��̗��L�^�́A鰒��́i�Z�j���ŏ�����Ă��邩��A��
���O���牽�x�������Ă邯��ǁA鰎ڂ͌������o�y���Ă��邩��A
鰒��S�̂��Z���������Ƃ���͕̂s��
�O���牽�x�������Ă��邪�A�u�ڒ�K�v�͎ڐ��n�̒�K�ł���A
�n�c��̗����n�Ǝڐ��n�̊��Z���߂ł���u1����6�ځv�́u�ڂ̐��@�v�ɂ́A
���̊W���Ȃ��A
�Ƃ��������A�ރX����͑S�������ł��Ȃ��E�E�E�E�A�z�B 978���{�������j����2019/02/15(��) 18:09:32.98
424>>847
���הn�䍑���炸���Ƒ�a�̐��͂����{�̒��S�Ƃ��Ē����ƌ����Ă���Ɨ������Ă���̂����m��
�u�쁂���v�Ȃǂɋ����āA�~�B 979���{�������j����2019/02/15(��) 18:14:03.58
424>>849
�����{���ɂ��郄�}�g�̒n������B�ɂ�����I�������B���הn�䍑���I
���������}�C�Ƃ����}�h�C�Ȃ�ēǂݐ������Ȃ��̂Ɏהn�䍑�Ȃ��I
�o�J��B���̘_���ɕ����悶���قǏ����� ��
�u�הn�㚠���הn�䍑�v�ł��邵�A�u�הn�i�����}�g�v�ł��邩��A
��a���́~�B
�o�J��a���̘_�ɕ����悶���قǏ��B 980���{�������j����2019/02/15(��) 18:25:09.03
>>975
�ǂ���������
�s���̈������X�͎���������
��B�����������o�J������ 981���{�������j����2019/02/15(��) 18:25:48.58
>>974
�������͋E�����̃X���Ȃ���A�E�������ؖ�����؋��������Ƃ����̂ɁA�C���C�������ď؋��������Ȃ��̂��˂����܂�Ă���킯�ŁB
����Ȃ��Ƃ�������
���ď؋��́H
��B���͂܂��˂��H 982���{�������j����2019/02/15(��) 18:29:06.07
�������
�w�����s�[�X�@����x�ƁwAION�x�`�Ƃ����Ȃ�����ł���A
�Ȃ������Ȃ́H���Ɓw�W�����x
983���{�������j����2019/02/15(��) 18:29:47.05
�������������ɖ{���������݂ɂ��闝�R���Ȃ���B����
�E�����X���ɎՓ�ȏ������݂�����Ă鎞�_��
���ʂ̐l�͂����@���ƂȂ��
984���{�������j����2019/02/15(��) 18:30:35.96
424>>858
��������̂́u�����i�̑���������ŁA�����i�̍\������푒�҂͏����̉\���������v��
�����Ƃ���܂ł�����������
������ł��邩��A�����̕�ł͂Ȃ��ɓs���̗L�͉ƌn�̕悾�Ƃ͌����邪�A
�䌴�����~�]��ՁA�O�_�쏬�H��ՂƔ�ׂĂ��A��̋K�͂���邵�A
�ɓs������̗��n�ł���O�_��ՌQ�̊O�ɂ��邱�Ƃ�����A�ɓs������Ƃ��݂Ȃ�������
������Ղ��܂ޑ]����ՌQ�ł́A������Ոȍ~�A�Õ�����ɓ����Ă��ݑ�I�ȑ��悪
�������A�O�_��ՌQ�̒[�R�Õ��A�z�R�Õ��Ɣ�ׂċK�͂��������A�ɓs���̈ꑰ�ł͂Ȃ�
������Ղ͈ɓs���̑��ʂ̉ƌn�ƌ���ׂ��ŁA�`���̉��̕�Ƃ���͖̂������恃
����A21���́u������v���̑��݂́A����̉����������ɂȂ����A�Ƃ��邵�Ȃ��A
������o����̂́A�ږ�Ă��A���̌�p�����̏@���̚��o�������Ȃ��B
�����āA��ʂ̋ʂȂǂ������o����̂́A鰎u�ɏ����ꂽ
�u���w�i�A�ُ�j�������O�\�l�A�v����ܐ�A�E����A�ٕ�趋ѓ�\�C�v�́A
���o�̕�ł������A�Ƃ����\�������ɍ����B 985���{�������j����2019/02/15(��) 18:31:09.86
�������A���ݖ�����������Ƃ��A
�قƂ�Ǔ����Ȃł���
986���{�������j����2019/02/15(��) 18:33:41.11
�܂�>>974�݂����ȃE�\�����珑���Ă��ˁ[
�e���v�����邩���
�����o���ł� 987���{�������j����2019/02/15(��) 18:35:27.19
>>984
������A21���́u������v���̑��݂́A����̉����������ɂȂ����A�Ƃ��邵�Ȃ��A
��B���Ƀf�b�`�グ�邽�߂ɂ́A����
w 988���{�������j����2019/02/15(��) 18:37:19.49
>>984
�ږ�Ă�鰂Ɏg���𑗂����̂͌i���O�N��
������鰎u�������ʂ��������A���{���I�A�ˉ��A�����䗗�ɏ����Ă���
���̌i���O�N��鰂̔N�������܂�Ă�����싾�̎O�p���_�b������
�ږ�Ă������鰂���̉������ŊԈႢ�Ȃ� 989���{�������j����2019/02/15(��) 18:38:27.71
���䌴�����~�]��ՁA�O�_�쏬�H��ՂƔ�ׂĂ��A��̋K�͂���邵�A
�ɓs������̗��n�ł���O�_��ՌQ�̊O�ɂ��邱�Ƃ�����A�ɓs������Ƃ��݂Ȃ�������
������Ղ��܂ޑ]����ՌQ�ł́A������Ոȍ~�A�Õ�����ɓ����Ă��ݑ�I�ȑ��悪
�������A�O�_��ՌQ�̒[�R�Õ��A�z�R�Õ��Ɣ�ׂċK�͂��������A�ɓs���̈ꑰ�ł͂Ȃ�
������Ղ͈ɓs���̑��ʂ̉ƌn�ƌ���ׂ��ŁA�`���̉��̕�Ƃ���͖̂�������
�������F�����B
�j���̂��Ƃ̋��������A�Ƀs�b�^�����ȁB
990���{�������j����2019/02/15(��) 18:38:32.06
�U���R�N�͂ǂ����Ă����l�����̂��s���Ȃ̑������
991���{�������j����2019/02/15(��) 18:40:13.82
>>984
���_�ȏ������݂��ĂȂ���
�_���R���u�y�t��̌Â����v����
�\�[�X�܂��[�H 992���{�������j����2019/02/15(��) 18:41:38.33
�E�����̐����S�Ăɂ���A�Ɣ������Ȃ���Α����Ȃ̂ʼn����l���Ȃ��łƂ肠�����ے肵�Ă���
993���{�������j����2019/02/15(��) 18:41:47.34
424>>860
������鏎Z�o�ɂ́A�������̉e���\��������Ă��邩��A�Ď������ł͂Ȃ��A
�ꉞ��N���v���ł����B��
�����̉e�̒������Ď��ȊO�u�S���Ԉ���Ă���v��I����
�~���Ɏ����Ă�3�����������Ⴄ
�v��Όv��قǃf�^�����ɂȂ邼�A��鏎Z�o�̉e���̐��l���g���Ă���ȁ�
����A���e�̍Ő�[�ł̌v���ŁA�L������1�����x�ȓ��̌v���l���\���ɓ�����B 994���{�������j����2019/02/15(��) 18:42:51.49
>>989
���Y�ЂƂɑS�������Ȃ��Ƃ��ߔk�������
���������ɂ��������Ȃ��ˁH 995���{�������j����2019/02/15(��) 18:43:54.91
>>993
������Ȃ�
���ʂ������������ĂȂ���
�v�Z�����o���́H 996���{�������j����2019/02/15(��) 18:45:46.56
>>948
�Ȃ�ő�K�͈�Ղ��K�v�Ȃ̂��A���������J���}�Z���B 997���{�������j����2019/02/15(��) 18:45:58.75
>>993
������A���e�̍Ő�[�ł̌v���ŁA�L������1�����x�ȓ��̌v���l���\���ɓ�����B
�L������1�����x�ȓ��̌v���l�������邩��ꗢ�͖�75m����
�C���`�L����ˁH 998���{�������j����2019/02/15(��) 18:46:41.02
>>996
��B���͂���הn�䍑�͏����Ȃ́H 999���{�������j����2019/02/15(��) 18:47:30.87
���悾���Ō�������ď؋��o���Ȃ�����
��B���͎���
1000���{�������j����2019/02/15(��) 18:47:31.52
>>946
���c�S���E�̂���g���͂��܂����B -curl
lud20191225230722ca
���̃X���ւ̌Œ胊���N�F http://5chb.net/r/history/1550028707/�q���g�F5ch�X����url��
http://xxxx.5ch
b.net/xxxx �̂悤��
b�����邾���ł����ŃX���ۑ��A�{���ł��܂��B
TOP�� TOP�� �@
�S�f���ꗗ ���̌f���� �l�C�X�� |
>50
>100
>200
>300
>500
>1000��
�V���摜
�@���u�הn�䍑�E�����@Part425 ->�摜>45�� �v�������l�����Ă��܂��F
�E�הn�䍑�E�����@Part415
�E�הn�䍑�E�����@Part444
�E�הn�䍑�E�����@Part416
�E�הn�䍑�E�����@Part424
�E�הn�䍑�E�����@Part435
�E�הn�䍑�E�����@Part465
�E�הn�䍑�E�����@Part437
�E�הn�䍑�E�����@Part493
�E�הn�䍑�E�����@Part462
�E�הn�䍑�E�����@Part422
�E�הn�䍑�E�����@Part467
�E�הn�䍑�E�����@Part405
�E�הn�䍑�E�����@Part494
�E�הn�䍑�E�����@Part414
�E�הn�䍑�E�����@Part480
�E�הn�䍑�E�����@Part470
�E�הn�䍑�E�����@Part488
�E�הn�䍑�E�����@Part495
�E�הn�䍑�E�����@Part453
�E�הn�䍑�E�����@Part400
�E�הn�䍑�E�����@Part423
�E�הn�䍑�E�����@Part474
�E�הn�䍑�E�����@Part428
�E�הn�䍑�E�����@Part445
�E�הn�䍑�E�����@Part421
�E�הn�䍑�E�����@Part427
�E�הn�䍑�E�����@Part455
�E�הn�䍑�E�����@Part409
�E�הn�䍑�E�����@Part406
�E�הn�䍑�E�����@Part449
�E�הn�䍑�E�����@Part440
�E�הn�䍑�E�����@Part437
�E�הn�䍑�E�����@Part491
�E�הn�䍑�E�����@Part481
�E�הn�䍑�E�����@Part433
�E�הn�䍑�E�����@Part420
�E�הn�䍑�E�����@Part447
�E�הn�䍑�E�����@Part484
�E�הn�䍑�E�����@Part407
�E�הn�䍑�E�����@Part417
�E�הn�䍑�E�����@Part439
�E�הn�䍑�E�����@Part432
�E�הn�䍑�E�����@Part404
�E�הn�䍑�E�����@Part464
�E�הn�䍑�E�����@part440
�E�הn�䍑�E�����@Part408
�E�הn�䍑�E�����@Part492
�E�הn�䍑�E�����@Part479
�E�הn�䍑�E�����@Part429
�E�הn�䍑�E�����@Part443
�E�הn�䍑�E�����@Part471
�E�הn�䍑�E�����@Part487
�E�הn�䍑�E�����@Part460
�E�הn�䍑�E�����@Part450
�E�הn�䍑�E�����@Part446
�E�הn�䍑�E�����@Part497
�E�הn�䍑�E�����@Part418
�E�הn�䍑�E�����@Part483
�E�הn�䍑�E�����@Part438
�E�הn�䍑�E�����@Part486
�E�הn�䍑�E�����@Part472
�E�הn�䍑�E�����@Part478
�E�הn�䍑�E�����@Part499
�E�הn�䍑�E�����@Part434
�E�הn�䍑�E�����@Part448
18:20:25 up 22 days, 19:23, 0 users, load average: 10.17, 9.96, 10.19
in 0.034754991531372 sec
@0.034754991531372@0b7 on 020508
|





 �u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016
�u��a�퐶�Љ�̓W�J�Ƃ��̓����v���V2016