https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170512-00000029-mai-pol
安倍晋三首相は憲法記念日の3日付読売新聞のインタビューと、同日の改憲派集会へのビデオメッセージを通じ、憲法を改正して2020年の施行を目指すと表明した。首相は第2次政権発足後、重要な政策やメッセージを発表する場合、記者会見などの開かれた場のほかに、一部のメディアをしばしば利用している。今回の手法にも「メディアを選別し、都合のよい情報発信をしている」との指摘が出ている。【青島顕、川名壮志】
「自民党総裁としての考えは読売新聞に相当詳しく書いてある。ぜひ熟読してほしい」。安倍首相は8日の衆院予算委員会で、長妻昭氏(民進)から憲法改正発言の真意を問われ、そう強弁した。
◇「読売を熟読して」 国会答弁に騒然
首相は内閣には改憲の発議権がなく、発言は自民党総裁としてしたものだと立場を使い分け、「(国会答弁には)首相として立っており、(自民党)総裁としての考えはそこ(新聞)で知ってほしい」と述べた。
「新聞を読めってのか」。野党側は答弁を避けた首相に反発し、騒然となった。野党の理事に詰め寄られた浜田靖一委員長(自民)は「一部新聞社の件等々あったが、この場では不適切なので、今後気をつけていただきたい」と収めたが、首相はどこ吹く風の表情だった。
首相は4月24日夜、読売新聞の渡辺恒雄・グループ本社主筆と会食した。その2日後の26日、失言問題で今村雅弘・復興相(当時)を事実上更迭した後、同紙の前木理一郎・政治部長のインタビューに応じた。
読売新聞は1週間後の3日、「憲法改正 20年施行目標」「9条に自衛隊明記」との見出しで首相の発言を1面トップで報じ、4面の大部分を使って全文を掲載した。
インタビューでは、現行の9条の条文を維持したうえで自衛隊を明記するという首相の意向が語られている。しかし、それによって自衛隊の役割が変わるのかといった肝心な点への質問はされないまま終わっている。首相は3日の改憲派集会にもビデオメッセージを寄せ、読売新聞のインタビューとほぼ同様の内容を語っている。
◇「批判的質問受けぬ方法選んでいる」
鈴木秀美・慶応大教授(憲法、メディア法)は「重要な問題であるにもかかわらず、首相が一方的に意向を表明しているだけだ。批判的な質問を受けずに済む方法を選んでおり、メディアを選別した非民主的な手法だ。自民党総裁として党本部などで記者会見し、質疑応答の中で真意を明らかにすべきで、首相の発言とともに各メディアの分析や批判も報じられるのがあるべき姿だ」と指摘する。さらに「読売新聞も首相のメディア戦略に呼応し、利用されている。報道機関として期待される権力監視の役割を果たすどころか、政権に協力し一体化していると言われても仕方がない」と批判する。
元テレビ朝日記者で「放送レポート」編集長の岩崎貞明さんは、読売新聞のインタビューが「改めて憲法改正にかける思いを」という質問から始まっていることに着目する。
「現行憲法をどう考えるかを問うことから始めるべきなのに、改憲が前提の質問になってしまっている。いまの憲法にどんな問題があるかという視点に欠けており、変えることが双方にとって自己目的化しているのではないか」と指摘する。
◇「憲法論議を官邸主導にした」
民主党政権で内閣広報室審議官を務めた下村健一・白鴎大客員教授(ジャーナリズム)は、読売新聞が1面の記事の肩書として「自民党総裁」を冒頭の2度のみにして、以後は「首相」を使ったことの効果に注目する。「安倍氏は国会で『総裁としての発言。読売を熟読してほしい』と答弁した。しかし、読者には首相としての発言として記憶されるし、首相と書かれた以上、内閣スタッフは首相としての安倍氏の意向をそんたくして動かざるをえない。結果的に安倍氏はメディアを使って憲法論議を官邸主導にした」と話す。
読売新聞グループ本社広報部は毎日新聞の取材に対し、「取材や記事作成の経緯等に関しては従来お答えしていません」としている。
歴代の首相は単独インタビューに応じず、記者会見の場でさまざまな形の質問に答えるのが内閣記者会との慣例になっていた。ところが12年末の第2次安倍政権発足後、単独インタビューを通じた情報発信を始め、各報道機関の申し出に応じるようになった。ただ最近は、発信の対象を一部メディアに限っているとの指摘もある。15年の安全保障関連法審議中に国民から反対の声が広がった時には、BS日テレとフジテレビに長時間出演した。
2017/05/12(金) 17:12:46.66ID:MiU83M+50
![【毎日新聞】安倍首相「読売熟読して」 「メディアを選別し、都合のよい情報発信をしている」との指摘が出ている [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>17本 ->画像>3枚](http://image.2chlog.com/2ch/live/livetbs/image/1492763448-0899-001.jpg)



 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube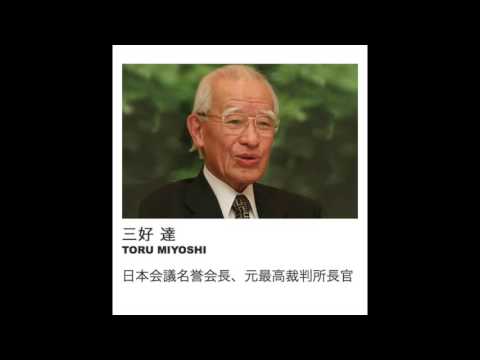
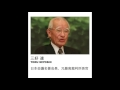
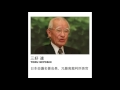
 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube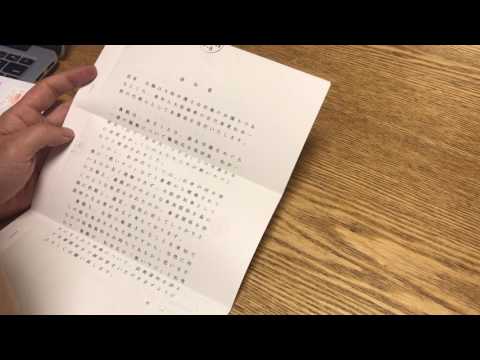


 @YouTube
@YouTube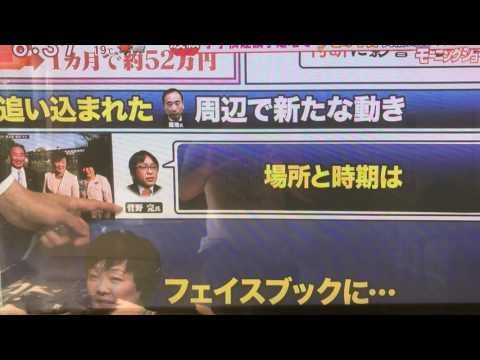


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube


 @YouTube
@YouTube![【毎日新聞】安倍首相「読売熟読して」 「メディアを選別し、都合のよい情報発信をしている」との指摘が出ている [無断転載禁止]©2ch.net YouTube動画>17本 ->画像>3枚](https://rz.anime-tube.win/pic.php?http://i.imgur.com/OxMCOLP.jpg)
